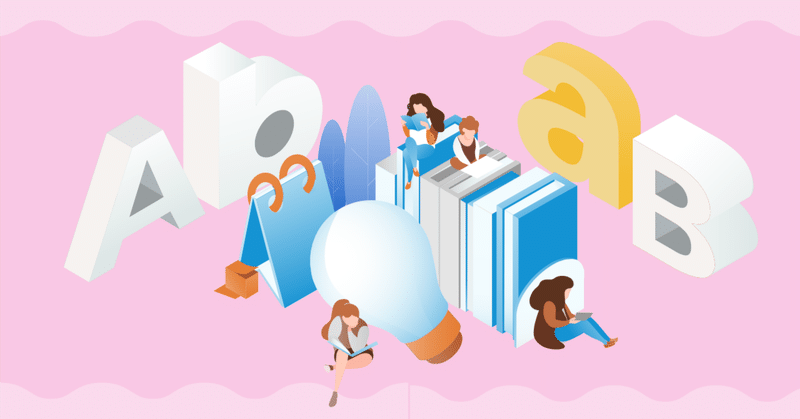
「伸びる中高生」の共通点:オンライン英会話Brighture(ブライチャー)の人気講師Celine先生の話の続き
先日、オンライン英会話Brighture(ブライチャー)のNo.1
人気講師、Celine先生の「人気の秘密」について書きました。
ここでひとつ書き忘れたことがあるので、今日はそのお話です。
そこから派生して、中高生を素直に勉強(など)に向かわせるポイントのようなものに思い至ったので、難しいお年頃の子育てをされている同士のみなさまと共有できたら、と思いこの記事を書いています。
(ちなみに、私自身は、小学校高学年と中学生をバイリンガル子育て中の母です)
朝4時起きで勉強していたCeline先生
前回記事に書いたように、オンライン英会話Brighture(ブライチャー)の人気No.1講師のCeline先生は、学生時代はフィリピンにあるインターナショナルスクールで勉学に励み、Honor(特に優秀な生徒に与えられる称号)として卒業した優等生だったそうです。そして、毎朝4時起きで勉強をしていたらしいです。
このとき、なぜそんなことができていたのか(What made you do that?)、その理由を聞いたところ、こんな答えが返ってきました。
勉強ができる環境に対して感謝していたから。世の中には学校に通えない人もいる。(「Brighture」人気No.1講師Celine先生)
このようにCeline先生は即答しました。
できるかぎりハイレベルの授業を取る、アメリカ留学中のYくん
一方、こちらの過去記事でインタビューした、アメリカ東海岸の伝統ボーディングスクールに通う高校生のYさん(取材時17歳)も、
「高いスタンダードに馴染みたい」と言い、できる限りの「Honorsクラス」を取っている、と話してくれました。
※アメリカには偏差値というものがないので、同じ学校の中にさまざまな学力レベル/興味の方向性の子が通うという特性があります。
そのため、1つの教科に対して(例えば数学など)、「普通のクラス」の他、「Honorsクラス」もしくは「AP(Advanced Placement)クラス」と呼ばれるハイレベルな授業を行うクラスが設置されていることが一般的です。カナダも概ね同様です。
「Honorsクラス」もしくは「AP(Advanced Placement)クラス」では勉強の内容が難しく、進度が速いなど、ハードワークが必要とされます。
彼に対して、「そのモチベーションはどこからくるのか」と問うたときの返答が
「期待にこたえたい、って常に思っています。僕を受け入れてくれたアドミッション(入試担当)の人をがっかりさせたくないし、アメリカに行かせてくれた両親、応援してくれている人、僕を知って声をかけてくれる学校の先生や先輩…。なんていうか、そういう人たちにGive back(恩返し)したいといつも思っています」(アメリカ単身留学中のYさん)
というものでした。
フィリピンでインタナショナルスクールを優等生で卒業したCeline先生。
アメリカ東海岸で名門ボーディングスクールに通う日本人留学生Yさん。
二人の共通点はなんでしょうか。
与えられた環境に対しての「感謝」
Celine先生は「家族への感謝」といい、Yさんは「受け入れてくれた学校、留学に送り出してくれた両親、応援し声をかけてくれる周囲の人への恩返し」と語りました。
二人のモチベーションの共通点は「感謝の気持ち」です。
また、「この学校・コミュニティにいい影響を与えたい」「ここでひと花咲かせたい」という思い、時には「うちの家族の一員として誇らしくありたい」という所属意識も、その動機になっているように感じます。
私は、子育ての中で、教育熱心な日本の親、マレーシアのインターナショナルスクールに通うさまざまな国籍の親や生徒を見てきて、また今カナダでもさまざまな考えを持つ教育熱心な親や「いい学校」に通う生徒たちを見ています。
いろいろな子ども・学習者を見ていて感じるのは、小さい頃は「親に褒められたい」という動機、精神的に大人になって以降は「将来のため」という動機が強くなっていくように感じるのですが、中高生時代に素直に勉強に向かわせるのは「感謝の気持ち」なんじゃないかということです。
心身共に不安定な時期であるプレティーンからティーンは、揺らぎやすく、友達や周囲の環境の影響も受けやすく、反抗期でもあり、難しい時期です。日本でいうと、中学受験から中高生くらいの時代ですね。
そして完全に親から自立しているというよりは半分は親がかり。
親としてもギリギリ手助けできる(ように見える)、もしくはする必要がある(と感じてしまう)時期だからこそ、「親の思い通りに伸びない」ことにやきもきしてしまうことも多いでしょう。
インターネットやゲームなどの誘惑も多い年頃です。
このヒントを子育て/教育移住に生かすには
話を聞かせてくれた2人の「国際的に活躍・成功する若者」の例から私が感じたのは、子育て中の親がこのことから学べることは、子どもが感謝の心が持てるようなサポートができているか、我が身を振り返ってみることだと思うのです。
感謝をしたくなるときって、どんな時でしょうか。
感謝をする対象って、どんなものでしょうか。
私もバイリンガル育児中の身として、「頑張らせなくてはならないこと」「やりぬいてほしいこと」がある場合もあります。
子どもの思いをできるだけ尊重したいとしながらも、親の考えで導いてきている部分ももちろんあります。
親が選んだ道であったとしても、「あなたのためだから」と押し付けるのではなく、この子が前向きに取り組めるような説明やムード作りができているだろうか。
(※ときとして正論よりも雰囲気が大事な時もあります)
無理強いをするのではなく寄り添ってやれているだろうか。
楽しくいられるように接してやれているだろうか。
この子の置かれている環境を理解してやれているだろうか。
自分がその立場だったらどうだろうか。
自分がこの子の環境にいたら幸せだろうか。
そんなことを振り返ってみて、自分が親として一方的だったり高圧的だったりしないか、いま一度振り返ってみることが、意外と(将来の)中高生時代の学習意欲を伸ばす第一歩かもしれません。
今まだ低学年などの場合は十分な時間があります。高学年でも、中高生でも遅くないです。もし子どものアカデミック面を伸ばしたいのに伸びない、と悩んでいるのでしたら、試してみてもらえたら、と思います。
この子の置かれている環境を理解してやれているだろうか。逆の立場だったらどうだろうか。
自分がこの子の環境にいたら幸せだろうか。
と考えてみてはいかがでしょう。
小さい頃は、怒ればなんとかなっちゃうんですが、いつかそれが通用しないときが必ず来るので、「子どもが感謝できるように」って視点を持つのも、ひとつの考え方として悪くないと思うのです。
スキやコメント、サポート、シェア、引用など、反応をいただけるととてもうれしいです☕
