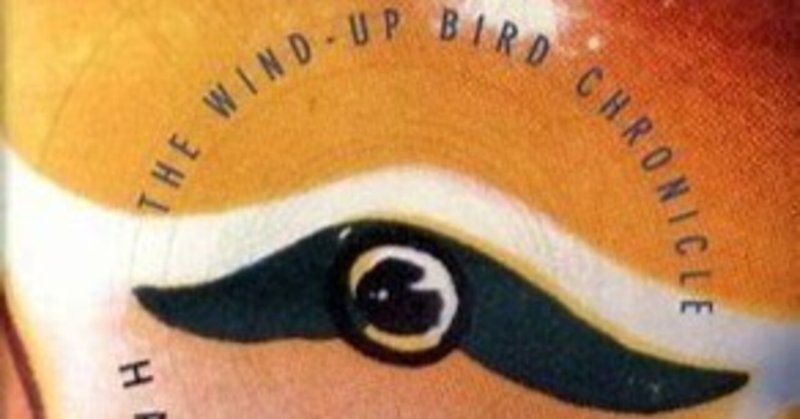
『ねじまき鳥クロニクル』を再読。村上春樹作品について、つれづれに思うこと。
村上春樹著、『ねじまき鳥クロニクル』は1994年発行の小説です。
第1部〜3部、合計1200ページを超える大作で、現在の東京と第二次世界大戦中の満州国で起こる摩訶不思議な出来事が交錯する作りとなっています。
初めて読んだのは私が高校生の時。
授業中にこっそり読んでいたのですが、「皮剥」シーンで貧血を起こしかけた強烈な記憶が残っています。そこから数年に一度のペースで読み返しているお気に入りの作品であり、読めば読むほど発見がある。モーツアルトのオペラ『魔笛』をモチーフに、人間の持つ「悪」「暴力性」を歴史に絡めて描いています。
何度読んでも全ての謎が解き明かされないところがお気に入り。「ブラックボックス」はそのまま置いておきたいタイプです。
「加納マルタ」「赤坂ナツメグ」「皮剥ボリス」猫の「サワラ」など…謎めいた名前の個性的な人物が入り乱れ、手に汗握る展開に夢中になってページを捲り、気づけば読了しています。素晴らしいイマジネーションの世界に連れて行ってくれる鮮やかな本だと感じます。
村上春樹の作品はほぼ全て(訳本以外)読んでいますが、『スプートニクの恋人』以降の作品はあまり好みではありません。
その主な理由は「一人称」の作品→好き、「三人称」の作品→イマイチ、だからかなと(あくまで個人的に)。
ただ、最新の小説『街とその不確かな壁』は主に一人称でしたが肌に合わなかったので、2000年前後の作品からのめり込めなくなったようです。
理由をいくつか考えてみました。
①『アンダーグラウンド』が村上春樹に与えた影響
村上春樹は『風の歌を聴け』でデビュー後、「僕」を主人公とした小説を発表してきました。『羊をめぐる冒険』以降は「僕」が不思議な出来事に巻き込まれ、何かを探しに行く、その過程で尋常でない体験をし、すったもんだあった後に生還する、といった骨子がほとんど。マジックリアリズムの手法が取られることが多いです。尋常でない体験=己を知る旅、であり、彼は友人や恋人を探し求めていると見せかけて、実は自分探しをしているのです。
この流れが変わった契機となる作品が『アンダーグラウンド』であると考えます。『アンダーグラウンド』は村上氏による、地下鉄サリン事件の被害者たちへのインタビューをまとめたものです。つまり、初のノンフィクションです。ここから「自己」の探求より「社会」にコミットメントした作品が増えたような気がします(特に長編)。
「三人称」を使用するようになったのも、その表れかなと。サリン事件の被害者に接することで村上氏の関心は内向的なものから外交的なものへ変わったのではないでしょうか。
私は徹底して「自分探し」をする作品が好きなので、社会性を帯び始めた作品にイマイチ乗れないのです。が、一人称でもあるに拘らず比較的新しい『騎士団長殺し』、最新の『街とその不確かな壁』は気に入りませんでした。それはなぜなのか?
②作者と主人公の年齢のズレ
『羊をめぐる冒険(29歳)』:33歳
『ノルウェイの森(大学生)』:38歳
『ねじまき鳥クロニクル(30歳)』:46歳
『海辺のカフカ(15歳)』:53歳
『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年(36歳)』:64歳
『騎士団長殺し(36歳)』:68歳
『街とその不確かな壁(16歳)(40歳)』74歳
※()は主人公の年齢、その後の数字は作品発表時の作者の年齢
主人公と村上氏の実年齢は離れる一方です。そこに違和感の正体がある気がします。どことなく、心情リアルでないのです。
また、村上春樹といえば…というほど特徴的であった軽妙な比喩やユーモアも、最近は冴えないと感じます。読んでいても心躍る事が少なくなりました。
②私自身の年齢の変化
私が初めて村上作品に触れた、高校生の頃から時は経ちました…切ないことに、あの頃の感性は戻ってこないです。上に書いたような作風の変化や作者の加齢に加えて、「私自身の変化」も大きいような気がします。
というわけで、最新の村上作品を読むたびに「読みたいのはこれじゃないんだよな〜」と言い続けています。それにも拘らず、新刊が出ると買ってしまう。若い頃に強烈な影響を受けた一種の「呪い」なのかもしれない。私には世に出た村上作品は全て読む、という選択肢しか残されていないのです。
ところで、今の高校生、大学生が昔の村上作品を読んだらどのような感想を持つのだろうか。ぜひ聞いてみたいものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
