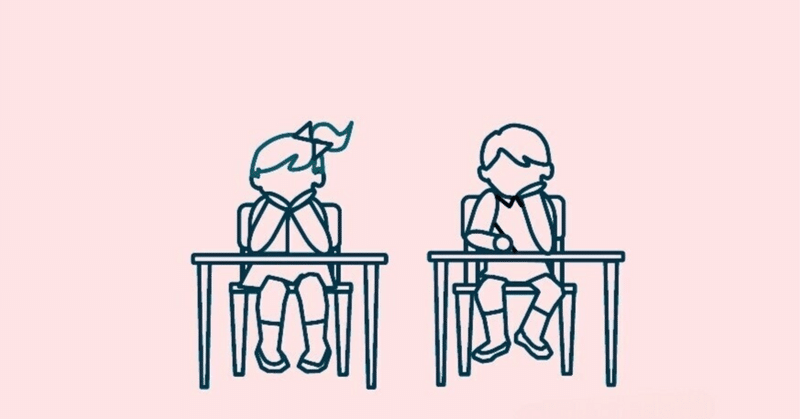
今だから言える発達障害児の息子に向かなかった習い事 その①
息子が3歳前から小学校5年生まで通っていた「くもん」。
当時から育てにくさを感じつつも幼児期からふれあいも兼ねて通っていた。
幼児期は歌やカードで言葉を覚えたり、他の幼児たちと触れ合ったり親子で参加する教室だったので大変な中にも私も外と触れ合う大切な時間だった。
繰り返し繰り返し同じ問題も解くくもんは粘り強さを鍛えるには良いかもしれない。普通の人にとって同じことを何度もすることは本当にしんどいことだと思うから。忍耐強さや真面目さを持つ発達障害児にとってピッタリとくもんははまる部分も多く、一日たくさんの枚数をこなし、通っている一部の生徒しかゲットできないトロフィー(三年先の学習ができた生徒)をもらったりした。
小学校二年生の時、クラスで一番計算が早いと話してくれた息子の嬉しそうな顔を今でも覚えている。
その頃は勉強に取り組む姿勢や独特の鉛筆の持ち方や歪な文字や大きさは気になっていましたが、成長とともに改善していくだろうと思っていた。
今思えば、体幹のなさや運動機能の低さから椅子に座ることも大変だったことや、不器用さから鉛筆がきちんと持てなかったんだろう。
学年が上がるにつれ、計算はものすごく早くても(親よりもはるかに早くくもん特有の計算方法で暗算に近い部分もあったが・・・。)、ケアレスミスが目立つようになった。国語は解答を書く枠内に文字を収めれなくなっていた。解答が合っていても、中学生レベルの問題を解いていた時、読む量も増え、文字も小さくなり、書く量も増える。不器用な彼は小さく枠内に書き切ることが徐々にストレスになっていった。
親としてもトロフィーをもらったりしたもんだから、勉強のつまづきに気づくのが遅くなった。寧ろ、普通より少し出来るくらいに構えていた。
小4くらいから問題文の理解が難しくなり、学校のテストでは応用問題などきちんと読んでないなというようなトンチンカンな解答をし始める。小5では先取りで勉強しているはずの算数に通知表に「がんばろう」の項目に⚪︎がつき始めた。その頃からあれ?もしかして学習障害もあるのかもと悩み出した頃だった。
ただただ繰り返し取り組んで覚えるだけで理解してなくてもそれが勉強の図が彼の中で出来上がってしまった。
その後、くもんは辞め近所の塾に通い始める。
集団授業は半年ほどでついていけなくなり、その後個別指導をしてもらっている。中学校になってさらについていけなくなりテストは赤点以下、こちらも一桁のテスト用紙を持って帰っても見慣れるくらいになった。現在は主要教科はオール2の状態だ。
たらればになってしまうが、くもんを習っていなかったら、彼の特性や勉強の困難さにもう少し早く気付いてあげれたとよく夫婦で話す。同じことをただただ繰り返しやるのではなく、個別でじっくり時間をかけて理解することを大切にしていたら・・・親としても学校にいち早く相談し、負担を減らすべく支援学級に通うなどサポートを増やせていたら・・・。
とはいえ、インプットの弱さも特性で顕著に出ているので、理解してもすぐに忘れやすい。なので理解→何度か繰り返す(定型発達の子よりこの作業がうんと多くしないと習得できないから、本人も辛いしストレスが大きい。そして習得までに諦めてしまう)→半分以下だが習得していくという流れが理想だったかもしれない。
発達障害も100人いたら100通り。みんなが同じ特性なわけではないし、
得意なこと不得意なことの振りが大きいのは共通だが、一緒ではないので
息子には向かなかった「くもん」を否定するつもりはない。
ただ、この経験が悩んでる発達障害育児の方に少しでプラスになればという想いだけでnoteを書いている。
頑張ったことには間違いないトロフィーは大切にしている。
そして息子の前でくもんへの気持ちはもちろん口にしてはいない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
