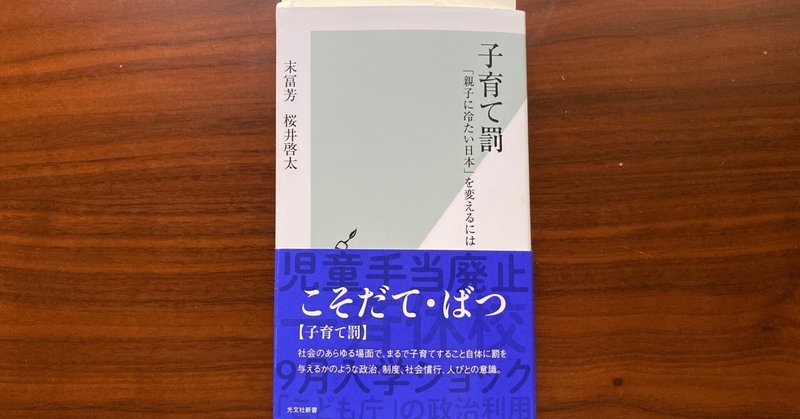
「子育て罰」と子ども家庭庁
「子育て罰」という言葉がある。
社会のあらゆる場面で、まるで子育てすること自体に罰を与えるかのような政治、制度、社会慣行、人々の意識。
児童手当などの「現金給付」、
保育や教育の無償化などの「現物給付」は、
所得の階層ごとに差別化され、
高所得層は給付を受けられず、
中所得層は給付を打ち切られる恐れを抱き、
低所得層はまったく足りていない。
企業は雇用、賃金、昇進などにおいて女性を差別し、
子どもを持つ母親の就労の不安定さは、
このコロナ社会になってますます問題が明らかになった。
そのうえで、企業も社会も、
子育ては母親がやるもの、という意識を強く持っている。
一方若い父親も、長時間労働(在宅勤務でも)や非正規労働の拡大で、
子育てに参加できない状況にある。
高校、大学での教育費は家庭の負担であり、
社会が負担するものではない「親負担ルール」。
「子育て罰」の正体:親、とくに母親に育児やケアの責任を押し付け、父親の育児参加を許さず、教育費の責任も親だけに負わせてきた、日本社会のありようそのもの。
子ども家庭庁が発足した。
子ども家庭庁は3つの部門で子ども子育てに関する課題に取り組む。
(1)全体のまとめ 「長官官房」 【少子化】
(2)すべての子どもの育ちを応援 「成育局」 【妊娠出産】【児童手当】【保育園】【性被害防止】
(3)困難を抱える子どもや親のサポート 「支援局」 【虐待】【ヤングケアラー】【貧困】【いじめ】
教育に関しては文部科学省と連携し、
ほかの省庁に改善を促す勧告権限を持っている。
子ども家庭庁は、「子育て罰」をなくして欲しい。
そうじゃなければ、日本から子どもがいなくなる。
それを後押しするのが有権者だ、
社会をつくっているのはオトナたちだ、
ということを忘れてはいけない。
『子育て罰 「親子に冷たい日本」を変えるには』 末富芳、桜井啓太 光文社新書 2021
