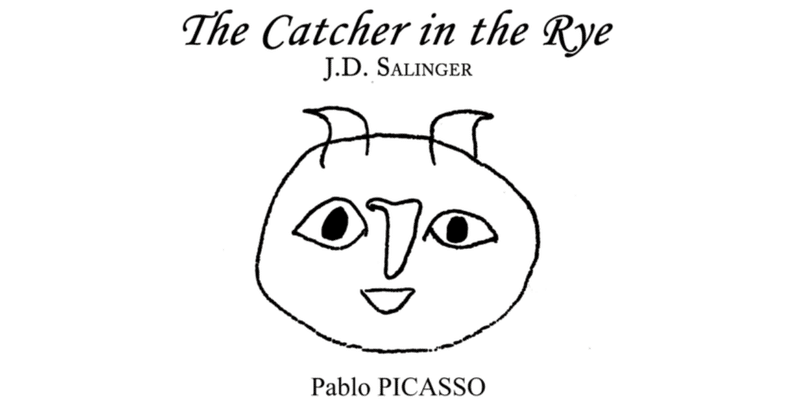
僕たちはみんなホールデン・コールフィールド
今からちょうど100年前の1919年の1月、
ある一人の男の子が生まれた。
J・D・サリンジャー
彼が書いた唯一の長編小説『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(邦題『ライ麦畑でつかまえて』)は
多くの若者を行動に掻き立てるまでに熱狂させた。
感動させたではなく、行動させたのだ。
ただの一小説なのに、だ。
彼がいなければ僕は文学部には進んでいなかっただろうし、
彼がいなければ多くの若者は学校なんてやめちゃおうなんて思わなかっただろうし、
彼がいなければマーク・チャップマンはジョン・レノンを殺そうとは思わなかったのだ。
彼が第二次世界大戦のさなか、ノルマンディー上陸作戦を経て、PTSDに陥り衰弱仕切った精神状態の中生み出した、
ホールデン・コールフィールドという少年に、多くの若者は自分を重ねた。
エドワード・ノートンは
「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』初体験は、ホールデンが自分の友達なんだと思うことじゃない。
ホールデンは自分なんだっておもうことなのさ。文字通りの意味でね。」
と言った。
まさしくその通りなのである。
高校生のあの日、僕はこの本を読み、
この少年は僕自身なのだ、と衝撃を受けた。
文字通りの意味で。
あの日僕は受験生真っ只中だったのだが、気分転換がてらにこの小説を読み、
あの、映画『ライ麦畑で出会ったら』の監督サドウィズが高校生だった頃、
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読み、ホールデンは自分自身だと思い、
サリンジャーに会うために突然旅に出たかのように、
僕も文学部に進む道を選んだのだ。気分転換が、人生の転換になった。
それはもはや共感という域を超えていた。
ホールデン・コールフィールドは僕自身なのである。
だからこそ僕は映画『ライ麦畑で出会ったら』の主人公ジェイミーに一切と言っていいほど共感できなかった。
なぜならホールデン・コールフィールドはジェイミーではなく僕なのだから。
そして同じことを多くの若者が言うだろう。
「ホールデン・コールフィールドは君ではない、僕だ」と。
僕たち若者はなぜここまで、
ホールデン・コールフィールドという少年に
自分自身を投影してしまうのだろうか。
それはきっとホールデン・コールフィールドという少年が、
強烈な個性を発揮しながらも、つかまえることができない存在として描かれているからなのだろう。
彼は時にタバコや酒を嗜み大人のように振る舞い、
時には13歳の子供ように振る舞う。(たしか実際は17歳)
時に正直者であり、次の瞬間には大嘘付きになっている。
社会のインチキを糾弾しつつ、しばらくすると同じことを彼自身も行っている。
彼はある日はホールデン・コールフィールドという少年であり、
別の日には赤いハンティング帽子を被り、死んだ赤毛の弟・アリーになりかわるのである。
これはサリンジャーの「純粋経験」へのチャレンジだったのかもしれない。
ホールデン・コールフィールドを「決定されない」存在として描くことで、
「純粋経験」としての「ホールデン・コールフィールド」を提供する。
読者は、主客未分の純粋経験としてホールデン・コールフィールドを経験する。
だからこそ、主観が入り込む共感ではなく、
ただの経験の事実として「キャッチャー・イン・ザ・ライ」をなぞるのだ。
だから読者は、その経験の元、
「ホールデン・コールフィールドは僕なのだ」と思い込んでしまうのかもしれない。
そしてそんなホールデンは声高々にこう叫ぶのである。
「ぐっすり眠れ、うすのろども!」と。
彼は大人をインチキだと嫌い、
学校という定められた場所を放棄し、
社会に「クソくらえ」を叩きつけた。
ホールデン・コールフィールドはことごとくシステムを嫌った。
彼は高くて硬い壁にたたきつけられる卵だった。
偏差値という定められた数字で評価され、
進学という決められた成功ルートに必死に乗ろうとし、
そんなシステムに雁字搦めにされた中、
自分とは何者かという自己同一性を追い求めている若者の叫びを、
ホールデン・コールフィールドは全て代弁しているのだ。
システムに疑問を感じながらもそこに乗っかるしか無い若者たちは、
システムという硬い壁にぶつかっていくホールデン・コールフィールドという卵の姿に夢中になり、
そしてホールデン・コールフィールドの「境界性」の無い描かれ方のなか、
読者たちはいつしかホールデン・コールフィールドは自分なのだと錯覚してしまうのである。
しかしながら、ホールデン・コールフィールドは
「自分とは何者か」という問いに対する答えを示してくれることはない。
サリンジャーにとっても「ホールデン・コールフィールド」は「答え」ではなく「過程」だったのかもしれない。
そして、読者もまた、「ホールデン・コールフィールド」を自身に重ねつつ、それぞれの「答え」を模索する。
では、サリンジャーはなぜ、どのように、
「ホールデン・コールフィールド」を生み出したのか。
何が彼を「執筆」という行為に駆り立てたのか。
そして彼の作品がなぜここまで若者を熱狂し続けるのか。
その答えのヒントの一つは1月18日公開の映画
「ライ麦畑の反逆児」にあるかもしれない。

楽しみ。
