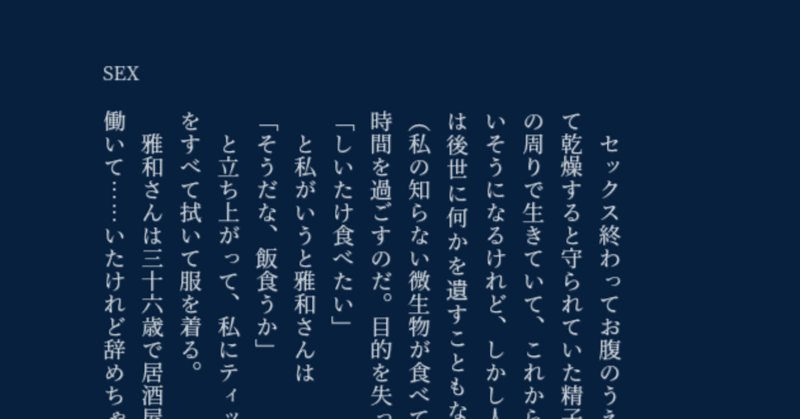
SEX(短編小説)
セックス終わってお腹のうえの熱い精液を見て、生であり死だな、と思う。液体として乾燥すると守られていた精子が死ぬって最近ネットで見た。つまりまだ精子は私の臍の周りで生きていて、これから死んでいくのだ。死を待つのみ。人間と一緒だねっていいそうになるけれど、しかし人間のように延命装置を発明したりはしないから、あるいは後世に何かを遺すこともないから、そして他の生き物の餌になることもないから(私の知らない微生物が食べているのかもしれないけれど)、ただ為せずに死ぬための時間を過ごすのだ。目的を失って、死ぬだけ。死だけ。
「しいたけ食べたい」
と私がいうと雅和さんは
「そうだな、飯食うか」
と立ち上がって、私にティッシュを渡すと服を着て手を洗って台所に立つ。私は体液をすべて拭いて服を着る。
雅和さんは三十六歳で居酒屋で働いていて、私は中学卒業後に進学せずサービス業で働いて……いたけれど辞めちゃって、解放感と後悔がないまぜになった結果スーツのまま未成年飲酒をかましていたら、なんやかんやあって店員の雅和さんのアパートでセックスすることになった。
未成年とやるような大人なんてまともじゃない、ってお母さんはいっていたけれど、私だってそもそもまともじゃないんだから、いまさらまともを求める気にならない。まともをやろうとして失敗したのに、まともを求め続けることになんの意味があるんだろう?
いまは夜中の二時で、雅和さんは次は夕方から勤務らしいから夜更かしをしても問題がないそうだ。私は勤務自体がないけれど、家で母が怒っているだろう。実家暮らしで、社会人とはいえ未成年の私が帰ってこないのは嫌なはずだ。社会人すら辞めてしまったと報告したら殴られるんじゃないだろうか。
少し怖いなあ、と思っていると雅和さんがしいたけをバター醤油で美味しくしたものを大皿に盛って持ってきてくれる。お米はレトルトのものをレンジで温めているらしい。雅和さんはビールを飲みながらしいたけを口に運ぶ。私は炭酸ジュース。美味しい。でも雅和さんは私が未成年飲酒をしているのを見ていたはずなのに、何をいまさら配慮しているんだろう?
温め終えたお米を持ってきた雅和さんに訊くと、
「身体に悪いからだよ」
と答えた。
夜中に食べている時点で身体に悪いと、私は思うけれど。
「別に、私、そんなこと気にしないよ」
「俺が気にするんだ。身体が健康なら、いくらでもどうにかなるよ、この先」
どうにかなる。どうにかなっちゃう。どうかしちゃう。怖い。
食べ終えると雅和さんに促され、シャワーで汗を流す。雅和さんも入ってくるかな、と思って少し待ってみるけれど来なくて、脱衣所には男性もののパジャマが畳んで置いてあった。パンツやブラはないけれど、タイミング的に私の着替えなんだろう。
身を包んで出てくると、今度は雅和さんがシャワーを浴びに行く。
「背中流してあげようか?」
「気を遣わなくていいよ。くつろいでろ」
そういわれても雅和さんの家は正直ちょっとつまらない。テレビもないし、ボードゲームもない。本棚があって、そこに並んでいる漫画はどれも知らないタイトルで、表紙を見る限りむさくるしいものか萌えっぽいものしかない。
萌えっぽいほうを手に取ってみると、どれもこれもスタイル抜群の女の子がモンスターとか主人公から胸や股間を触られたり逆に女子から男子にエッチなことをしたりするものばかりだ。……でもそのうえで恋愛やってる話もあって、女の子が都合のいい感じこそあれ可愛いし、主人公もやや気持ち悪いけどまともに優しくもあるから、殴り合い入ってる話以外は読みやすい。エロも別に、ああ男子向けなんだなって思うだけだ。
性奴隷とかいってるのはさすがに引くけど。
あらすじから厳選して肌に合いそうなものを探し、読んでいると、
「何読んでんだよ」
とパジャマ姿の雅和さんにいわれる。
「くつろいでろっていったじゃん」
「そうだけど……」
雅和さんはなんだか気まずそうだ。ひょっとして恥ずかしいのかな。セックスした仲なのに。未成年に手を出すおじさん以上に恥ずかしいことってないんじゃないの?
「そんなん女が読んで面白いのか? イケメンとかいないだろ」
「別に、女の子が可愛いし。恋愛もの好きだから面白いよ」
「……それ、全巻あるから」
「お、よかった」
読み切る頃には三時になっていて、終盤はエロ控えめで集中して読めたしハッピーエンドでよかったなあ、と思いながら本棚に戻す。寝室に行くと、シーツが代えられていて、雅和さんはベッドに寝転んでノートパソコンをパチパチと打鍵している。
「雅和さん。何か仕事?」
「いや。趣味のブログの下書き」
「ブログやってるんだ。見せてよ」
「駄目」
「ええー。なんで」
「念のため」
せめてどんなブログをやっているのか教えてよ、と訊いてみるけれど答えてはくれなくて、さっさとノートパソコンを閉じてしまう。本人が嫌がっているならばそれ以上の追及はよしたほうがいいだろうか?
ベッドに並んで横たわる。眠くなって、寝る前に雅和さんに訊く。
「ねえ。私とやっちゃったこと、どう思ってる?」
「はらはらしてる。誰にもいうなよ?」
「いわないよ、たぶん」
「たぶんって」
「そんな怖いならやらなきゃいいのに」
「……たまってたんだよ、ちょうど」
「男子ってそんなもんなんかねえ」
いいながら私が思い出すのは、中学の教室で、やりてー! って叫んでいた馬鹿な男子たちのこと。そうじゃない落ち着いた男子のほうが人気だったけれど、叫んでいないというだけで、本当は一緒だったんだろうか? 白けているふりをして、わかる~って思っていたんだろうか?
他人の気持ちなんて私が一番わからないけれど。
「そういや、初めてじゃなかったんだな」
「気にする? そんなこと」
「そういうわけじゃない」と雅和さんはいう。「俺だって童貞じゃなかったし、それに付き合うわけでもないだろ」
ああそっか、と私は思う。よくわかってなかったけれど、キスとかしたけど付き合うわけじゃないよな。私だって雅和さんと付き合いたいわけじゃないし、責任取ってよね、なんていう気もないし。
でも少し寂しかったのは、さっきまで恋愛の漫画を読んでいたからだろうか。漫画の向こうの彼と彼女は、処女と童貞で、最後は気持ちを伝えあってセックスをして結ばれていた。でも私と雅和さんは非処女と非童貞で、酔った勢いと性欲の勢いでセックスをして、それはただそれだけのことだった。
「私たち、まともじゃないね」
と私がいう。
「そうか? 案外みんな、そんなもんじゃねえの」
と雅和さんはいった。
そんなことはないだろうと思う。みんなそんなもんというなら、もっとゆるい世界だったはずだ。みんな私みたいなもんだというなら、雅和さんみたいなもんだというなら、私と雅和さんみたいなもんだというなら、私は辞職なんてしなかっただろう。
辞職。そうだ。雅和さんは居酒屋で六年くらい働き続けられていて、その前は十二年間も同じ会社にいたのだから、私の気持ちはあんまりわからないのかなと思う。その会社が倒産しなかったら、いまでもそこで働いていたはずだ。
雅和さんはきっと、まともだ。私よりはずっとずっとまともだ。未成年とやっちゃうような倫理観はあるけれど、それを大っぴらにする気はないし、しっかり社会でやっていけている、受け入れられているくらいにはまともだ。
私とは違う。
「おやすみなさい」
「おう、おやすみ」
と交わして、私はベッドのうえで背中を向ける。ぽろぽろ泣いてしまうし鼻水も出てしまうけれど、ばれたくないからすすらない。私たち、なんていってしまった自分が最悪だと思う。勘違いしちゃいけない。私は雅和さんよりずっと歪んでいる。まともじゃない人のなかでもきっと、それでもまともにやれる人とまともにやれない人がいて、私だけが後者だ。
鼻水の音を立てまいとするあまり口呼吸になってしまって、それはそれで音として不自然だったみたいで、雅和さんは不意に私を後ろから抱きしめて、いう。
「大丈夫だって。まだ若いから。身体が健康ならいくらでもどうにかなる。勉強して高卒認定とれば大学に行けるし、社会もお前は頑張ってるほうだって思ってくれる。色んな仕事があって、色んなやつが求められてるから。時代が進めばそれはさらに拡張されるから。まだ自分の価値を見捨てるには早いよ」
雅和さんは私が雅和さんと比べて劣等感を抱いているなんて思ってもいない。でも、私が私の価値について失望していることは伝わっている。中卒で仕事を辞めたばかりで泣いてるから、そういうことだと察知されたのだろうか。
「雅和さんにはわかんない」と私はいう。「雅和さんのほうがまともだから。まともじゃないけど、まともをやれるから」
「まともをやるのなんて、最初からは無理だろ。まともなんて結果で、過程は俺も結構ごちゃごちゃだよ。最終的に、五年だか十年だか時間かけて、なんとかまともに近い結果を出せるようになればいいんだ」
「……時間かけるためには、時間をかけさせてもらえるくらい、まともじゃなきゃいけないんじゃないの」
「そんなん、かけさせてもらえなかったら転々とすればいい。自分がダメダメだって知らないやつらなんてごまんといるんだから」
「たくさんの人に迷惑をかけていくことにならない?」
「迷惑をかけ続けなきゃ、何を気をつければ迷惑じゃないのかなんて、本当の意味ではわからないし……完全に迷惑をかけないようになる、ってのは政治家やスターになれるようなエリートでも無理だろ」
そんな風に開き直ることが私にできるだろうか。
できないかもしれない。私はきっと、自分を踏みにじることはできても、他人を踏みにじることはできない。自分を踏みにじってきたから、私はどんどん沈んでいって、高校にも受からなくてお母さんを泣かせて、仕事を始めることができて少しだけ安心させられたのに、自分から辞めてしまって。
先輩たちからしっかり教育してもらえたのに、いつも迷惑をかけてしまうことに引け目を感じて、場に上手く馴染めないことに、どころか遠ざけられ始めていることに耐えきれなくて。
「私は誰にも迷惑をかけたくない。迷惑をかけるくらいなら死にたい」
「死ねばもう迷惑をかけないなんて甘いよ。誰かの死を一生引きずるやつもいるんだ。精神的に迷惑をかけてるじゃないか、それは。死の哀しみ、衝撃に比べれば、生きてるだけの迷惑なんて短期的なことだろ」
「場合によるじゃん。生きててする迷惑の結果、誰かの人生を長期的に捻じ曲げてしまうかも」
「でも生きてさえいれば、たくさん謝ってゆっくりお金を払うとか、めちゃくちゃ殴られておくとか、責任に向き合ったりスカッとさせたりすることもできるだろ。死の迷惑は責任の取りようがないし、それによる鬱憤の行き場がないんだ。死んだばかりのやつを悪くいうのはよくないって道徳もあることだし」
「……生きなきゃいけないかなあ」
「一方的に迷惑をかけたくないなら、生きたほうがいいんじゃない? まあ、考えるのはそっちだよ」
私は生きて死ぬことについて考える。迷惑をかけることについて考える。眠いからか、じわじわととりとめのない連想が始まって、私は生きることはセックスなんじゃないか、なんて思ったりもするけれど、薄い根拠もすぐに忘れて、いつの間にか寝ていて、起きると昼前だ。
「おはよう」
「おう、おはよう」
「これからどうしよう」
「とりあえず家に帰りな」
「ねえ雅和さん、パパ活とか興味ない?」
「そんな余裕ありません。まともに働こうとしなさい」
「だよねえ」
手を出しといてそんなこというなよとも思うが。
私は雅和さんに借りたパジャマを返してスーツを着て、寝癖を整える。雅和さんが作ってくれた軽食を食べると、さあ帰ろうって気持ちになる。
平日の昼間は人どおりが少ないけれど、それでも人目につかないよう気をつけながら雅和さんと一緒にアパートを出る。駅前で別れて、私は家に帰る。お母さんに朝帰り(昼帰り?)を怒られる。雅和さんの件は伏せつつ、仕事を辞めてきた話をすると叱られたり泣かれたりする。殴られもする。きついなあと思う。
雅和さんには迷惑をかけるのが嫌で死にたいといったけれど、正直いって深い部分の気持ちに寄り添ってもらえないだけでも軽く死にたくなる……生きることにうんざりする。
でもまあ、生きていこうという気持ちはある。まともにやれるかは知らないけれど、まともにやれない気しかないけれど、それでもどうせいつか、精液が渇いた精子のように死ぬときがくるのだ。だったら過程がどんなに無為でも有為でも、誰かを嫌な気持ちにしてしまったとしても、それ自体は逸脱ではなく、ごくありふれているんじゃないだろうか? そしてありふれているのならば、雅和さんも言っていたように、どこかに私のいられる場所があるんじゃないだろうか?
……なんて前向きな気持ちが起こるのは明るいうちだけで、夜になるとまた色んなことが気になって暗くなるんだろうけれど、でもまあ精子も朝のほうが活発みたいな話を聞いたことがあるし、精子と卵子から生まれた人間がそういう性質になるのもおかしくはないのかもしれない……とか思いながらお母さんのお説教から解放されたあと検索してみるとそれはデマっぽいみたいで、私はまだまだ精子のことを理解していないなあと思いました。別にしなくていい?
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
