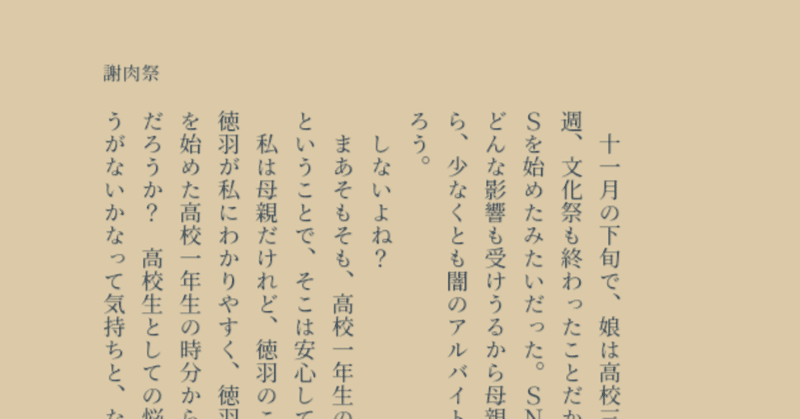
謝肉祭(短編小説)
十一月の下旬で、娘は高校三年生だけれど大学は指定校推薦でほぼ決まっていた。先週、文化祭も終わったことだからと部活を引退して、そうなると気持ちが暇なのでSNSを始めたみたいだった。SNSなんて結局は人の集まりの集まり……の集まりだから、どんな影響も受けうるから母親としては心配だけれど、でも娘は、徳羽は冷静な子だから、少なくとも闇のアルバイトに誘われて応募して犯罪の片棒を担いだりは、しないだろう。
しないよね?
まあそもそも、高校一年生のときから光のアルバイトをしているからする必要もないということで、そこは安心していい……よね?
私は母親だけれど、徳羽のことはわからないところのほうが多い。一番大きな理由は、徳羽が私にわかりやすく、徳羽自身のことを教えてくれないから。それこそアルバイトを始めた高校一年生の時分から、訊かれていないことは話してくれない感じが出てきただろうか? 高校生としての悩みを話すなら、友達とのほうが話が合うだろうからしょうがないかなって気持ちと、なんでよって気持ちがあって、前者は理性から、後者は感情……のなかでも子供っぽい部分から湧き出ている。
私は母親なのに、赤ちゃんのころから十七年間ちゃんと育ててきたのに。でも、ちゃんと育ててきたと言い切れてしまえない/言い切っちゃいけないと思うのが私の理性と大人としての感情で、じゃあきっと、ちゃんと育てられてなんていないんだろう。
それでも私と徳羽は一緒にご飯を食べる。私も仕事で疲れているから、という理由で簡単なメニューばかりで申し訳がないけれど、それでもインスタントにはしていない甲斐あってか、徳羽はいつも黙々と食べてくれる。
その日は徳羽がバイト代で買ってきた林檎があった。私はデザートにそれを剥いて切って、お皿に盛ってテーブルの中央に置いたとき、ウサギにしておけばよかったかなと思った。いつもそんな風に、こうしていたら愛情表現らしくなったんじゃないの、ということに終わってから気づいてしまいがちだ。
でも徳羽はいい子で、
「ありがとう、おかあさん」
と言ってくれる。私は少しだけ安心して、林檎を食べる。
「これ、蜜があって美味しいね。徳羽、ありがとう」
「うん」それから少し置いて徳羽は言った。「美味しいね」
「ねえ、いまのバイトってさ、大学に行っても続けるの?」
「変えると思う。引っ越すし」
「そっか。そうだよね、寮があるもんねえ。面接も小論文も上手くいくといいね、って徳羽は頭いいから大丈夫かな」
「……まあ頑張るよ」
あ、と私は思う。プレッシャーになってしまったかもしれない。
できないかもしれないって可能性を匂わせるの縁起が悪いかなって思っただけだったけれど、できて当然だよねって圧になってしまったかもしれない。実際、指定校推薦を貰えればふるい落とされる可能性は低いと聞いているけれど、ゼロじゃないはずだ。そしてそれは、徳羽だって把握しているに決まっている。
でも、じゃあどう繕えばいいか、というのはわからない。私は本当に馬鹿だ。
「徳羽」とりあえず名前を出して、それから言うことを思いつく。「この林檎、いくらだった? 私も美味しく食べてるし、代金を払ってもいいよ。割り勘でも」
「いいよ別に。あたしの気持ちのためだったから」
「じゃあ、なおさら私は本来、食べないほうがよかったんじゃないの」
「じゃあ、おかあさんも今度、何か買ってきて」
「何かって?」
「食べたいもの。幸せになれるもの。一緒に食べよう」
幸せになれるもの。
復唱しながら、徳羽は幸せになりたいんだ、と思った。それから、徳羽は幸せになれるよな、と思った。私と違って、幸せになれる、きっと。
次の日、仕事帰りにスーパーに寄る。徳羽は今日バイトがあって、基本的にそういうときは軽く買い食いをして帰るから、晩ごはんは私のぶんだけでいい。だから今夜はインスタントで済ますとして、明日の晩ごはんで出すものを探さないといけない。といって、食材そのものはすでにあるから、いま私は私の食べたいものを探している。幸せになれるもの。徳羽と一緒に食べるために。
果物のコーナーを見て、林檎をもう一度食べたいと少し思ったけれど、でもそれだと徳羽はつまらないだろうか。それに、どれが蜜のある林檎なのか、私にはよくわからない。徳羽は狙って選んだのだろうか、それとも偶然に引き当てたのだろうか。梨、甘蕉、苺、葡萄、甜瓜、それらより人を選びそうな果物、色々とあるけれど、食指が伸びない。どれもじっと見ているとグロテスクに見えてしまったり、そうでなければデザインされた玩具っぽく見えてしまったりして、食べたいと思わない。
それに、正直ちょっと高いかな、と思う。
でも高いくらいのほうが幸せになれるだろうか。
というか私は何を食べたいんだろう? わからない。食べたくないものは思い浮かぶ。大人になっても好き嫌いが多い。子供の教育上、嫌いだから食べない、ということをしなくなっただけで。
食欲のない人間じゃない。もしかしたら林檎以外の果物の気分じゃないのかもしれない。だったら林檎を買うべきなのかもしれないけれど、でも徳羽にとってつまらないかもしれないという懸念が邪魔だ。青果コーナーを出る。お菓子のコーナーに入ってみる。二十年以上前、私が学生時代に食べたものと同じお菓子が並んでいる。ロゴデザインだったりイメージキャラクターだったりは変化を見せているけれど、フレーバーが少し増えたり減っている気がしたりはするけれど。チョコレートクッキーやフライドポテトを、しかし私は食べたいだろうか? いまでも美味しいんだろうか? 徳羽は内容量がどんどん減っていると言っていたけれど、味はそんなに変わらないんじゃないだろうか? 大人になってから全然、食べていない。
試しに買うとして、実際じゃあどのタイミングで、どの流れで食べるのが適切だろうかと考えてみると、どうにも捻じ込みづらい気がした。晩ごはんはお腹を空かせた状態で食べたい。食後すぐにお菓子を食べるのはなんとなく違う気がする。時間を置いてしまうと、お風呂や家事をしているうちに、やや気の引ける時間になっていそうだった。休日の午後三時だろうか。でもお昼ご飯を食べると夕方まで空かないほうだし、お菓子を食べるためにお昼ご飯を減らすのは奇妙に思える。そうだ、と私は気づく。大人になってから食べなくなったのは、子供っぽさからの脱却や美容志向というよりは、単純に適切なタイミングがなくなったからじゃなかったか。
……だからこそ、不適切なタイミングで食べるという背徳を楽しむ、そんな幸福を求めるべきだろうか?
なんて考えるけれど、そもそも、罪悪感を楽しめるタイプではないのだ、私は。大して体型を気にしているわけでもないのに。深夜に太るものを食べることの何が罪で何が悪かはっきりとはわからないけれど、でも罪意識も自罰的な気持ちの流れも心に刻まれているものだから、それは理性がわかる/わからないの問題じゃないのだ。
不当な行いではないと頭でわかっていても、悪いことをしているという気持ちにはなる――それでも、不当な行いだと頭でわかっているうえでの罪悪感よりは、いくらかマシなのかもしれないけれど。
お菓子のコーナーを出る。もういっそ、食べものに拘ることもないんじゃないだろうか、大きめの柔らかいぬいぐるみでも買ってきてしまおうか、でもそういうのって万単位かかるんだよな、と思いながら精肉コーナーに通りかかる。
立ち止まる。
お高いお肉、食べたいかも。
買って帰って、洗濯をして晩ごはんのインスタント麺を食べてお風呂を掃除して沸かしてゆっくり入っていると徳羽が帰ってくる。一応確認をすると、今日もバイト先の人と買い食いをしてきたそうだ。
「あのね、徳羽が、私の食べたいもの買ってきたらって言ってたでしょ」脱衣所の徳羽に、ドア越しに言う。「和牛買ってきちゃった」
「え。お肉?」
「うん。割引してたやつだけど、いいお肉が食べたいなって思って」
「そうなんだ。なんか面白い。お肉かあ。あはは」
「そんなに笑う?」
「だってさ」徳羽は言う。「あたし、シャニクサイのつもりでいたから。本当に肉が出てくるとは」
シャニ臭い? って思っているうちに徳羽は風呂場に入る。これ以上はひとりにしてあげたほうがいい、と判断して私は自分で検索する。
次の検索結果を表示しています:謝肉祭。
ああ。なんかえっと、宗教的なやつだっけ? と思いながらヒットしたネット事典をクリックする。カーニバル。肉などを断つ四十日間の節制期間の前に、一週間くらい楽しいことをたくさんして美味しいものをたくさん食べる。お祭りをしたり劇をしたり。厳しい苦行の前に発散して、肉食にしばらくの別れを告げるお祭り。
私の啜り泣く声は徳羽に聞こえただろうか? シャワーの音で搔き消されてくれていただろうか? ごめんね、そうだよね、本当にごめんなさい、とどうしても口から洩れてしまう言葉は、背中を丸めた私の手のなかに収まっていてくれていただろうか?
いまは十一月の下旬で、十二月まであと一週間くらいしかない。
十二月になったら、東北で農業をしている夫が関東のこの家に帰ってくる。
だから徳羽にとって、いまは謝肉祭の時期なのだ。
私にもその権利はあるだろうか?
こんな私に?
お風呂から出た徳羽に、牛肉は普通に焼くのとカレーにするのとどちらがいいかと訊いた。おかあさんの食べたいほうでいいんだよ、と徳羽は言った。私は徳羽の喜ぶやりかたで一緒に食べたかった。
それでも意見をねだるのは気が引けて、結局ビーフカレーにした。ちょうど金曜日で、カレーっぽい曜日だった。いつものカレーよりもコクがある気がして美味しかった。徳羽も美味しいと言ってくれた。
食べながら、徳羽の予定について聞いてみると、別に友達と遊ぶ予定があるわけでもなさそうだった。
「周りに推薦の子がいないから。楽な代わりに仲間外れになってる気分」
「ピリピリしてそうだね。他の推薦の子と仲良くなってみるのは?」
「推薦の人だって知ってるの男子しかいない。たまたま聞こえただけだし、学校の外で会うほど仲良くないし。いちいち確認して回るのも、先生に誰が推薦組ですかって訊くのも、変な気がして」
「じゃあ日曜日どうするの? バイトもないんでしょう」
「わかんない。何もしないのかも」
私はそこで思いついて、いやいやそれはと迷うけれど、言うだけタダかな、と勇気を出して提案をしてみる。
「お母さんと一緒に……遊びに行く?」
「……え、どこに?」
「遊園地とか……?」
なんとなく、謝肉祭という言葉とその説明に引っ張られて、華やかなところに行きたくなっていた。でも、もう十七歳、来年の三月には十八歳になるのに親と遊園地なんて恥ずかしいかもしれない。だから断られる覚悟くらいはしてあった――むしろ、普通の買いものとかよりもハードルが高いからこそ断りやすいかな、という計算すら後づけしていた。
「いいよ」
「いいの?」
「おかあさんの奢りならいいよ」
徳羽はそう言って笑った。ふたりぶんとなると一万円以上はかかりそうだったけれど、まあ謝肉祭ということでいいか、と思った。それに私なんかより徳羽が一番可哀想なんだから、私は徳羽のために我慢をするくらいでちょうどいいのだ。
ちなみに徳羽はまた林檎を買ってきていたけれど、同じ理由で、私は食べなかった。
土曜日。私の仕事は土日休みで、徳羽は朝から夕方までバイトだった。一緒に起きて徳羽にお弁当代をあげて、昼まで家事をして、入浴をした。私は休日のお昼のお風呂が好きだ。服を脱いでお湯に浸かっていると、いまは休んでいいよと言われているような気がする。実際、湯を張ってしまったからには浸からないともったいないし、浸かったからにはしっかりと温まって出ないと身体によくないはずだ。自分でセッティングしたとはいえ、ある程度の言い訳の介在する状況で得る快楽は心にもいい。
お風呂を出て昼食を摂る。朝に炊いた白米と冷凍食品を食べながら、テレビを見る。色々な暴力を、様々な死を、めいめいの生を流し込むニュースを眺めて、どんなことも偶然で、ただそういう流れだっただけなんだよ、と思った。私が生きているのも、徳羽が生きているのも、そういう運じゃなかっただけだ。私が罪深いのも、徳羽が傷ついていくのも、そういう流れだっただけだ。そうだよ。何かのドラマで聞いた言葉を、そんな風に都合よく言い換えたところで、結局は、どうにもならないのだけれど。
謝肉祭。徳羽はどこでその言葉を知ったのだろうか。授業で普通に紹介されるだろうか。いまの世界史の教科書にはどんなことが載っているんだろう? 私は二十年以上前のそれしか知らなくて、ということは全然別物になっている可能性のほうが高い。色んな事件や変化が追記されただろうし、何か訂正もされているかもしれない。
ちょっと覗いてみようかと思う。
徳羽の部屋に行く。棚の教科書もプリントも整理されていて、それで生まれた余剰に独特な絵柄のぬいぐるみとか、色んな小説やエッセイがある。木倉昨日子の本が多い。中学三年生くらいの徳羽の心を掴んだ、徳羽が初めて好きになった作家。いまも家で読んでいるのをたまに見かける。私はあんまり読書をしないので、そういうのにハマれるだけで徳羽は私より頭がいいのかなと思う。そして徳羽は大学に行くわけだから、高校を卒業してすぐ社会人になった私とは、少なくとも学力の面では大きく引き離していくのだろう。
それでいい。私みたいにならないといい。
整頓を荒らしてしまわないように世界史の教科書を探す。ない。じゃあ通学鞄に入れっぱなしなのかな、と思って開けてみる。いつの間にか筆箱を新しくしていて、革っぽいの可愛いな、と思いながら慎重に漁る。
世界史の教科書はそこにあるけれど、私はしかしそれを手に取る前にラブレターを見つける。まだ読んでいないから内容は知らないけれど、白い横型封筒にはハート型シールがついていて、マジックペンで書かれた『太田徳羽様へ』という宛名書きは、見づらくはないが見るからに男の子の字だ。封筒とシールを選ぶとき、ラブレターを出すぞって気合いが王道の装いを構成したのだろうか。ちょっと可愛らしい。
読んでいいのかな?
まあ駄目でしょう、と私は封筒を鞄のなかに戻す。封筒を抜くことで生まれた隙間にそっと挿す。記憶を頼りに出したものを戻して、チャックを締めて、部屋を出る。
うん、ラブレターの存在に気がついたところまでは事故でいいと思う。狙いは世界史だったのだ。ただ、世界史の教科書は結局、手に取ることもできなかったけれど。しょうがない、どうすればいいのって気持ちでいっぱいになってしまったのだから。いまもどきどきだ。
夕食の準備に入る前に昼寝に入ろうとしたけれど、寝つくことができなかった。徳羽はラブレターを読んだのだろうか。開封済みらしい気配はなんとなくしたけれど。いつ渡されて、いつ読んで、どうしたのだろう。そのラブレターには何が書いてあったのだろうか。
そもそもあれは本気のラブレターだったのだろうか。装いがあまりにもラブレター的であるのは、確実に勘違いをしてもらって、文中で指定された場所に向かった徳羽を嘲笑うというような、じっとりとした嫌がらせ行為ではないだろうか。徳羽はそういう目に遭う子だろうか。例えば指定校推薦を受けているという事実が、受験勉強に勤しむ他生徒にそこまでの意地悪をされるほど憎たらしく思われてしまうこともあるだろうか?
徳羽はただ、頑張って毎日ちゃんと学校に行って授業を受けて提出物を忘れず出して、委員会や部活動もまともにこなしてみんなの役に立ってきたことを、認めてもらえただけなのに。徳羽は何も怠惰ではないし、誰かに軽んじられたりガス抜きに消費されたりしていい存在じゃない。それなのに指定校推薦だから、受験勉強を周りよりしなくていいからという理由で嫌がらせをしていいと判断する人がいるのだったら、どれだけ受験勉強に勤しんでいようと、その人は馬鹿だと思う。私は。
でもそれはすべて妄想だ。全然そんなことなくて、そのラブレターは真面目に徳羽のことが好きな人と通じているのかもしれない。徳羽はその相手のことをどう思っただろう? その相手は、どれだけの間柄でラブレターを送ったのだろうか? 友人であるならば、高校生にもなってラブレターに頼るようなことがあるだろうか? いまどきの子はメッセージアプリで告白をすると聞くけれど。でもメッセージで送るとクラス中に共有されてしまうから電話か何かで告白をするとも聞いたことがある。それをいうなら、ラブレターだってみんなに回し読みされることが怖ければ送らないんじゃないだろうか?
どうして私の考えはなんというか、嫌な方向に逸れるのだろう? もう少し平和に、面識こそないけれど純粋ないい人が徳羽にラブレターを出したというくらいの想像に留めることができないのだろうか?
そして徳羽はまだ返事をしていない。受諾したら初めての彼氏になるけれど、そうするべきかということについて私に相談するほど悩んでいるわけではない。単純に、結論は決まっているけれど金曜日にもらってしまったから月曜日まで返事のしようがない、ということだろう。妥当なのはそのあたりだ。
徳羽はどんな返事をするのだろうか? というか徳羽は、彼氏とかそういう存在がほしいのだろうか? 徳羽が小学生のとき、片想いの男の子がいると教えてくれたことがあったから、異性に興味を持たないという子ではないと思う。でも、推薦をもらっているとはいえ面接などの準備はしておかなければいけない、それが終われば男子禁制の女子寮に引っ越す準備も始めることになる状況で、それらを夫が――父親がいる状態で進めていかなければならない状況で、恋愛までする余裕があるのだろうか?
ちょうどいいタイミングで始まる恋愛なんてあんまりない、と言われたらそれまでだけれども。
私と夫の恋人時代を思い返して、なんでこんなことになってしまったんだろうと考えているうちに昼寝を終える時間になる。夕食の準備を始める。バイトが終わるくらいの徳羽から時間にメッセージが来る。いつもより帰りが一時間くらい遅くなるみたいで、忙しい日だったのかな、なんて思いながら豆腐を切る。
尿意で、いつもより早い時間に目が覚める。お手洗いから寝室に戻るとき、徳羽の部屋の前を通りかかる。ドアが少し開いていて、部屋は暗いけれど徳羽が起きている気配がある。徳羽の声が聞こえる。
「うん。お土産とか買ってくるね。……そうだね、ふたりで行こ。来月とか、バイト代が入ったら。……うん、楽しみ。……そっか、またね。好きだよ」
え? 誰? と思いながら私は寝室に引っ込む。女友達相手、というような空気ではなかった。女友達同士で好きとか愛してるとか言うことはあるだろうけれど、そういうときの他意がない前提での気安い「好きだよ」ではなかった。大切にラッピングしてシールをつけてそっと贈るみたいな、絶対に聞き違えられないよう慎重に深いところに安置するみたいな、好きだよ、だった。
誰ってそんなの恋人しかない。私はラブレターのことを思い出す。徳羽はとっくに返事をしていて、男の子と付き合い始めている。試しに付き合ってみるというような感じではなく、徳羽にとってもある程度は真剣な気持ちを携えて、交際を始めているのだ。そして私は、そんな徳羽と彼氏くんの朝通話を少し聞いてしまったのだ。
呆然としているうちに、今日のスケジュール的にそろそろお弁当を作り始めたほうがいい時間になる。とりあえず何も考えないようにして準備をして、それから二度寝を決め込んでいた徳羽を起こす。
徳羽は少しすると秋っぽい可愛い格好で出てきて、朝ごはんを食べると私が準備をしている間に前髪を巻き始める。どこで買ったんだろう、どこで覚えたんだろう。バイト代で買って、友達に教えてもらったんだろうか。中学生のときはいつも一緒に服を買いに行っていたし、小学生のとき三つ編みの仕方を教えたこともあったな、なんて懐古しながら準備を終える。徳羽は私の知らないところで色々なことを知っていて、自分で働いたお金で私の知らないものを買って楽しんでいる。それはすごく健全なことだし、私もそんな風に子供から大人になっていったのだ。
いいことだなあ。
寂しいけれども。
バスで駅に向かうとき、
「どこで買ったの」
と訊いてみると、
「んー? ひみつ」
と徳羽は答えた。
秘密ってあなた。
でも徳羽が自分で買ったものなのだから私が把握しておく理由はない。
ないけれど。
私と徳羽は別の話をときどきしながら、電車に乗った。私はずっと、その服をどこで買ったのか、どう思って買ったのか、どれくらいの値段だったかの話をしたかったけれど、一問目から教えてくれなかったし、それに徳羽は電車のなかであんまり喋る気もなさそうだったから、黙ったままで遊園地に着いた。徳羽はずっと『いなたいはるは』と書かれた文庫本を読んでいた。薄桃色の表紙に、クレヨンで書いたみたいな書体のタイトルと春の田園の写真と、木倉昨日子の名前が刷られていた。私は徳羽の部屋を思い出して、それからあのラブレターのことを思い出した。いや、それはずっと忘れたことなんてなかったけれど。
遊園地のチケットは昨日のうちにウェブで購入してあった。大人一枚と学生一枚。来年また行くことになったら大人二枚になるのだ、と考えたけれど、来年にはさすがに、私とは行かないだろうか。
徳羽とお化け屋敷に行くと、徳羽より私のほうがぎゃあぎゃあ騒いでしまって、徳羽に笑われてしまった。恥ずかしいよおかあさん、と言いながら大笑いしていて、徳羽がこんなに笑っているの久しぶりに見たかもしれないな、来てよかった、と思った。
色々なところに行った。徳羽は家のなかよりずっと元気だ。そういえばふたりで遊びに行くことすら、二年くらいしていなかった気がする。高校生になる頃には徳羽の世界は完成して、そこに私の入り込む余地すらないような気がしていた。自立しようとしているのだから手を離しておいてあげるべきなんじゃないかと考えていた。けれど、こんなに楽しいのなら、ゆっくりな遊びも速くて怖い遊びも楽しめるのなら、余計なことを考えずにいっぱい一緒に遊んでも問題なかったのではないかと思った。
余計なことを考えずに。後ろめたさもきっと、必要なかったのかもしれない。
私たちは同じ傷とともに、同じ苦しみを前に、同じ祭で幸福と別れる。
母と娘である前に、友達のようだった。
夕日がきれいに見える時間、私と徳羽は観覧車に乗った。そういえばこの観覧車には、徳羽がもっと小さいとき、小学生のときにもふたりで乗った。夫は高所恐怖症だから、三人で遊園地に行ったあの日、初めてふたりきりになれた時間だった。
徳羽はそのとき、片想いの男の子がいるの、と教えてくれた。私だけしか聞いていないときだから、言ってくれた。夫が聞いていたらどう反応したか想像できないけれど、徳羽は、夫にだけは、そういう大切な話をしようとしなかった。初めて友達と絶交をすることになったときも、初めて生理がきたときも、初めて好きな作家ができたときも、ふたりきりでいるときだけ、夫が聞いていないときだけに話してくれた。私は、徳羽が本当に大切な話をするときの言葉の質量を感じていたから、夫に横流しするようなことはしなかった。
言葉の質量。
早朝、電話の向こうの誰かに贈呈していた、好きだよ、の質量も、同じくらいだったかもしれない。
夕暮れの、何かを探したくなるような光が、景色を見つめる徳羽の前髪を茶色く彩っていて、夫に似た美しい瞳を煌めかせていて、素敵な女の子に育ったな、と思った。まだ子供の顔だけれど、高校一年生のときより、色んな経験を徳羽は積んできたし、色んな知見を徳羽は吸ってきたんだと思う。
そしてそんな蓄積と吸収で、私の知らない徳羽を、作ってきた。これからも作っていく。彼氏とふたりきりのデートで。大学の女子寮で。私の知らないところで。私の知らない人と一緒に。喜ばしいことだけれど、寂しいとも、思ってしまう。私の子供の部分が、感情的な自分がどうしても、疎外感に悲鳴を上げている。
だから、つい、
「ねえ、徳羽。徳羽の彼氏って、どんな人?」
と、訊いてしまった。
徳羽は一拍遅れて、大きな音でも鳴ったみたいにこちらに顔を向けた。
「どうして?」
どうしてそんなことを訊くの?
どうしてそんなことを知っているの?
どっちもを、訊かれている。
「……朝、電話してるの、聞こえて。部屋のドア、ちょっと開いてて。いるんだって、思った」
徳羽はそれを聞くと、鼻から深く息を吸って、口からゆっくり息を吐いた。
「昔さ」私は言う。「小学生のころ、一緒に遊園地で観覧車に乗ったときには。そのときには、好きな男の子のこと教えてくれたなって」
「そうだね」
「その子に振られちゃったときも、私に教えてくれたよね。お父さんがいないときにさ」
「そうだね」
「ねえ、どうしてそういう話、してくれなくなったの。どうして徳羽は、私に徳羽のことを、教えてくれなくなってしまったの」
「なんで」徳羽は言う。「なんで、知りたいの」
「だって。だって、私は。私は徳羽の、お母さんだから。私には徳羽しかいないから。……徳羽しか、子供が、いないから。徳羽には、色んな人が、いるだろうけど」
「……職場に、友達とか、いないの。おかあさん」
「男の人が、多くて。それに、忙しいし」
「そっか」
「徳羽」私は徳羽の目を見て言う。「私、寂しい」
「ごめんね、おかあさん。その寂しさ、どうでもいいです」徳羽は言う。
「どうでもいい。どうでもいいよね。そうだよね。寂しいかどうか、どうでもいいよね。ごめん、徳羽。でも、なんで、どうでもいいの」
「だってあたし、おかあさんのこと大嫌いだもん」
ああ言葉って胸を刺すな、と思った。夫と付き合っていたとき以来な気がする。麻痺させて久しいその痛覚が呼び起されて、私はもう何も聞きたくなかった。ぎゅっと目を瞑ると、ぼろぼろと涙が出てきてしまった。誰かに拭ってほしかった。徳羽が撫でてくれればいいと思った。
「辛そうな顔されてもさ、あたしは何もしないよ。寂しいとか言われても、絶対に助けないよ。泣かれても、汚いなってだけだよ。おかあさんは、あたしのことなんて助けてくれなかったから」
おとうさんがあたしに何をしても。
おかあさんは何もしなかったから。
徳羽は振り下ろすみたいにそう言った。
「ごめん、徳羽。ごめん。ごめんなさい。本当にごめん。お父さんの邪魔したらもっとイライラされて、徳羽がもっとひどい目に遭うって思って。何もしないほうがいいと思ってたから。何もできなかった」
弁解なんてするべきではない。私だって、その不当性にはとうに気がついていた。悪化を避けて改善を目指さないことを、善だとは思っていなかった。私自身、その罪深さは知っていた。けれど、流れを変えることなんてできなかった。夫の帰還を前に、謝肉祭を求めるほど徳羽を苦しめているこの状況を、覆すことなど、頭の悪い私にはできない。それに、夫に虐げられていたのは徳羽だけではなかった。私だってたくさん傷つけられてきた。だから歯向かうことが恐ろしかったし、だから徳羽と同じ立場にいるのだと、思わないと言えば嘘になる。そしてもしかしたら徳羽だって、やっぱり親子だし女同士だし、仲間のように思ってくれているんじゃないかと、……そんな風に期待していたのだと、いま思い至って恥ずかしくなる。
罪悪感に浸りながら。
それでもちゃんと育ててきたのだから。
これくらいの罪は許されると――思っていた。
私の感情のなか、子供っぽい部分が、そう信じたかった。
「中学生くらいまでは、そう思ってたよ。だからしょうがないよねって思ってた。おかあさんも諦めるしかないんだなって。むしろおかあさんは、あたしが余計に痛い目に遭わないように気を遣ってくれてるんだって思ってた。わかってたから、おかあさんのこと、中学まではね、好きだった」
でも、と徳羽は言った。
「でも高校で、ちょっと色々と友達できて。バイトとかで色んな大人と接して、読書とかも続けてたら、気づいたよ。おかあさんって、自分が楽できそうな言い訳に乗っかってるだけだなって。楽したくて、そういう安易な誘惑に弱いんだろうなって。それでもう、嫌になりました」
だからあたし、恋愛の話は絶対しません。
おかあさんに自分の幸せのこと、何も知られたくないので。
観覧車を降りる時間がやってきた。
遊園地を出て家に帰るまでずっと無言で、家に帰ってからもずっと無言だった。
徳羽は、言い過ぎたとかそういう風に謝ったり修正したりしなかった。それはつまり、徳羽にとって歪みようのない真実であり、ありのままをきちんと伝えたということなのだと思う。
言うに過ぎてなどいない、その結果として私が黙りこくっていても何も問題に思わないということなのだと思う。
しょうがない。ああだこうだと理由をつけて子供を守ってこなかった私が悪い。それなのに彼氏がどうとかのプライバシーを聞き出そうとした私が悪い。徳羽がいつまでも私に、なんだかんだ娘として母に、情を持っていてくれているなんて期待した私が悪い。
十一月が終わって、夫が帰ってくる。謝肉祭は終わって、私と徳羽の幸せは断たれ、苦しみがこの家を支配する。徳羽は家に帰ってくるのを限りなく遅くして、夫が寝たあとの帰宅となるように調節したりするけれど、そのせいである朝、帰宅時間が遅いという理由で叩き起こされる。夫に髪を掴まれて部屋から台所に引きずられていく徳羽を見ながら、両手の空いている私はどうすればいいのかわからない。どうしたいのかもわからない。わからないから何もしない、を、何もできない、に言い換えている自分に気づく。
こんなことだから徳羽に嫌われるんだと思う。
嫌われて当然だ、こんな親は。
……なんでよ?
それでもバイトのときにお昼のお弁当を用意してあげたり晩ごはんだって作ってあげたり遊園地のチケットとか奢ってあげたりしていたのに。彼氏とか連絡するスマートフォンだって私が高校入学の祝いに携帯ショップに連れて行って買ってあげたものだし、中学や高校の制服だって買ってあげたものだし大学の学費だって奨学金じゃなくて私と夫で出してあげることになっているのに? 清潔な服や家で過ごしていられるのも私が家事を頑張っているからなのに? 生理用品はあなたが自分で買っているけれど、そもそもあなたに生理への対処について色々と教えてあげたのは誰だったっけ? そもそもといえばそもそも、あなたがいま生きていられるのも私が産んだからなのに?
母親として頑張ってきたことすべてが、夫から守らないことで帳消しになるの?
でもそれは親としての義務だよ、育児ってみんなそうだよ、そういうのをやらなかったら私自身だって虐待の罪を背負うことになるんだよ、と理性の私が言うけれど、奔流がとめどない。感情の子供の部分が、遊園地で徳羽から与えられたストレスに狂って暴れているのを感じる。
違う。
しょうがないことだから。
徳羽は私を嫌いになる権利があるし、嫌いになる理由としてはきっと十分だから。
じゃあ私も徳羽を嫌いになってもいい?
徳羽だって私なんかに愛されたくないんじゃなくて?
娘なのに親を愛さないことが許されるなら、親なのに娘を愛さないことだって許されていいでしょう?
そんなことを思ってしまうということは、少なくとも感情の私は、徳羽のことが嫌いになったのだろうか? 罪深い私が、傷ついた娘を?
もしもそうだとしたら、いっそ私だって、夫と一緒に徳羽を虐げてしまおうか、なんて考えがふらりと過る。
でも、それはひとまず却下する。
嫌いであること、嫌われていることはしかし、暴力を振るっていい理由にはならない。
さすがにそれは違うって。
馬鹿な私が知らないだけで違くなんてないのかもしれないけれど、とりあえず私はさっき徳羽のことが嫌いになったばかりで、突然の気持ちの変遷に混乱しているから、そこまで思い切ったことができるほどの、いい言い訳が思いつかない。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
