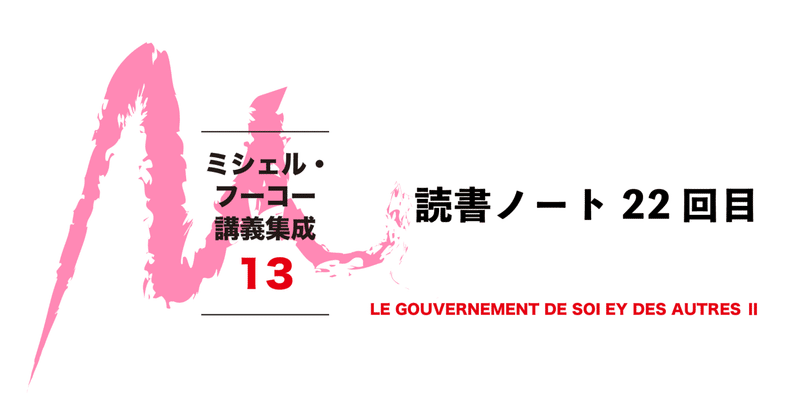
[読書ノート]22回目 2月29日の講義(第一時限〜第二時限)
講義集成13 1983-84年度 207頁~241頁
今回のまとめ
キュニコスはホームレス
芸術への期待値……高っ!
もし、真理がなかったらどうする
今回ははじめにキュニコス主義の特徴が整理され、そのあと、キュニコス的様式の現代的意義とも読める内容になっています。とくにクリエイターの方に読んでいただきたい回です。
キュニコス主義の特徴
外見、行動、態度
(『ヘラクレイオス駁論』で描かれるキュニコス主義の人とは)杖を持つ人、頭陀袋を持つ人、マントを纏う人、サンダル履きあるいは裸足の人、髭もじゃの人、薄汚い人であり、また、彷徨する人、どこにも溶け込まない人、家も家族も家庭も祖国も持たない人であり、物乞いする人である。
この種の生【生き方】がキュニコス主義哲学と完全に一体をなしている(単なる飾りではない)。この生の様式は、そのパレーシア、その「真なることを語ること」との関係において、非常に明確な機能を持っている。
①道具的機能
この生の様式が「真なることを語ること」に対して、可能性の条件の役割を果たすということ。(人に危険を顧みず率直に語るためには)いかなるものにもつなぎ止められないようにしなければならない。つながりから自由でなければない。それ【家族や集団に属さないこと】がパレーシアの行使のための可能性の条件である。
②縮減の実践
通常は受け入れられ万人に受けれられている【常識や習慣、しきたりや信条】けれど、自然によっても理性によっても基礎づけられていないような、【良き生活にとって】無益な責務のすべてを縮減【=ミニマムに】するという機能がある。無益なしきたりのすべてと余計な意見の全てを縮減するもの。
③真理表明術
人間の生にとって最も基本的で最も基礎的な本質を構成するものを、還元不可能な裸の姿で明るみに出すこと。『アルキビアデス』で見いだされたソクラテスの手続きは、自己自身への配慮から出発して、ラディカルに分離される魂の存在そのものがいったいどのようなものであるかを定義しようとするものだった。対してキュニコス主義には逆の操作がある――生を生自身へと還元しようとする操作、生が真理においてそうであるものへ、生を還元しようとする操作があるということ。
ようするに(①②③を通して)キュニコス主義によって、生、生存、ビオスが真理表明術と呼びうるようなものとなる。
キュニコス主義の核心
真理の証人であること
「マルテュローン・テース・アレーテイアス」(真理の証人であること)この表現は後の時代のものだが、キュニコス主義の特徴を【ある一面でよく】示した言葉である。それは、語の最も具体的で最も物質的な意味での一つの生存ないし一つの生の形式によって与えられ、表明され、その真正さが示される証言である。身体、服装、行動様式、働きかけたり反応したり行動したりする仕方などによって――ある種の生のスタイルのなかで、真理の身体そのものが可視的となり、読解可能になるということ。つまり、キュニコスのスタイルのテーマとは真理表明術としての生であり、(言い換えると)自分の生のなかで、そして自分の生によって、真理のスキャンダルを起こすことである。
出現と歴史
紀元前四世紀にその出現を位置付けることができて以来、ヘレニズム時代から少なくともローマ帝国の末期に至るまでキュニコス主義によって実践され、さらにはそれをはるかに超えて【現代まで】多様な形態のもとでさまざまな目標とともに続けられることになる。
西欧の歴史全体を貫く一つのカテゴリー
キュニコス主義のテクストはほんのわずかしか残っておらず、学説としてはいわば消え去ってしまったといえる。しかし、ヨーロッパの長い歴史のなかで、キュニコス主義的生存様式を【現代まで】伝えることができたものとして、3つの要因、3つの要素が見いだされる。
A. キリスト教古代
ヨーロッパへと移転し浸透する際の最初の支えはもちろん、キリスト教文化によって、つまり修徳主義の実践と制度によって[構成された]。キリスト教の黎明期に、キュニコス主義的実践とキリスト教的修徳との非常に顕著な混交があったということ、これは驚くべきことではない。注目すべきは、キリスト教の修徳と修道院制度を介して、非常に長い期間にわたって伝達されたということである。
フーコーはその歴史の具体例として、托鉢修道会やフランシスコ会修道士、ドミニコ会修道士などを挙げます。逆に言えば、その歴史的研究を示唆するだけです。
そして、その研究を行ったのが、ジョルジョ・アガンベンになります。彼のホモ・サケルシリーズの構成の最後の二冊、特に『いと高き貧しさ』でそれらについて研究され、その上で「生の形式」を意味づけたのが『身体の使用』です。
(キュニコス主義的実践による)生の選択、生の簡素化は、キリスト教の歴史全体を通じて、教会、その諸制度、その裕福化、その風紀の乱れに対して立ち向かったあらゆる改革の努力のなかで、単なる一つのテーマだったのではなく、とりわけ活発で強力かつ強固な一つの実践だった。(キリスト教にとって)反制度的キュニコス主義、反教会的キュニコス主義があったということ。
なぜ、いわゆる他の宗教改革よりも「強力かつ強固」だったといえるのか――それはイエスの生き方そのものであったからと言える。そのことは、もちろん上述のアガンベンの著書でも知ることができるが、とりわけ私たちにはイエス本人についての高水準の研究があるので紹介しておく。田川建三『イエスという男』作品社……もちろん多くの国で翻訳されている。イエス本人は、なにより生活は簡素であり、反制度的で反教会的であったことが、厳密なエビデンスとともに描かれている名著である。
B. 革命的運動
宗教的実践ではなく政治的実践のなかに見いだされるが、それはもちろん革命的運動である。キュニコス主義的考えは、革命的実践の一部をなすものであり、一九世紀を通じて革命的運動がとった諸形態の一部を実際になした。そしてそれはただ単に政治的な企図であっただけではなく、生の形式でもあった――より正確に言えば、革命は、ある種の生の様式を決定する一つの原理として機能したのである。
生を革命的活動として、あるいは逆に革命的活動を生として、定義し、特徴づけ、組織し、規則づけるやり方を、便宜上「戦闘的態度」と呼ぶことにする。
フーコーが示している年代から分かるように、ここでの「革命的運動」とはフランス革命でもアメリカ独立革命でもない。ソビエトにつながる十月革命のことである。この革命はたしかに「戦闘的」になっていくが、その初期の平等主義(民族で区別しない)、平和主義、そしてまさに「真なることを語る」、ある意味で理想的な民主主義的な特徴と、その具体的表明にキュニコス的機能を見ていると思われる。もちろんフーコーは、その後のソビエトの歴史は知っている。講義では話されなかった講義ノートには以下の文章がある。「革命的運動においては、それが組織的形態によって支配されてしまうやいなや、つまり、革命的運動が政党として組織化され、政党が、ノルム【規則】に完全に従う画一性、社会的かつ文化的な画一性によって「真の生」を定義するやいなや、キュニコス主義的機能は単に周縁的なものになる、ということである。」これは下記の①〜②への移行で起こることであり、フーコーがわざわざ言及せずともよく言われることでもある。だからこそ、それらとは別の③にフーコーは興味を示しているのだろう。
全体的にせよ部分的にせよ革命に捧げされた生としてのその戦闘的態度は、十九世紀および二十世紀のヨーロッパにおいて、3つの大きな形態、側面をとったと言える。(興味深いのは③である)
①社会性と秘密という形態のもとでの革命的生、秘密結社における革命的生(現在の可視的な社会に対抗するための結託や千年王国思想の目標に従った不可視の社会性の構成)。
②可視的で認知され制度化された組織を持ち、その目標とその活力を社会的かつ政治的な領野のなかで価値づけようとする戦闘的態度がある。それは、組合組織のなかに、あるいは革命的機能を担う政党のなかに現れ、自らを認知させる態度のこと。
③生存のスタイルという形態における生による証言としての戦闘的態度。革命的な戦闘的態度に固有のこの生存のスタイルは、社会のしきたり、習慣、価値と真っ向から対立すべきものだ。それはその恒常的な実践とその無媒介的生存によって、真の生としてのもう一つの生の具体的な可能性とその自明の価値を、直接表明しなければならないものだった。
以上の、革命的な戦闘的態度の3つの側面(①秘密結社②制度化された組織③生による証言)は十九世紀において支配的に現前していた。……と言うとき、その側面(特に③)は今や完全に消え去ってしまったということ(が言いたいの)ではない。(フーコーはフランス共産党の制度的構造のなかでそれらが転倒されているものの存在していることに言及しつつ)革命的政党を自称する諸々の政党において、受け入れ難い真理のスキャンダルとしての革命的生というキュニコス主義的な考えと、戦闘的態度のための条件としての型どおりの生存という定義とが、どのようにして対置されることになったのか。これはまた別の研究の対象である。
C. 芸術
(芸術については)非常に複雑な歴史がありおそらく古い時代まで遡らねばならないだろう。古代においてはサテュロス劇(喜劇)、中世にはファブリオー(韻文の多い小話)がそれに属するであろう文学のまるごと一つの側面を一種のキュニコス主義的芸術とみなす必要がある。またバフチン【ミハイル・バフチン ロ シ アの文芸理論家】は(研究対象した)文学をとりわけ祝祭とカーニバルに関連付けているが、私(フーコー)が思うにその文学は、間違いなく、キュニコス主義的生を表明するものでもある。
しかし、キュニコス主義の問題が非常に重要なものとなるのは、とくに近代芸術においてであると思われる。ルネサンスにヴァザーリ(『画家・彫刻家・建築家列伝』)において見いだされる芸術家の生とは――芸術家は芸術家である限り通常の規模や通常のノルムに完全には還元されえないような特異な生のみを送らねばならないという(すでに定説となっていた)考えである。それが十八世紀末から十九世紀の初めにかけて、異なる何かが現れる。それは、芸術家の生が、それがとる形式そのものにおいて、芸術がその真理においてそうであるものについてのある種の証言を構成しなければならないという考えであり、これは近代的な考えである。それは二つの原則に依拠する。
まず、芸術は、生存に対し、他のあらゆる形式と真っ向から対立する一つの形式、つまり真の生の形式を与えることができるという原則。次に、芸術家の生が芸術のおかげで確かに真の生の形式を持つとすれば、逆に生の方は、その生のなかにそしてその生を出発点として根を張るあらゆる作品が、芸術の王朝および芸術の領域に確かに帰属していることを保証する、ということ。
反プラトン的、反アリストテレス的なものとしての近代芸術
これがすべてではない。近代世界のなかで芸術が確かにキュニコス主義の運搬手段であったと言えるもう一つの理由がある。それは、芸術はそれ自身、現実とのあいだに、もはや装飾や模倣に属すのではなく、生存の暴露、その露呈、その研磨、その掘削、生存にとって基本的なものへの暴力的還元などに属するような関係を打ち立てなければならない、という考えた登場したこと。十九世紀半ば以来、ますます顕著なやり方で、α. 芸術は、下にあるもの、低いところにあるもの、一つの文化において表現の権利あるいは少なくともその可能性を持たないものが闖入する場所として構成されるのだ。
基本的なものが闖入する場所としての芸術――まさしくここから、芸術は、文化、社会的ノルム、美学的な諸価値や諸規範に対して、還元、拒絶、侵害といった論争を呼ぶ関係を打ち立てる。すなわちそれは、β. 先立つ諸行為の各々から出発して設置されたり演繹されたり帰属されたり導かれたりした一つひとつの規則を、後の行為によって絶えず拒絶し棄却する運動となるということ。
そこでは、文化のコンセンサスに、その粗野な真理における芸術の勇気を対立させることが問題となるような、本質的に反文化的と呼びうるような一つの機能が果たされる。近代芸術、それは、文化におけるキュニコス主義である。そして、我々のこの世界において、不愉快な思いをさせるかもしれないというリスクを冒す勇気を備えた「真なることを語ること」は、芸術のみではないにしろ、とりわけ芸術のなかに集結しているのだ。
実際の講義はここで終わっているが、講義ノートにてもう一つ……「ニヒリズム」について詳細に書かれている(つまり4つ目の要素)。
D. ニヒリズム
ニヒリズムについて【私たちは】今日それが考察されているような側面においてのみ考える習慣を捨てなければならない。十九世紀におけるキュニコス主義と懐疑主義は、真理に関する倫理の問題を提起する二つのやり方であり、ニヒリズムにおけるそれらの交差は、西欧文化における本質的で中心的な何かをはっきりと表明している。それは、真理への配慮が真理を絶えず問いに付すとき、そのように問うことを可能にする生存の形式とはいかなるものであるか、真理が必然的でないとしたら、必然的な生とはいかなるものであるか、といったものだ。
ニヒリズムの問題は、神が存在しないとしたらすべてが許される、ということではない。むしろ、次のように問わなければならない――もし私が「何も真でない」に直面せざるをえないとしたら、いったいどのように生きればよいのか、と。学説の歴史はたいして重要ではない。重要なのは、生存の諸技法の歴史を打ち立てることだ。
数多くの多様な真理を発明し、かくも多数多様の生存の技法をこしらえたこの西欧において、キュニコス主義は絶えず次のことを思い起こさせる。すなわち、本当に生きることを望む者にとって不可欠なのはほんのわずかな真理であり、本当に真理に執着するときに必要なのはほんのわずかの生である、ということを。
今回は以上です。次回は、古代キュニコス主義に関するもっと重大な事柄に戻るそうです。
私的コメント
まず、形式的なことから。今回の話題は私にとってそれぞれとても興味深く、この「コメント」の場所でそれぞれ言及することは、煩雑でもあるし、読解上のヒントを含ませる意図も含めて「注釈」を多用しました。ただ、記事を書いていて一番楽しかった回なんじゃないか、と思っています。
次に、弁明を。「コロス(12と13の間の感想文)」で革命が諦められていると書きました。違っていましたね。フーコーは革命について意外としぶとく諦めていないようです。ただ、「コロス」で言及しましたがトロツキズムについての知識がなかったら、今回の「B. 革命」に関する文脈をよみ違えていたでしょう。そういう意味ではとても良かったと思います。
あと良かったというか、(別ジャンルですが)直前の記事の最後で芸術の一部である文学について――しかし、いずれにせよ「クリエイター」の皆さまに語りかける形で芸術について一言だけ言い添えたのですが、まさに今回の「C. 芸術」の部分は、フーコーの言葉で濃密に、現代的意義の道筋が語られたと思います。このパートは、ほとんど手を加えていません(だから若干長くなっています)。「芸術家」を「クリエイター」に置き換えて、読んでいただきたいと思います。もちろん、皆が(この例えが適切か分かりませんが)バンクシーみたいにはなれません。もっとずっと平凡化しつつ、しかし現代においてクリエイターに特異なあり方としてのヒントがあると思います。
他方、隠し玉的な「D. ニヒリズム」については(一応)私の領分ですから言葉を加えてもいいでしょう。フーコーの講義に内在的に読むなら、ニヒリズムは、冒頭のキュニコスの特徴(①②③)を担える哲学分野だ、と肯定的に捉えるべきでしょう。
少し解説的に話を広げると、真理がないというのは、パレーシアの中核がないということです。しかしながら、現代に生きる私たちは、古代ギリシャの人たちが想定していた――あるいは近代哲学がそれを受け継いだとして、近代哲学の人たちが想定していた「真理がない」ことを知っています。そのうえで、まだ旧来型の「真理」を追うのは、言葉の厳密な意味で哲学者(見つかりもしない知を愛する人)=バカであって、「真理がない」を乗り越えることができるのはニヒリズムだけだ、と言えるでしょう。「もし私が「何も真でない」に直面せざるをえないとしたら、いったいどのように生きればよいのか」というのは、そういうことです。つまり、現代の哲学でキュニコス的でありうるのは、ニヒリズムを乗り越えた立場だけです……こういう風にある程度言い切っているのは、(ニヒリズムというより)ニーチェ解釈について、フーコーは(ここは完全に推測ですが)ハイデガーじゃないことはもちろん、ドゥルーズでもなく、おそらくピエール・クロソウスキーの解釈に近い立場をとっていると思うからです。『ニーチェと悪循環』は、新品はなさそうですが、まだ手頃な価格で入手できるので興味がある方は(手にとれたら)手にとってみてください。
もしサポート頂けましたら、notoのクリエイターの方に還元します
