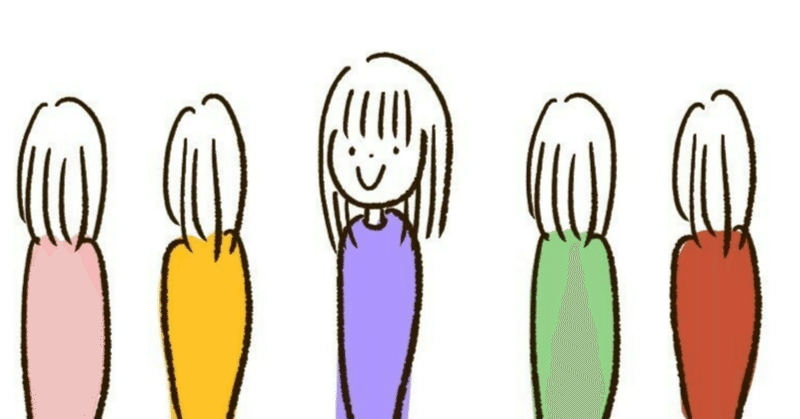
サリヴァン読書ノート:まえがき
次の記事は、20世紀の前半を生きたアメリカの精神医学の先駆者、ハリー・スタック・サリヴァンの一つのテクスト(初出は講演)について読書ノートとします。今回は、その外堀の情報整理です。……追記で関連する短い出来事を参照してみました。
テクストの読解(の不完全性)について
「個性」という幻想――を読んでみます。内容に関わることですが、文字通り明白なので言及しておくと……サリヴァンはこのテクストで「個性」や「自己」といったものを幻想=科学的に根拠のないものと主張します。「人格」についても(仮説内仮説としての)サリヴァンなりの定義があるのですが、それは読書ノートに残しておきましょう。
私の過去の(哲学関連の)記事――とりわけイタリアン・セオリーや源流としてのヴェイユと同じテーマについて、精神医学+若干のアメリカ哲学の観点から述べられている(短い)テクストというわけです。哲学と違ってある種、科学的な率直さで「個性は幻想」と述べられるのは、それに賛成か反対かは別にして爽快と言えるでしょう。私の精神医学の素養は無いと殆ど無いの間ぐらいであることを前提にしつつ、ある程度まで妥当性を提供できるであろう哲学的視点からこのテクストを読んでみようと思います。以下に私の臆見(=限界)を整理できる範囲でやっておきます。
精神医学は心理学ではない
念のため最初に強調しておきますが、これは私の臆見です。学問的正しさはないですし、読者が同じように考える必要はないものです。
精神医学は、名前の通り「医学」です。心理学は、「学問分野(=科学)」です。私が学生時代に科学哲学の恩師といえる人から第一に教わったことは、「医学」は「科学」ではない――(5000円札の)「野口英世は偉人ではあるが科学者としては有能ではない」という文脈だったと記憶しています(野口自身、自覚があったようです)。まぁ、このことは、科学とは何かに関わるのですが、記事に直接関係しないのでここで止めておきましょう。
もっとも実際は、精神医学と心理学は無関係ではありません。臨床の場面では重なっている部分もあるといえるでしょう。ここからが(記事として)大事なところですが――サリヴァンの精神医学は後の社会科学に大きな影響を与えたという点でも、心理学よりよほど科学的であるということです。さらに私に引き寄せると、よほど哲学的であるということでもあります。
精神医学の素養がない
テクストは精神医学の素養がある人に向けられた講演が元になっています。つまりテクストにおける、その種の専門用語のほとんど全てを私は正しく理解していないか、分からないので読み飛ばしているということです。また、こちらも重要なことですが、(フロイトやホワイトヘッドの名前が挙がるものの)哲学とのつながりについても正しく理解していないか、背景を(時系列含め)充分に把握していません。
そして、これらを補うことなく読んでいくつもりでいます。つまりテクストの読解の体を成さない……まぁ、哲学の記事だって専門的ではないので程度の問題ですね。ただ、次のことは確実です――哲学のテクストのように文脈を丁寧に追っていかない……追えないからです。
テクストについて
言うまでもなく、日本語訳で読みます。具体的には、『個性という幻想』阿部大樹編訳、講談社学術文庫、2022年に所収されている「「個性」という幻想」というテクストです。一冊の本のタイトルと同じなので紹介する側としてはややこしいですが。
この『個性という幻想』は、上記のように最近出版された、日本語版オリジナル論集です。サリヴァン・アンソロジーといったところでしょう。私のように手軽に読みたい人にはありがたい出版物となっています(以前から知ってはいたんですがこの前のアマゾンセールで買ったわけです)。
サリヴァンの論争的主旨
解説文などによれば……このテクスト(講演)は発表された当時から、ラディカルな危険思想として受け取られたとのこと。サリヴァンの主張を端的に記すと「独立ないし自立した人間というのが机上論に過ぎないことの指摘」です。仮にこの主張に一定程度の科学的水準でエビデンスが明らかになっているとして、依然として(現代の)私たちは「個性」があることは当然と思っています。読書ノートではその理由も私なりに考えてみます。
サリヴァンは「患者一人ひとりを診るのではない精神医学」を提唱した先駆者なわけですが、学的系譜としては、いわゆる(学際的であることが特徴である)アメリカ社会科学を主導したシカゴ学派に属しています。したがって、学的にはサリヴァンの主張は、むしろシカゴ学派らしいと言えるもので、論争的なものがあったとしたら、それは欧米の常識との間だと思います。
サリヴァンのポジション
個人という言葉を使ってはいけないのかという質問への回答
講演なので質疑応答の時間があったようです。上記の質問にサリヴァンは次のように答えています。
ここまでに散々繰り返してきたとおり、人間が個々独立した個体であるというのは可能性の一つに過ぎないわけです。そして私が言っているのは、その考え方が果たして役に立っていますか、ということです。
役に立っているかどうか――この点についての私の考えもありますが、これまた保留して、まえがきとして指摘しておくべきは、シカゴ学派の源流の一つでもあるアメリカ(哲学)らしいプラグマティズムから、返答されているということです。
アメリカのプラグマティズムは……私としては(哲学的側面は)ローティでフォローしているつもりですが、社会学的側面においても重要な考え方であったと強調しておきましょう。いや、これは余談です。
サリヴァンのポジションは、精神医学――つまり病理の治療にとって「役に立っていますか」ということです。行間に書かれているのはもちろん、むしろ治療の妨げになっていませんかです。
サリヴァンは個人ではなく実社会の方に病理があると考えるわけです。このポジションは現代の社会科学に大きな影響を与えている……あるいは先駆者という意味では、現代社会科学の出発点の一つとすら言えるでしょう。
テクストの締め
サリヴァンの人柄(考え方)が表れている部分――さっきの質問の回答の最後=テクストの最後を引用します。
多くの父母にとって我が子が唯一無二で、まったく代えがたい存在であることは良いとしましょう。あるいは何もかもがうまくいかないとき、自分を唯一無二のものとして扱ってくれたからと家族を宝物のように感じることも良いでしょう。人間とは何であるかとこれまで同僚たちが頭を捻ってきた成果を否定したいのでありません。ただ私は、より妥当かつ有用であるような枠組みを主張しているのです。
彼は、患者に対しては一人の人間(あるいはその人が抱える病)と向き合いました。個人の持つ感情や、自尊心といったものを軽視することはありません。それらのことは別に、より有用な、学的あるいは治療のアプローチ(枠組み)をターゲットにしたのです。
さいごに
門外漢の私がなぜサリヴァンの(解説は無理でも)紹介をするか――ある意味で、私のポジションといえるものを明らかにしておきましょう。
精神医学‐哲学というライン――そこにサリヴァンであれ、ガタリであれ、がおり彼らのテクストがある。それらは全て時代遅れだと思っています。一方で、そのラインから提起された、個人・個性・自己・自分・人格――こういったものがフィクションであるということ。これは科学的に正しいと思います。フィクション=ニセモノではありません。フィクションは道具です。何かの役に立つ道具‐器官です。問題は、何の役に立っているのかです。それが、convivialityのための道具なのか、それとも虐殺器官なのか。
イタリアン・セオリーの論者たちや國分(功一郎)さんが、バンヴェニストを通して、人間を別様に捉えようとする試みを私は、個人・個性・自己・自分・人格といったものが虐殺器官であること――だからこそ、それを作動させないようにすることだと思っています。『中動態の世界』が医学書院より、「シリーズ ケアをひらく」から出版されたのは、とても意義あることです。
「個性」は、現代の平凡な用途において、ケアのための道具なのか、虐殺器官なのか、「私たちは考えなくてはなりません」といった某N○Kの決まり文句――この構文はクソです。私たち自身がどっぷり腰まで浸かっている虐殺器官に対して様々な手段で抗すること。これが現代におけるクリティシズムだと、私は思います。
追記
ここに加えて語るのは、私の身の回りで起きた出来事だ。「身の回り」ということは、経緯(あるいは事実)についての意見を私が複数の当事者から聞くことができたということである。この出来事を三人称で記してみよう。例の(哲学的)三人称=非人称とは関係ない。私がなかば当事者の一人である出来事を出来事として一般化するためだ。
ある少女は私学の学校に通っていた。その学校では「個性」を大切に(尊重)するといったようなことを理念の一つに掲げていた。少女(彼女)は、たしかに他の在校生の多くとは違った、生活における規範なり様式を――平たく言うとさまざまな「こだわり」を持っていた。入学に際しては彼女の両親は学校側にその両親なりの説明を行ったし、おそらくは学校側も学校側なりの理解と配慮を行っただろう。
私学であっても懇談会はある。その少し前のある日、彼女は親に、クラスの日常――係り決めや何かの発表といったようなもの――においてクラスメイトと認識の違いがあって辛い思いをしたことを話した。いじめや嫌がらせ等の大きな話ではなく、学校生活で誰もが経験するような事であったが、もちろん親は彼女をやさしく慰めた。また担任と話す機会があった際に、娘の思い込み/思い違いについて話しをした。
少ししてから懇談会(担任と親が一対一で話す形式的な機会)で、彼女の親は、担任の先生から「彼女の認知は歪んでいる=他の多くの人のいう事実と異なったことを事実と思っている」「それによって彼女は、クラスのみんなに気を使わせているので一度病院にいってほしい」と言われた。
親は色んな意味で落胆した。娘が多くの人と違うことは(担任よりも)よっぽど分かっていた。自分の娘であるからその種のニューロダイバーシティについての知識も独学した。担任の言う「認知が歪んでいる」という言葉の用法はズレていて、いかにも研修で知ったような浅知恵だった(学校の教師は忙しいのだ)。そしてなにより、(担任は知らなかっただろうが)娘はずっと以前から定期的に病院で診てもらっていたのだった(担任の提案である「病院に行く」は初めから解決への道が閉ざされているのだ)。
この出来事で、私が最もクソだと思うのはクラスのみんなという幼稚かつ明らかな虚偽表現であるが、それは置いておこう。「個性」を大切にする私学で、なぜ個性が蔑ろにされたのか――読者はこのように思うかもしれない。担任が悪いのか、クラスメイト(の数人)やその保護者が悪いのか、あるいはやはり「彼女」が悪いのか……。私は、どれも違うと思う。(記事の流れでいえば)悪いのは個性を大切にするというその学校の理念である。もし、その学校が個性を大切にするという――虐殺器官を掲げていなければ、「彼女」の個性は蔑ろにされなかっただろう。同じことを言い換えているだけだが、(クラスのみんなの)個性を大切にすることは「彼女」を虐殺することとイコールなのだ。
学校あるいは担任といった責任主体が悪いのであれば、原則として責めることができる。ところが理念が悪い場合はそれができない。そこから距離をとるしかない。つまり、現実的にはその学校をやめるということだ。そしておそらく実際にそうなるだろう。
三人称で語ったものの、これは実際に起こった、個性という幻想によって一人の少女(とその家族)が潰されたという出来事である。
もしサポート頂けましたら、notoのクリエイターの方に還元します
