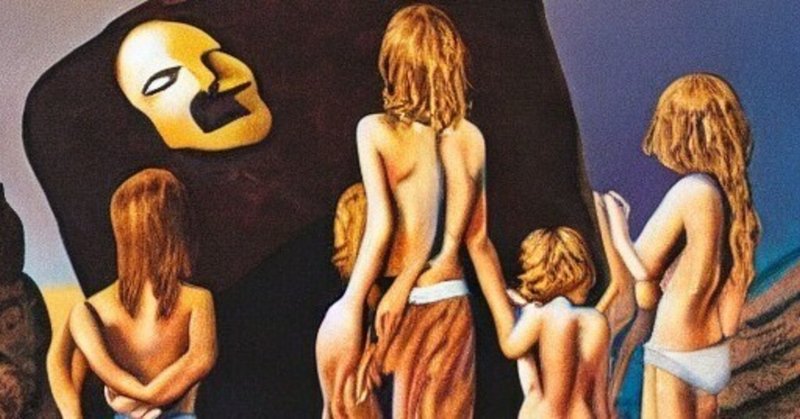
林光《流れ》(1973)まわりみち解説(2)1973年の日本現代音楽、そしてトランソニック
前回、1973年までの林光の歩みを見ていきました。ようやく林光が《流れ》を作曲した年、1973年の話です。でも、やっぱり今回も書きすぎてしまったので、日本現代音楽史における1973年についての話で終わります。林光にとって1973年とはなんであったか、という話はまた次回。
音楽史の転換点
1968年。フランスで五月革命。チェコではプラハの春。日本やアメリカを含む多くの国で、新左翼による学生運動が起こった。モダンからポストモダンへ、歴史の転換点として位置付けられる1968年は、音楽史にとってもまた転轍点であった。このことは沼野雄司『現代音楽史』に分かりやすくまとめられている。
一言で言えば、「前衛の時代」の終わりである。「前衛」という物語を信じていたひとたちがこぞって自省をはじめ、社会とのつながりを強く意識した作風に移行した。本連載の文脈で重要に思われるのは、沼野の書籍でもこの「1968年的なもの」の象徴として挙げられる、ベリオ《シンフォニア》(1968/69)、シュトックハウゼン《シュティムング》(1968)、ライヒ《カムアウト》(1966)といった作品が「声」の作品であるということである。「声」こそが音楽と社会を結びつける紐帯であったといえるかもしれない。
日本における現代音楽の転換、大阪万博(1970)
日本においても、同じような動きがはっきりとみられる。とはいえ、1970年には「EXPO'70」、いわゆる大阪万博が開催された。行動経済成長期の経済大国日本をアピールする場であったこのイヴェントには、もちろん大きな反発を伴いながらも、武満を含む多くの一流作曲家が参加した。最新の電子音響装置など大規模な仕掛けが、新たな音楽を可能にした。その意味で、まだ前衛の時代は続いていたように見える。
同時に、8月に行われた「今日の音楽」と題されたイヴェントは音楽の方向性の転換を示唆するものであった。「今日の音楽」の企画の一つとしてピーター・イェーツの司会によって行われた討論会では、ルーカス・フォス、ヴィンコ・グロボカール、ピーター・スカルソープ、湯浅譲二、松平頼暁、松下眞一、一柳慧、辻井英世、武満徹、髙橋悠治という豪華な顔ぶれの中に、林光も名を連ねている。その議論では、サウンドスケープの問題、発音やアクションの問題、ヨーロッパ中心主義の問題など、「68年的」な問題意識が顕わになっている。
そして1973年
「前衛の時代」の終焉と「社会とつながる時代」の到来、日本の音楽界に二つの鐘を鳴らした大阪万博から3年後、それが1973年である。1973年前後の変化をいくつかの例でみてみよう。
一柳慧は《ピアノ・メディア》(1972)で図形楽譜から五線譜に回帰し、以後歌劇等のジャンルにも足を踏み入れていく。
柴田南雄は自身の作風を四期に分けており、その第四期の幕開けがシアター・ピース《追分節考》(1973)である。この作品は《流れ》を語るうえでもっとも重要な作品であり、次回もまた議論の俎上にあがるだろう。
武満徹が、大阪万博の企画と同名の「今日の音楽」という企画をはじめたのも1973年である。「世界のタケミツ」として認知され始めていた彼が、世界的作曲家としての活動を開始した年として位置付けることもできるだろう。
「トランソニック」の結成
この時代を象徴する最も大きな出来事は、「トランソニック」の結成ということになるだろう。「トランソニック tranSonic」は高橋悠治を中心に1973年11月に結成され、1973年から1976年にかけて活動を展開した作曲家グループである。発足時の同人は高橋のほか、武満徹、柴田南雄、湯浅譲二、林光、一柳慧、松平頼暁の計七名である。1975年に武満が意見の相違から脱会し代わりに近藤譲が入会、しかし1977年には林と中心メンバーの高橋までも脱会するという事態によって崩壊した。
とはいえ、約4年間の短い活動はこの時代を示すものとして、非常に重要であるように思われる。「トランソニック」のもっとも重要な活動は、機関誌『季刊トランソニック』(全12号)の刊行である。ここでは『季刊トランソニック』の内容から時代状況を読み取ってみよう。高橋による「創刊のことば」には、それを明らかにするような言葉で埋め尽くされている。この雑誌の目的は「毒にもくすりにもならない時評や、他人のしごとについての評論家のもったいぶった解釈ではなく、創造の指針を提供する」ことだ、としたあと以下のように語られる。
われわれは誤解されているように、前衛音楽ショーをやるためにあつまったのではない。教養主義と家元的教育制度のなかで、西欧音楽を「身につける」ことにはげんできた日本の音楽界(聴衆でさえも、この点では同罪である)で、また権威主義的な文化の風土のなかで、自由な討論によって独自の音楽の場のための方法論をみつける目的をもって、われわれはここにいる。(…)
一九六〇年代の後半から、現代音楽は模索の時代にはいった。いままではっきりみえていた、とおもわれた音楽の進路は幻影にすぎなかったし、音列技法や音群作曲法、それにかわるものとしての、いわゆる偶然性や図形楽譜、あるいはトーン・クラスターの使用のように、技法によって区分された前衛音楽の諸流派は、すでに「あたらしさ」による衝撃力をうしなったばかりか、そのような区分自体が意味をうしなってしまっている。
「大きな物語の終焉」ということばがまだなかった時代に、「いままではっきりみえていた、とおもわれた音楽の進路は幻影にすぎなかった」と語られていることは少し驚きも覚える。ともかく、前回のnoteで書いたような1950年代の「実験工房」と「山羊の会」が並立していた時代とは大きく状況が変わったことがよくわかる。実際に、「前衛」の物語を突き進んでいた「実験工房」の作曲家たち(武満、湯浅)と「大衆」にこだわった「山羊の会」の林光が「トランソニック」に結集したのは、まさにそういうことである。
『季刊トランソニック』は全十二号それぞれで特集が組まれている。「全体劇場」(第1号)、「記号・かたち・楽譜」(2)、「学習」(3)、「テクノロジー空間」(4)、「組織」(5)、「音楽の政治参加」(6)、「エリック・サティ」(7)、「脱コンサート」(8)、「伝統」(9)、「音と都市」(10)、「運動」(11)、「民衆の歌」(12)。「テクノロジー空間」のように前衛の傾向をもつ回もあるが、「全体劇場」「脱コンサート」「音と都市」といった新たに音楽にとって重要になってきた問題、そして「組織」「音楽の政治参加」「運動」「民衆の歌」といった社会性、政治性の強いテーマが目を引く。
また、『季刊トランソニック』は、本邦に新たな音楽思想を紹介したという功績も大きい。翻訳が紹介されたのは、たとえばサウンドスケープ論のマリー・シェーファーや1970年代以降を象徴する作曲家、ヴィンコ・グロボカールやコーネリアス・カーデューなどである。さらに、会員・非会員の作品の楽譜が毎回掲載された。そのなかには、一柳慧《プラティヤハラ・イヴェント》(1963/73)や湯浅譲二《演奏詩「呼びかわし」》(1973)そして林光《流れ》も含まれる。
次回に向けて
今回は1973年の(とりわけ日本の)音楽の状況について、見てみました。いよいよ次回は、林光にとって《流れ》を作曲した1973年がどんな年であったかという話になります。今回挙げた「トランソニック」と、もう一つ、林光と切っても切り離すことのできない「オペラシアターこんにゃく座」がポイントになってくるでしょう。
主要参考文献
・日本戦後音楽史研究会編『日本戦後音楽史 上 戦後から前衛の時代へ : 1945-1973』平凡社、2007年。
・日本戦後音楽史研究会編『日本戦後音楽史 下 前衛の終焉から21世紀の響きへ:1973-2000』平凡社、2007年。
・沼野雄司『現代音楽史 闘争しつづける芸術のゆくえ』中公新書、2021年。
・『季刊トランソニック』第1-12号全音楽譜出版社、1973-1976年。
今回も登場した作品の音源を紹介しておきましょう
ベリオ《シンフォニア》(1968/69)・・・「コラージュ音楽」の傑作という見方もできる。この時期のコラージュ音楽と言えば、ベリオのほかにもベルント・アロイス・ツィンマーマンやルイ・アンドリーセンがいるが、僕は大好きなひとたち。
シュトックハウゼン《シュティムング》(1968)・・・倍音唱法というすごい歌い方をする作品。詳しいことは松平敬さんのサイトや2015年に演奏された際のページ(以下のリンク)を参照のこと。
『シュティムング』の楽曲構造 | 松平 敬 website (matsudaira-takashi.jp)
長木誠司がひらく サマーフェスティバル2015 サントリー芸術財団 (suntory.co.jp)
ライヒ《カムアウト》(1966)・・・「声」は白人警官に暴行を受けた黒人少年の証言である。
一柳慧《ピアノ・メディア》(1972)・・・かっこいい。
一柳慧《プラティヤハラ・イヴェント》(1963/73)
(文責:西垣龍一)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
