
31 ダルマパーラ 一九〇二年の来日 近代アジアの運命を見据えて|第Ⅲ部 ランカーの獅子 ダルマパーラと日本|大アジア思想活劇
アメリカでの布教活動
(当時)私は積極的に仏教運動家として認知されてはいたが、いまだに仏教学生(在家修行者)の白いローブを身につけていた。しかし一八九五年の十月に、私は黄色のローブを身にまとった。私はひとりの〈アナガーリカ anagārika〉となったのだ。
正式な得度の儀式を受けず、黒い巻き毛をたたえたまま、僧侶の衣装である黄衣をまとった「異形」の仏教者アナガーリカ・ダルマパーラ。彼は十九世紀の末から二十世紀にかけて、世界を股にかけた活躍を始める。一八九五(明治二十八)年から翌年にかけてのブッダガヤ紛争を通じて、ベンガルの進歩的知識人層の間に仏教徒への同情が高まっていた。その結果として一八九六年五月二十六日、カルカッタでインド仏教の滅亡以来数百年ぶりに釈迦牟尼ブッダの誕生日が祝われた。ブッダガヤ大菩提寺をめぐる紛争は膠着状態のままであったが、ダルマパーラ自身は国際的な仏教宣教師としての名声を高めていった。近代南アジアの仏教はダルマパーラというカリスマの肉体に体現されていた、といっても言いすぎではないだろう。
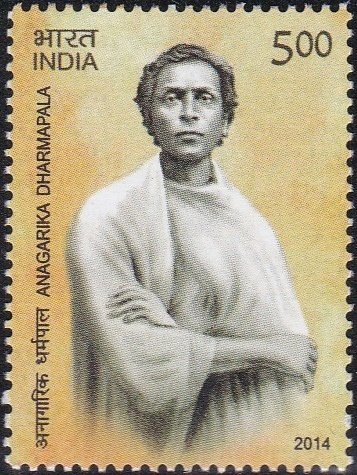
インドでの仏教復興を象徴する『仏陀降誕祭(ウェーサーカ・プージャー)』を晴れて成功させて数週間後、ダルマパーラはポール・ケーラスの招きで再びアメリカ合衆国に向けて船出した。このときのアメリカ訪問が鈴木大拙渡米の呼び水となったことは前章で触れたとおり。途中ロンドンでアーノルド卿、リス・デイヴィッズ、マックス・ミューラーら東洋学の権威と会見したのちアメリカに上陸したアナガーリカは、全米各地を巡業してブッダ・ダルマの宣揚に努めた。
煩悩(passion)の奴隷となり、低級な意識に支配されて感情に溺れるいわゆるクリスチャンたちは、互いに殺し合い、互いに嫌悪し、互いに騙しあって、いままでなかった処にまで酒と悪習を持ちこみ生活している。彼らは自ら煩悩の奴隷となっているのみならず、他人をも彼等自身とその悪習の奴隷たらしめている。
これはダルマパーラがアメリカで書いた日記の一節である。褐色の仏教徒のもとへ群がる異教徒たちに向かって、彼は「純粋」な仏教のあり方を訴え、仏教経典と仏教心理学およびヨーガ(止観)の幽玄さを説明し「神聖にして完全な清らかな生き方」を実践するように説いた。欧米で仏教に関心を寄せていた人士の多くは神智学協会の支持者であったから、これは珍奇な東洋神秘主義に惹きつけられた欧米の知識人を、真の仏教へ導くための一種の「啓蒙活動」だったといってもよいだろう。翌年五月には、彼は数百人の参加者を集めてアメリカで史上初めてウェーサーカ祭(ウェサック vesaka,wesak)を執り行う。彼の欧米伝道の旅はささやかながらも着実な成果を上げていった。
インド大飢饉救援と日本の「骨騒動」
ダルマパーラ三回目の来日について触れる前に、もうしばらく寄り道をしよう。まず、この頃ダルマパーラとインド大菩提会の呼びかけを受けた日本仏教界有志によって、インド国内での大飢饉に対する募金活動が行われたことを記しておきたい*17。
十九世紀末のインドは大飢饉や伝染病の流行による惨禍を繰り返し受けていた。一八九六年にはボンベイで腺ペストが発生、在インドのイギリス人はパニック状態に陥り、インド人家庭のプライバシーまで侵害する過剰な予防処置をとった。民衆はこれに怒り、ボンベイ州のプーナでは伝染病対策に従事していたイギリス人二人が殺される事件も起きた。これにとどまらず、一八九六〜九七年にかけてインド全域が大飢饉に見舞われる。この二つの大災害で英領地域だけで約百万人が死亡したという。
明治三十(一八九七)年、当時シカゴに在住していたダルマパーラは、日本仏教徒によるインド救援を求め駐米の星公使に訴えた。星は大隈重信外相にその旨を上申するとともに、真宗大谷派(東本願寺派)管長の光瑩こうえいに協力を依頼し、日本仏教徒によるインド救援の動きが始まる。ダルマパーラが大隈重信宛に宛てた書簡(三十年七月十八日付)には、「キリスト教国であるロシアとアメリカは既にインドへの救援活動を開始しているというのに、仏教国の日本が仏陀の祖国に対して何も救援の手を差し伸べぬとはどういう了見なのか。」*18といった激しい文章が躍っていた。
日本仏教界の一部にはダルマパーラに対し「不埒千万」であるとの感情的な反発さえ起こった。しかしインドの窮状は悲惨を極め、インド大菩提会のチャンドラ・ボースからも日本の印度仏跡復興会幹事宛に「印度数百万の生霊が飢餓の為め斃死するを救援せんと尽力せらる可きは慈悲円満の仏陀を奉ずる各信徒の本分なるのみならず又人類の本分と被存候」との切々たる書簡が届くなかで、仏教ジャーナリズムはダルマパーラの檄に応え、日本仏教の祖国・インド救済のための一大キャンペーンを張るに至った。
基督教国たる欧州各国の志士仁人は挙って印度人民の窮困を哀念し、同胞相愛の教義に基き之が救恤に従事せりと。此際仏教徒たる者、卒先熱心此慈善事業に尽力し、大に祖国(注インド)を思うの情誼を発表せざるべからず。
蛇足になるが後日談を述べると、その後、明治三十三(一九〇〇)年にもインド大菩提会からインド飢饉救済の要請があり、日本仏教界による救援基金とキャンペーンが行われた。殊に同年、タイから日本へ仏舎利を招来する計画が持ち上がり、各宗派の管長らが『大菩提会』(!)なる団体を結成し、六月にはタイに向けて仏骨奉迎使節団を送ったのだが、それが各派の見栄の張り合いのような豪奢な旅行になったことがインド飢饉の惨状と対比され、仏教ジャーナリズムから痛烈な批判を受けた。仏教主義雑誌社連合会は『日本大菩提会』に向けて書簡を送り、タイからの仏舎利を安置する覚王殿建設の費用の半分を割いてインド飢饉の救済にあてるよう強く訴えた*20。
タイから招来した仏舎利の安置場所をめぐる泥仕合は、またまた日本仏教界の「骨騒動」と揶揄され朝野の失笑を買った。紛争の渦中で宙ぶらりんになった仏舎利は明治三十五(一九〇二)年十一月になって最終的に名古屋に移された。仏舎利を安置する覚王山日泰寺の建立が始まったのは、翌三十六年十月のことだ。日泰寺には伊東忠太の設計によって総大理石造りでガンダーラ様式の仏舎利奉安塔が建てられており、現在は年に数回の開帳時にのみ拝観できる。
神智学協会との訣別
十九世紀末から二十世紀初頭にかけての数年間は、ダルマパーラと神智学協会の関係が決定的に冷えきった時期でもあった。一八九七年の末、一年に及ぶ仏教宣伝ツアーを成功させ、ヨーロッパ経由でインドへ帰還したダルマパーラは、オルコットに「神智学協会を辞職し、スリランカでの仏教活動に専念して欲しい」と訴えた。実際その希望を抱いていたにもかかわらず、オルコットは愛弟子の申し出に応じなかった。「簡単に云えばこのアイデアは、私に火中の栗を拾えということなのだ。」オルコットはダルマパーラが彼を側に置くことで、大菩提寺闘争をはじめとして、暗礁に乗り上げたさまざまな社会事業に関する経営上の困難を回避しようと目論んでいると疑った。すでに一八九六(明治二十九)年、ダルマパーラが渡米する直前にオルコットが大菩提会の理事と主席顧問を辞職していた。彼はブッダガヤ大菩提寺をめぐるマハンタとの抗争を国際問題化して煽り立てる「弟子」ダルマパーラおよび大菩提会のやり口に対して徐々に批判的になっていたのだ。
二人の対立を決定付けたのは、翌一八九八年、セイロンに拠ったダルマパーラが『仏教徒神智学協会』の名称から「神智学(Theosophical)」の語を取り除くべきだとの主張を始めたことだ。ヒンドゥー教改革運動への支持を公言するベサントが神智学を率いている現状は、スリランカの仏教徒が「神智学」の名称を捨てることを正当化するのに充分だと思われた。
しかし老大佐はこれに激怒、セイロンの仏教徒がブランチの名称から「Theosophical」の表記を削除するのであれば、彼は彼らとの関係を即刻破棄して、今後一切の援助に応じないだろうと言明した。オルコットの強硬姿勢の前に、さすがにダルマパーラも矛を収めた。前述のように、オルコットはその弟子から「仏教復興運動への専心」を懇願されていた。仏教世界の連合ユナイテッド・ブッディスト・ワールドのために、彼が果たすべき仕事はまだ残されていたはずだ。しかしオルコット自身何度もそのそぶりを見せながら、結果として死ぬまで、神智学協会における地位に固執し続けた。その一方で彼は、自分がセイロンの仏教徒に対して家父長的な態度で「分派行為」を戒める権利を保持していると信じていたのだ。
……もしもブッディズムに単一のドグマを承認することを強いることが含まれたなら、我々はパンシル(訳注:五戒pañca sīlaのシンハラ語訛り)を受けなかったし、また十分間であっても仏教徒として留まらなかったろう。我々のブッディズム〜マスター・アデプト、ゴータマ・ブッダの仏教〜は、アーリアン・ウパニシャット(アーリア人の秘教)や凡ての古代世界信仰のソウルと全く同様のものだ。我々の仏教は一言でいえば、哲学であって、主義・信条ではない。
オルコットが一人合点した「神智学的」仏教観は、ダルマパーラにとってもはや我慢ならない偽善に映っていた。ブラヴァツキー死後から一八九〇年代を通じて、ベサント率いる神智学協会(アディヤール派)はヒンドゥー教への傾斜をいよいよ強めてゆく。協会の「変節」はインドやセイロンにおける仏教復興運動の立場を危うくするものだった。「ブラヴァツキー夫人の時代、セオソフィストの大部分が仏教を受け入れ、五戒を保っていた。……しかし現在、神智学協会はヒンドゥー教を最高の宗派として持ち上げている。」一八九九年の春、ダルマパーラは、神智学協会の関与したシンハラ仏教復興運動の失敗を宣言した。
「たわごとだ!」オルコットは仏教復興運動の障害となっているのはダルマパーラの管理上の無能であり、社会改革を実現し、それを継続するうえで必要なビジネス知識の欠如であると激しく批判した*21。二人の師弟関係は完全に冷えきってしまった。オルコットはダルマパーラの鼓舞するシンハラ仏教ナショナリズムを「反ヒンドゥーであり、反神智学である」と非難し、一方ダルマパーラはオルコットとその追従者を「神智学の堕落者」と呼んで応酬した。
一九〇五年九月、オルコットは『神智学徒』誌上でとんでもない失言を漏らしてしまう。シンハラ仏教徒の頑迷さを嘆いた彼は、キャンディ仏歯寺に保管され、セイロン仏教徒の精神的支柱であるところの『仏歯(釈迦の犬歯と謂われる聖遺物)』の非歴史性を挙げつらい、「オリジナルの釈迦の歯は十六世紀にポルトガル人によって破壊されており、現在の仏歯は鹿の角で作られた紛い物に過ぎない」と断定したのだ。

シンハラ人のアイデンティティを侮辱する「最も邪悪な攻撃」に対して、ダルマパーラは恩師であるオルコットの仏教理解の杜撰さを全面攻撃することで応じた。彼は「オルコットが奉じる神智学の教義は、仏教の立場と相容れない異端である」と結論付けたうえで、公式に「仏教徒として、私は多神崇拝の神智学協会と関係を断絶する」と宣言した。ダルマパーラは『仏教徒教理問答集ブッディスト・カテキズム』にお墨付きを与えたスマンガラ大長老にも同様の処置を取るよう働きかけ、大長老はこれに応じた。オルコットはスリランカ仏教界における地位を完全に失いかねない情勢に追い込まれた。もしこの危機を乗り切ったとしても、老大佐に残された時間はあとわずかであった*22。
一九〇七年にオルコットが没するまで、二人の間に和解が訪れることはなかった。「私はあの人たちといて、共に『さようなら』と握手を交わしたときの感激をいまだに記憶している。」ドン・ダヴィッド少年と「神智学の双子」が出会ってから四半世紀を経て、神智学運動と伝統仏教との幸福な関係は、その始まりの地セイロンでも幕を閉じた。
スリランカの仏教リバイバルは、神智学協会という西欧の「パチもの仏教」の保護を脱し、力をつけたシンハラ人仏教徒自身の手によって担われるべき段階に入りつつあったのだ。
セイロンでの活動
スリランカ仏教と神智学協会との関わりに強引に一区切りをつけたところで、また時間を十九世紀末に戻したい。一八九八(明治三十一)年を通じて、「今やこの国の人々にとってポピュラーな英雄」となったダルマパーラは牛車に揺られてセイロン島内をくまなく旅行し、ランカーの伝統文化と宗教の栄光を説いてまわった。
同年、彼は『信者規則 Gihi Vinaya(The Daily Code for the Laity)』というパンフレットを発行する。その本のなかで、ダルマパーラは仏教徒の細かい日常生活の指針を明文化した。いまだに版を重ねており、一九五八年に第九刷が出て五万部も売れたという。同書には、食事のマナー(二十五規定)、キンマの葉を噛むこと(六規定)、清潔な衣服を着ること(五規定)、トイレの使い方(四規定)、道路を歩くときの作法(十規定)、公的な集まりでの作法(十九規定)、女性の作法(三十規定)、子供の作法(十八規定)、教団に対する在家の作法(五規定)、バスと電車の中での作法(八規定)、社会が行うべき村の守り(八規定)、病人を見舞いに行く際の作法(二規定)、葬式(三規定)、荷馬車屋の作法(六規定)、シンハラ人の衣服(六規定)、シンハラ人の名前(二規定)、教師の義務(十一規定)、召使いの作法(九規定)、祭りの運営方法(五規定)、男女在家信徒の寺での作法(三規定)、子供の親に対する作法(十四規定)、家庭内での儀式(一規定)両親に対する作法、家庭祭祀などなどについて、全二十四項目二百カ条に及ぶこまごまとした信者の戒律が定められている(『スリランカの仏教』三二〇)。
彼が強調したのは、洗練されたコロンボの中産階級ーービクトリア朝的な生活様式を身につけていたーーに育ったダルマパーラから見ればだらしなく野卑に見えた、シンハラ農民の習慣の矯正であった。『信者規則Gihi Vinaya』は当然ながら読み書き能力のあるシンハラ人ブルジョアジーを対象にしていた。ゆえに食事にはフォークとスプーンを用いるべきだとか、トイレの際には洗う前にトイレットペーパーを使うべきだとか、女性は身体が見えるような服装はすべきでないとか、十九世紀末の西欧社会で標準的とされる生活習慣に沿った規定が説かれていた。それと同時に、ダルマパーラはテーラワーダ仏教の実践を日常生活のなかに導入しようともした。つまり朝起きたらブッダに礼拝し、五戒を守る誓いをすること。週に一回は寺院で説教を聞き、ポーヤ・デー(布薩日)には八戒を守ることなど、(指導的)在家仏教徒のあるべき宗教生活を指針として示したのである。
一方、島内の津々浦々で一般大衆を相手に行われた「ランカーの獅子」の演説は決して高尚で七面倒くさいものではなく、「酒を飲むな」「牛肉を食うな」という単純なスローガンに集約されていた。先にも述べたが、「忌まわしい牛肉食も、精神を堕落させる飲酒の悪習も、ヨーロッパのキリスト教徒たちがセイロンに持ち込んだものである」という一点において、シンハラ民族の「堕落」の責任を外来の習慣に転嫁することは容易だった。そして指導的立場のシンハラ仏教徒には『信者規則』に示された近代人にふさわしい道徳的な生き方を率先して実践し他に及ぼすことが求められた。ダルマパーラが展開した「生活改善運動」は、シンハラ仏教徒のアイデンティティを生活習慣という底辺から叩き直し、彼らに「国民」としての自覚と確かな宗教的・民族的なプライドを付与したのである*23。
ダルマパーラは同じ時期、社会事業に貢献する尼僧を育成するための教育機関『サンガミッタ・コンベント』を設立したほか、彼の教育思想を実現する『セイロン倫理心理学校』を建設するべく、父を説き伏せてコロンボ近郊の土地を購入したりもしている。二千三百年にわたって初期仏教を護り伝えてきたシンハラ民族の栄光を、新たなる時代のなかで再編成し蘇らせるために、ダルマパーラがなすべき仕事はあまりにも多かった。
インド大旅行
汝の目を開け、そして見よ。一億四千百万の人々の苦しみの叫びを聞け。彼等の涙をもって汝の乾いた心を冷やしてみろ。『神佑』が汝を救うなどと妄想するな。『全能の神』は汝のもつ時計で時を数えてなどいない。彼にとっては『一千年が一時間』なのだ。(そんな神の情けを)腕を組んで待っているなんて馬鹿げている。兄弟たちよ目を覚ませ。この世のいのちは短いのだから。汝の夢みるような哲学や、肉欲に導く儀式をやめよ。数百万の人々が毎日飢えに苦しみ悩んでいるのだ。森の動物も飲まぬような穢れた水を飲み、毎日毒を吸いながら、家の中に寝起きしている。インドにはすべての人々を食べさせる十分な富がある。しかしカーストや信条や宗派間の憎悪が数百万人の人々を苦しめ続けている。
一八九九年の初頭、ようやくカルカッタに帰還したダルマパーラは二カ月の滞在ののち、北インドへの大旅行に出かける。前章では旅行中と書いたがおそらくその前に、彼はブッダガヤで河口慧海と会見し、ダライ・ラマ十三世に贈る仏舎利塔を託した。約四カ月にわたるインド旅行中、彼は列車の三等、または二等座席の旅客に交じって、貧しいインド人と同じ食事をとり、同じ場所に眠り、インドが置かれた状況への洞察を深めていった。上に引用したのは、ダルマパーラがサハランプールから送った公開書簡の一節である。
彼は「カーストや信条や宗派間の憎悪」に蝕まれたインドを改革するためには、仏教の復興こそが求められていると確信していた。カルカッタに帰還したダルマパーラは南インドのマドラスに招かれ、そこで仏教について講演し、民衆への教育と不可触民アウト・カーストの解放を強く訴えた。大菩提会の支部がマドラスにも創立され、不成功に終わったものの、ヒンドゥー教徒の不可触民アウト・カーストを仏教に改宗させる試みも行われた。
当初はオルコット大佐も関係していたこの仏教改宗運動は、一九五六年の仏教二千五百年祭ブッダ・ジャンティを期してアンベードカル博士の指導で挙行されたインド不可触民の仏教への集団改宗の先がけともいえる。しかし神智学協会がモットーとした八方美人の諸宗教融合主義シンクレティズムと、ダルマパーラの仏教原理主義が最も先鋭的に対立したのもこの運動をめぐってであった。インドで仏教を復興させるというダルマパーラの構想を実現させるならば、そこでは必ずヒンドゥー教徒をはじめとする異教徒への改宗運動が伴う。ヒンドゥー教の矛盾を最も激しくこうむっているアウト・カーストに仏教をもたらそうとしたダルマパーラの狙いはまことに的確であったが、そこで彼はヒンドゥー教に覆われたインドそのものとの対決を迫られたのである。抽象論や教養のレベルではなく、現実的に仏教をインドに根付かせるためには、宗教紛争という近代インドの宿痾のなかに、仏教自体が身を投じなければならなかったのだから。
セイロンでは「シンハラ人の伝統文化」を仏教とリンクさせて民族意識を煽ったダルマパーラは、インドにおいてはより大きな視野で仏教の役割を捉えていた。孤独な仏教ミッショナリーは「ブッダ・ダルマ」の現代的な意義を、欧米・セイロンそしてインド、それぞれのフィールドで微妙に言い換え、矛盾撞着を背負いながらも必死に模索していたのだ。
三回目の来日──活動仏教の提唱
明治三十五(一九〇二)年四月末、ダルマパーラはついに三回目の来日を果たす。彼は日本仏教界の指導者に対して、仏教学校設立への援助を要請するスマンガラ大長老の親書を携えていた*24。資金面でははかばかしい成果を得られなかった滞在中、ダルマパーラは盛んに「活動仏教」の必要を唱え、出家者主体の仏教の停滞を批判し、在家信徒や青年仏教徒の活動を促した。スリランカでYMBA(仏教青年会)が結成されたのが一八九八(明治三十一)年一月*25、日本で新仏教運動の旗手として『仏教清徒同志会』が結成されるのが一八九九(明治三十二)年十月*26。出自を別としながらも、南北の仏教革新運動の始まりが近接していることは興味深いが……。ダルマパーラは滞日中、『中央公論』誌上に掲載された講演録でこうアジっている。
予は日本に来たりしこと前後三回、最初は今より十三年以前なりき。この十三年間来る毎に人を驚かすものは百般事物の進歩なり、活動なり、……しかれどもこの活動の日本に於いて、ただ一の活動せざる部分有り、これは何物ぞと問わば宗教すなわちこれなり。思うに日本の仏教も現在その弊は南方アジアと同一に非る無きか。南方アジアの中にてもセイロンの一島のみは今や仏教の活動ことごとく僧侶の手を離れて青年にして教育有る活気ある部分に徒れり。その慈善事業、その教育事業、すべて信徒の手にあり。僧侶はただ擯椰子を噛んで殿堂のうらに横臥せるのみ。彼等は一の外国語すらこれを知らず、況んや近世の学術に於いてをや、況んや生ける伝道に於いてをや。日本の僧侶、特に老輩はこれに類すること非る無きか。軽率に断案を下す能わずといえども、定めて同一の状態にあるならんと信ず。
二十世紀アジアの革命は先ずかかるエセ仏教徒を征伐せざるべからず。これをなす先ず仏教の活動をセイロンの如く信徒よりし、今のいわゆる隠退睡眠を主義とせる僧侶より脱せざるべからず。日本に起れる一宗真宗(筆者註:浄土真宗のこと)の如き仏教が活気ある青年の手によりて躍動するに至って初めて宗教も他の軍事教育商業等とその活動を争うに至るべきなり。
ダルマパーラが「南方アジアの中にてもセイロンの一島のみは今や仏教の活動ことごとく僧侶の手を離れて青年にして教育有る活気ある部分に徒れり。その慈善事業、その教育事業、すべて信徒の手にあり」と喝破した背景には彼が一八九八年からセイロンで組織したさまざまな草の根の仏教運動への自信があったろう。
滞在中、彼のもとには多くの仏教徒青年が訪れた。そして彼の来日を契機に日本の仏教青年運動の国際的飛躍を図る動きが起こり、同年五月十六日、東京は高輪仏教大学に『万国仏教青年連合会』が結成された。九月二十二日には高輪仏教大学講堂にて発足式が挙行し、島地黙雷を会長に推した。この席ではアイルランド人比丘ダンマローカ師の英語演説も執り行われた。

万国仏教青年連合会は結成から翌年にかけて活発に活動したようである。「世界各国の仏教信徒及び仏教の研究に従事しつつあるものの交通機関となり、互に気脈を通じて仏教の真精神を発揚するを目的とし、各国仏教者と連絡し、各地仏教の現状及び意見等の通信をなし、日本より海外に赴く仏教徒、及び海外より日本に来る仏教徒に便宜を与え、また英文にて各地の通信其他を報告し、時々日本その他にて大会を催すこと」などを主要な事業に掲げ、ハワイ・アメリカの仏教青年会とも連合した。オーストラリア・クリーンスランド州の熱心な仏教徒だったゼフリン夫人が支部を設立したり、会員・高田栖岸の尽力により香港・広東・彼南に支部が開設された。翌明治三十六年四月には、英文と邦文の『万国仏教青年連合会会報』が創刊され、会館建設も決議された。しかし順調だったのもここまで。西本願寺派宗門内の教学問題によって高輪仏教大学が廃止(京都の佛教大学への統合)となったため万国仏教青年連合会は雲散霧消、『会報』も続刊されずに途絶えてしまった*28。
日英同盟と日印協会の設立
西本願寺の若きプリンス、大谷光瑞(一八七六〜一九四八)がぶち上げた大谷探検隊のシルクロード遠征や、河口慧海のチベット旅行など、この時期、日本仏教界の海外事業への関心は高まっていた。一方で二年前のタイ国からの仏舎利招来と覚王山への奉安をめぐる内部抗争で権威を失墜させ、金銭スキャンダルを抱えるなどしていた一般仏教界には、彼の来日に対して冷ややかなムードも存在していた。
好奇心に富める日本人、オルコット氏の始めて来たりし時はこれを歓迎せしこと非常なりしも、再び来たりしときは誰も相手にするものなかりしが故、落胆して帰り去れり、先年ダンマパラ氏の始めて来たりしときは、これを歓迎せしことオルコット氏に譲らざりき、されど今回の再来には余りこれを歓迎するものなきが如し、氏の意見は日英同盟を機として、南北仏教の連合を謀るにありと、意気壮なりといえども、その実地に至りては到底行われざることなるべし、何となれば日本一国内に於ける仏教の連合だに出来ざるを見てこれを証す、一宗の統一だにむつかしき仏教徒が如何にして南北仏教の統一を計られ得るべきや
しかし一方で、ダルマパーラの日本での活動範囲も、従来の仏教活動家という枠を超えていた。彼は滞在中、平井金三・桜井義肇らとともに日本国内のいくつかのインド関係の組織を束ね、『日印協会』の設立に尽力した*29。またブッダガヤ問題のスポークスマンである彼の来日を機に、日本でインド仏蹟巡礼の旅行会「佛陀伽耶参拝講」の企画が持ち上がった*30。
ダルマパーラは、同年二月の日英同盟体制成立(ロンドンにおける一月三十日の日英同盟締結には、釈雲照・興然の後援者でもあった林董が特命全権公使として尽力した) を背景に、通商・文化面を通じて日本とインド・南アジア圏の関係を深めるための民間外交使節という役割も担っていた。極東の新興国家日本が、インドを支配し続ける大英帝国との間で対等の同盟を結んだ意義について、ダルマパーラはこのように語っている。
日英同盟すでに成る、この際を機として欧米人の間になお存する種族的嫌忌の念(注・人種差別思想)を去らしめ、一面アジアの同胞をその不幸より救うは覇を太平洋上に握る日出帝国の任務に非ずや。二十世紀新革命の先駆者たる使命を帯べる日本はインドなる一国のその背後に在るを決して忘るべからず。帝国の有志家がインドに対する趣味と注意を払う事の一人にても多からんことを予の深く大に希望するところなり。
単なる仏教活動家の域にとどまらず、近代アジアの運命を見据えるイデオローグとして、ダルマパーラは前二回の訪日の時よりもずっと大きく成長していた。さて、彼は日本滞在中にあるカリスマ的仏教活動家との会見を果たしている。その名は田中智学(一八六一〜一九三九)。在野の日蓮主義活動家として、近代日本の国家主義運動・右翼革命運動にも大きな影を落とした智学とダルマパーラ。二人の巨隗がぶつかり合ったその記録を、次章でお届けしたい。
註釈
*17 一八九七年のインド大飢饉の惨状とインド大菩提会による救援アピールが『仏教』第一二四号に大きく掲載されている。一九〇〇年の飢饉救援の記事は同じく『仏教』第一六三号に見られる。
*18 原文は次のとおり。「以書翰致啓上候。陳者幾百万ノ印度生霊飢餓ノ惨状ヲ及御報道度旁々其惨怛タル現状ヲ写候別紙書翰差進候。閣下幸ニ本件ヲ日本仏教徒ニ御差示相成候上其賛助ヲ得て此悽然タル禍難ヲ相救候様御取計成度致希望候。印度人民ハ仏教徒ノ救助ヲ渇望致居候。此事件ニ付キ露国皇帝陛下ハ親シク同情ヲ表セラレ且墨斯科ノ大僧正モ其救恤基金ニ相応ノ義捐ヲ為スベキ旨人民ニ勧誘被致。米国人ハ亦印度ニ満船ノ穀物ヲ輸送致候。独リ日本ノ仏教徒未ダ此挙ニ出ヅルヲ聞カズ候。然ルニ貴国人ト印度トノ関係多キヲ加ヘ候不遠ト存候得バ閣下ニ於テモ充分御高察ヲ賜ハリ出来得ベキ限リ御救助被下候様致希望候」(四明余露一一八号付録)
*19 ここまでの記述は、「日本近代仏教社会史研究」吉田久一(吉川弘文館 昭和三十九年)による。
*20 『仏教』第一六四号 同じ頃『教学報知』では、「暹羅電話(仏骨奉迎の奇譚集)」として仏骨奉迎使一行に関わるゴシップを書き立てている(明治三十三年十月五日など)。「速かに大菩提会を破壊せよ」(同年九月二十九日)といった激しい内容の記事が並んでおり、仏教界の内部対立が背景にあると考えても「日本大菩提会」の悪評は凄まじいものがある。
*21 〝The White Buddhist -The Asian Odyssey of Henry Steel Olcott-〟Stephan Prothero, Sri Satguru Publications, India, 1997, p162
*22 Prothero、同書p167 ダルマパーラの反乱を「子供の遊び」と突き放していたオルコットも、スマンガラ大長老からの抗議には狼狽した。彼は批判を受けた『ブッディスト・カテキズム』のいくつかの項目を書き直す姿勢を見せ、大長老との関係修復にひとまず成功する。
*23 『スリランカの仏教』リチャード・ゴンブリッチ、ガナナート・オベーセーカラ、島岩訳、法蔵館、二〇〇八年(Buddhism Transformed Religious Change in SriLanka 1988の邦訳)三二一頁以降で、ダルマパーラの「生活改善運動」の背景について詳しく解説されている。
*24 『中外日報』明治三十五年五月七日
*25 YMBA(Young Men's Buddhist Association)の歴史と役割については『現代スリランカの上座仏教』四九三頁に詳しい。
*26 『日本仏教史 近世・近代編』圭室諦成監修、法蔵館、一九六七年、三五八頁
*27 ダルマパーラ K・T訳「日本と印度」(日印協会の設立) 駿河台浩養館にて(『中央公論』一九〇二年六月号)
*28 『龍谷大學三百年史』龍谷大學編 龍谷大學出版部、一九三九年七月、八二二頁参照。なお『中央公論』一九〇二年五月号にも万国仏教青年連合会の設立宣言と会則などが掲載されている。ちなみに『龍谷大学三百五十年史 通史編 上』七五七頁の記載では、ダルマパーラの履歴についてダンマロカ師と混同して「アイルランド人にして深く仏教に帰依し」云々と記しているが、これは間違い。
*29 「日印協会は明治三三(一九〇〇)年 に創立したインド研究会と日印クラブ等を併せて、明治三五(一九〇二)年に長岡護美氏、大隈重信氏、渋沢栄一氏等によって組織され、日印両国民の親善を計る傍ら、インド事情の調査、日本文化と経済事情の紹介等を行った。大正年代からは経済活動に重点を置いて、カルカッタに日本商品館を経営したり列車バザー等でインド各地に日本商品を紹介したりして、日印貿易の発展に尽くした外、仏蹟を中心とする訪印旅行団を派遣し両国の理解促進に努めた。」(「日印協会の生いたちと歩み」財団法人 日印協会) 文中にダルマパーラやその周辺の人々の名前は出ないが、〝The Maha Bodhi〟Vol.41 no.7,8,9(Devamitta Dhammapala Number)に掲載された日印協会創設時の集合写真にダルマパーラの姿が写っている。協会によれば、関東大震災や先の大戦時の空襲で、協会創設時の記録はその多くが焼失してしまったそうである。
*30 日宗生命保険会社社長の河合芳次郎の企画による。『中央公論』一九〇二年五月号、『浄土教報』一九〇二年六月一日(第四八九号)に記事が掲載されている。
*31 ダルマパーラ・K・T訳「日本と印度」
最後まで読んでくれて感謝です。よろしければ、 ・いいね(スキ) ・twitter等への共有 をお願いします。 記事は全文無料公開していますが、サポートが届くと励みになります。
