
コミュニケーションを意識することからはじめよう
杉並区の生涯学習プログラム「杉の樹大学」で講演をしてきました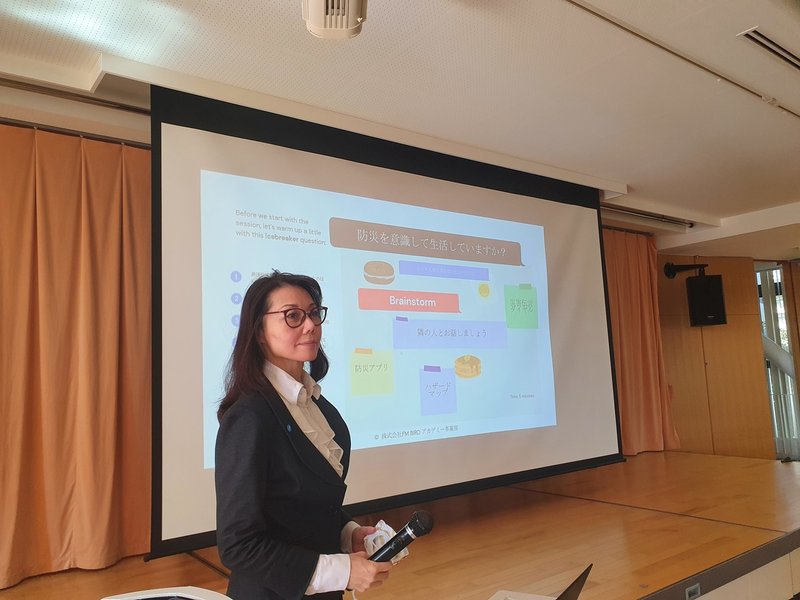
今年の私の授業テーマは「私が杉並区でできること」ですが、中期の授業は「防災とコミュニケーション」をお話しています。杉並区で生まれた私が、杉並の現状、区や行政の防災に対する取り組み、そして地域コミュニケーションがいかに防災・減災にとって大事なのかをお伝えする時間となり、大変有意義な時間を過ごしました。皆様、真剣に受講してくださったことは嬉しく、感謝いたします。
実はコロナ禍で、前期の授業は吹き飛び、ようやく再開されてリアルになっても、感染症対策のため、出席者はおよそ半分に減席されました。とても楽しみにして下っていた方々、受講できなかった皆様には申し訳ない気持ちです。半分の出席者となっても出席者の方々の意識は非常に高く、鋭い質問もたくさん出て、互いの学びの場になりました。
なぜ防災とコミュニケーションなのか
答えは極めて単純です。
実は現在災害と呼ばれるものの中で、コミュニケーション不足による「人災」が増加しているからです。
日本は古くから、地理的条件、季節性天候条件などで災害に繰り返し見舞われてきた世界でも特異な国です。そのため、天災に関する歴史的なノウハウが各地域には「地名」「表示」または「土地の工夫」として残されています。
しかしながら近年核家族化が進み、そうした昔の知恵は継承されず、形骸化されてしまい、「津波がここまできた」という表示さえ見過ごされて家が建つ、「大きな土砂崩れがあった」という地名を意識せずにお店や公園が作られるなど、人為的な災害ともいうべきことが起きているのです。
これはまさにコミュニケーション不足による人災であり、どうやって伝えていくかの命題の解決は、人々の生命に直結していることを意識しなければならないのです。

被災地でのコミュニケーション

傾聴という言葉、あまり聞きなれないことかもしれませんが、コミュニケーションの中で「傾聴」「真剣に聞く」という行為は、そもそも一番根幹であり、コミュニケーション能力を高めるための必須事項です。
コミュニケーションはキャッチボールにたとえられます。
ボールという言葉は受け取ったら、その人とつながりたければ、だれでも返したいと思うものですが、うまく返せないときもあるものです。
それでも傾聴し、聞く姿勢を保っていると、聞こえてくる言葉がはっきりとみえてくる瞬間が訪れます。うまく返せないことを悔やむ必要はありません。聞いているという姿勢を保つ、それが話している人とのコミュニケーションの第一歩です。
被災地でのコミュニケーションはつらく、一緒にもらい泣きすることもたびたびです。それでも、話すことによって、被災地の人の気持ちが軽くなるのであれば、そのコミュニケーションは決して無駄ではありません。
そして何も返せなくても、聞いたよという姿勢をとるあなたのコミュニケーション能力の経験値は確実に上がっています。
傾聴するとき一番大事なのは、「話を聞く筒のようになる」瞬間が訪れるよう、辛抱強く集中することです。
命は、公助に任せきりではいけないのです
たとえば、阪神・淡路大震災で閉じ込められた人が救助隊に命を救われたのは、たった1.7%。7割は自助、自分で家からはい出したり、家族に救われています。
友人や知人からも2割以上の人が救われています。大きな災害がおきたとき、救助隊はすべての人を救うことは極めて困難です。
だから防災には日頃のコミュニケーションが必要不可欠です
地域の中で、コミュニケーションをスムーズにとれる人を探すことが、いざというときの「保険」「安全弁」になるのだと認識する必要があるのです。
お隣はだれが住んでいますか?いつごろ帰ってきますか?お盆やお正月など、どこへ出かけているのかコミュニケーションしていますか?要介助の方はいませんか?すべてを聞くのは憚られても、一年を通じてどういった行動をされているのか、せめて向こう三軒両隣くらいはわかっていたいものです。
最近は自治会費を納めないご家族もでてきましたが、街頭の電球や、備蓄の水、毛布など地域で取り組んでいる防災への備えを、各家庭に説明しない町内会もあるようです。自治会はどうしても古くから居住されている方々の寄り合い所になり、なかなか新しい人が入りにくい雰囲気もあるかもしれません。班長さんなどが先導して、声をかけていくことは大切ですが、人が変わらないなら、地域に住んでいる自分が率先してまず近所の方との声かけをすることは、尊い防災コミュニケーションの一歩です。
都市計画や防災ハザードマップに頼らない
市区町村の防災課や危機管理課の皆さんもちろんがんばっていますが、例えば、水害担当は杉並区で昨年はたった二人。今年は久我山駅や阿佐ヶ谷駅での浸水がありましたので、増員したそうですが、数名だとのことです。区役所の人は毎日50万人以上の人々の管理に追われ、突然くる危機の管理には人材を割けないのです。しかし災害はある日突然やってきます。自助という言葉は、公助を当てにしていた阪神淡路大震災前と違い、今は、自助と共助で助かろうというのが一般的な認識に変わってきています。
自助への備えは、他人とコミュニケーションすることを認識することから始まり、地域で助け合うコミュニケーションの成功率が、地域の自助生存率につながることを認識することが大切です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
