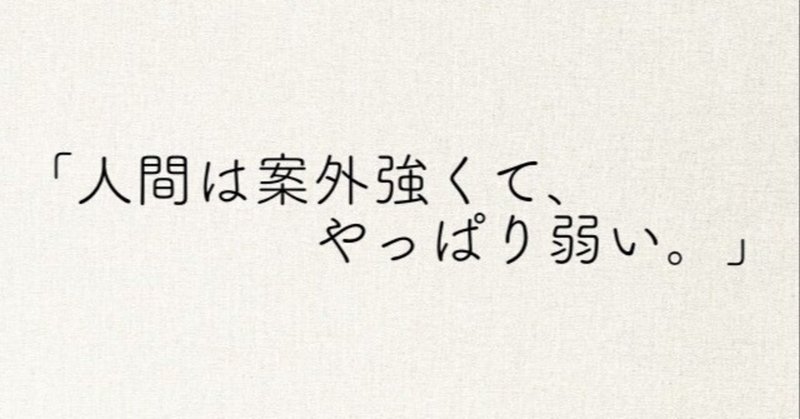
十二個目の話題「人間は案外強くて、やっぱり弱い。」
(本編前の小話省略します……!!!)
(いきなり本編どうぞ!!!)
夏が来た。
あれだけ困っていた雨はあっさり止んで、今度は太陽が我が物顔で空を支配している。
……こうやって天候に振り回されるのが人間の定めなんだろう。
「ぷはぁっ!!」
「え、一気に飲んだ?」
「うん。夏の醍醐味!ラムネ一気飲み!!」
「もう炭酸をそんな勢いでは飲めないな……」
「陽……もうそんなに体が老いたの……?」
「光莉が元気すぎるだけだと思うけどな」
雨が止む頃に光莉は俺の事を呼び捨てするようになった。
だからって関係性が変化した訳では無い。
ずっと心地いい。
それはきっと会話のテンポが合っているから。
「ラムネってさ、もう一個醍醐味があるよね」
「……ビー玉?」
「そ!このキラキラがたまんないのよ!」
『キラキラしてるものって何色なんだろうね?』
「……」
「陽?どしたー?キラキラ嫌いだった?」
あれはまだ出会った頃のシロが言ってたこと。
シロのお母さんが亡くなる前の、まだ無理に笑おうとしなかったあの頃の記憶だ。
俺も俺で特になんにも考えること無く「キラキラは白じゃね?ほら太陽って白じゃん」って言ったのを覚えている。
今思えば太陽は大抵赤かオレンジで描くことが多い。
絵描きのシロからしたら、馬鹿なこと言ってんなって感じだったんだろうか。
「光莉、キラキラって何色?」
「えー?なんだその質問」
「だよね」
「ちょっと待ってね。考えてみる」
そう言って光莉は空になったラムネの瓶を空にかざした。
「ん~?今は青だな」
「…ラムネの瓶が?」
「そう。プラス空が青いから」
「まぁ、確かに」
「でも太陽は白だな」
「えっ…?白?」
「うん。直視できないけどね」
「そうだね」
光莉のことを分かってきた今なら、光莉が何も考えずに発言する人じゃないと確信を持って言える。
それなら「太陽が白」と言ったあの頃の俺も何も考えてないわけじゃなかったのかもしれない。
今はもう、あの頃何を考えていたのか一つも思い出せないけど。
「でもさ、キラキラに限らずだけど…擬音の色ってその時々で違うと思うな」
「例えば?」
「ドキドキが分かりやすいんじゃない?緊張してたり嫌な時のは青で、恋してたり待ち遠しい時はピンクとか赤みたいな明るい色って感じがする」
「確かに。それは言えてる」
「でしょ?」
「心模様、って案外色で表せるのかもね」
「そうかもね。…陽は今何色なの?」
「…何色だろう」
決して暗い色はしていない。
特別良いことは起きないけど、特別苦しいこともない。
「ベージュ、とか?」
「なんか渋いね」
「渋い色って深緑とかじゃない?」
「色自体がというより、それが心模様だった場合渋いなって思った」
「心模様が渋いのってどうなんだ?」
「う〜ん。落ち着いてるんじゃない?」
「…落ち着いてる、か」
平坦で、浮き沈みのない生活をしているのは生まれてきて初めてかもしれない。
父親が家にいた頃は親の喧嘩があれば頭を悩ませていたし、シロと一緒にいた頃はいつ消えてもおかしくなかったシロの一挙一動を注意深く見ていた。
今は相変わらずほとんど喋らない母親が家に居て、学びたかったことを学んで、光莉とこうやって他愛のない話をして、夜が来て朝が来る。
それの繰り返しだ。
それをベージュと言ったのを、心模様が落ち着いていると言い換えるのは正しい気がする。
「毎日騒がしくしてるつもりなんだけどな」
「光莉が?」
「うん。陽の毎日明るくなってない?」
「明るいよ。今日だってこの後ドーナツ食べに行くんでしょ?」
「そうだよ!新作。ラムネ味もあるって」
「…ラムネめちゃくちゃ好きじゃん」
「確かに。え?私今日ラムネどんだけ摂取するんだろうね?」
「間違いなく今日の光莉のキラキラは青一色だね」
「そだね。心模様は明るいブルーってことで」
平坦ではなかった頃の俺は、もしかしたらずっとブルーだったのかもしれない。
今はもうその頃の記憶があるだけで、心模様までは思い出せない。
父親が出て行った頃は家族3人で仲が良かった時代に思いを馳せて、母親に見られないように部屋でよく泣いていた。
その時に色を聞いたら、素直に青って答えてくれただろうか。
…そういえば、結局誰にも家の話をしないままやり過ごしてきたな。
最も近くにいた人物は、俺よりも家のことで悩んでるの分かってたから。
言えなかった、というよりは考えることもしなかった。
今は、なぜか家族のことをよく考えてしまう。
平坦な毎日を送っているから、心に余裕でも出来たんだろうか?
「…電話鳴ってる?」
「え」
「私のじゃない。ってことは陽じゃない?」
「あ、ほんとだ…ごめん少し話してくるね」
「うん。ドーナツ逃げないからゆっくりでいいよ」
「ありがとう」
震えるスマホをポッケから取り出して、応答ボタンを押す前に手が止まった。
表示されている名前を見るのは、何年ぶりだろうか。
「…もしもし、母さん?」
家で話しかけられることも少なくなったが、電話をかけてくるのなんて本当にいつぶりだろう。
思い出せないくらい前だ。
そう言えば一週間くらい会話もしていない。
そんな人から電話がかかって来たら、緊張して声が震える。
「ああ、陽。今忙しかった?」
「…少しなら大丈夫」
「そう。」
何を言えばいいのかも分からない。
何を言われるのかも分からない。
さっきまでテンポよく会話をしていた俺は居ない。
少しの沈黙が、緊張を加速させる。
「…何?」
「…………いや、伝えておかないと…って思ってね」
きっと母さんも緊張している。
声が小さくて、聞き取りづらい。
「うん」
「あのね、陽」
「………うん」
「お父さん、帰ってくることになったの」
「え……………」
心臓がドキドキと動き出す。
これは、確実に明るい心模様ではない。
背中に冷や汗までかき始めて、おまけに息も吸いづらくなった。
「急な話だけど、明日…夜に帰ってくるわ」
心の準備をする時間すらないらしい。
母親の声が少し明るくなった気がする。
…それも、なんか嫌だ。
「ごめん、もう行かなきゃ」
返事も待たずに電話を切った。
「…はぁ」
最近考えていたとはいえ、会いたくなったわけではない。
むしろ世間の常識とはかけ離れたあの人間性を、明確に嫌い始めてもいた。
それなのに、今更…帰ってくるだって?
母さんも母さんで、自分があれだけ苦しんだ記憶はもう…ないってこと?
「あれ陽?俯いてどうしたの、なんか嫌な電話だった?」
「…大丈夫。ドーナツ売り切れる前に行こう?」
「うん…?行こっか!」
俺も俺で冷や汗をかいたまんま、前を向いて歩き出せる。
心模様がブルーでも、ベージュに戻ったフリができる。
これが今まで平坦じゃない毎日を歩んできた俺が得た強さなのかもしれない。
そんなもの強さと呼べるのかも分からないけど。
でも。
明日が来ないで欲しいと願う俺も、そのすぐ隣にいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
