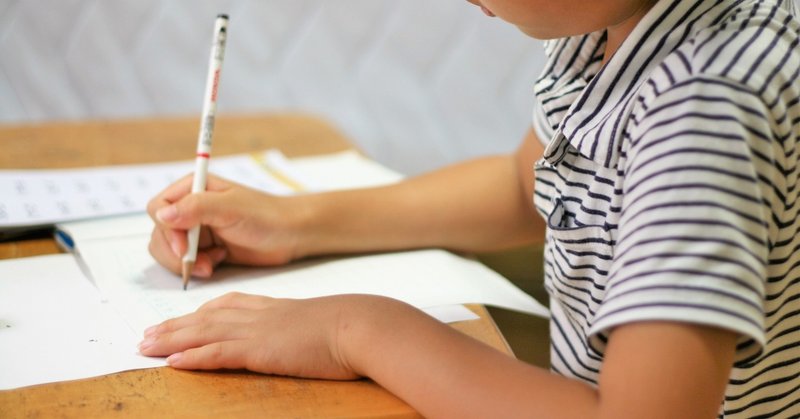
「勉強したフリ」をする子どもを徹底的に叩き潰した話
はじめに。
ちょっと過激なタイトルを付けましたが、虐待事例ではありません。
人が道を踏み外す時には、ずいぶん前に小さな兆候があります。
同じ角度で道がそれても、軌道修正は早いほうが小さな修正ですみます。
* * *
我が家のここ一ヶ月くらいの話です。
日頃からうちの子たちは、田舎の一般家庭という基準で考えると、わりと家庭学習も頑張っている方だとは思います。ただ、人間ですから、浮き沈みもあり、全然だめなときもあるわけです。
未就学の頃から、遊びの延長で、親子で一緒にいろんなことを学んできました。
小学生に上がると、今時は宿題は毎日出されますし、宿題の内容が「家庭学習」という日もあります。課題は自由だけど、やったことは先生がノートをチェックしますよという意味です。
先生が悪いとは言いませんが、これは良くないシステムだと感じています。
なぜなら、たくさんのページを埋めた子が頑張ってるように見えるから。
そんな中、事件は起きたわけです。
「解答集は、子どもに持たせるか」問題
この問題については、以前も記事にしたことがあります。
この記事の中でも書いた結論は、最終的には子ども自身が自分で解答を活用できるようになるのが望ましいということです。
そうではなければ、どこまで行っても、親なり、先生なりの力を借りなければ家庭学習ができないからです。
家庭学習はテストではないので、そのときわからないことは悪いことではないのです。むしろ、わからない問題を発見できたということが収穫で、わからないことが自分で解答を読み、理解できれば、自立型の家庭学習が完成したといっても過言ではありません。
そうはいっても、手元に答えがあればズルしたくなっちゃうよねーって、話です。
しばらく放置していた
うわべの成果主義はよくないと常々思ってはいましたが、僕も油断していました。
言い訳にはなりますが、自分の仕事も忙しく、子どもたちの家庭学習とは少し距離を置いていました。
6年生の長男は、まあまあ自分でなんとかする術を身につけ、家庭学習自体は自立にかなり近づいています。(まあ、ゲームも大好きでそこは別な問題はありますが・・笑)
3年生の次男は一応机に向かってるようだし、それなりに「今日はこれをやった」なんて報告はしてくるので、「今日も頑張ったね」なんて軽く返事をしていたのです。
ある日、どうも内容が薄くなっているような気がして、今日やった課題を見せてもらったのです。
はい、もうわかりますね。
テキトーに答えを写して、テキトーに赤丸をつけているわけです。
「ほう・・、この問題、計算もしてないけど、暗算でやったの?(某私立中入試の難問)」
次男「違う紙で計算した」
「まあ、計算はいいんだけど、どういう作戦で解いたのか教えて?」
次男「・・・えっと、どうだっけなー、もう時間たったから・・えーっと」
という具合なのです。
癖になると本当に怖い
その日は、そんなことしても全く勉強になっていないので、時間の無駄だし、自分のためにならないよ、ということろで話は終わりました。
ところが、翌日も、その翌日も、同じことを繰り返すわけです。
しかも、少しでも本当にやっているように見せかけるために、理解もしていないくせに、解答集の解説にある途中の計算式を写したり、わざと間違えて直したフリまでし始めました。
当然ですが、ちょっと中身をみれば、間違えそうなポイントでありがちな間違いというのは、むしろ問題の意味をよく理解していないとできないものです。トンチンカンな間違いを書いたら、そんな小細工はすぐにばれてしまいます。
3日目の夜、ぶち切れてみた
僕も大人なので、子ども相手に感情的になるようなことないのですが、正論で話も伝わらず、ますます状況が悪化したので、意図的に感情を出したようにしてぶつかってみました。
具体的には、勉強道具を一切取り上げて、「もうやらなくていい!そういうことやってると、どういう人生になるか考えてみろ?」というカウンターからの、KOするまで怒濤のラッシュ。
要するに・・・
小さな嘘を隠すために、もっと大きな嘘をつかなければいけないし、他人をだませばいつかバレる。そして、本当に実力をつけた人と、ずっと自分も他人もごまかし続けて生きていく人との人生は、雲泥の差であるということ。
たかが小学生の算数というくだらない次元で嘘をつき、選択できる素晴らしい人生のほとんどを自ら放棄してしまっていること。

「どっちの人生に進むかは、おまえの自由だ」
そんなことを、懇々と説教したのです。
(自分で言ってて苦しくなってきました。僕は若い頃に自分も他人も騙し、人生15年は損してます。なので、30代から倍速で生きてます。)
ちなみに、もちろん手を上げたりはしませんよ。
ただ、あえて、精神的にはズタボロになるくらいは言ってやりました。
叱るのは愛か罰か
子どもを叱るということに悩んでいる親は多いですよね。
一番よくないのは、親の方が感情的になってコントロールできてないことです。
「褒めて伸ばす」「叱らない」ということも、昨今はまことしやかにささやかれていますが、状況を完全にコントロールできる範囲においては、叱ることも有効な場合があると僕は考えています。
つまり、親の方は本当にカッとなっているわけでなく、いつもよりも言い方がキツいというパフォーマンスはありだということです。
それは、むやみやたらに出すとすぐに効果はなくなります。線路の高架下に住んでも3日で騒音が気にならなくなるのと同じですね。
また、いくらパフォーマンスとはいえ、叱りっぱなしもだめです。
そのことで、子どもが改善したのか、幸せに近づいたのかということを検証し、アフターフォローをしてフィードバックしていかなくてはいけません。
アフターフォロー
しこたま叱られた次男は、翌日になっても複雑な表情をしていました。
いじけているわけでもなく、反抗的な顔でもなく、落ち込んでいるわけでもない。たぶんだけど、反省はしているが、いきなり生まれ変わったように改善するのは気恥ずかしいというところでしょう。
解答集は本人に持たせました。
つい、考える前に見てしまうなら預けてもいいし、自分で答えを見てやって良いと、本人の判断に委ねました。
実際に預けにきたり、わからないところは自分で開いて読み込んだりしていますが、少なくともその日から、理解もせずに答えを写すようなことはしなくなりました。
そうするとノートも、問題集も、当然それ以前のようにページ数は稼げないのです。
「別に、何ページもやる必要なんてまったくないよ。1問でもいいから、自分で考え、わからないことに気づき、自分で解決できるようになったら、それは本当に有意義な1問だ」
ということを、繰り返し、繰り返し伝えています。
家庭学習デーに学校に提出した書き込みが少ないノートを先生が何と言おうと、たった半ページでも、本当に有意義な勉強したなら親が認めてやればいいのです。
(今日はたったこれしかやってないの?)
って思うことは正直あるのですが、問題は中身。
「全然わからないから、Youtubeで調べたらやり方がわかった。こういうことでしょ?それから答えを見たら、意味がわかった。」
ブラボー!
そういうことだ。

方法はなんでもいいので、自分に合った方法で「解決する癖」をつけなければなりません。
おわりに
悪い癖とは恐ろしいもので、どんどんエスカレートしてしまいます。
嘘をつく、ズルをする、あきらめる、投げだす。そういうことは、瞬間的に脳がストレスから解放されるので、中毒性があります。
依存症と同じで、はまると抜け出すの本当に大変になるのです。
手取足取り家庭学習の様子を見てあげられるのなんて、せいぜい小学生くらいだと思っています。
僕が考えている小学生の親がやるべき家庭学習対策は、学習時間の強制ではなくて、自立した家庭学習ができるようになる土台を作ってあげることです。
具体的には、やる気が起きず時間が確保できないとか、勉強場所、兄弟がうるさいなど環境が確保できないという場合に、自分自身をコントロールし環境を作る能力。そして、【まだ習ってない】という呪文の封印。
これだけ休校や学級閉鎖が頻発したり、受験システムの変更、災害や疫病による社会的なトラブル・・その上、テクノロジーの変化が非常に早いので、【まだ習ってない】は、通用しない時代になっています。

誰かのコントロール下でしか勉強できない人は、いつになっても本当の自分の人生を送ることができないと思うのです。これは、きっと大人になっても一緒です。
学校、塾、教材といった学習システムは、踏み台にして自分の人生を築くためのものでるのに、学習システムに振り回されるような人生にしてほしくないと思うのです。
「自分の力で解決したときの快感」これこそが、子どもたちが家庭学習において味わうべきものです。その、良い快感を体が覚えていれば、多少の困難にぶつかっても「なんとかなるはずだ」という自信につながっていくのです。
・・ということをいつも考えていますが、現実には、そう簡単にすべて良くなるわけではありません。
それでも、そんな思いで今後も見守っていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます^^ いただいたサポートは、今後もよりよい記事を書くための情報集計費に充てたいと思います。よろしくお願いします。
