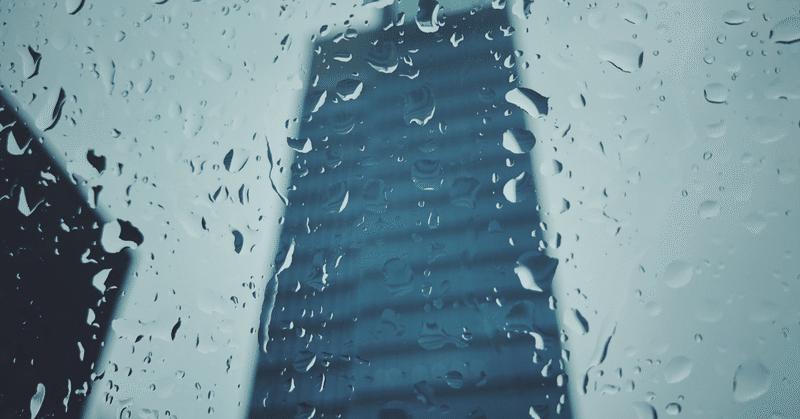
【短編小説】死神の涙
《約1700文字 / 目安5分》
雨が降る都会の街で、適当にそこら辺を散歩していた。いや、散歩というよりは浮遊。わたしは幽霊だ。
毎日こうやって浮遊していると、見たくないものを見てしまう日がある。今日はまたそんな日。
ビルの屋上、柵を超えて小さな少年が立っていた。少年は泣いている。いや、顔に雨が当たって泣いているように見えるだけかな。悲観というよりかは絶望の顔。
なんでこんな小さい子が、とわたしも絶望してしまいそう。でも目を背けてはいけない。それが幽霊になったわたしの、せめてもの償い。じっと私は少年を見つめた。
今にでも空に飛んでしまいそうな少年は、数秒後、途端にわたしを見た。少年と目が合った。
「そこで、なにをしているの?」
わたしは驚いて何も言えなかった。もしかしたら気のせい、そうとも思ったけど違うようだった。
「お姉ちゃんは、死神?」
「……死神じゃないよ。ただの幽霊」
死神と言われて少し腹が立った。
「あなたこそ、なにをしているのよ」
「見たらわかるでしょ。死のうとしている。こんな世界とは、さよならするんだ」
「まだあなたのことはよく知らないけれど、もうちょっと生きてみたらどう?」
「こんな世界に未来はない。あるのは絶望だけ」と少年は冷めた顔で言った。
見た目は小学生ぐらい。黒のジャージを上下に着ていて、裸足でいる。髪は雨でずぶ濡れ。まるで既に幽霊だ。この少年に、なにがあったのだろう。
わたしは少年の横に座って、いろいろ話を聞いてみることにした。
どうやら、少年は学校でいじめられているらしかった。理由は本人にもわからないらしい。
「でもそれだけだったらいいんだ。ぼくには、家族という、帰る場所がちゃんとあった。家族はぼくを、愛してくれた」
「それならなんで、こんなこと」
「パパが死んじゃったんだ。仕事に行ったきり帰ってこなかった。あっさりと、交通事故で死んだ。それでママは悲しんで、部屋から出てこなくなった」
そう少年は言って、ビルの下を覗いた。雨といっしょに落ちてしまいそうだった。
「結局、パパありきのぼくでしかなかったんだ。ママはぼくを捨てたんだ」
わたしは、この子になんて言ってあげればいいんだろう。止めるべきではない、そう思った。この先、生きていればいいことがある、そんな綺麗事を言うのはおこがましかった。
でも、こうやってまた止めなかったら、わたしは後悔する。
幽霊になる前、わたしは、愛する人を守れなかった。きっとこの人はいつか自ら死を選んでしまう、そう予感していても止めるべきではないと見守っていた。その結果、愛する人を失い、そしてわたしも後を追うことになった。
この少年の自殺を止めなければ、わたしはまた、後悔してしまうんだ。
「ぼくは世界に絶望しているんだ。だから死にたい。けれど、いつもこの一歩が踏み出せないんだ。やっぱり、怖い」と少年は言った。「お姉ちゃんが羨ましい」
「わたしなんて……」
わたしのことなんて、羨ましがっちゃだめだよ。わたしみたいになるな。そう言いたかっけど、言葉が喉につっかえた。
何も言うことができず、わたしは泣くしかなかった。
「お姉ちゃん、泣いてるの?」と少年は言って、わたしの涙を拭こうとした。けれど少年の指は、わたしを通り抜けた。
「やっぱりお姉ちゃん、ほんとに死神なんだ」
「……だから、死神じゃない。幽霊」
「そっか」と少年は笑って言った。
「なんで笑うの?」
「なんか、嬉しくって。ぼくのために泣いてくれて」
わたしは祈るように少年の目を見つめた。
「頼むから、死なないで──」
「ぼくさ、勇気がでた」と少年は言った。
少年は、顔をわたしに近づけた。少し、唇を尖らせて、ゆっくりとわたしの唇に向かって近づいた。けれどやっぱり、少年の唇はわたしを通り抜ける。
「ぼくがもし幽霊になれたときは、ちゃんとキスをさせて。そして涙を拭かせて」
少年はそう静かに言って、体を空に傾けた。これから死ぬというのに、笑っていた。
「はは……わたし、ほんとうに死神みたいじゃん」
ビルの下で鈍い音が響いた。雨は毛布のように、降っていた。
◆長月龍誠の短編小説
◆自己紹介
気が向いたらサポートしてみてください。金欠の僕がよろこびます。
