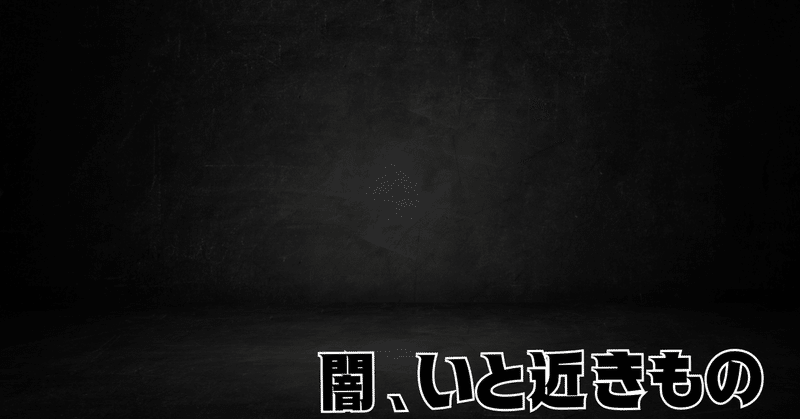
闇、いと近きもの #3
商人の忠告から、数日が過ぎた。
「おーい、ルア兄! こっちにデカいのがあるんだ! 助けてくれぇ!」
「わかった、今行く」
現時点では平和な日々が過ぎており、彼らの日常に変わりはない。いつも通りに廃材置き場へと向かい、金目の物を回収する。日銭が必要な少年たちのためにも、それを止めるわけにはいかなかった。日銭がなければ彼らは、たちまち食い扶持を失うからである。ともすれば彼らは、未だ年若い弟妹さえも抱えているのだ。
「んーーー! 抜けた!」
「良くやった。君の功績だ」
「へへん、やったぜ」
ガラリと音を立て、鐘楼の鐘ぐらいには大きな金属物が姿を現す。かつての使途は不明だが、金目の物には変わりない。丁重に引き取ることとした。ルアーキーは腕に力を込め、塊を持ち上げる。今日はこれを運ぶので精一杯になりそうだ。
「みんな、大きいのが拾えた。今日のところはここまでにしよう」
「はーい!」
「わかった!」
ルアーキーが声をかけると、少年たちは口々に返事をする。彼ら彼女らは概して素直であり、明るかった。一年ほど前、傷と報仇の情を背負ってこの街に流れ着いた彼にとって、少年たちの姿はどこかで救いにもなっていた。
「今日はもしかしたら結構な額になるかもしれないぞ」
「ほんと!?」
「ああ。そうしたらどうする?」
「弟に腹いっぱい食わすんだ!」
「あたしは父ちゃん!」
「おいらは妹!」
「そのくらいになると良いな」
他愛無いやり取りを重ねながら、ルアーキーたちは一団となっていつもの商人の元へと向かう。しかしその途上、ルアーキーは嫌な予感を抱いた。傍目に見る市場の空気が、あまりにも常と異なっている。こちらを憐れむような視線に、どこか物々しい空気。なにかあったのかと、彼らに尋ねるか。だが、直後に考えを切り捨てる。彼らと市場の民の間にある断絶は、その程度の違和感で超えられるものではなかった。ところが――
「おお、兄さん」
「やあ今日も……」
「なにも言わん。金目もこの子たちも預かるから、早く帰りなせえ」
「む?」
いつもの商人までもが、態度の違いをあらわにする。顔に汗まで浮かべて、彼に貧民街への帰還を促したのだ。意味を飲み込めなかったルアーキーが立ち尽くすと、商人は急ぎ足で彼に耳打ちをした。
「先日の忠告が、現実になっておりやす。少年たちに、それを見せたくはないでしょう?」
「――!」
ルアーキーの表情が、にわかに変わる。少年たちの頭目が、目ざとく彼に問う。
「どうしたルア兄。調子でも」
「君たちはここにいてくれ。おれは戻る」
「じゃあ俺たちも!」
「駄目だ」
ルアーキーに群がる少年少女を、彼は極めて低い声で制した。少年たちを連れて行けば、間違いなく強い衝撃に襲われる。それほどの光景が待ち受けていることを、彼は苦く、痛ましい経験から知っていた。
「申し訳ないが、君たちは足手まといになる。ここにいてくれ」
「……」
そのことを、彼は極力短い言葉で告げる。少年たちの頭目が、彼を見上げる。その目にはうっすらと涙が浮かんでいた。
「わかった。だけど、戻って来てくれよ」
「ああ。極力そうする」
ルアーキーは、少年の目を見て言った。彼はそれきり背を向け、疾風の如く貧民街へと向かって行った。早く、早く。少しでも早く。そう念じて、目的地へと向かう。彼には、加護を招く紋様がない。あくまで、鍛え上げた彼の足のみが現場へと向かう手段だった。それ故に。ああ、それ故に。
「……」
彼がたどり着いたのは、すでに惨禍が為されている現場であった。貧民街の各所から火が立ち上り、住民たちが無慈悲な刃に殺戮されている。路地裏でダハ鶏を戦わせていた男が。ルアーキーがこの街の土を踏んだ頃、心優しく貧民街に迎え入れてくれた者が。子どもたちを引き連れる彼に、柔らかく声を掛けてくれた娘が。領主の無慈悲な手によって、惨たらしい目に遭わされていた。
「ああ……」
ルアーキーは呻くように声を上げた。頭がズキリと、痛んだ気がした。心の奥底に封じていた、『あの日』の光景が蘇る。眼前で行われている惨禍に、重なっていく。
「ねえさん」
気付けば、言葉が一つ漏れていた。同時に、彼は己を恨んだ。報仇を成すために己を鍛え上げたのに、目の前の惨禍一つさえ止められないのか。握り締めている手が、皮膚を突き破る。血が土に落ちた時。彼の耳へと声が響いた。
『汝、力を望むか』
「望む」
ルアーキーは、自分でも驚くほどにはっきりと答えていた。相手が何者かとも知らず、ただただ答えていた。
『ならば、我の手を取れ。汝ほどの闇をたたえておれば、供物など要らぬ』
ささやき声が、力を増す。ルアーキーの前には、漆黒の大鏡が見えていた。おお、闇を知悉する者であれば震えたに違いない。それは闇の象徴。それは闇がその身を預けたもの。写し身でも偶像化されたものでもない、まさに闇そのもの。今こそ思い出せ。闇はいと近く、いと優しい。いと暗く、いと黒い。
「わかった」
しかしルアーキーは手を伸ばす。彼の心中には、もはや怒りしかなかった。目の前にある光景を、打ち払う力を求めていた。なれば、差し伸べられた手を取るのは、彼にとっては全くの道理だった。
ぴたり。
ルアーキーの右掌が、黒き鏡へと触れた。同時に、鏡から漆黒の淀みが溢れ出した。淀みは彼を粘液のように包み込み、いと優しく彼を包んだ。
『思いに身を委ねよ。怒りに身を委ねよ。汝の奥底にある、その泥濘。抑えている情念を解放せよ』
ささやく声に、ルアーキーは身を委ねた。自らの底を形作る、報仇の念を解き放った。そうだ。おれは。姉の敵を討たねばならない。村の復讐を、果たさねばならない。
「お、お、お、お……」
ルアーキーの目が見開く。その目からは、光が消えていた。一見、変わりない出で立ちに見えるが、呼気からは闇色の気配が立ち上っていた。
今再び、かつて闇を語った男の言葉を説こう。闇とは、人を許容する。すべてを許す。いかに汚れた行いであれ、闇はそれを許してしまう。いと優しく、いと恐ろしきもの。
ああ。ルアーキーは今。心底からの情念によって、自ら闇へと踏み込んだのだ。
『我が使徒、成れり。さらばだ』
ルアーキーの前から鏡が消える。同時に、彼の視界は平常を取り戻した。目前に立つのは、暴挙の痕跡を色濃く残した、兵士数人だった。
「なんだぁ? 混ざりてぇのか?」
「いんや、このナリはむしろ」
「殺っちまおうぜ。見られてるのは厄介だ」
ジリジリと兵士が寄って来る。ルアーキーは、目を閉じた。心の底から、情念が立ち上ってくる。こいつらを、殺さねばならない。
「あ゛!!!」
ほとんど蛮声にも似た声を上げて、彼は突進した。それは、彼には思いもよらぬ疾さだった。徒手空拳にもかかわらず、彼は瞬く間に兵士たちを屠っていた。
「……」
彼は血に染まった両の手を見る。今までも遥かにあっさりと、彼は事を成し遂げていた。しかし他の兵士たちが近寄って来る。口々に叫ぶ。
「反抗する奴がいるぞ!」
「殺せ!」
「貧民なんざ、この町にはもう要らねえんだ!」
五人。十人。興奮のままに近寄って来る。ルアーキーは、倒れた兵士から槍を奪った。こともなげに振り回す。無造作に突き出す。それだけで、面白いように兵士が倒れていく。
「へ」
無意識に出た声は、嗤いか。それとも、闇に堕した己を、嘲る声か。ともかく彼は、ここより闇色の風となった。槍を振るう。刀を振るう。それだけで、面白いように兵士が死んだ。十から先は、数えてもいない。貧民街にに入り込んだのは百程度だろう。だが、もしかしたらそれより多くを殺したかもしれない。ともかく、彼は殺した。殺して、更に殺した。冥府にすらたどり着けぬよう、念入りに壊した。
「……」
だからそれは、初期衝動からの目覚めと言ってもいいだろう。ルアーキーが力なく理性を取り戻した時、すでに火は消えていた。彼のいた街は、焼き尽くされていた。
「あ……」
憑き物が落ちたように、手にかけていた相手を見る。まさかの同類。貧民だった。見窄らしい格好をして、血にまみれていた。顔は原型を留めていない。ルアーキーは、確信した。
「おれだ」
呟く。
「この惨禍をやったのは、おれだ」
頬から、涙がこぼれた。血涙だった。血涙はやがて、闇色となる。それこそが彼に、闇の手を取ってしまったことを自覚させた。瞬間、自害が浮かぶ。しかし首を振る。闇の使徒となってしまった以上、闇からの加護が彼を護ってしまう。
「ああ」
彼は思い出した。恩人からの言葉を。戒めのように噛み締めていたはずの、その言葉を。
『闇に呑まれぬよう、心せよ。細心の注意を払え』
おれは、と。小さく言葉を吐き出す。心していたはずなのに、一時の感情で呑まれてしまった。彼は、力なく呟いた。
「戻れない」
それは決意だった。二つの意味での決意だった。少年たちの元へと戻らないこと。そして。
「すべてを成し遂げ、あの人に斬られる。それまでは、戻らない」
そうしてルアーキーの姿は、荒野へと消えた。少年の声が脳裏によぎるが、彼は即座に打ち消していた。
もしも小説を気に入っていただけましたら、サポートも頂けると幸いです。頂きましたサポートは、各種活動費に充てます。
