
『音声学者,娘とことばの不思議に飛び込む』の書評(拡大版)
先日,大修館『英語教育 2022年10月号』で以下の書籍についての書評を寄稿した。
誌面上での書評は600字程だったため,内容を精選したり限定したりせざるを得ず,書きたいと思っていたことの多くを書くことができなかった。そのため,雑誌の店頭販売が終わったタイミングで,「拡大版」として改めて書評を公開することにした(実際は「書評」なんて大それたものではなく,感想のようなものだが)。
本書は,音声学者である著者が,自身の子育ての経験や子どもの言語獲得をユーモアあふれる事例や研究成果に基づき,音声学の視点で分かりやすく語ったものである。いわゆる「子育てあるある」に共感しながら,音声学的な知識を得られるというのが本書の最大の魅力であると言えるだろう。
ちなみに,著者の配偶者も言語学者でいらっしゃるそうだ。そもそも私に書評の依頼が来たのは,この分野(英語教育)で「小さい子どもがいる研究者」で「パートナー(配偶者)も研究者」という,そう多くはない存在だからということであった(もちろんこの分野で同じ境遇の方は他にもいらっしゃるし,その中でたまたま私のところに依頼が来ただけで,私が音声学に詳しいとかそういうこともない)。
子育てあるあると音声学
序章にあたる部分で「子育てをしなければ絶対に出会わなかった発見が多くある」 (p. 21) と書かれているように,本書の主要なテーマは子育ての中で出会う音声学的事象の発見やその解説である。以下,私が特に面白いと思った(共感した)事象を取り上げてみたい。
両唇音はかわいいイメージ
「子育ての中で出会う音声学的事象の発見」の一例として,冒頭の章では,子ども向けのキャラクターは両唇音(発音するときに両唇が閉じて始まる音: [b], [p], [m] など)で始まる名前が多いという発見が紹介されている。プリキュア(の各キャラクター名)がその好例として挙げられているのだが,その他にも「パンパース」や「メリーズ」「ムーニーマン」などのオムツの名称にも当てはまっていることが興味深い。これらの名前に両唇音が多くなる理由は,「両唇音にはかわいいイメージがあるから」ということらしい(このような音が持つイメージを「音象徴」と呼ぶそうだ)。
自分の子どもについて考えてみると,確かに1歳半を過ぎた私の息子が好きな「ぷしゅぷしゅ」(©シナぷしゅ)もご多分に漏れず両唇音から始まっている。(ちなみに,この番組のダンス動画募集に我が子の動画を投稿したのだが,まだアクセプトの通知は来ていない)
1つ気になったのが,この知見において両唇音の位置はどれだけ関係があるのかということだ。本書では,基本は「両唇音で始まる」事例が挙げられているのだが,「アンパンマン」など「両唇音を含む」ケースが許容されている箇所もある。「両唇音で始まる」から「両唇音を含む」というルールに緩和すると,これまた息子が好きな「あーぷん」(Eテレ©おかあさんといっしょ)もそれに当てはまるし,「おかあさんといっしょ」の1つ前のキャラクターに至っては「ガラピコ」「ムームー」「チョロミー」の主要3体(3人?)のキャラクターすべてにこの法則が当てはまる。素朴な疑問として,「両唇音【で始まる】」ことに理論的な重要性はあるのか,統計分析において重みづけされたりするのか,などが気になるところである。
幼児語は(C)VCCVのリズム
もう1つ自分の子育て経験とリンクして興味深かったのが,いわゆる幼児語は「(C) VCCV」のリズムが先に決まっていて,そのリズムに合わせて単語が作られているということがある。例えば,「くっく」「立っち」「ちっち」「ねんね」「まんま」などがこれにあたる。
実のところ,「くつ」を幼児語で「くっく」と呼ぶことを知らず,妻が使っているのを聞いて「本当にそんなふうな呼び方があるのか」と思っていた。しかし,実際に子ども番組を見ていると,靴のことをあえて「くっく」と呼んでいることに気が付いた。それ以降に本書を読んでこの「(C) CVVC」のリズムの存在を知り,ある程度の規則性のもとにこのような幼児語が作られていることを理解した。
また,これにも関連していることとして,子ども向けの言葉には繰り返しが多いということも書かれている。改めて意識してみると,Eテレの「いないいないばあっ!」の「うーたん」が歌う歌のタイトルにはそれが顕著に表れている(以下参照)。
「だいじょうぶんぶん」
「じゅんばんばん」
「ごみごみポイ」
「フーッ、ちゃっぽんぽん」
タイトルだけではなく,歌詞全体で見るとさらに多くの繰り返しを見つけることができる。
名付けと音(共鳴音と阻害音)
本書の後半では,「名付け」に関する研究成果が紹介されている。ざっくり言ってしまえば,共鳴音(マ行,ナ行,ワ行など濁点を付けられないもの)は丸く女性的なイメージ,阻害音(タ行やカ行など濁点を付けられるもの+濁音・半濁音)はとげとげしく男性的なイメージで,その特徴が名付けにも表れているというものだ。このことをベースに男女の名前,メイドやアイドルの名前(ニックネーム),悪役やポケモンの名付けにまで話が発展していく。
あくまで傾向であり,もちろん例外も多々あるのだが,自分の息子の名前は阻害音が入っており,名前全体の音のイメージも角ばった印象を受ける。少なくとも,我が子にはこの知見は当てはまっているのかもしれない。子どもの名付けはちろん,様々な場面で分析できそうな視点であり面白い。
子どもがもう少し大きくなったら
ここまで記したことは,今まで自分が子育てをしていて共感したり,実際に体験したりしたものであるが,これから子どもが成長して発語が増えたりするとさらに共感したり,体験したりするのであろう事例もたくさん紹介されていた。たとえば,「連濁」(○○組をぐみという),「音位転換」(「ばんじゃい [ばんざい]」を「じゃんばい」という),「硬口蓋化」(「つめたい」が「ちゅめたい」になる)など,特に子どもの言い間違いを通して知る事例が多いようだ。今後,これらの事象を観察できることを楽しみにしたい。
子どもの言語発達は個人差があるため具体的に何歳から何歳までという期間を記すことは難しいが,本書の内容は乳児が「音」を発する段階から幼児が「単語」や「文」を発する段階くらいまではカバーしている。そのため,すでに子どもがある程度大きくなっている方は,自分の子どもの言語発達と同時進行で,あるいは振り返って楽しむことができるし,これからお子さんが本格的にことばを身に付けていくという方は,様々な視点で子どもの言語発達を見守るきっかけにもなるだろう。
ラップと音声学
さて,ここまで自分の子育て経験をもとに本書の中で紹介されていた興味深い事例を取り上げてきたが,本書には子育てから離れて「ラップと音声学」について解説されている章もある。著者は日本語ラップへの造詣が深く,私も熱心な視聴者であった某人気ラップバトル番組の審査員を務めたこともある。その放送回を私も視聴していたのだが,審査中に熱心に韻をメモしていた姿が印象に残っている。
韻は小節末で母音を合わせることが基本であるが,著者のデータではラッパーの方々は子音についても音声学的に近いものを組み合わせていることが示されており,これは驚きであった。実際,どの程度このような現象が見られるのだろうと思い,自分でも少し探してみることにした。一応,本書にある子音のIPA表(図5-2)を見ながら,調音点や調音法が同じであるものをピックアップしてみたのだが,如何せん音声学の専門家ではないのでこれが「音声学的に近い音」と言えるのかどうかの確信はない。この点は予めご了承いただきたい。
「子音が音声学的に近い韻」を探すにあたって,とにかく韻を多く固く踏んでいる曲のほうが見つけやすいだろうと思い,すぐに思いついたのが餓鬼レンジャーの「The Skilled feat. LITTLE & FORK」だ。聞いてもらえば分かるが,とにかく韻の量と質がすごい。
歌詞をざっと眺めてみると,以下のような組み合わせを見つけた。
「磨くとさ」[migakutosa] /「味覚の差」[mikakunosa] ([g]と[k]は軟口蓋音, [t] と[n]は歯茎音?)
「(実)感と証拠」[kantosyouko] /「感度良好」[kandoryoukou] ([t]と[d]は歯茎音, [s] と[r]は(後部)歯茎音?)
「研磨」[kemma] 「鍵盤」[kemban] 「(駆け抜)けんだ」[kenda] ([m]と[b] は両唇音, [b] と[d]は破裂音)
全ての組み合わせが音声学的に近いと言えるのかは分からないが,感覚的には非常に似ていると感じる。
ラップに関してもう1つ,著書の別の書籍『フリースタイル言語学』で書かれていた事例になるのだが,面白い知見として「日本語ラップの字余りに含まれやすい母音は『い』と『う』」であるというものがある。これはこれらの母音が短く静かである(聞こえなくなることがある)ためだそうで,字余りでも韻を感じやすいからのようだ。このこと意識してラップの歌詞を吟味してみると,当てはまる事例を多く見つけられるのではないかと思う。たとえば,上記の「証拠」と「良好」も後者が字余りで「う」が含まれているが,実際に曲を聞いてみるとほとんどそのような字余りが意識されることはないだろう。
英語教育関係者に向けて
知的に面白い内容であるためそれだけで十分に書くことがたくさんあり,書評の際には忘れがちだったのだが,媒体の読者層を踏まえれば(というか自分の立場も踏まえれば),当然「英語教育関係者に向けて」ということをもっと意識すべきだったと反省している。結局,字数の問題で「(私のように)音声学に苦手意識のある英語教育関係者にも,ぜひ手に取って頂きたい1冊」という一言しか書けなかったのだが,英語教育関係者に向けてという点でもう少し詳しく書いてみたいと思う。
音声学をポップに学ぶ
立場上自分が言うのも憚られるのだが,私は音声学には多少の苦手意識を持っていた。特に学生の頃は,出てくる用語が難解だったり,音声学の理論と実際の英語授業場面をうまく結びつけることができず,音声学を敬遠していた記憶がある。その後,英語教育を深く学んでいく過程で音声学の重要性を否が応でも認識することになるのだが,苦手意識はなかなか払拭できないでいた。私の半径5メートル以内では,今も昔も英語教職課程の中にこのような学生は少なからずいる(いた)ように思う。
英語教育における音声学の役割や,英語教員養成における音声学の重要性やその在り方などは,音声学をご専門の先生方が論文や書籍など様々な場所で語られている。もちろん,本書だけで英語教育における音声学を学ぶのに十分だと言うつもりもないが,ここではあくまで本書の書評として,音声学に苦手意識のある英語教育関係者が日本語や身近な話題から音声学を学び直すための入り口としておすすめだということを強調したい。音の出し方(調音点・調音法・有声性),音の区切り方(音節),音韻変化(連結や弱化,同化)などは「英語科教育法」を冠する多くのテキストで解説されていることではあるが,本書ではこれらの基本的な知識をユニークな事例とともに楽しみながら(=ポップに)学ぶことができるだろう。本書を入り口にして,自分が持っている音声学のテキストや英語科教育法のテキストを読み直してみると,より理解が深まるのではないか。
小学校の先生にこそ読んでほしい
英語教育関係者に向けてもう1つ言うとすれば,本書はぜひ小学校の先生に読んで頂きたいと思える内容だった。もちろん,中高の先生でも楽しめる内容であるし,小学校の先生で音声学に詳しい方もいると思うのだが,現状小学校の先生の多くは,外国語が導入される前に免許を取得したので教職課程で英語教育についてほとんど学んでいないか,あるいは外国語導入後に免許を取ったとしても,初等教職課程では他の教科とともに英語を学ばなければならないので,中高英語免許を同時に取得していない限りは初等教職課程で英語の音声学的な内容に触れる時間・場面は非常に限られている。なお,最新の調査でも,小学校で外国語を担当する割合の半分以上は学級担任,小学校教員で中高英語を免許を取得している教員の割合は7.5%という結果が報告されている(文部科学省 令和3年度「英語教育実施状況調査」の結果について)。
また,ただ単に多くの小学校教員にとって音声学を学ぶ十分な時間・場面がなかったということだけが理由なのではなく,小学校外国語(英語)の特性も関係している。小学校では,英語を初めて学び始めることや児童の発達段階を踏まえて,英語の音声言語(聞くこと,話すこと)の指導が中心となる。高学年になれば文字言語の指導も行われるが,それもあくまで音声言語の十分な指導を前提としたものであり,音声指導に重きが置かれることに変わりはない。将来的な英語の文字や単語の読みに音韻認識が重要な役割を果たすことを踏まえれば,文字言語の習得のためにはむしろ音声指導が重要と考えることもできる。また,小学校では英語を通じて児童の「言語意識」を育むことが重要であるともされており,日本語と英語の音の区切り方の違いなど,音声学的な知識はこのような指導にも貢献する。このような小学校での音声指導の重要性を鑑みれば,本書は小学校での英語指導に携わる人にこそ読んで頂きたい内容なのだ。
日本における女性研究者のキャリア
最後に,冒頭に述べた通り著者の配偶者も研究者(言語学者)ということもあり,コラムではあるが女性研究者のキャリアの問題についても触れられている。
妻の仕事のために旦那が引っ越さない問題
特に印象的なのが「妻の仕事のために旦那が引っ越さない問題」と題されたものであり,夫婦の職場が互いに遠い場合,大抵は妻が夫の職場近くへ引っ越すというものだ。これは研究者夫婦に限ったことではないものの,特に夫婦ともに研究者である場合はそれぞれの職場は違うけれども近い場所にあるというのは相当な幸運でない限り難しく,研究者夫婦は多くの場合で当てはまることではないだろうか。また,私の周りでの話になるが,妻が研究者で夫が非研究者だったとしても,その多くは夫の職場近くに引っ越し,妻は長い通勤時間を掛けているケースが多いと思う。それでいて夫がその分妻よりも育児や家事を多くこなしているかというと,必ずしもそんなことはないと聞く…(自戒を込めて)
自分自身もこの状況に当てはまっているので偉そうなことは言えないのだが,これからこのような状況を迎えるかもしれない方々は,決して「夫の仕事のために妻が引っ越す」ことがデフォルトではないと考えるべきだし,すでに引っ越してしまったという場合は,職場が近いという恩恵を享受している分,育児や家事を多くこなすべきだろう(2回目の自戒を込めて)。
子どもを連れての学会参加
また,このコラムでは「家族みんなで学会に行こう!」 (p. 229) と題し,「自由に子どもを学会に連れていける文化が育ってほしい」(p. 230) という思いも述べられている。
英語教育の分野でも同じような声があがっていて,もう5年以上も前に論文という形できちんと世に出されている(星野,2017)。それから数年してパンデミックにより学会はほぼオンラインになってしまったわけだが,少なくとも私の記憶ではパンデミック以前であっても,本書のコラムや上記の論文に書いてあるような「家族で学会に行く」ことの障壁が低くなったようには思わない。対面の学会も再開される兆しが見えてきた昨今,英語教育分野ではどの(全国レベルの)学会が「子連れ学会ウェルカム」の姿勢を最初に打ち出すのかが見ものだと個人的には思っている。
当事者以外は無関心
女性研究者のキャリア問題にしろ,若手研究者の雇用体制や待遇の問題にしろ,これまで幾度となく声はあがっていると思うのだが,哀しいかな,そういう問題に関心があるのはほとんど当事者だけと感じざるを得ない。もちろん当事者以外でも関心を寄せてくださる方はいるのだが,それはマイノリティーであって,学会や大学の中心・上層にいる方々の多くはあまり関心がないか,あるいは問題をそこまで深刻に捉えていないように思える。本書もこういった方々が手に取って読んだとしても,このコラムは読み飛ばされてしまうのではないかと危惧してしまう。だからこそ,誌面上の書評では,限られた字数ゆえに一貫性を欠くと分かっていながらも,本論からずれるこのコラムに触れて「管理職や学会の運営に携わる方にぜひ読んで頂きたい内容」と記した。その思いが伝わればいいのだが。
終わりに
誌面上の書評は以下の一文で締めくくった。韻を踏んだ一文を書いたのだが,編集の方ですら誰にも何も言われることはなくて,虚無感と羞恥心だけが残った。
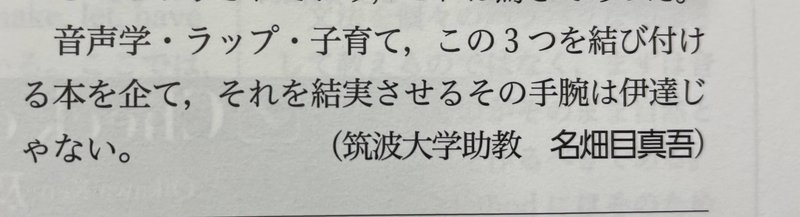
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
