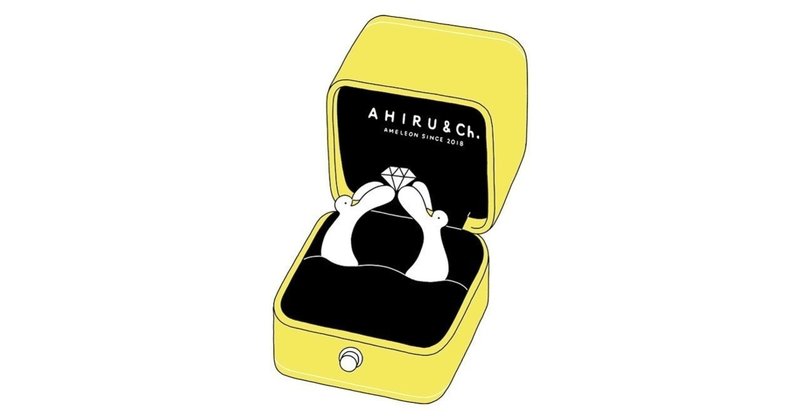
だれかの気持ちが分かるということ
エコマムの記事です。14年前のお話ですなぁ。月日のたつのは早い。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
千年前の人が美しいと感じたことが伝わる
春休み。京都に遊びに出かけてきた。子どもたちは動物園と映画村でおおはしゃぎ。親たちの行くお寺にもいくつかつきあってもらった。薄暗い本堂に並ぶ仏像に4歳児は「なんか、こわいねー、早く行こうよ」。9歳児は「これ、なんて書いてあるのー?」と解説をせがむ。
ぼんやりと仏像を眺めながらふと思った。「たとえば、仏像のこの裾のひだの流れ方。千年前の人も美しいと感じてこんなふうに彫ったんだよねー。それを今の世界の私もきれいだなー、と感じられるというのはどういうことなんだろう」あるものを美しいと感じたり、すごいなーと感動したりということ。「美しいと感じなさい」「感動しなさい」と言われても、絶対無理、ということを思うと本当に不思議。でも、振り返ってみると、小さいころは仏像に対してそれほど感動したり、美しいと感じたりはしていなかった。むしろ、「早く行こうよー」という口だった。それが、いつのころからか「味わう」とでもいうような感覚が出来てきた。
「感じる」ことの素地
この感覚は花を見たり、絵を見たりということでも同様だ。親に連れられて梅林に行ったり、ハイキングに出かけたり。親たちが梅だらけの小山をめぐりながら「まあ、きれい」とか「いい香り」とか言っている間、小学生ぐらいの私は「何でこんなところにくるのかなー」「何だか、うすら寒いし、面白くないし、早く帰ってTVでも見たいなー」なんて思っていた。ハイキングも中学生ぐらいになると「私、待ってる」。「面倒くさい」といった気分が強くなった。「シュンランが咲いてる!!」だの「これは何の花かしら」だのワクワクと弾む親たちの声ほど、子どもの私には楽しくはなかった。たまに、わらびとかが生えていて、それを摘んだりするのは面白かったけど。
それが、大学生ぐらいになって久しぶりに友だちと東京の近郊にある高尾山に行ったら、これが楽しい。農学部の学生たちなので野鳥研究会の子が鳥の解説をしてくれたり、木に詳しい人が木の名前を教えてくれたり。そんなこと抜きにしても、山や緑が本当に「気持ちよい」と感じた。こう感じたのは、それまでに親たちに連れまわされた体験があったからなのかなー、とも思う。時々、「緑が足りない!!」という気分になって、近くにある井の頭公園に発作的に出かけたりしているのも、そのせいなのかもしれない。
実感レベルで感じるということ
絵を見ることを考えてもそう。高校生ぐらいのとき「絵を見るというのはどうも高尚なことらしい」という「考え」で、あるいは「カッコつけ」で見に行ったりしていた。そのころは何が面白いのかよくわからないまま、内側から感じることなどたいしてないまま、通り過ぎていた。あるとき、この状態が何か変だと思い始め「もし、この中の一枚をもらえるとしたら、どれが欲しいか」という目でみてみた。すると、俄然、見方が変わった。自分にかかわりがあると思って見ると、これまでとは全く違うふうに見えてきた。すごく熱心に見る自分に驚き、何てゲンキンなヤツなんだとあきれてしまうほどだった。
そんな目で見て、「これが欲しいなー」「好きだなー」「この雰囲気はなんだか好きじゃないなー」と感じてみる。すると、何百年も前の異国の人に対して「ああ、あなたもこの感じがいいなー、と感じたのね」という気分になることがあり、これもとても不思議な感じがする。
だれかの気持ちをわかろうとすること
カウンセラーという仕事、だれかの感情を理解する、わかろうとするということがその大半なのだけど、自分以外の人の気持ちや考えが「わかる」というのは本当に不思議なことだと思うのです。そして、自分以外の人のことがわかるためには、もしかすると小さいころわけもわからず、ハイキングに連れられて大人たちが感動したり、感嘆したりするのを見ていたことが素地となるのと同様に、大人たちがだれかを理解し、わかろうとする姿を見かけることとか、子ども自身が共感されたり、「わかってもらえた」実感といったようなものを、そこここで経験することが必要なのかなーなんていうことも、つらつら考えた春休みなのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
