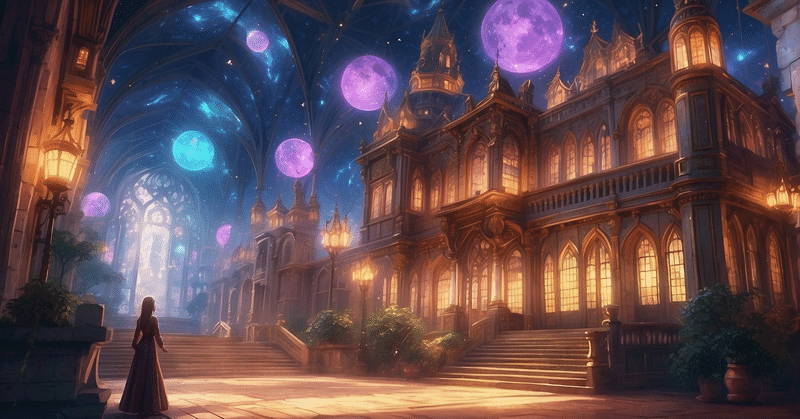
シリーズ 昭和百景 「疎開とダム移住」 歴史に学ぶ、移住の成功体験は「集団で」「コミュニティごと」。
移住ブームもついに平成から令和へ、さらにコロナ移住という新しいニーズを取り込み、久しぶりの「地方回帰トレンド」として定着した。
あらためて現代における「移住」の歴史を振り返ってみたい。
現在、移住誘致を積極的に行う自治体は、基本的に「個人」を対象にしている。
移住におけるトラブルは行政による制度や仲裁を経ても、決して解消されることはない。もちろん、その場その時の個別状況に行政が目配りして手当てをすることは必要だろう。しかし、それはどこまで行っても「対症療法」にとどまる。移住成功のヒントを「集団移住」に探ってみる。
戦前の官製移民を除けば、都市部の人間の移住の流れが生まれたのは、第二次大戦中の「疎開」である。
石川達三の小説「暗い嘆きの谷」などでは、長野に集団疎開した児童や付き添い教諭らが受けた悲惨とも言える状況が描かれている。
移住は必ずしも心温まる風景ではなく、暗い記憶としても知られている。
だが、退職を契機とする「田舎暮らし」や移住市場を手堅く支えているのは、こうした学童疎開の世代でもある。
戦時中に疎開先での食糧確保や人間関係に悩まされながらも、老後に田舎暮らしを求めるのは、当時の移住体験が決して「悪い思い出」ではないからと言える。これは、現代の移住層の内面を捉える上で見落とされがちな一面でもある。
私がヒアリングした東京都葛飾区在住の80代の女性の体験は、次のようなものだった。
終戦から70年以上が過ぎた今日まで、帝釈天で名高い東京・柴又と新潟との間で、学童疎開を縁とする一本の絆が育まれてきた。
始まりは昭和19年(1944年)8月の東京・柴又からの学童疎開に起因する。彼女たちを乗せた疎開列車が上野駅を発ち向かったのは、日本海側の新潟県東頸城郡浦川原村(現・上越市)であった。小さな農村の集落である。受け入れ先は顕聖寺という禅宗のお寺。柴又小には現在も「疎開名簿」がb残っている。それによれば戦時中、総勢131名が顕聖寺を始め四つの寺に分かれて滞在した。
突然の大量の転校生に、地元の児童らは当然、戸惑う。同じ学級でも、疎開組と地元組とで水と油さながらに分離した学校生活だったという。もちろん、教室を離れても、疎開児童に対する心理的な影響は強く見え隠れした。
「やっぱり、疎開してきた者を受け入れるということで、集落でさえ戦争中の大変な時に、私たちのせいで負担が大きくなるでしょ。子どもながらに親が家庭で話すのが聞こえているんでしょうね。だから、子どもとしても疎開児童をどこか疎ましく思うことがなくはなかったでしょうね」
下校途中、山の中腹で待ち伏せされ、地元の男の子から石を投げられることもあったという。いわば、強烈なイジメに遭ったのだ。
「そろそろ、この辺で石が飛んでくるわね」などと言いながら、身構えつつ、茶化しつつの下校の思い出だった。
思い出において辛さより美しさがまさるのは、時間が経ったからではない。現代なら「村八分」になりかねない状況から回避できた背景には、学童疎開が「集団移住」であった点が見逃せない。
つまり、コミュニティそのものの移動によって、対外関係の辛さが仲間内で緩和されたのだ。
「疎開先での嫌な思い出や出来事も、孤独ではなく仲間と一緒だったから」という事情が、田舎暮らしに対する決定的な悪感情を取り除き、むしろ晩年になってからの憧憬を育んできたという。
ここに移住成功の鍵がある。集団か個人かは、その後の移住史においても、移住の成否に時に決定的な違いを生むのだ。
戦後の大規模な集団移住には「ダム移住」がある。例えば、バブル期に栄えた山梨県・清里を開拓したのは、昭和30年代に奥多摩湖の着工で沈んだ東京都奥多摩町の人々であったことはあまり知られていない。
彼らはダム湖建設による生活圏喪失にともない、当時はまだ「未開拓の不毛の地」であり、地元民でさえ容易には寄りつかなかった清里高原に、生活の新天地を求めたのである。彼らは見事に「地元化」を果たして今日に至る。
日本には現在、治水対策と電力需要、水源確保の目的から3000を超えるダムがあるとされる。全国で生活圏を失った山間部集落の多くが、かなりの規模で集団移住を果たしている。比較的近隣の都市部に移った例が多いとされるが、中には以下のような例もある。
岐阜県奥飛騨の山中からダム移住の一団が、保証金を元手に、今や東京有数の歓楽街となった渋谷に集団で移り住み、道玄坂・円山町界隈に旅館街を形成した。ブティックホテル街が発展する発端となる。
表面の喧騒からは見えにくいが、渋谷は現在も岐阜県出身の旅館経営者らが数多く残る、隠れた「岐阜村」である。
富山県と石川県の県境に近い現在の刀利ダムに沈んだ村の人々の多くは、峠を越えた金沢市に移り住んだ。そして令和の今に至るまで、当時の村のコミュニティを維持したまま、身を寄せ合うように居を構えている。


移住先の金沢市内は現在でも、いわゆる血縁とは別に地域内での後ろ盾となる「親代わり」が必要な場所で、本来であれば土地に縁のない者の移住は容易ではない。
しかし、戦後の水害対策からダム建設の計画が浮上したのち、1961年に最後の住民27戸189人が集団移住を果たす。かつての村から背丈以上もある仏壇を村人全員で運び出し、移住が完了した。彼らの多くは今日まで「定住」している。
文化、習慣のまったく異なる場所に移住しながら、数十年に亘り小さな社会を維持し続けているのが、戦後から高度経済成長期にかけてのダム移住の特徴ともいえる。
現代の移住の課題は、既成のコミュニティに個人単位で流入することの難しさに集約されるケースが多い。その点で成功しているのが、同じ信仰を持つ人々によるまとまった数での集団移住である。
昨今、移住者人気が高いとされる山梨県北杜市では、いくつかの信仰団体が本部拠点を構え、全国から信者らが流入している。彼らの多くは、地元集落から離れた別荘地ばかりに住居を構えるわけではない。
特徴的なのは、集落に隣接しながらも集団で住宅地を形成し、ある種の「ニュータウン方式」を実行している点だ。まとまった土地を購入し、そこに戸建て住宅街を形成し、全国から転入してくるのだ。
数の力に数で対抗する対立的な共存でなくとも、集団と仲間そのものが、異なる習慣や環境からの緩衝域として機能するのが集団移住である。移住者を受け入れる側にも「移住コミュニティ」をブロックで形成することは、共存共栄という視点から見てデメリットばかりではないはずだ。
本稿は『日経グローカル』誌の連載を修正・改稿
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
