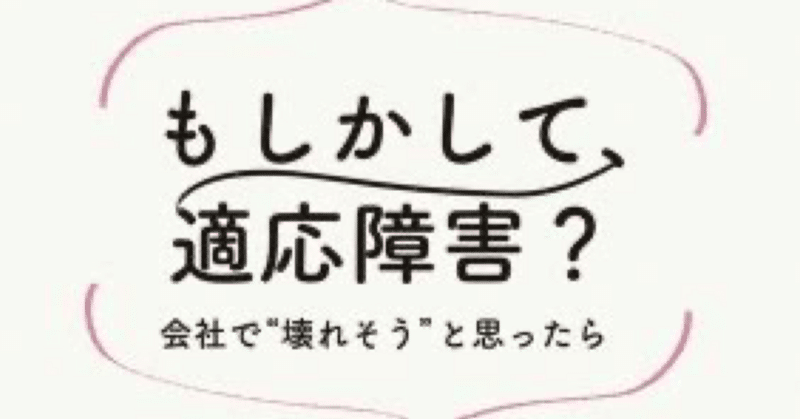
適応障がいと診断されてから半年、働き続ける為に大事な事は
適応障がいと診断されて半年経ちました
今年の2月頃にコロナ禍のピークを迎えた事もあり体調を崩してしまいました。
その時の様子はこの記事に書いてますので良かった読んでみて下さい
あれからおおよそ半年経ちました。
現状としては
・年休を削って休憩時間を延ばして働いている
・嘔吐の症状は今の所出てない
といったところです。
身体としてはある程度運動が出来るくらいに健康なのですがメンタル的には「あの人といると萎縮してしまうな。。。」というのが残っています。
適応障がいになって改めて身に染みた事
適応障がいなんて絶対にならない方がいいです。
ならない方がいいんですけどもし身に染みた教訓があるとするなら
・職場は自分の心身の健康までは保証してくれるわけじゃない
という事です。
職場で適応障がいと診断された事を伝えた時も上席者の対応としては”出来れば同じように働き続けて欲しい”、“シフトの穴を埋め続けて欲しい”というのが見え隠れした対応だったような気がします。
職場の人の一人一人は良い人間なのかもしれないけど組織になると優先されるのは業務を滞りなく進める事が優先されるんだなぁと思いました。
それでも働き続ける為に大事にしたい事
これからも自分は働き続けないといけないし多分、働き続けた方が自分の為にも良い気がします。
働く事でお金の他に社会人としての経験や、自分はこういう事が出来る、人の役に立っているという充実感、職場の人との繋がりが生まれてきます。
なので発達凹凸の事も考慮しながらどんな形であれ働いていた方がいいと思います。
発達凹凸の傾向がある人が働き続けるために大事なことは自分の価値観や何が得意で何が苦手かを理解することが大事です。
自分の事で書き出してみると
・マルチタスクや早く作業したり、能率を求められることは苦手、一つの事にじっくりと取り組みたい。
・お金も大事だけど、それより人の役に立ちたい。ありがとうと言われたい
・一番のストレス要因は”人間関係”。声が大きく、プレッシャーをかけられるのがストレスになる
といったところでしょうか。
自己分析は一般の就活でも行われますが、発達凹凸の傾向がある人は苦手な事と得意なことの差が大きい分自分が何が得意で、何が苦手かを見極めることが大事になっていきます。
ではどうやって自分の得意、不得意、価値観を見極めていけばいいのでしょうか?
身も蓋もないですけど実際に働いてみるのが一番分かると思います。
僕は介護職の前はテレビ局で契約社員として働いていたのですが分かった事は
・マルチタスクが苦手な事
・ドタバタした現場に強くストレスを感じる事
・同僚にお礼を言われると嬉しい事
でした。
3年間働いた後、将来性に不安を感じた事と両親に人の面倒を見る仕事が向いているんじゃないかと言われたのを思い出して介護職へと転職しました。
介護職の仕事は人の役に直接立ちたい。ありがとうと言われたいという自分の価値観に合っていました。
発達凹凸の傾向がある人が働いていく為に大事な事は苦手な事を避ける事、ここはなんとか出来そうな事を探してみる事。
つまり自分の凹凸を見極めて社会の中で適応する場所を探す事だと思います。
まとめ
・適応障がいと診断されてから半年、大きな症状は出ていないけどこの人といるとしんどいなという萎縮はある
・職場の一人一人はいい人なのかもしれないけど業務を滞りなく進める事が優先されるのかなと感じた
・発達凹凸の傾向がある人が働き続ける為に大事な事は当人の得意、不得意を見極めて職種を選ぶ事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
