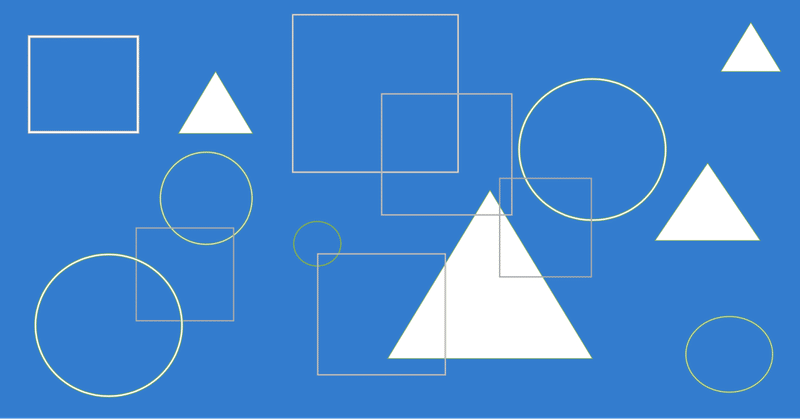
『パラダイムシフト』を読む
ネットで話題になっていた『パラダイムシフト』という漫画を読んだ。(https://twicomi.com/manga/e3_noguchi/913693963118190594)
とても面白く、ストンと納得のいく部分の多い作品だった。ネタバレになるが、まずはあらすじを紹介しておこう。主人公は父親から虐待を受けて育つ。歴史が大好きで頭もよく、高校受験の際に名門校を勧められ、父を見返せる、という思いもありつつ勉強に励み、見事合格を果たす。しかし入学直後に鬱病を発症、成人後も悩まされ続けるが、恋人が背中を押してくれたこともあってそれを「治す」ことを考え始め、さまざまな過程を経てようやく鬱が消える。この「鬱が消える」までの過程、そして消えてからの日常に「自分を見つめること」が徹底的に描かれており、鬱病のみならず、自己肯定にもつながる問題がていねいに示されている。くわしい内容は本作を読んでもらうとして、核心は結局「自分の本心に寄り添う」ということに尽きると思う。このことについて、以下に要点を整理していく。
1)本心の声を聞く
本心とは要するに、自分の中にいる子どものようなものだ。インナーチャイルドという言葉は私も聞いたことがあるが、そのチャイルドの声を聞き、受け入れるということである。ただし、「受け入れる」というのはなかなか難しい問題を含む。何でもかんでも聞き入れる、というのとは違うからだ。この時に重要なのが、事実と感情を分けるということである。本作で紹介されているのは次のような例だ。インナーチャイルドが「仕事がめんどうくさいから行きたくない」と言ったらどうするのか。「行かない」ですむなら休めばいいが、このチャイルドは「お金がないのもイヤだ」と言う。この時、「お金なんかどこからか湧いてくる」というのは事実のごまかしであり、「ごちゃごちゃ言わずに仕事に行け!」と言うのは本心を無視することなので、どちらもダメだ。この「事実と感情」の二つを区別しつつ折り合いをつけていく、ということは、日常生活をフラットに生きるために、非常に大切なことなのではないかと思う。
2)アドラー心理学
本作にはもう1つ、興味深いポイントがある。アドラー心理学である。
アドラー心理学は、確か3、4年前に大ブームになった。御多分に洩れず、私も『嫌われる勇気』と『幸せになる勇気』を読んだ。一見逆説的なことが書かれているようにも思えるのだが、読んでみるときちんと納得できる。私はアドラーの考えは支持したいと思っている。
本作に大きく関わるのは、まず第一に「褒めてはいけない」という点だ。アドラー心理学では、人間の問題行動を5つに分ける。1. 称賛の欲求、2. 注意喚起、3. 権力争い(=争いを挑む)、4. 復讐、5. 無能の証明である。この点に注意しつつ本作を読み返すと、まさに主人公がこの問題行動のステップを踏んでいることがわかる。
主人公(S君)の父親は、突然キレて暴力を振るう男だ。そこにはルールがなく、幼いS君はルールを見つけようとあれこれ模索するも、虚しく終わる。ところが幼稚園の面接でS君がかけ算を披露し、それを母親が話した時、父親は初めてS君を褒める。S君はそれを嬉しいと思い、以後褒められようと行動するようになる(称賛の欲求)。幼稚園でも歴史上の人物の名を延々と披露し、先生は戸惑いながら「褒めてほしいのかしら」と考えつつもあえて褒めない。するとS君は、「足りなかった」と考えて、さらに知識を披露する(注意喚起)。ここで褒めない幼稚園の先生は、実は立派だ。
小学校に入り、父親のことでイライラすることが増えたS君は、ある日友だちに喧嘩をふっかける。これは「争いを挑む」状態である。さらに中学に入り、名門校を受験すべく勉強に打ち込む。ただしこの奥には父親を見返したいという思いがあり、すなわち「復讐」に当たる。それゆえ、目的を果たしたもののうつ病に取り憑かれ、何もできない生活を送らざるを得なくなる。そしてアドラー心理学を知って「無能の証明」という言葉を見たとき、S君は「今の自分だ」と感じるのである。このプロセスの描き方に説得力があってわかりやすい。
改めてここにS君の辿った心の経緯を整理してみて思うのは、承認欲求が強い「かまってちゃん」、やたらマウントを取りたがる人、というのはどこにでもいて、そういう人の振る舞いは要するに問題行動といっていいのだ、ということだ。そういう人からはとっとと逃げるに限るし、「話せばわかる」などということは決してない。
第二に、「過去は存在しない」ということも主人公に大きな影響を及ぼす。アドラーによれば過去の出来事は単なる出来事であり、そこに意味づけしているのは「今の自分」だ。だからトラウマも存在しない。かつてアドラーを読んだ時、私はここに一番心を動かされた。確かに出来事それ自体には意味はない。貧困や飢えでさえも、それを「不幸だ」と見なすのは自分である。この考えを知ると、「今」がとても自由である気がした。この「過去は存在しない」ということを頭に置いて本作を読むと、二つの興味深いシーンに思い当たる。まず、S君が鬱病について調べ、それが自分に当てはまることに気づいて絶望し、自殺を図る、というエピソードである。この後「一度死んだのだから」とS君は心療内科の門をくぐることになるのだが、この時S君は一度過去の自分をチャラにしている。次に、実際にアドラー心理学を知り、「過去は存在しない」という言葉に出会う場面である。この時からS君は、過去のひどい出来事が存在しないとしたら、鬱病はなぜまだ自分の心に居座るのか、ということを考え始め、少しずつ鬱病の声に耳を傾けるようになり、やがて病と手を切ることに成功する。この構成も巧みである。
3)自己虐待
最後にもう一度インナーチャイルドに話を戻そう。本作では「本心に寄り添う」ことがとても丁寧に描かれるのだが、その反対は「本心を受け入れない」こと、すなわち自己虐待ということである。本作に登場するカウンセラーは、「人に言ってはいけないことは自分にも言ってはいけない」と言う。ここを読んだ時、よく話題になる「日本人の自己肯定感の低さ」の原因がわかったような気がした。日本人の親は、子どもを人前でよく貶す。謙遜なのだろうが、自分の子どもの至らぬところを(本人の聞こえるところで)言うのだ。これは絶対にしてはならないと思う。これは多分、子どもを「自分のエリアにいる人」と思っているからだろう。実は私の夫というのは、近しい人物のことを人前で「下げる」傾向があり、私もその対象にされたことがある。親しさの表れとして貶したり茶化したりするのだ。夫にしてみれば「自分のエリアの人」ということで「近い存在」ということなのだろうが、私はそれが非常に不愉快で、徹底抗戦した。よく日本の男は妻のことを人前で貶してみせるが(そして妻も聞いていたりする)、ピントのずれた謙譲の文化は相手の自己尊厳を削るだけなので、やめたほうがいい。
結び
昔『最高の離婚』というドラマがヒットした。この主人公の光生というのは、歯医者に行ってそこの歯科衛生士に妻である結夏(我が「推し」である尾野真千子さんが演じている)の悪口を延々と言い続ける。妻はその悪口を直接聞いていないけれど、光生は妻の結夏のことを全く認めていない。そんな人と暮らすのは、さぞかし傷つくことも多かったことだろう(それが爆発するのが、伝説の第4話だ)。そう言えば、昔、恩師が授業の合間の雑談で「今の親は子どもを甘やかしすぎる」「子どもが少ないから小皇帝や」「昔は自分の子を豚児と言ったもんや」などと言っていた。それを聞いた時はまだ学生で、自分が子どもを持つということなど考えもしなかったが、少なくとも親に豚児などと言われるのはまっぴらごめんだ、と思ったことだけははっきりと覚えている。ちなみに恩師には子どもはいない。また、身内を貶すという文化以外にも、日本には「本心の虐待」のタネがあちこちに蒔かれている。空気を読むことを強要され、無理矢理そこに合わせなくてはならない、というのは自己虐待そのものである。「空気を読んでも従わない」という鴻上尚史の著書のタイトルは、実はとても大切なことを言っているのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
