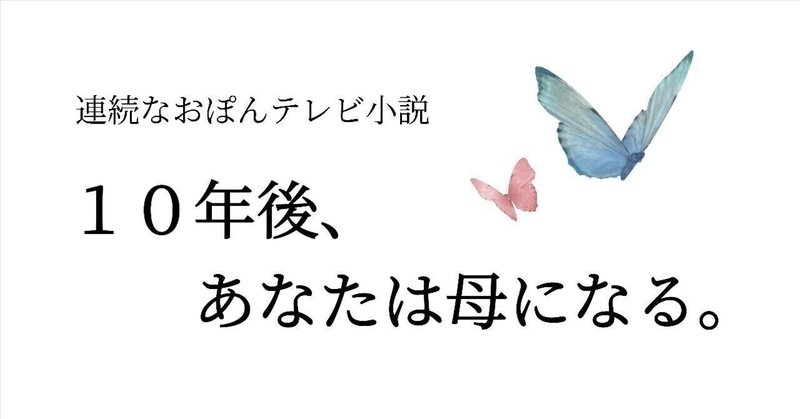
連続なおぽんテレビ小説 「10年後、あなたは母になる」 一部 第4話
10年前、私は「子宮頸がんの恐れがあります」と健康診断の通知を受け取った。
売れない芸人を養っていたら、生活破綻すれすれの状況に陥り、水商売のバイトでどうにかしのいでいたときだった。
勤め先のジムのオープンまでに、トレーニング機器の状態を確かめ掃除するのは、毎日の業務だった。
大手スポーツクラブから高級スパ施設併設のこじんまりとしたスポーツジムに引き抜かれて、3年が経っていた。
いつもなら目をつぶってもこなせるルーティンワークの途中、パワーラックのベンチ台にへたりと座りこんで、立ち上がれなくなった。
「至急、精密検査を受けてください」
真っ赤な紙にかかれたメッセージ。
なぜ、わたしが?そこから考えが前に進まない。
しばらくして出社してきたスタッフに「どうしました? 顔が青白いですよ?」と声を掛けられて、我に返った。
とっくにオープン時間を過ぎていた。
人には相談できなかった。健康な身体だけが自慢の自分に病気の疑いがあると、人には言えなかった。
ひとりこっそりと情報を集め、地元の病院ではなく、水道橋にある大きな病院を選んだ。
今思えば、一度検査に引っ掛かったくらいで大袈裟だったのかもしれない。けれど、突然目の前に現れた「がん」という言葉のインパクトは大きく、精密検査の日まで生きた心地がしなかった。
検査は淡々と、機械的に終わった。
結果を待つ病院の廊下には、がん早期発見の啓発ポスターやら、不妊治療の案内やらが雑然と貼られていた。
「しばらく3ヵ月ごとに様子をみましょうか」
診察室で医師が言った。
がんが疑わしいのに様子見?
意味がわからずに黙っていると、医師が丁寧に説明を始めた。
「今はいわゆる前がん状態で、がんがあるわけではないんです。直ぐに処置をする必要はない。でも、しばらく経過観察する必要はあると思っています」
それを聞いてやっと、緊張の糸がふっと解けた。
帰り道は、白黒映画の中にいた自分に、色が戻ってくるようだった。空は青みがかったオレンジが美しく、居酒屋街から漂う香りに空腹を感じた。
同時に、まるでプールから上がったあと全身に重力が急にかかるような、どっかりした疲労感に襲われた。
ポケットから携帯を取り出した。
がんじゃなかったよ、とひと言だけメールを送ろうとして、指が止まった。足も止まった。
人生が一度、止まったように感じた。
がんではなかった。
でも、人はある日突然大病を宣告されることもあるのだ。
私のような健康な人間でも、自分の人生が永遠ではないことを知った。
そして、素直な自分の気持ちに気がついた。
もしも、子宮頸がんという結果だったとしたら、それでも、今のように楽しく生きていられれば幸せだと、心の底から言えただろうか。
過去の結婚では恵まれなった、子ども。そのまま、諦めていいのだろうか。
この子宮が使えなくなる前に、子どもがほしい。
もう一度、今度こそ、幸せな結婚をしたい。
安定した毎日を過ごしたい。
そう思った瞬間、夢から醒めた。
将来のわからない働かない芸人を、昼も夜も働いて、養っている場合ではない。私の「有限な時間」を、生きなくてはいけない。
夜の仕事はもう辞めよう。西新宿の店のオーナーにも話をしよう。
でも、私はもう32歳だ。間に合うのだろうか。
急に焦りが湧いてきた。重い不安が背中に、のしかかってきた。
モヤモヤとした気持ちを引きずりながら出勤した西新宿の店で、私は一人のサラリーマンと出会った。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
