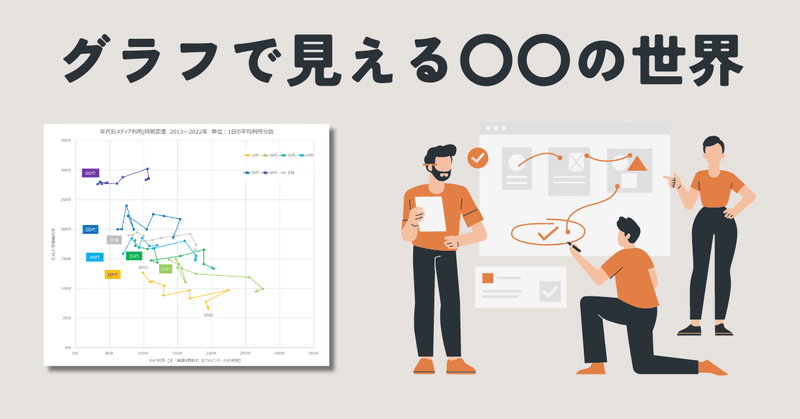
グラフで見える〇〇の世界 メディア編 #2
ここでは、数字やデータが苦手な人向けに、グラフで見える〇〇の世界と題して、世の中に落ちているデータをちょっとだけ加工すると、新しい発見ができる!をTipsも交えてお届けします。なお、数字やデータを扱う際は、数学ではなく、”算数”を使っていますので、ご安心を。
1.ジェネレーションギャップは、どこにある?
前回でも取り上げたメディアの利用時間を違う切り口でみると、また違った風景が見えてきます。前回はメディアの利用時間を構成比にして、どの年齢層に使われているか見ました。今回は、各年代が時系列でメディアの利用時間がどうなるかを見てみたいと思います。
グラフは、とっても簡単、横軸(X軸)にネット利用時間、縦軸(Y軸)にテレビ利用時間を配置して、2013年から2022年までの点を散布図にして、その時系列の点を線で結んでみました。

ぱっと見気づくことは、みんなX軸の右方向に直線が伸び、直近2年は変化が小さいのがわかります。ただ、この小さい変化はコロナ期の特殊環境なので、明けた2023年は、踊り場として高止まりするのか、はたまた、一気呵成に激変するのか、2023年の最新調査が見ものです。

高齢層
少し込み入っているので、年代を2つに割って見てみましょう。すると特徴がもう少し見えてきます。高齢層は、縦のY軸=テレビ利用は多少の上下動はあるのですが、概ね変わっていないことが分かります。40代以上のテレビ利用は底堅いのです。

若年層
一方、若年層は、シンプルに右肩下がり、ネットが増えて、テレビが減る。確実に可処分時間がネットに移行しているのがわかります。
こうやって、時系列で並べてみると、また違った特徴がわかります。最近筆者が気になるのが、40代が均衡点というジェネレーションギャップ。40代は、特にネットに関しては、古き良き昭和の時代をしりつつも、社会人になってから急速にITリテラシーが求められ、仕事でもプライベートでも積極的に活用したハイブリット世代です。でも、その下の世代は、物心ついたときからネット、ちょっとでも便利なものが現れると、それを利用するのに古い仕組みやサービス体験がない分、躊躇がないののだなと。
2.Tips
今回のデータは以下からグラフ化しています。
情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査(総務省)
ここから、テレビとネットの利用時間を年別に抽出。
ポイントは、散布図。
二軸のテーマを論じたり、比べたりするのにとっても便利なグラフです。
本記事、お読みいただきありがとうございます。
無料記事にしては、情報量や質が”あったな”と思ってくれた方は、
以下にて「応援課金」よろしくお願いします。以後の執筆の励みにさせていただきます。
ここから先は
¥ 100
是非、サポートお願いします。データやメディア、そして、普段のビジネスで気になること、活用できることを発信して、少しでもみなさんの役に立つコンテンツになりたいと思います。
