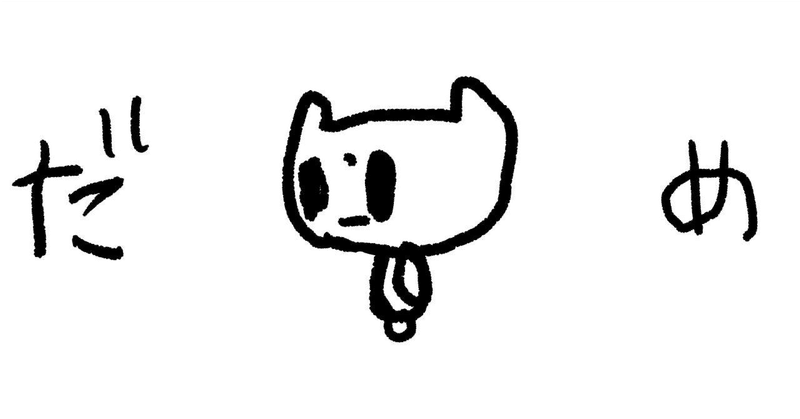
私が好きなお釈迦様のエピソード
ありがたいことにマシュマロをいただきましたので、その回答を記事にしてみます。

私が好きなお釈迦様のエピソードは以下のようなものです。
-以下エピソード-
コーサンビーにマーガンディヤというバラモン(インドにおいて最も高い身分の者)がいた。彼は街に現れたブッダを一目で気に入り、美しいひとり娘マーガンディヤの嫁ぎ先にと考える。そして、その娘と妻を同伴し、直接ブッダに会い、娘を娶るように勧める。しかし、ブッダは「この糞尿に満ちた(女が)なんだというのだ。私はそれに足でさえも触れたくない」という過激な言葉で彼の申し入れを拒絶した。この言葉で自身の誇りを傷つけられた娘のマーガンディヤは、ブッダに深い恨みを抱くようになる。一方、親であるマーガンディヤ夫妻はブッダの言葉を聞いて預流果(悟りの第一段階)を得て、親戚に娘を託して遊行者となった。
-エピソード終了-
なんとも過激なエピソードです。
ちなみにこのエピソードが書かれている同じ偈に「婬欲の交わり」という言葉があり、その言葉の示す意味は性行為、セックスのことなのでブッダはマーガンディヤの娘に対して面と向かって「こんな糞尿に満ちたものには足でも触れたくないし、とてもそんな気になれません」と酷い断りの文句を述べたことになります。
現代日本で有名人がこのようなことを言ったら大問題です。即座にSNSにアップされて大炎上の末、社会的に抹殺されるでしょう。もしかしたら物理的にも抹殺されるかもしれません。古代インドはおおらかですね(違
ちなみにブッダが「糞尿に満ちた」と表現したのには少し説明が必要かもしれません。
仏教には身体への執着を捨てるために「不浄観」という瞑想法があります。
その瞑想法は自分の身体を髪や爪や皮膚や筋肉といった組織、胃や心臓や大腸といった内臓、そして内臓の中の胃の内容物であるとか胆汁であるとか小便・大便といったものに細かく分けて観察し、「それら全て、執着するに値しない」と観ることで身体への執着を捨て去る、というものです。
こういう身体観があるため、ブッダがマーガンディヤの娘を拒絶するときに「糞尿に満ちた」という表現を使ったのだと思います。
このエピソードを聞いて不快に思われる方は多いとは思いますが(特に女性にとっては不愉快だと思います、すみません)、そういう方々には申し訳ないですが、私にはとても痛快なエピソードに感じられるのです。
私がこのエピソードを痛快だと感じるのは、こうした振る舞いに憧れる癖に、私は決してこういうことができない(言えない)からです。
ブッダの教えは悟りを目指すもので、悟りとは世俗の価値観を超えたところにあるものです。
もしブッダに「こういうことを言ったら世間から何を言われるかな」みたいな気持ちが少しでもあったなら、こんな過激な言葉は使わないでしょう。
まあ、それにしても相手の女性を傷つけるこんな過激な物言いはしなくて良い気もしますが、このときのブッダにとっては相手への忖度よりも、自分が性欲などの煩悩から完全に離れていることを示し、きっぱり拒絶することの方が大事だったのでしょう。(そうはいっても、多分ブッダが現代にいたならば、ここまで過激な言葉は使わなかったと思います)
私はブッダと全く逆で、周りの人から何を言われるかはとても気になる人間なので「いい人」ぶりたいし、性欲だってあるので美人の女性に言い寄られたらデレデレしてしまうでしょう。そういう世俗の価値観や煩悩まみれの自分に嫌悪感を抱く自分もいますが、自分がそうしたものから完全に離れるのは到底難しいこともはっきり分かっています。
自分が世俗の価値観や煩悩から離れることに憧れながらも、それが到底叶わないからこそ、そうしたものから完全に離れたブッダの振る舞いに痺れてしまうのです。
人は自分にないものを持つ人に憧ると言いますが、まさにそういうことなのでしょう。煩悩まみれの私からすると、煩悩を滅尽したお釈迦様の言行はとてもまぶしく見えます。
マシュマロをくださった方は、お釈迦様の優しい、心が温まるエピソードを期待されたのだと思うのですが、すみません、御希望に沿った回答ではなかったと思います。謹んでお詫び申し上げます🙇
でも現代日本の価値観から見ると「おいおい」と言いたくなるお釈迦様のエピソードは実は多いです。
何が善い、何が悪い、と判断する価値基準は地域や時代によって大きく変わるので、現代日本の価値観で判断すると「悪い」にカテゴライズされるエピソードが多くても不思議ではありません。2500年前の、それも日本ではなくインドの話ですからね。文化も歴史も違います。
しかし、個々のエピソードに受け入れがたいものがあっても、その人が説く教えがこうして2500年後の日本という異国にまで伝わっているのは、その教えに時代で変化する善悪の基準で測れない、人々を引き付けるなにかがあるということの証拠ともいえるでしょう。
そういう意味でも、私はこのエピソードがけっこう好きです。
本日は以上です。スキやコメントいただけると嬉しいです。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
