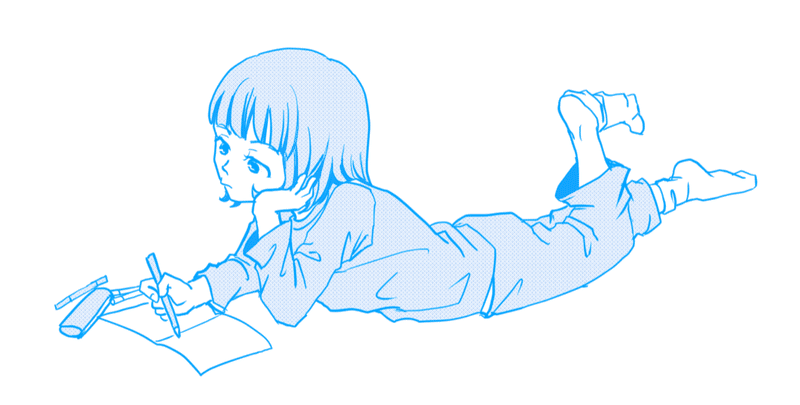
機会があれば子どもにも伝えたい勉強のコツ。
今日は、当時スマホのメモ帳に書き留めていて、そのまま長らく振り返りもなく眠ってしまっていた過去のメモの中の1つを、復習的な意味合いで転記してみようと思います。
メモしたのはおそらく6〜7年前になるのだけど、どこで見かけたのか、媒体や出典なんかもまるで覚えていないし、残していない…。
わりと几帳面な性格の自分としては、出店不明のまま公にするのは我ながらどうかと思うけど、ボクの性格・行動の傾向的に本やニュースからではないと思うし、気になった方は検索すると同じソースに辿り着くかも知れませんので、気にせずいってみます。
※基本的にボクの言葉ではなく受け売りである事は事前に断っておきます。
<勉強には2種類ある>
勉強には、大きく分けて次の2つのものがある。
1.知識を学ぶ(理術:利口になる技術の習得)
2.何かをする能力を学ぶ(技術の習得)
以上の2つの活動は、全て社会的な空間(=実践共同体)の中で生起する。
<授業から学ぶコツ>
授業から学ぶ最大のコツは、それだけで単体の知識であると思いこまないこと。
授業を活性化するためには、そこで得られる「知識」をそれまでの知識と有機的に関連づけること。
★授業からまなぶコツは、以下の通り。
1. 学んでいる授業についてのあらゆる情報の収集をする。
2. すでに学んだことと新規に学んだことを<節合=せつごう>する。
3. 新しい情報に居場所を与える。
4. 新しい情報を既存の情報と同様に使えるようにする。
5. 新しい情報を、同じ授業内で理術として使ってみる。
6. 新しい情報を、他の授業と関連づけて使ってみる。
<理術を関連付ける>
「知識」を関連づけるといっても、関連づけには、グレードがある。
★理術(りじゅつ=利口になる技術)とは以下のよな事を指す。
1. 自分の持つ勉強の課題とは何か、を明確にする。
2. その領域の中で最も惹かれるものは何か、を明確にする。
3. まず、それを実現するための行動をはじめる。
4. 雑念を除去するためにオープンスペースを確保する。
5. 集中するという時間を間隔をおいて実行する。
6. 1回あたりの集中する時間を長くできるようにする。
7. 集中力が伸びても、体力には限界がある、休みを定時にとるようにする。
8. 難問・疑問・スランプは成長の<肥料>、悩むことおそれない。
9. 一定の考えがまとまれば、友人や教師などアドバイスできる人に気楽に相談する。
<理術の行使>
知識というのは狡猾なもの。
ずる賢い人間の知恵とつきあうには、自分自身も智慧に関する技術、つまり理術を身につけねばならない。
★理術(りじゅつ)を行使(こうし)する
理術とは、利口になるための技術である。
広い意味での知識のことであるが、知識は身体の外部から食べ物のように吸収されるというふうには見ず、知識は鉄棒の逆上がりのように口で説明すること(=狭義の知識)だけではなく、それに身体の行為が伴わないと完成しない(=広義の知識) 。
そのように捉える知識の見方に力点をおくように、我々は知識の見方を変えねばならない。
<読解の技法>
資料を読解することは、人間が最も効率よく知識を収集する方法の一つ。
★読解の技法(1):アウトラインを把握する(概読する)
1. なぜ、その本(=テキスト、ウェブページ)を手にしたかを考える。
2. その情報を読む前に、収穫を期待する個別情報について考える。
3. その本(=テキスト、ウェブページ)についての予備的印象をもつ。
【チェック項目】タイトル(標題と副題)、著者名、刊行年、出版社、目次、序文、スタイル
4. 全体を読む(概読:がいどく=私の造語・速読・抄読)。
5. このテキストをどのように再読するかについての方針を立てる(2.を立て直す)。
6.. 必要な箇所(場合によっては全部)を精読(せいどく)する。
【必要用具】借用本の場合はポストイット、個人蔵書はマーカー、鉛筆ならびに読書ノート(あるいはパソコン)
(以下、精読の技法)
7. 必要な箇所をノートにとる。
【チェック項目】かならず出典の書誌をメモする。要約と引用を区別する。
8. 読書中は適宜、収穫を期待する個別情報メモ(→本項2.参照)を参照する。
★読解の技法(2):精読する
1. 著者の主張なのか、引用されている論者の主張なのかをチェックする。
※事実を論じているのか、解釈に力点がおかれているのかもチェックする。
2. パラグラフ単位に主張が何であるかを考える
3. 読みの速度を変化させる。
※分かっていること、興味のないことは飛ばしてよい。興味のあること、重要と思うことに精力を集中させる。
※ただし、逆説的だが、分かっていることや興味のないことに、落とし穴や重要な発見があることも。
このミスを防ぐには、なぜ飛ばしているのか、その理由を自覚すること。
4. 必要な箇所をノートにとる。
【チェック項目】かならず出典の書誌をメモする。要約と引用を区別する。
5. 自分の資料として活かすために、取ったノートの再組織化をおこなう。
<ノートの取り方>
日本人に最も欠けているのは、このノートを取る力とのこと。
ただ、これは訓練すれば必ず上達する。
一度上達すれば、その技術はなかなか忘れない。なぜなら、ノートの技法は、理術に属するものだから。
★授業ノートの取り方
1. この授業が何であるかを受講前にチェック
※前回は何について学んだのか、今回は何について学ぶのか?先だって自問自答する。
2. 教師の言うアウトラインに注目する。
※アウトラインが話されない場合はリクエストする。要求せずに駄弁を弄された場合、責任の一部は自分。
3. キーワードを列挙する:教師の発話より
4. キーワードを列挙する:自分が連想した言葉で
【ポイント】教師の言うキーワードと自分が連想したキーワードはノートの中で区別して書く
5. 教師のいう命題に注目する。命題は完成した文章の形であらわすこと
6. 教師が強調した言葉には下線を引いておく。
※ノートは後で想起し、考えるためのツール。ゆえに記述内容は殴り書きでもOK。ただし、後から情報を復元できる程度まで。
【教訓】きれいにノートを取るに越したことはないが、まず、後で自分にとってわかる実践的かつ現場力的な力をつけることが先決。
7. ノートに基づいて質問する:授業中
※授業中に質問やコメントがある場合は「?」や「!」をつけておき、適宜質問する。
8. ノートに基づいて質問する:授業のまとめに
※質問する権利を行使せよ。最後に質問する際には4.で取って置いたキーワードが威力を発揮する
9. かならず復習する:「復習するは我にあり!」
※復習とは、講義ノートを読み返し、キーワードを使って授業で書ききれなかった命題を文章化することである。
その際には、授業とは異なった筆記用具や色のものを使って、<追記>したことを区分するようにする。
これは試験対策で、友人のノートを借りた時に、授業中の教師の主張なのか、自分のコメントなのかを区分し、かつモノクロの複写では、友人に重要情報が漏洩しないためのテクニックでもある(裏技)。
今すぐではないにしろ、自分も、そして子どもにも、これらは教えたいと思う。
ただ、この内容を子どもに分かるような言葉に翻訳して伝えられる自信がないのが悩みどころだ…。
過去のボクは昭和の固定観念や慣習に縛られ、自分や家族を苦しめていた事に気付きました。今は、同じ想いや苦しみを感じる人が少しでも減るように、拙い言葉ではありますが微力ながら、経験を通じた想いを社会に伝えていけたらと思っていますので、応援して頂けましたら嬉しいです。
