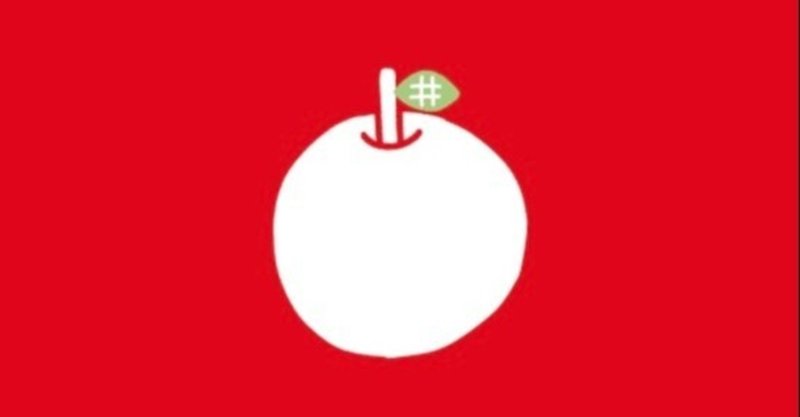
携帯電話とリンゴ[短編小説]
『流れ星』
知るか。メッセージを読んだとき、香助はあまりの唐突さにそう呟いた。ちらりと窓枠を一瞥すると、茜色と紺青が入り混じった、微妙な空模様がそこにはまっている。月はたぶん、うっすら見えるだろう。携帯電話をデスクに放って席を立った。
なんのつもりなのだろう。
触れた窓枠は結露していた。指先から手首へ水が伝う。
メッセージを送ってきたのは雪吹という奴で、十一年前の友人だ。と、思う。香助たちの出身地は、この国で長年うっすらと続いている戦争の、不運な爆撃によって瓦礫となり、今も復興活動が続いている。香助には八つ上の姉が遺ったが、雪吹には誰も遺らず、たしか父方の遠い親戚に引き取られて引っ越した。それ以来、ほとんど連絡は絶えていたのだ。せいぜい年明けの挨拶と、連絡先が変わったという事務的なメッセージしか、交わしてこなかったというのに、急に何なのだろう。
だいたい、このメッセージが送られている時点で、彼が見た流れ星はすでに消えたはずだ。目を凝らしたが、空には常駐の星しか見当たらなかった。赤いカーテンが風で翻る。かなり悩んで、香助はメッセージを送り返した。
『ひさしぶり』
なれなれしいのかそっけないのか。姉が呼ぶ声が聞こえて、自室を出る。デスクの上に真っ白な進路希望調査の紙を乗せたまま、部屋は外の空よりも暗くなった。
「さっきさあ、雪吹から意味わかんねぇメッセージ来たんだけど。ひなは覚えているか、雪吹」
夕食を囲みながら、香助は姉に話題を振った。テレビは反政府組織が抗議デモしている様子を映している。世間の代表者、という右上のテロップに心の中で嗤った。十一年前から、この組織は活動している。香助たちの故郷が壊れたとき。そのときは、メディアは彼らに見向きもせず、戦争をあおっていたはずだ。姉が番組をクイズ番組に切り替えて、ぱちりと瞬きをした。長い黒髪が彼女の肩にしだれていく。
「童話作家のお父さんの子でしょ」
その返答は香助が予想とは違って、香助もぱちりと瞬きをした。
「そうだっけ」
「そうよぉ。あなた、あの絵本好きだったでしょ。『月とウミガメ』とか、『ダビデの魔女』とか。……あぁ、『妖精のリンゴ』とか」
たしかに、その話は覚えている。しかし、その作家が雪吹の父親だったかと首を傾げた。口紅がほとんどとれた薄い唇に味噌汁を注ぎ込んだ後、ひなは眦を緩ませて呟く。
「かわいい男の子だったよねぇ。いつもお父さんの絵本抱えてさ、にこにこして、ははは……って笑う子」
彼女の言葉で、香助はようやく、小学生のあいつが、ランドセルにいつも入れていた本の正体を知った。
・・・
むかし、むかし。おおむかし。妖精たちは森に棲んでいました。妖精の棲む森の木には、中に魔法が隠されていて、木や花はとても大きく育つので、人は、森の木を外から眺めて、妖精たちのことを知っていました。この、魔法というのは、ものが生きるためのちから、いのちのかたまりのようなもので、妖精たちは、森の中で、魔法によって、豊かに暮らしていました。
「彼らは、森の真ん中の、いちばんおおきな木の虚に、いちばんの魔法を隠している。だからあのリンゴの木は、空に届くほど高いんだ。豊かな実りをひとりじめする、卑怯な妖精たちめ」
人は、そういうわけで、妖精たちがすきではありませんでしたが、かといって、彼らの森を侵すこともできずにいました。
妖精たちの棲む森の、その近くに、人の棲む町がありました。妖精たちは、ときおり、町のあかんぼうを攫ったり、妖精のあかんぼうを押し付けたりするので、この町では、生まれたばかりのあかんぼうにしるしをつけていました。そして、しるしのついていないあかんぼうは、妖精のいたずらをうけた子、ちゃんとした人ではない人として、「いらない子」と呼ばれていました。
この、いらない子は、今は町にひとりだけいます。ほかのいらない子は、死んでしまったので、今は、ひとりでした。
いらない子は、からだも小さくて、ぐずで、働かせることもできなかったので、ずっとひとりのままでした。いらない子は、さみしくて、いつも町の隅で泣いていました。
あるとき、町の畑が動物に荒らされて、ぜんぶダメになってしまいました。すると人たちは、口々に、
「妖精の魔法さえあればなぁ」
と言って、ぼやくので、それを聞いたいらない子は妖精の森へ行って、魔法を盗むことにしました。いらない子の背丈ほどあるゼンマイの門をくぐって、スズランの灯りを頼りに、顔よりもおおきいツツジの道を歩きました。木の隙間から、水色の透けた羽をはためかせて、妖精たちがちらり、ちらりといらない子を覗きますが、このちいさな侵入者に、手を出すことはありませんでした。あかんぼうのころ、妖精にいたずらされたいらない子は、妖精のにおいを持っていたので、妖精たちは、彼女を自分たちの仲間だと思ったのです。いらない子は、森の真ん中の、いちばん大きなリンゴの木の足元にくると、いらない子の顔ぐらい大きい、落ちていたリンゴをひとつ手に取って、虚のなかへ差し出しました。そうすると、いちばんの魔法は、リンゴの中へするすると入って、赤いひかりをひとつ、のこします。ぱくり。いらない子がひかるリンゴをひとくち齧ると、いちばんの魔法は、彼女の中に入っていきました。
いらない子は魔女になりました。
魔女は町にもどると、畑のやさいを実らせて、町に豊穣をもたらします。彼女をしいたげた町は、彼女をよろこんで迎え入れました。魔女はよろこびました。彼女は、たくさん魔法をふるまって、町はじゅうぶんな豊穣をもらいました。
いっぽうで、いちばんの魔法を盗まれた妖精たちの森は、すっかり痩せてしまいました。いちばんの魔法を取り返そうにも、その魔法は、魔女そのものになってしまったので、取り返すには、魔女を、あの木の虚に、閉じ込めるしかありません。夜、妖精たちはみんな黒い蛇に変身して、魔女を捕らえてしまいました。そうして、リンゴの木の虚に放り込むと、そこに、銀のふたをして、閉めてしまいます。町の人たちは、魔女を助けようとはしませんでした。もうじゅうぶんな実りをもらいましたし、恐ろしい妖精に、逆らおうとは思いません。もうずっと、妖精の森を侵したことはないのですから。魔女は、かわいそうに、がらんどうの、まっくらな木の虚の中で、ほかのいらない子のように死ぬこともできないまま、ずーっと、ひとりで、泣き続きました。……。
むかし、むかし。おおむかし。いらない子がいました。ぐずでばかな、かわいそうないらない子は、ずっといらないままでした。
おしまい。
・・・
そんな話だったな、と香助は黄ばんだ絵本を閉じた。本の隙間に挟まった小さなクモを掃う。妖精のリンゴなんかより、いらない子の印象の方がずっと強すぎてタイトルがかすんでいたが、姉が列挙したおかげで思い出した。まるくなってうずくまった少女の真ん中に、赤いリンゴがはめられている絵はただ不気味である。こんな絵本、子供に読ませたら号泣ものだ。香助だって、べつにこの話が好きだったわけではない。どちらかというと、
「いやな話だな」
と、過去の自分は、そんな判断を下した。眉を寄せて嫌そうにする香助を、雪吹は快活に笑ったのだ。
「ははは!だよねぇ。かわいそうだってなんだって、ないものねだりも悪いことも、だめだよー。って、話らしいよ」
「はー」
今思えば、ここで「らしいよ」というのは、ひなの言う通り、父親が筆者だから、何かしら聞いて出たコトバなのだろう。
「いらないんだったら、捨ててしまえばよかったのにね」
「……じぶんをぉ?」
「そー」
絵本なんかより、雪吹のそのコトバのほうがずっと好きで、幼い自分は初めて、両親に絵本を買ってもらったのだ。ちらりとテレビを見ると、戦争で家族を亡くした女が、反政府組織のデモで警官を殴っていた。そうだな。かわいそうでも、悪いことをしてはいけないのだろう。それでも、この女に悲しさや寂しさを捨てろなんて、そんな残酷な話は論外である。しかし、そう言い切ってしまう、幼い子供の感性が好きだった。
携帯電話を見る。雪吹からの返信がきていた。
『こうすけとピィ姉の目ってでかくてさ、星が入ってそうだったよね。』
ひなの小さいときのあだ名に思わず笑ってしまった。いったい何年ぶりに聞いたのか。そういえば、雪吹は目つきの悪い、ちいさな一重だったな、と忘れていた子供の目元だけを思い出す。そうか。と短い返信を送る。その次の、雪吹からのメッセージは早かった。
『士官学校に入るから』
気の抜けた息が漏れた。入るから? なんのつもりなのだろう。だいたい、香助の知っている雪吹は、すぐ貧血で倒れて、熱を出して、過呼吸を起こすような、病弱な奴だった。とても、そんなところに行ける奴じゃない。
『なんで』
『おじさんが行けって。幼馴染っていうか友達も行くし、まぁ、いいんじゃない。ほんとうは、音楽の専門行きたかったけど、さ』
ぎち、と錆びた鉄を擦り合わせたような音が、奥歯のほうから響いた。ゆっくりと息を吐き出す。たぶん、この連絡は「だから、挨拶もできなくなるかもしれないし、連絡も途切れるかもしれない」という意味だ。結局、いつもと変わらない、事務的なメッセージ。納得はしたものの、鉛を飲まされたような不快感がずっと、体の真ん中でくすぶっている。白紙の進路希望調査を迎えに行こう、と香助は思った。
「あのさ、ひな」
「いいよ」
携帯電話からようやく顔をあげた香助に、彼女は笑って答える。香助の膝の上に置きっぱなしだった古びた絵本を、ひなは引き取って腕に抱えた。ずっと絵本を捨てなかったのは、姉の方だった。
「おねぇちゃんはね。あなたが行きたい場所に行って、したいことをしててくれたら、それでいいよ」
「……うん」
外はもう、締め切った部屋よりも暗くなっているだろう。
・・・
治療室のシュレッダーの中身をぶちまけて、死にそうな顔をしている男の横で、香助は紙片を拾った。紙の切れ端のいくつかには、衛生隊の縮小について議論されている。こんなところにあるはずがない書類だ。けれど、捨てられたものだ。あぁ、せっかく、黙っていたのに。つい、男をにらんでしまう。こいつが、雪吹を殺した。俺よりも、あいつとずっと長く、一緒にいたくせに、わからなかったのか。
あいつは、自分を捨てられるやつだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
