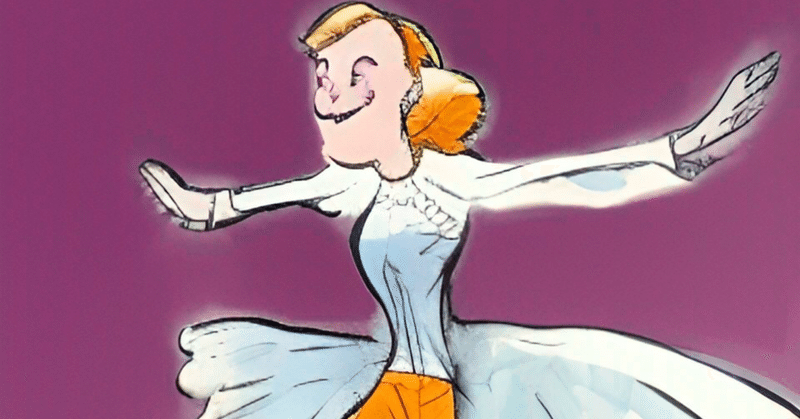
飛来するマザーQ
決して疑ってはならない
決して詮索してはならない
確証が持てたならば、ただちに抹殺せよ
「マーコリン、入るわよ〜」
聞き慣れた母親の声に咄嗟に背を向けた。
「Shit!! ノックくらいしろよババア!」
オレは今、自分を慰めていたのだ。
これは独りでなければ出来ぬ仕事で、誰にも見られてはならぬ儀式であった。
「はいはいソーリーソーリー。それよりあんた、これ」
そう言って差し出された母親の右手には、丸められた本のようなものが握られていた。
オレは荒ぶる下半身に布団を掛けたまま起き上がり、母に訊ねた。
「なんすかそれ」
「ほら」
そう言って母はそれをオレの膝の上に投げ捨てた。
その表紙には衣服が乱れ、胸の露出した女子高生のイラストがあった。
「これは⋯⋯!」
それを見たオレの口は輪ゴムのようにまん丸に大きく開き、そのまま動かなくなってしまった。
この本はオレが先週インターネットで取り寄せた日本の〈エロ本〉というヤツで、カモフラージュのために茶封筒に入れ、さらに机の奥深くに隠してあったものだ。
「あんたって子は勉強もしないでこんなことばかりしてねぇ。チンポばっか握ってないで鉛筆握りなさいよねまったくイヤになっちゃうわホント息子がこんなエロガキに育っちゃうなんてもうほんとにもうほんとーーーに⋯⋯⋯⋯あら?」
顔に刻まれた無数の漣を上へ下へと動かしながら暴言を並べる母。
その漣を見ていると気分が落ち着くので、オレのアソコもスモールになってしまう。
それにしても、さすがに言い過ぎだよマミー⋯⋯。あと『あら?』ってなに? こわいんだけど
「くんくん⋯⋯くんくん⋯⋯」
丸められてカピカピになったティッシュでも探しているのか、鼻を釣具の浮きのようにピクピクと動かしながら部屋の中を歩き回る母。追撃するつもりか?
「⋯⋯さてはあんた、女がいるわね?」
「ふぁいっ!?」
匂いだけで分かるのか!?
「いるのね」
「⋯⋯だったらなんだよ」
そうだ。
たとえオレがエロ本を買っていようが、彼女を部屋に連れ込んでいようが、誰に何を言われる筋合いもないはずだ。
「ていうか息子の彼女のこと『女』って呼ぶ母親がいるか? 酷くない?」
「そうね、ちょっと言い過ぎたわね。とにかく、ちゃんと勉強しなさいってことよ。この前のテストも下から数えた方が早かったんだから」
「あいよ」
「分かればよろしい」
そう言って母は部屋を出た。
⋯⋯なんなんだよ。
成績の話ならばエロ本や彼女を出してくる必要はないはずだ。それをわざわざ言うということは、オレを傷つけることが目的なのではないか。
「マミー、オレのことが嫌いになっちゃったのかな⋯⋯」
マミーはつい先日までこんなふうではなかった。
勘は鈍く、計算も出来なければ記憶力もない、正真正銘腑抜けのフー左衛門だったはずだ。オレのことなど叱れるような頭ではなかったはずなのだ。
それがなぜ急にこんなに勘が鋭くなって、ガミガミ言うようになってしまったのか。
などと考え事をしていると、スマートフォンが鳴った。LINEの音だ。画面には
『ケツ 今
カラオケ行かね? 』
という通知が来ていた。
小学校の頃からの友人であるケツからだった。
実は先日部屋に連れ込んだ彼女というのは、このケツから寝取った女性である。
しかしおそらくケツはこのことには気づいていない。なぜなら、バカだからだ。
よし、カラオケ行こう。
マミーにガミガミ叱られてちょうど気分が沈んでいたんだ、カラオケでニッポンのアニソンを歌いまくって元気になろう!
⋯⋯いや待てよ?
カラオケに行っても何も歌えなくないか? なろう運営は著作権の中でも歌詞には特に厳しいから、ずっと鼻歌で歌うくらいしか方法はないぞ?
ったく、なんで小説になってる時に限ってカラオケに誘ってくるかなぁ。昨日だったら著作権とか気にせずに歌いまくれたのに。
でもストレス発散したいな。デタラメな歌詞で叫びまくるか。よし、そうしよう。
「マーコリン〜! ケツくんが来てるわよーっ!」
ケツもう来たの!?
1階に降りると、玄関にケツとマミーがいた。まだカラオケの返事してないんだけどな。
「さぁ行くぞ、マコ!」
暑苦しいヤツだ。
ケツはなぜかオレのことを〈マコ〉と呼んでくる。自分の名前が2文字だからオレのことも2文字で呼びたいのだろうか。
「ねぇケツくん聞いてよ〜、マーコリンったらエッチな本ばっかり読んで全然勉強しないのよ〜」
マミー、余計なことを⋯⋯!
「は、はぁ⋯⋯」
ケツも困ってんじゃん! エロ本の話されて困ってんじゃん!
「部屋に女の子も連れ込んでるみたいだし、もうホント困っちゃうのよ! ケツくんからも勉強しろって言ってやってよ!」
「え、お前ついに彼女が出来たのか!?」
めんどくさい話題を!
「うん、この前ね⋯⋯」
「水くさいなぁ! なんで俺に教えてくれねーんだよ! 今度紹介しろよな!」
「わ、わかったよ⋯⋯」
無理に決まってるだろ!
まったく、マミーが余計な話するから!
「ということでおばさん、行ってきます!」
「はい行ってらっしゃ〜い」
ケツが来ている時だけはいい顔をする。
とはいえマミーからお許しが出たので、オレたちは遊びに行くことになった。
「なぁマコ⋯⋯お前のかーちゃんあんな感じだったっけ? 前はもっとおっとりしてたような」
やはりケツもそう思うんだな。
「ああ、なんか最近別人みたいに厳しくなっちまってさ。勉強勉強うるさいし、さっきなんかどうやって見つけたのか分かんないけど隠しておいたエロ本持ってきてさ、マジで怖いわ」
「こわ〜」
オレがあまりにも勉強しないからキレちゃったのかなぁ。
「あっ」
ケツが思い出したように言った。
「どうした?」
「お前さ、マザーQって知ってる?」
「そりゃ知ってるだろ」
マザーQとは、十数年前に流行った、ドッペルゲンガーによく似た怪異だ。言うなれば、母親版ドッペルゲンガーだな。
「おばさん、マザーQなんじゃね?」
やっぱりケツはバカだな、と思った。
「本気で言ってんの?」
「⋯⋯ああ、本気だ」
ケツの目が変わった。冗談を言っているような顔ではなくなったのだ。
「お前、マザーQ信じてるのか?」
本気で信じている顔をしているので心配になってきた。
「信じてるもなにも、実在するからな」
バカとかそういう問題じゃなくて、もしかしてもっとめんどくさそうなヤツなのか?
オレは幽霊を全く信じていない。テレビに「あなた、憑いていますよ」とか言っている霊能力者が出てくるとアホらしくなってチャンネルを変えてしまうほどに信じておらず、チョーゼツ嫌っている。
ケツ、お前もそういうヤツだったのか。そっち側だったのか。
「なんつー顔してんだよ。動き出した道端のフンを見るような目でオレを見るなよ」
「道端のフンが動くとこなんて見たことないぞ」
もし見つけたらテレビに出られるんじゃないか?
お、カラオケ屋が見えてきた。
「なぁケツ、ここって前払いだっけ? 後でよかったっけ?」
「それどころじゃないだろ」
とれどころなんだ?
「マコ、今からお前に大事な話をする。2人だけになれる場所に行こう。そうだな⋯⋯よし、このままカラオケ屋に入ろう」
行くのかよ。
じゃあさっきのくだり要らんかったやん。
久しぶりのカラオケ屋は、風俗店のような匂いがした。後払いだった。
部屋に入ると、ケツが神妙な面持ちになって言った。
「心して聞いてくれ」
「なんだ?」
「お前のかーちゃんはマザーQの可能性が高い」
「まだ言ってんのかよ」
なんだこいつ。
「実はじいちゃんがマザーの研究に関わってた時期があったんだ。マザーの存在は表向きでは都市伝説扱いされてるけど、本当はあれは実在してるんだ」
「マザーQのことマザーって言うヤツ初めて見たよ」
「お前、そもそもなんでマザーQがマザーQって呼ばれてるか知ってるか?」
「え、知らん」
「マザーは26体いるんだ」
26体も!?
「てことは、AからZまでいるってことか?」
「そうだ。19年前にじいちゃん達が26体全てを捕獲したんだが⋯⋯」
だが⋯⋯?
「ある時、17番目に捕まえたマザーが逃げ出しちまったんだ。マザーの中で1番性能が高い個体だった」
なるほど、17番目だからQなのか。
「その後1回捕まえたんだがな、最近になってまた逃げ出しちまったみたいで⋯⋯」
なんでそんな何回も逃げられるんだよ。ケツのじいちゃんのいた組織弱すぎるだろ。
「それにしても、性能が高いんならああはならないんじゃないか? もしマザーQがマミーと入れ替わってたとして、あんなに別人みたいになったらすぐバレちゃうだろ?」
「いや、それがそうでもないんだ。実際お前もおばさんがマザーQに成り代わられてるとは想像もしてなかっただろ? 見た目があまりにもそっくりだから」
まあそうだが⋯⋯
「なぁマコ、信じてくれたか?」
「いや全然」
信じるわけなくない? これまで都市伝説が実際にいたことなんてなかっただろ? 実はおじさんがめっちゃ厚着してて変なの持ってただけでしたみたいなパターンは見たことあるけど。
「なぁ、信じてくれよ! おばさんの命が危ないかもしれないんだよ!」
「いやでもオレ都市伝説とか妖怪とかそういうの絶対いないと思ってるし、ていうかそもそも科学的にありえないし」
「マコ、マザーはそういう類じゃないぞ?」
そういう類じゃないの?
「マザーはエイリアンだ」
「エイリアンなの!?」
「そうだ。マザーは宇宙の遥か彼方からやって来た超生命体なんだ」
超生命体!!!
「ヤツらは俺たちの母親に擬態し、本物の母親を異次元に飛ばして成り代わるんだ」
ドッペルゲンガーみたいな感じで2人が出会ったら最後だと思ってたんだが⋯⋯
それにしても異次元って。
異次元っておい。
「はいはいワロタワロタ。異次元ってワード出した時点でもうダメだわ。やっぱバカだわお前」
それを聞いたケツがオレを睨んで言った。
「表の人間であるお前が信じられないのはよく分かるが、俺は本当のことを言ってるだけだ。おばさんを死なせたくないなら俺の言う通りにしろ」
バカバカしい。
⋯⋯いや、ちょっと待てよ?
こいつがここまで言うってことは本当にそうなんじゃないか?
もし嘘でオレをからかってるだけだとしたらさすがにもうネタばらしというか、終わりにしてもいいはずだ。いつまでもこんなに意地になって主張することでもないし⋯⋯
ということは、本当にマミーを助けたいという気持ちからこの話を⋯⋯?
「ごめんケツ、疑って悪かった」
完全に信じたわけではないが、ただごとではないということだけは分かった。
「よかった、これでおばさんを助けられる」
「で、オレはどうすればいい?」
ケツは少し考えたあと難しい顔をして、マイクを握って立ち上がった。
「♪この頃はやりの女のk⋯⋯」
「キェエエエエエーーー!!!!」
なんだこいつ危なっ! 著作権違反になるところだった! なんでいきなり歌い出すんだこいつ! オレが大声でかき消さなかったら運営にアカBANされちゃってたよ!
「♪こっちを向いてよハn⋯⋯」
「キィヤァァアアアアアア!!!!!」
「なんだお前! 邪魔すんなよ!」
「今歌うタイミングじゃないだろ!」
オレが怒鳴るとケツは優しくマイクを置き、オレの前に座った。
「そうだったな、ごめん。大事な話の最中だったな」
こいつ怖。
「マザーとの戦いにおいて、必ず守らなければならないルールが3つあるんだ」
必ずって⋯⋯めっちゃ大事な話じゃねーか。なんでさっき歌ったんだよマジで。
「疑わないこと。詮索しないこと。マザーだと確信したら隙を見てすぐに殺すこと。この3つだ」
「殺すって⋯⋯そんなこと」
「やるんだ。やらなきゃおばさんは永遠に異次元にひとりぼっちだ」
「えっ!」
マミー⋯⋯!
ということは今この瞬間もマミーはひとりで寂しい思いを⋯⋯
「分かった。オレ頑張る!」
「よく言った! マコ、ルールは絶対に守るんだぞ。疑ってることを悟られたら失踪されるからな。そうなったら絶対におばさんは戻って来られなくなる。だから調査も絶対にバレないようにやれ」
「分かった。オレ頑張る!」
「オレ頑張るbotかよ」
そんなツッコミされんのかよ。
それからオレたちはニッポンのエロめのアニメの主題歌を6時間歌い、カラオケ屋を出た。
「だだい゛ま゛ー゛」
「おかえり。マーコリン、どれだけ喉を酷使したのよ。伸ばし棒に濁点つくのはさすがにおかしいわよ。ていうか私たち日本人じゃないのにこんな会話するの変だわね。と思ったけど濁点の話したの私だけだったわ」
セリフ長っ。
マミー⋯⋯
見れば見るほど分からなくなる。本当に偽物なのだろうか。確かに性格は驚くほど変わってしまったけれど、見た目は完全にマミーだ。
この人を、殺すのか。
そんなことオレに出来るのか?
いや、やるんだ。やらないと本物のマミーが帰って来られない! 永遠に異次元をさまよわせるわけにはいかない!
「どうしたのマーコリン? そんなところにずっと立ちっぱなしで⋯⋯」
声まで完全にマミーだ。
「何か考え事でもしてたのかしら?」
ギクッ!
「いや、なんでもないよ! そんなことより夕方届く荷物、勝手に開けないでね! すぐに取りに行くから!」
「悶絶美女鬼イカセ 楓ゆ⋯⋯」
!?!?
「ぎゃあああああああああああああああああぁぁぁい!!!!!!」
「なによいきなり大声なんか出して」
「なんでオレが注文した商品知ってんだよ!」
「そりゃあんたの母親だからね。なんでも知ってるのよ。それより早く手洗ってらっしゃい」
⋯⋯嘘つけ。マザーQだから知ってんだろが。なにが「母親だからね」だ。
でもダメだ。疑ってると悟られる訳にはいかない。ここはぐっとこらえて⋯⋯
「分かった。晩ご飯なに?」
「まだよ」
えっ!?
「手洗ってこいって言ったのに!?」
「外から帰ってきたから言ったのよ。ご飯の時間までまだ1時間くらいあるでしょ? それまで勉強してなさいね 」
確かに。
手洗いうがいを済ませ、オレは自室に向かった。
見違えるように片付いていた。あいつがやったんだな。
それにしても大胆なヤツだな、自分が疑われているとも知らずに。
結局夕飯までエロサイトでエロ動画を見て過ごした。
「うぃーす」
1階に行くとダディがすでに帰ってきていた。
「チャッス」
オレたちの挨拶はこんなもんだ。
夜ご飯は寿司と天ぷらとラーメンと蕎麦と肉じゃがとケバブだった。
「いやぁ和食はいつ食べても美味いんにゃあ〜」
幸せそうに食べているダディ。
ダディは気づいているんだろうか、このマミーが偽物だということに⋯⋯
よし、あとであいつが風呂に入っている間に聞いてみよう。
「いやぁこのキンキンに冷えたお蕎麦は絶品絶品! ママの料理で1番好きだにゃあ〜」
ダディ、違うんだ。この蕎麦はマミーの蕎麦じゃないんだ⋯⋯限りなく似てるけど、ちがうんだ。
「それで、勉強のほうはどうなんにゃ? マーコリン」
いきなり勉強の話になるのかよ!
「マーコリンったらね、全然勉強しないでニッポンから取り寄せたエッチな本ばかり読んでるのよ? あなたからも言ってやってよ」
「にゃにゃっ!? マーコリン、エッチな本を読んでいるのかにゃ!?」
ダディ、そこ突っ込むのやめてくれよ⋯⋯
「読んでないよ」
「嘘おっしゃい! 読んでるでしょ!」
「読んでなんかないもん! もういいよ! うわぁーぁーぁーぁーァァァ!」
食卓でエロ漫画の質問攻めにあったオレは泣きながらその場を離れ、自室にこもった。
それからもオレは泣き続けた。
あんまりだ。家族3人の団欒タイムになんであんな話をするんだ。マザーQめ、お前はいったい何がしたいんだ。そんなんじゃ人間社会に溶け込むなんて無理だろ。
コンコン、とドアを叩かれた。
「にゃあ〜」
なんだ猫か。
コンコン、とドアを叩かれた。
「にゃあ〜! パパだにゃ〜!」
ダディか!
「開けていいかにゃ?」
「どうぞ」
勉強しろしろ攻撃だろうか。夫婦揃ってめんどくさいなほんと。いや、今は夫婦じゃないか。
「エッチな本を読んでいたというのは本当かにゃ?」
ほらやっぱり。オレを責めるつもりなんだ。
「⋯⋯なんでそんなこと聞くのさ」
「ママに内緒で貸して貰えにゃいかと思って⋯⋯ニッポンのエロ漫画、読んでみたいのにゃ」
マジで!?
「いや、いいけど⋯⋯マミーに見つかったらやばいんじゃない?」
「ママは今お風呂入ってるから! 今のうちにコソッと貸してにゃ!」
早いな、もう風呂入ってんのか。
風呂!! ということは今がチャンスだ!
「ねぇダディ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど」
「そんな真剣な顔してどうしたにゃ?」
「マミー、最近変わったと思わない? オレの部屋勝手に漁ったりしてるみたいだし、なんか異様に厳しいしさ⋯⋯」
「そりゃお前が受験生だからじゃにゃいか? ママも必死にゃんだと思うよ」
必死とかのレベルじゃないだろ。変わりすぎなんだよ。やっぱりダディは気づいてないんだな。教えてあげないと。
「ダディ、ちょっと耳貸して」
「にゃ? 分かった」
「実は、今お風呂に入ってるマミーは⋯⋯」
「パパ、何やってるの?」
マミー!?
いつからいたんだ!? どこから聞かれてた? 疑ってるの、バレてるか⋯⋯?
「もしかして、私に内緒でマーコリンからエロ本借りようとしてた?」
お見通しすぎるだろ!
「いや、ちょっとママの話してただけにゃ。エロ本なんてマーコリンしか読まないにゃ」
なんてヤツだ!
エロ本の話はまだしも、マミーを疑ってる話はされるとまずい!
「私の話ですって?」
「いや、あの、その、マミーは蛾が良く似合うなって話してたんだ」
「それって褒めてるの? 貶してるの?」
「とにかく似合うんだ! さぁ勉強するから2人とも出てった出てった!」
「⋯⋯⋯⋯」
困ったような顔をしながら部屋を出る2人。困った顔してるけど、こっちはもっと困ってんだぞ。
さて、今日はサゾエさんのワコメちゃんのエロ画像でも見るか。
コトを済ませたら眠くなったので、風呂に入らずそのまま眠ってしまった。
翌日、オレは朝早く家を出た。近所の人に聞き込みをするのだ。ダディが言っていたようにオレが受験生だから厳しくなっただけの可能性が1ミリくらいはあるからな。できるだけ証拠を集めて、マミーマザーQ説をより確実にするんだ。
「おはようございます!」
「グッモー忍!」
まずは斜向かいに住むアニメオタクのおじさんだ。ラーメンの具が主人公の忍者アニメの大ファンで、いつもニンニン言ってるんだ。
「ねぇコックリさん。うちのマミー、最近変わったと思いません?」
「うーん、最近全然喋ってないからなぁ。というか元々喋らなかったしなぁ」
確かに、うちのマミーが斜向かいに住んでる無職のニンニン言ってるだけの変なおじさんと喋る理由はないもんね。
オレはコックリさんに今までで1番軽い会釈をして次に向かった。
次は民生委員のおじいさんだ。口が2つあって、いつも右の口がタバコを吸っている。
「おじいさん、おじいさんのお口はなぜ2つあるんですか?」
「ひとつは嘘をつくために、ひとつは正義を語るため」
マミーの話をしたかったのだが、嘘と正義しか出てこない口に聞いても意味がないので、次に行くことにした。
「おはようございます!」
「あらおはよう」
隣の隣の家に住んでいる、いつもピンクの服を着ている通称ピンクのおばさんだ。いつもマミーをいじめているので、マミーについてはよく知っているはずだ。
「おばさん、ちょっと聞きたいことが」
「なに? なんでも聞いてね」
「最近マミーいじめてます?」
「いや、それがねぇ、最近どうも⋯⋯あっ」
ピンクのおばさんがオレの方を向いたまま固まった。
「マーコリン、こんなところにいたのね」
マミー!?
いつのまに後ろに!?
「朝からなにやってんのよ。早くご飯食べないと学校遅刻するわよ!」
「ごめん、ちょっと寝ぼけて近所歩き回ってたみたい!」
ちょっと変な言い訳になったけど、悟られる訳にはいかないからな。
朝食を済ませたオレは、いつものように自転車で学校へ向かった。
途中で邪魔が入ったけど、ピンクのおばさんの反応からして最近はいじめていないようだった。マミーが強くなったということなのだろう。
ということはやはり、あれはマザーQなのか⋯⋯
「よっ! マコ!」
ケツだ。いつも遅刻してばかりなのに、今日はちゃんと家を出られたんだな。
「どうよ、調査は」
「やっぱりお前の言う通りマザーQの可能性が高そうだ。昨日オレがダディとマミーの話をしてた時もいつのまにか居たり、さっきも近所のおばさんに聞き込みをしてたら突然後ろに現れて⋯⋯」
「そうか。じゃあ、早いうちに退治しないとな」
退治か⋯⋯
「そうだな」
そうは答えたものの、まだオレには殺せるビジョンが浮かばなかった。蚊より大きなものを殺したことがないオレが、いきなり人間サイズをだなんて。
午前中の授業はうわの空だった。
昼休みになっても集中力はなかったが、腹が減ったのでとりあえず弁当箱を開いた。
色とりどりの具材の入った弁当だった。ちゃんと栄養バランスが考えられているとひと目で分かってしまうような、そんな弁当だった。
マザーQのことがイマイチ分からない。
オレの敵じゃないのか?
それとも母親に成り代わってるだけで、オレのことを本当の息子のように思っているのか?
思い返してみれば厳しくなったことと勘が鋭くなったこと以外はオレにとってマイナスなことはなかった。
今まで通り家事もしてくれているし、美味しいご飯も作ってくれる。
じゃあ、マザーQの目的はいったいなんなんだ?
「マコ〜〜〜〜!」
隣のクラスからケツが走ってきた。ほんとに暑苦しいヤツだ。
「マコ、ごめん!」
「なんだ?」
いきなりどうしたのだろうか。
「先生に残れって言われちゃって、今日一緒に帰れないわ! ごめん!」
「いちいち言いに来なくてもいいよ、別に一緒に帰る約束してるわけでもないんだし」
時間が同じだから一緒に帰ってただけだからな。
「そうか、わりーな! じゃあな!」
オレの言ったことをちゃんと理解しているのだろうか。
帰り1人か⋯⋯
コンビニでも寄るか。
結局午後もうわの空で過ごし、オレは帰路についた。
考えごとをしながら自転車に乗っていると、自分がここまでどうやって来たのか覚えていないことがある。
ちゃんと赤信号は止まっていたのだろうか。
ちゃんと左側を走っていたのだろうか。
誰かとぶつかったりはしなかっただろうか。
あ、そうだ。コンビニ行くんだった。
適当にお菓子とジュースと、ホットコーナーのチキンでも買おう。
コンビニに着くと、駐車場にオレと同い年くらいの学生服を着た男子が数人たむろしていた。
ウザっ。と思いながらオレはコンビニに足を踏み入れた。
変な味のグミが大々的に売り出されている。
ふむふむ、スモークチーズ味か。
こっちはウォッシャー液味か。
カゴにきくらげ味のグミとポテチとペプシコーラを入れ、レジに向かう。
「ラッシャセー、アッタメマスカー」
「お願いします。⋯⋯あ、フライドチキンください」
「カシコマリマシター」
ボン!
レンジの中からすごい音がした。
ピー ピー ピー
レンジが鳴った。
「あつっ、あつっ、あっつ!」
店員が熱そうにレンジの中身を取り出し、レジ袋に移していく。ドロドロになったグミと、袋が破裂したポテチと、爆発したペプシコーラとチキン。
「アザッサッシャー」
店員がこちらを向いて深々と頭を下げる。
教育がしっかりしているのだな、などと思いながら店を出たところで、肩になにかがぶつかった。
「あぁん? やんのかコラ」
たむろしていた高校生の1人とぶつかったようで、怒らせてしまった。
「やりません」
「じゃあ慰謝料払えや! 肩脱臼したかんな!」
脱臼!?
「大丈夫ですか!? 救急車呼びますね! あ、スマホ家だ! コンビニで電話借りてきますね!」
パニックになったオレはコンビニ店員のもとへ走った。
が、後ろから肩を掴まれて止まってしまった。
「何するんですか! 邪魔しないでください!」
「うるせぇよ」
そんな言葉と共に、頬にゲンコツが飛んできた。
意味が分からなかった。さっき脱臼したはずの高校生が、脱臼したほうの腕で殴ってきたのだ。
オレは右頬を押さえ、高校生と向き合った。
「どういうことですか」
「金出せや⋯⋯」
高校生の仲間らしき数人が集まってきた。
「ですから、慰謝料は病院で治療を受けてから支払いますので!」
いくら払えばいいのかも分かんないし!
「ごちゃごちゃ言ってんじゃねぇ! やっちまえ!」
リーダーらしき男の言葉と共に、数人の男がオレに襲いかかってきた。
「やめてください!」
フグホ!
「やめ⋯⋯てください!」
ハコフグ!
ぐ⋯⋯!
次々に手足が飛んでくる。
ようやく理解した。こいつらは、不良というやつだ。こいつらに絡まれると怪我をさせられ、金をむしり取られるのだ。
「そろそろ金出す気になったかぁ?」
「もういいよ、こいつムカつくしこのままボコしちまおうぜ」
「それもいいな」
物騒な会話だ。
クソ、なにか武器になるようなものは⋯⋯あ、ボールペンがある。こんな状況なんだ、過剰防衛だのなんだと言ってる余裕はない。
「よぉし、おめェらやっちまえー!」
四方八方から飛んでくる不良たち。どいつからやればいいんだ!
「やめなさい!」
コンビニの駐車場に聞き覚えのある声が響いた。
声のするほうを見てみると、マミー⋯⋯いや、マザーQが震えながら立っていた。
「なんだおばさん、邪魔すんのか? あ?」
「早くその子を離しなさい! 警察を呼ぶわよ!」
そう言いながらこちらに近づいてくるマザーQ。彼らを睨むその顔は、額にびっしょりと汗をかいていた。
「呼ばせねぇよ! オラ!」
1人がマザーQに襲いかかり、腹に蹴りを入れた。
「うぐぁ!」
マミー!
「フン、威勢だけかよ。おばさんこいつの母親か?」
「そうよ!」
なんの迷いもなく即答するマザーQ。
そこまでしてオレの母親を演じる理由はなんなんだ。不良に絡まれてるオレなんて放っておけばいいのに。
分からなかった。
「マミー! なんでオレを助けるのさ! なんでこんな危ないところに来るのさ!」
「バカね、あんたの母親だからに決まってるじゃない」
マザーQはオレの前に立ち、不良たちと向き合った。オレより小さな体のはずなのに、その背中はとても大きく見えた。
そうだ。
偽物かもしれないが、マザーQはいつもオレのために動いてくれていたんだ。敵なんかじゃない。いつもオレたちを第一に考えてくれてたじゃないか。
それを、殺そうだなんて⋯⋯
オレは、バカだ。
いや、でもこいつが生きてたらマミーが異次元から戻って来られないよな? どうすればいいんだ?
マザーQが悪いやつじゃないのは分かったが、どうすればいいんだ?
生きるためにマミーに擬態して、人間社会に溶け込んで、オレのために命をかけてくれてる。そんなやつをオレは殺せない。
誰も傷つけずに解決する方法はないのだろうか。
「ママに守ってもらってんじゃねーよマザコン野郎が!」
不良の言葉が聞こえた。
そうだ、今こんな状況だったんだ。考えごとしてたせいで忘れてた。
「マーコリン、早く逃げなさい!」
「ママを置いて逃げちゃうんでちゅか〜? マザコンちゃんは偉いでちゅね〜」
もはや不良の煽りなど聞こえなかった。
「死ねオラァ!」
不良がマザーQの腹を殴った。
「うぅ!」
苦しそうな声だ。
本物のマミーも今頃異次元で苦しんでいるのだろうか。
異次元ってどんなところなんだろうか。真っ暗で何もない、誰もいないような寂しい場所なんだろうか。
だとしたら、マミーはどれだけ寂しい思いを、苦しい思いをしているんだろうか。
マミー⋯⋯
マミー⋯⋯会いたいよ⋯⋯
マミー⋯⋯
「なにやってるのマーコリン! 早く逃げ⋯⋯マー⋯⋯コリン⋯⋯?」
気がつくと、オレはボールペンでマザーQの背中を刺していた。
「なんだ!? こいつ自分の母親を刺したぞ!」
「ヤバい奴じゃねーか! さっさと逃げるぞ!」
「こんな奴と関わっちゃいけねぇ!」
不良たちが次々と自転車で逃げていく。
「マーコリン⋯⋯どうして⋯⋯?」
刺してしまった。
⋯⋯もう後戻りは出来ない。
「マミーを返せ!」
こちらを向いたマザーQの胸に、オレは再びボールペンを突き立てた。
「うぐぁっ! マーコ⋯⋯リ⋯⋯」
それからオレは、何度も刺した。完全にマザーQが動かなくなるまで、何度も何度も滅多刺しにした。
そしてオレは、捕まった。
初めて面会に来たのはケツだった。
「おいケツ、どういうことだ! マミーが戻ってこないじゃないか!」
ケツの情報に誤りがあったに違いない。そう思ったオレはケツを怒鳴りつけた。
「お前、バカだろ」
ケツはそれだけ言って帰っていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
