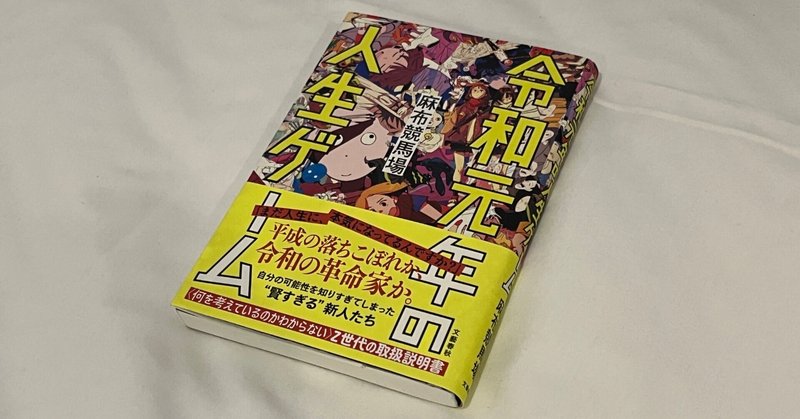
書評:令和元年の人生ゲーム (麻布競馬場)
「次は別冊文藝春秋で連載やるんですよねー、連作短編でまとめる感じで」
今から振り返ること1年と少し前。麻布十番の寿司屋で、目の前の男が炙った海苔をつまみにお猪口を傾けながらこう話すのを聞きながら、意外だなと思った。同時に少し安堵したことをうっすら覚えている。
「そうか、こいつも結局、『作家先生』になりたい、『こっち側』の人間だったのか」
薄汚れた感情とともに呑み込む純米大吟醸の酔鯨は旨かった。
当時、目の前に座る麻布競馬場という存在はTwitterという枠を飛び越えつつあった。デビュー作『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』は重版を重ね、どこの書店でも平積みに。ホリエモンや峯岸みなみといったテレビ画面の向こう側の人々との対談を繰り返し、彼の代名詞ともなった「タワマン文学」とともにネット上のミームでは片付けられなくなっていた。
そんな彼を出版社が放っておく訳が無く、日本を代表する大手出版社から次々とオファーが届いていることは聞いてはいた。突如現れた天才・麻布競馬場が次にどこで何を書くのか、そして出版社は何を書かせるのか――。何ら関係ない私にすら麻布競馬場への執筆依頼が届く始末で、界隈はちょっとしたバブルの様相を呈していた。
そんな中、「スマホに最適化された人類の脳はもう長文を読むことができないんですよ」と公言してはばからない彼が次の一手として小説を選んだのは個人的には意外だった。
麻布競馬場というアカウントが紡ぐ文章の美しさや、現代の東京を鋭く描く切り口の秀逸さがTwitterの片隅で局地的に盛り上がっていたタワマン文学という存在をメジャーに押し上げたは間違いない。しかし、商業的な成功の背景にはスマホで気軽に読めるというフォーマットが時代に合っていたという事実も見逃せない。普段小説を読まない層に売り込む上で、『この部屋から東京タワーは〜』が短編集という形を取ったのは必然だった。
一方、小説はそうではない。ただでさえ忙しい現代社会において時間を奪うコンテンツは敬遠されがちであり、受け手に読解力をも要求する小説というのはその最たるものだ。短編集で誰もが認める結果を出した人間が、あえてレッドオーシャンに突入する必要などないはずだ。同時に完全に余計なお世話ながら、短編小説とはいえ原稿用紙何十枚という文量は彼の持ち味を消してしまうのではとも危惧した。 あの美しい比喩表現も、流麗な文章も、長文で重ねると陳腐になるのでは、と。
そして何より、小説を書くという作業は孤独で、自らを削り出す工程が生み出すものだ。スマホを使って140文字の投稿をTwitterにツリーを書き連ねるスタイルが短距離走だとしたら、パソコンに向き合って十万文字を超える長文を書くことはマラソンに相当する。それは「書き始めた時点では着地点を決めずに、洗濯物を干したりしながら、その場で浮かんだフレーズをバイブスで書いているんですよ」という彼の創作スタイルとは真逆のものだ。その難しさを、辛さを、長編小説を書き終えたばかりの当時の私は身を持って痛感していた。
小説なんてしんどいものには手を出さず、エッセイやコラムを好きなペースで書き、港区で飲み歩いて気まぐれに有名人と対談し、「結婚する気はないんですよ〜」とかうそぶきながら気がつけばそこそこ知名度のある芸能人と電撃結婚し、広尾あたりのヴィンテージマンションで丁寧な暮らしをする。そんなコスパの良い人生を歩むものだとばかり思っていた。
すでに「何者」かになった彼が「作家として評価されたい」という純度100%の下心を持っている自分と同じような方向性に進むというのは、天才だと思っていた人間が案外俗っぽい場所に降りてきたように見え、少しばかり酒の進みを早めた。
そしてその数カ月後。「電子献本です」というメッセージとともに、別冊文藝春秋に掲載された『令和元年の人生ゲーム』第一話のゲラが届いた。
iPadでゲラを読み始めたとき、私が最初に感じたのは「なるほどね」というものだった。慶應大学、ビジネスコンテスト、意識高い系の若者たち――。扱うテーマはこれまでの延長線上にあり、長文になっても独特のシニカルな心情や天賦の才を感じる美しい文章は変わらない。ケチの付け所もなく、文句なしに面白い。
しかし、長文になったことで、麻布競馬場を麻布競馬場たらしめる爆発力や天才性は薄まっているように思えた。意地の悪い見方ではあるが、読者がスムーズに読み進められるよう、あえて平易な表現を用いることで読者に迎合していると理解した。それは私がTwitterから長編小説へとステージを移した時に最も気をつけていたことでもあった。
圧倒的な才能で牽引するのではなく、読みやすい文章を描く麻布競馬場。なるほど、これからも彼はこうした本を世の中に出し続け、時には有名な文学賞を取ったり、ドラマ化するようなベストセラーを世に出したりするのだろう。しかし、ノーモーションで140文字を連投して誰にも真似できない世界観を紡ぐ、ひりつくような才能の煌めきは感じなかった。その時私は、一つの時代の終わりを感じた。それは優しく、そして僅かに切なさの残る読書体験だった。
……はずだったが、読み進めていくうちに、それは私の勘違いでしかないと思い知らされた。ネタバレになるので詳細は割愛するが、一話の後半、全編を通じて登場する「沼田さん」と典型的な意識高い系の若者である「吉原さん」がそれぞれ転機を迎え、主人公である「僕」が怜悧な視線を送る場面で、私は思わず悶絶した。大学生特有の意識の高さ、そして痛さ。時代背景こそ異なれど、それは今から十数年前に私が日吉に、そして三田に置いてきた若気の至りであり、社会人になって家庭を築く中で完全に忘れていたものだった。
自身の黒歴史をこれでもか、これでもかと見せつけられながら、心の奥底にあるかさぶたを剥がされながら、塩を塗り込まれながら、それでも続きが気になってページをスワイプする手が止まらない。その読書体験は、かつてTiwtterで麻布競馬場の投じるタワマン文学の続きが気になって何度もリロードしていた時と同じものだった。
慶應大学のビジコンサークル、圧倒的成長を謳いながら踊り場に差し掛かったメガベンチャー、意識の高い若者が集まるシェアハウス、感度の高い人々に評価される老舗銭湯――。そこで描かれるのは男同士の歪んだ絆であり、娘が母に対して持つ湿度のある感情であり、女の友情における温度差であり、若者の持つ焦燥感であり、老いに対する恐怖であり、自分だけは秀でた存在でありたいという劣等感であり、要するに我々が日常生活で目を背けたいドロドロした何かだ。
4編の連作短編を通じ、麻布競馬場は確実に読者のトラウマ、あるいは現在進行形で抱えている傷を狙ってきた。最初に感じた「らしさ」を抑えた読みやすい文章も、平坦な書きぶりも、すべては罠だった。
無遠慮な外部者になって、東京のあちらこちらにある密室のドアを叩いて回りたい。その内部にいる人たちを揺さぶるだけ揺さぶっておいて、そうして「悪気はないんです」みたいな顔をして去ってゆきたい。そうすることで、多くの人の不安や不快と引き換えに、たった僕ひとりが救われたような気になれるのだとすれば、僕の執筆活動の収支は十分すぎるほどに黒字になる。
結局のところ、麻布競馬場は麻布競馬場だった。前回は短編集、今回は小説という形をとったものの、効果的に人を不安や不快をもたらすために最適な手段を取ったにすぎない。長編小説であれ、漫画であれ、ドラマであれ、きっと今後もそれは変わらないのだろう。新境地を見せつけた彼が次にどんな一手を繰り出すのか、どうやって我々を嫌な気分にさせるのか。ファンとして、心の底から楽しみである。
個人的な願いがあるとすれば、書き手である彼の感情が揺さぶられる場面を見てみたい。本作なのか、それともその先にあるのかは分からないが、将来、彼の作品が文芸賞にエントリーされるような日がきっと来る。その時は是非、タワマン文学界隈の一員として「待ち会」に呼んで欲しい。自らをヒエラルキーの外側に置き、人生を達観したような人間が飄々とした仮面を脱ぎ捨て、喜怒哀楽を露出する場面を見せて欲しい。私が嫉妬心を押し殺しつつ特等席で麻布競馬場の表情を確認するその場面こそが、我々が細々と紡いできたタワマン文学の到達点であり、終着点であるはずだから。
麻布競馬場の『令和元年の人生ゲーム』、第一章の終盤で心の奥底に存在していた古傷のかさぶたを剥がされて塩を塗り込まれて無事死亡した。読む人によって刺さる場面が異なれど、みんなうっすら嫌な気持ちになりながら次のページを求めてしまう怪作。https://t.co/r0r12XMutf
— 窓際三等兵 (@nekogal21) March 8, 2024
追記
検証した訳では無いが、Web版から単行本への改稿にあたり、彼の代名詞である秀逸な比喩表現や卓越した筆使いが復活しているようにも思えた。それも読み易さを維持したまま。これは読者を不安・不快にしたいという歪んで倒錯した愛だけで説明できるのだろうか。彼も心のどこかに「沼田さん」のような、得体のしれない何かを抱えているのではないか。凡庸な私にはよく分からない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
