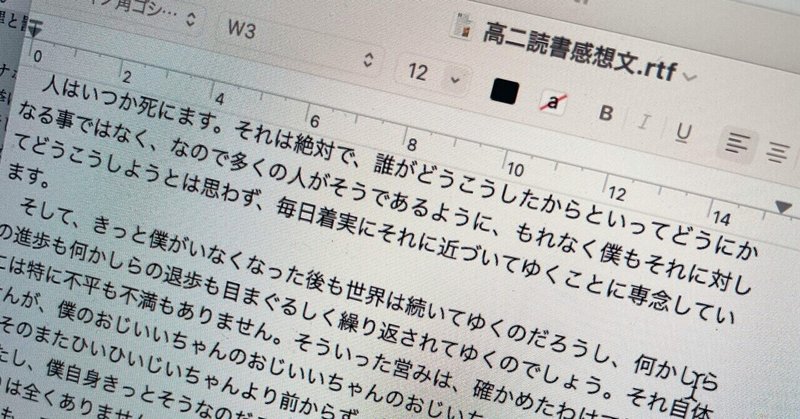
高校二年生の頃の読書感想文『夏目漱石 - 夢十夜(第七夜)』
人はいつか死にます。それは絶対で、誰がどうこうしたからといってどうにかなる事ではなく、なので多くの人がそうであるように、もれなく僕もそれに対してどうこうしようとは思わず、毎日着実にそれに近づいてゆくことに専念しています。
そして、きっと僕がいなくなった後も世界は続いてゆくのだろうし、何かしらの進歩も何かしらの退歩も目まぐるしく繰り返されてゆくのでしょう。それ自体には特に不平も不満もありません。そういった営みは、確かめたわけではありませんが、僕のおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのひいじいちゃんのそのまたひいひいじいちゃんより前からずっと続いてきたことだと教えられてきたし、僕自身きっとそうなのだろうと思っているので、僕だけが異端になるつもりは全くありません。
でも、そうだとしたら、何故僕はこういった退屈な毎日を(それでいて時々は目覚ましく楽しいこういった日常を)、単純に受け入れながら生きているのでしょうか。
こんな問答は何千年も前から研究されていながら、未だ僕に何の答えも教えてはくれません。死後の世界の有無、宇宙の起源に始まり、人類の誕生、進化、考えればきりが無く、一体誰がどうしてこの一切の閉塞から抜け出せるでしょうか。
笑ったと思えば泣いていて、怒ったと思えば照れていて、いたって脈絡無く続く一瞬一瞬の繋がりが人生なら、そこにはその感情以上も以下も無いように思えて、そんな考え方が行き着くのは、こういった単調に僕はいつまで耐えられるだろうか、ということです。
感情を押し殺せば瞼が痛くなり、取り乱せばやっかまれ、無関心でいたなら人間がわからなくなります。何処へ行っても楽は無く、此処にいたなら成長はありません。
期待をすれば失意の落差は激しく、自惚れれば過ぎた後の羞恥は虚しく、そこかしこにある感情全てが何かを戒める足かせのように思えてなりません。人生は至ってシンプルに窮屈です。
その窮屈の中で模索する自分の心もまた、ひどく不可解です。死にたいと思う瞬間があったとして、それが自分では本当に悩みぬいた答えとして持っていたはずなのに、数秒後には何も無かったかのように、生きたいと願うことすら出来ます。いつかは消えるのだから、と手を抜いて一つ一つをやりくりしたあげく、いつかがすぐには来ないことを知るや否や、急に焦燥に駆られることもあります。人生がどこへ流れてゆくのか、意味も無く思い煩うこともあります。
しかし、手のひらを返すようですが、こうした考察は必要以上に傲慢になりがちです。近年、テレビのニュースでよく見られるようになった未成年の自殺や殺人、その他の異常な問題は、まさに行き過ぎた、もしくは至らな過ぎた稚拙な空論の結果によるものが多いように思えます。
戦後の急成長で豊かになりすぎた日本は、生きるうえで贅沢すぎる悩みを勝手に抱え込んでいるのではないでしょうか。
一瞬の昂ぶった感情で決めたものごとは、そのふり幅が大きい故に取り返しのつかない場合が多いようです。
「自分はどこへ行くんだか判らない船でも、やっぱり乗っているほうがよかったとはじめて悟りながら、しかもその悟りを利用することができずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波のほうへ静かに落ちて行った。」
巷のワイドショーを賑わした未成年の、とりわけ自殺者の中に、漱石が描いた主人公と同じ気持ちでいた人がどれくらいいるのでしょうか。考えただけでもぞっとします。
ただ、もっと怖いのは、こういった感情にすらなれずに生きている人が確実にいることです。
感情をなくしてしまった世代が向かう場所はどこなのでしょうか。それが明るいものであることを願います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
