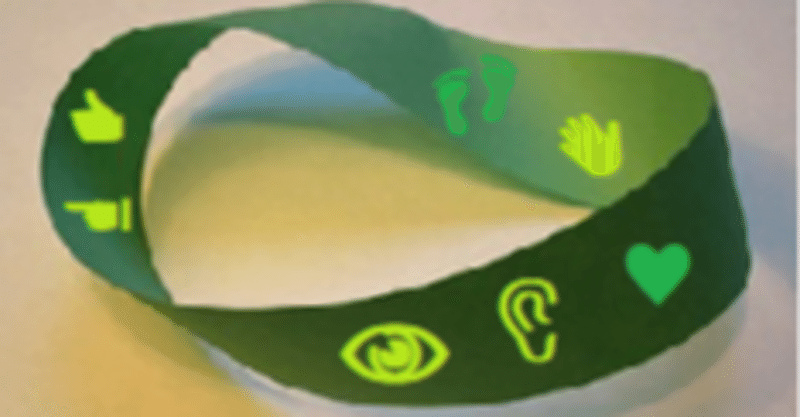
こんな流れだった哲学史
はじめに
ある地方の一乱読家だった33年前の10月頃、「哲学史って結局こういう流れだったんだな」と気が付き、そのシンメトリー(左右対称性)かつエターナル(永遠不変性)な完璧さに非常に驚いたことがある。
最近になって、もしこれを公開しないでいたら、この先22世紀になっても誰も知らないままだろうなとしきりに思うようになってきた。
しかし、いい表現方法が見つからない。取っつき易さなら難解な文章よりも簡易な漫画だろうと考え、ありきたりだがまずは4コマにまとめてみた。

プラトン著「パルメニデス」の中の有名な一節である。自分で描くよりも既存の絵画を貼り付けた方が哲学者の顔の深みが分かりやすい。そして、予備知識が特になくても4コマで十分に哲学のエッセンスを伝えられ、またギャグも盛り込めたのでこの路線で行くことに決めた。
次に、各哲学者間の関係だが、そこに現代の通俗的な人間法則を使用する。例えばビジネス本に載っている有名な「アイドマの法則」もその1つである。

「商品を見る」「商品に興味を持つ」前に、「商品が存在する」段階があるとすると、まさしくここにパルメニデスの存在論が該当する。
そして、若い頃に彼に叱られて、泥も汚物も髪の毛も「見る」ようになったソクラテスの4コマ漫画が次にきて、さらに弟子のプラトンが「イデアに憧れて興味を持つ」話が続く。
題をメビウスの輪にひっかけた理由は後で自ずとわかってくる。ただ、アイドマの法則だけではまだ足りず、他の人間法則も参考にしたい。やがて、こんな真実が見えてくる。
1.人間法則は合体できる=哲学史になる
まずはアイデアを生む方法の1つ「NM法」を見ていただきたい。

「①課題を決める」と「②キーワードを決める」の2つが、アイドマの「商品を見る」と「興味を持つ」に重なる。
他にもアイデアに関する説があるので紹介したい。アメリカの広告王、ジェームズ・ウェブ・ヤング著「アイデアの作り方」(TBSブリタニカ)の5段階である。

ヤングは「第一段階 資料集め」で情報をカードにまとめることを勧め、それを縦横に組み替えてみると書いたが、その部分はNM法の前半にも合致する。
いずれにせよ、見て興味を持った後に情報をいったんまとめる段階、次に思考する段階が来ることは共通しており、再び哲学史を振り返ると、アリストテレスとデカルトが該当する。
動物や植物などの各情報を博物学にまとめたアリストテレス。しかし、膨大な資料がいわゆる教条主義に陥ったために、自分の理性で考えることを勧めるデカルト。確かに合致する。
では次に、いよいよアイデアを閃く段階、そのアイデアの種を現実的にしていく段階がくるが、これを簡潔明瞭にまとめた現代の説が作家、藤本義一氏の「カンコウスイドウ」である。

たまたま古本屋で手に取った、月刊PHP(1988年8月号)内「藤本義一のシナリオ教室」の中の一節。観察までがパルメニデス~アリストテレス、考察がデカルトに当たる。そして推察(アイデアを閃く)がきて、洞察にいたる。この辺りの哲学史が次の3人である。
ロック、ヒューム、カントの3人は人間がものを見て考える流れを述べた。ヒュームは「かもしれない」とまでしか言えないところで止めたが、カントはその先の洞察段階まで進め、二律背反に至った。
以上がギリシャ哲学から近代認識哲学までの流れである。次はアイドマの法則によると、メモリーからアクション、つまり動く段階になる。すると、こんな真実がわかってくる。
2.哲学史は二列に平行して並んでいる
いったいどういうことなのか? まずは現代の人間法則の紹介から始めたい。下記はアメリカの著名な心理学者、ウェイン・ダイアー氏の「自己実現の5段階」である(三笠書房「自分を創る」より)。

第1段階で厳しい現実を“認識”してパニックに陥り、第2段階で無力となるが、少しずつ“動き”、やがて“こうやった方がいい、ああやった方がいい”と第3段階の努力へと進む。この辺りに該当する哲学がある。
マキャベリがぶつかった過酷な現実、ホッブスの2コマ目の人間機械論、そしてベンサムの功利主義はただ動くだけでなく功利性を意識する。
そこで、表紙部分を見ていただきたいが、一番上の赤い字の段は左が存在、右が認識で確かに隣同士で並べられる。次のオレンジ色の段は左がただ見聞きするだけ、右がただ動くだけなので対置できる。そして紫色の段は左がイデアに憧れて興味を持って意識が芽生え、右が功利的に動いて意識が生じているのでこれも対置でき、3つの段が平行して並べられるのである。
ダイアーの説は4段階目「対応」と5段階目「自己実現」の間が短いが、そこを詳しく述べた説が有名な千利休の「守破離」である(Wikipedia)。

師の教えを守る段階が4番目の対応にあたり、いわゆる“一人前”になる。次に師の教えを破る段階がくる。この2つに該当する哲学がヘーゲルとキルケゴールである。
ヘーゲルの「家族」「市民社会」に続く3番目の「国家」が一人前になった段階に当たるが、そこにキルケゴールは異議を唱え、それまでの客観から主観への転換を謀る。
だから、表紙の青色の段は左が認知していったん落ち着くアリストテレス、右も独立していったん落ち着くヘーゲルで隣り合い、次の緑色の段になって、主観から客観へと変わるデカルト、客観から主観へと変わるキルケゴールとなる。
では最終的にどこへ向かうのか? ダイアーは自己実現の完成と述べたが、それは存在が確立することでもある。存在といえばパルメニデス、そこで、こんな真実が見えてくる。
3.哲学史は一巡する
まずは、守破離とよく似たことを述べているベストセラー「ものぐさ精神分析」の著者、岸田秀氏による4段階を紹介したい。
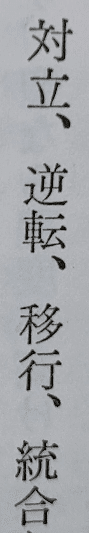
歴史上の幕府や政府の交代時もこの4段階を経るという。まず対立段階に当たるのがヘーゲル、逆転段階に当たるのがキルケゴールとすると、移行から統合、そして完成に当たる哲学者は以下の実存主義の3名となる。
表紙の薄い茶色の段では、左が観念を連合するロック(記号論の創始者でもある)、右が知人や友人を振り切って突き進む(連合ではなく分断に近い)ニーチェ、濃い茶色の段の左が疑似現実(かもしれないのヴァーチャルリアリティー)でとどまるヒューム、右が実存から存在への間にいるハイデガー、そして最後の赤い色の段が、認識に至る段階を述べたカントと、アンガージュマンという形で存在に至るサルトルである。
こうして哲学史は、存在から始まって存在に終わって一巡した。それがめでたいことか否か? 最後にもう1つだけ現代の人間法則を紹介したい。「オルグ学」(村田宏雄著 勁草書房)の4段階である。

ある集団が人を組織化する、これをオルグすると言うが、その時に使う4段階であり、地獄に落ちるぞ、天国に行くには、等と使ったりする。
第一公式が立場を揺さぶるので上の表で12段階目、第二公式が13で踏み込み、第3公式の心理学上合理化で納得して移行する14、そして第4公式の選択愛他的で15となり、16段階に至る。
つまり、存在に至る境地はいろいろあり、サルトルのようにノーベル賞は断っても盛大な葬儀となる成功もあれば、平凡な人生やあるいは失敗する人生などいろいろある。
ただ哲学史は輪のようにつながっている、というだけの話なのである。そこから何が言えるのか?
さいごに
まず言えることは、サルトルが最後の大哲学者であって、その後に誰も、デリダやフーコーなどの思想家はいても大哲学者は出て来ない事実の理由が判明した。
大哲学者は16人しかいないのである。もし今後、大哲学者が現れるとしたら、別のパターンとなる。
今までの大哲学者は、それまでの知を一段アップさせてきた。こうして人類の知は向上してきた。しかし、17番目以降の大哲学者はそんなタイプではない。
次に、この哲学史のリングは2列に分けられ、互いに平行してつながっている。だから“メビウスの輪”になっているといえる。そんな中で、いまや我々は適時適切な状態の選択を行うべき時代に入っている。
戦争を起こしたり政府が事件性の高い新興宗教にハマったりする場合ではない。この哲学史の真実を多くの人が知ることで、民度が高まって畜度が低くなればとは思うが、いかに漫画と法則でまとめてみたとはいえ、誰もがよく分からないままで終わってしまうものなのだろう。
ともかく33年の時を経てここに公開した。以上。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
