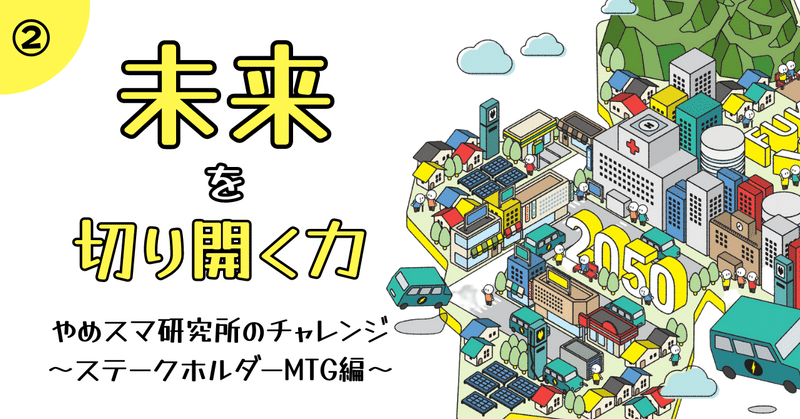
未来を切り開く力:やめスマ研究所のチャレンジ~ステークホルダーMTG編②~
「やめスマ研究所」は、強い田舎を創りたいという想いを軸に地域課題を解決するため、地域で活躍するプレーヤーたちに横串を刺し、それぞれのありたい理想の未来を実現するために立ち上がった団体です。八女には魅力的な資源もありますが、課題も多くあります。まず、本記事ではその目標に向けて「やめスマ研究所」の立ち上がった背景や活動、ゴールについてパート毎に紹介します。
④活動内容(ステークホルダーMTGに関して):内容編
いつも読んで頂いている方も初めての方も本記事をご覧頂きありがとうございます。
今回は前回の方針編に引き続き実際の内容について触れていこうと思います。
⑴キックオフMTG
前回の記事でも触れましたが「それぞれのありたい地域」の実現に向けて力をお借りしたい方々にお声がけをしてステークホルダーMTGを開催することにしました。
初回はお声がけしていた方にも地域の未来をイメージして頂くために環境省所管の地方環境事務所や環境パートナーシップオフィス(EPO)の皆様のご協力を頂きながら対談形式で未来のイメージを共有する会としました。
会の最後には参加頂いた皆様に受け入れてもらえた安心感からか、社長も漢泣きするなど非常に温かな雰囲気で会をスタートすることが出来ました。

⑵「SDGs de 未来構想」を用いて未来に向けたアイデア出し
昨年はキックオフMTGを除くと計4回のステークホルダーMTGを開催しました。
そこでは「SDGs de 未来構想」というプログラムを用いて地域課題や地域資源の洗い出しから自分たちのありたい未来の整理、そして地域課題を解決するためのアイデア出しを4回に分けて行いました。
この後は各回の内容に触れていきたいと思います。
Module1. 森の地図を描く~イシューマップの作成~
4回のうちの一回目は自分たちのまちが抱える課題の全体像を描くことから始まりました。
そもそもイシューマップとはイシュー(課題)をSDGsと連動させたマップに表現をして問題の構造とそこに紐づく分野の整理を行えるオリジナルマップです。
これを参加者皆さんでふせんに描き出した後にグループの皆さんとああだこうだ言いながらマップに表現をしていきました。ここでは課題を描くだけでなくその課題が何を地域にもたらしているのかまで表現をすることで自分が思う地域課題の全体像を把握出来たのではないかと思います。
実際に自分も体験しましたが、地域の課題も独立しているわけではなく様々な要因が絡み合って課題になっているということに改めて気づくことが出来ましたし、頭の整理をしながら他の参加者の方と話しをすることで地域課題の全体像を今までにない解像度で見ることが出来ました。
ステークホルダーMTGの初回として参加して頂いた皆様にとっても今後のイメージが沸く非常に良い会になったのではないかと思っています。

Module2. ベースキャンプを決める~コアイシューの設定~
課題の全体像を把握した前回に続いて2回目はその中心にある課題が何なのかを把握するとともにその問題構造を突破する糸口(レバレッジポイント)がどこにあるのかを見つけるところからスタートしました。
糸口を見つける手段として前回作ったマップの中で
1、課題の起点になっているところ
2、矢印の出入りが多いところ
3、直感的に気持ちが動くところ
をイメージしながら1~3つのポイントにまとめ大きな付箋に描き出しを行いました。
また、そこまで情報の整理を行った後にコアイシュー(中心課題)の設定を行いました。
ここでいうイシュー(課題)は「自分が問い続けたい、熱を持って解決したいと願う課題」という設定をしています。
また、それを
「○○(課題を抱える主体・対象・状況)の□□(解決・改善・向上・悪化せず現状維持)のために(私たちに)何が可能か」
というようにフォーマットで文章化することで、自分が持つ「ありたい地域のイメージ」をより具体化することにつながったのではないかと思います。
ここでは、先程の課題を自分事として解決する下地を改めてつくりながら他の参加者の方に共有することでよりイメージを固めることが出来たのではないかと思います。

Module3. 森を良くするアイディアを考える~アイディア発想~
前2回は課題の洗い出しを中心とした内容だったので精神的にもグッとくる部分も多くありましたが3回目以降はその課題たちを解決するアイデア出しからストーリーの作成とすごくワクワクする内容になったかと思います。
3回目ではタイトルの通りアイデア発想ということで、前回出た課題にどうアプローチしていけばいいかを”未来の芽”と呼ばれるSDGsに紐づく未来に向けた世界中で実行されているアイデアをベースに自分たちの地域に活かせそうなものやそこから発想される新たなアイデアを参加者の皆様と意見を交わしながら付箋に描き出し、ブレインストーミングのような形で一枚の紙にまとめていくワークを行いました。最終的には約50のアイデアが参加者の皆様から出るほど有意義に感じてもらえる回になったのではないかなと思います。
この回では地域課題を解決するために活用できる地域資源の見直しをすることで自分たちも気づいていないような地域の魅力を再発見できる機会になったと同時にワクワクしながらアイデアを出し合う参加者の皆様の表情を見ることが出来たので、個人的には非常に充実感を覚える会になりました。
Module4. 森の未来を想像する~未来のストーリーの作成~
全4回の締めくくりとなる4回目は今まで行ってきた課題の整理から地域資源を活用したアイデアでコアイシューの解決を行い、それによってどんな未来が実現できるかを4コマ漫画の要領でビジュアル化するワークを行いました。
ビジュアルで表現するという普段し慣れない作業に戸惑いながらもそれぞれが思い思いにシートに描き出している風景が記憶に残るくらい素晴らしかったです。
こうやって様々な分野の方が「地域の未来を考える」というテーマのもと自分たちに何が出来るかを共に考える機会を実際につくることで今までになかったものが地域に生まれるのではないかという希望を持てましたし、こういった場を地域でつくり続けていくことが自分たちのミッションだと改めて認識することが出来ました。
この全5回のステークホルダーMTGを通して出来上がったマンダラがこちらです。

参加した皆様から出た理想の未来像が実現できるようにこれからも活動を続けていくのももちろんですが、まだ意見を聞けていない地域住民の方も巻き込んでマンダラをより皆さんが自分事として捉えられるイメージ像にしていきたいと考えています。
この記事で大枠の設立の背景から活動内容の振り返りは終了します。
ここまで記事を追って読んでくださった皆様。本当にありがとうございます。
次回以降は出来ていなかったコアメンバーの人物紹介や今年度の方針及び活動紹介、イベントの告知等を行っていきたいと思いますので引き続き目を通して頂けると嬉しいです。

やめスマ研究所 所長
佐賀県武雄市出身 2018年に八女に移住。
ワクワク出来る未来をイメージしながら地域で活動中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
