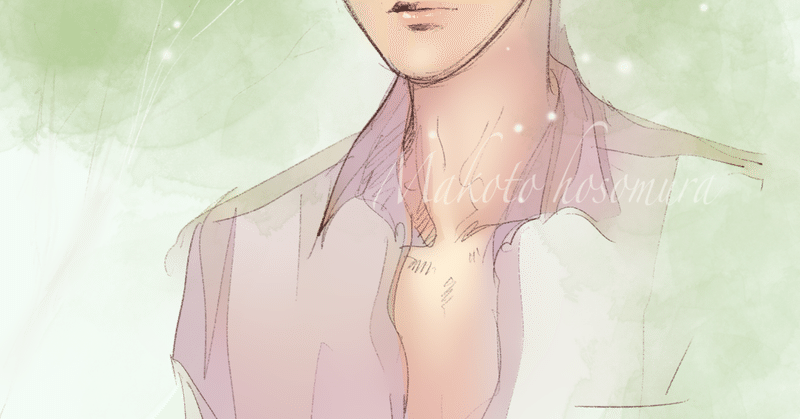
オリジナルの中のオリジナルの男【掌編小説】
※本作品2,519字数。
勇侍(ゆうじ)は極度に女性に弱い。
なぜか。
赤面症で、あがり症で、緊張しいだ。
一見すると、好青年風なのに非常にもったいないこと他ならない。もっとグイグイ積極的に行けば、運命が変わるし、毎日が楽しくなるはず。同じバイト仲間の爽介(そうすけ)はイケメンでモテる。自分から何のアクションが無くても、女性が声を掛けてくる。勇侍は素直に羨ましいと思っている。
勇侍は一度だけ、爽介に自らの女性観について相談したことがある。確か、バイト帰りだった。モテる為にはどうしたら良いかを。
「俺は自分がモテるとは、思ったことがない」爽介にとっては本音であった。
「じゃあ、俺ってモテるオトコになる?」爽介のストレートな回答を追うように、単刀直入に訊いていた。
爽介は、「俺はお前の親友だから」と敢えて前置きをした。鳥が口笛を吹いたようにピューと鳴いた。
「モテる為に、みんな大なり小なり努力している」
勇侍は意外な回答にドキッとした。爽介なりに悩んでいることを知った。爽介も、女性コンプレックスを抱えている。そう思うと、自らの悩みなんぞ矮小な悩みだと思えた。
勇侍は女性にモテる方が悩むし、もしかすると弱いどころか嫌いになるかもしれないと思った。イケメンの横顔は、バイトで失敗した時よりも何倍も暗く見えた。勇侍の苦手意識はさらに増した。
爽介は駅前に到着すると「オーイ」と遠い先に手を振った。手の先には小柄で華奢な女性が立っていた。
俺の彼女、と言うなり肩をそっと抱き寄せた。女性は何の抵抗もせず、爽介に身を委ねた。
「はじめまして」
小柄な女性はニコッと愛想笑いをした。無慈悲に思えた。いかにも、お前には興味が無いと言わんばかりに。
女優の小芝風花に似た、真面目そうな女だった。訊くと爽介と同い年だと言う。つまり、この3人全員同い年だ。
勇侍は同じ空間にいることがいたたまれ無くなった。単に同じ年と言うだけで、他は何も共通点が無いような気がした。
それから小芝風花似の彼女と他愛も無い話をして、気がついたら二人を駅で見送っていた。勇侍も同じ駅から電車に乗るはずだったのに。
電車に乗り車窓から風景を眺めた。
沈む夕陽がいつもより眩しかった。嫌味なほど明るくギラギラとしていた。
爽介は今頃、女優似の彼女と恋を燃やしているのだろうか。予想の及ばない世界に、想像を掻き立てられた。ただひたすらに羨ましく、妬ましく思った。俺だって、いつかは・・・。根拠の無い画家のような絵を描き始めていた。そう思うと、あがり症なんて精神で克服出来るような気がした。
自分も女性からモテたい。自分ならモテる。じゃあ、モテる為には。
実際問題外見を変えることは出来ないのだから、出逢いの場を沢山作ったり、積極的になるとか、自らを変えるしかないと思い詰めた。
勇侍は爽介のアドバイスを思い出していた。
もし、爽介が自分のようなイケメンではなからどうするだろう。今すぐに知りたくなった。
翌日、バイト先であるピザ屋に出勤すると何やらザワザワしている。皆一様に悲しげな表情をしていた。異様な雰囲気に、ただならぬ予感がした。
爽介がバイトを辞めたらしい。
急に『精神の不調』を理由に申し出てきたそうだ。
勇侍は悪寒がしたと同時に、昨日見た羨ましいまでの仲睦まじいカップルを思い出した。もしかして、あの後、彼女は別れを切り出したのか。真実は分からないが、何か無いと「精神の不調」などとはならないだろう。
バイトの合間に爽介に連絡をしたが、一向に連絡はつかない。勇侍は、自分はそのぐらいの存在なのかと絶望の淵に立たされた。
バイト仲間は、何もなかったかのように淡々と業務をこなしていた。生地をこねて、広げて、ソースを塗ってトッピングをつけてと、勇侍も仕事に没頭するしかなかった。ピザ屋は焼いて、配達してとせわしなく作業がエンドレスに続く。
勇侍は近くのマンションに配達を行うことになった。少しは気を紛らわしてやろうという店長からの配慮だった。
「オーイ、勇侍。15分後に近くの青葉マンションの長井さん、渕上さん、剛田さんへ持って行って」
店長はから元気のような雰囲気だった。不自然であればあるほど勇侍は傷つくし、事が大きいような気がした。
配達用バイクにピザを3枚載せて、ヘルメットをしっかり被った。安全運転の意識を忘れずに。出発前にしっかりルーティンを確認した。
店を出ようとしたところ、遠く先に見覚えのある女性が立っていた。小柄で大きな瞳を湛えている。まさかと思いつつも近付いた。
昨日見た、爽介の彼女だった。
しかし、なぜここに。
「爽介とは昨日別れた」
名を小百合(さゆり)という女性は悪びれる様子は全くなかった。
疑念を抱きつつも、勇侍は小百合とそこまで親しくない間柄であることにある種の恥ずかしさを覚えた。あんなに、爽介とは親しかったのに、俺は何も理解していなかったと。いや、女性というだけで敬遠していたのか。
そう思うと、居ても立ってもいられなくなった。自分が、今、彼女いや元彼女に真実を訊かなくてはならない。親友を自称する自らが聞く権利がある。何者かから、責任感に似た何かを求められていた。
目を合わせたが、大きな瞳に気圧された。
やはり、かなりの美女だ。
可愛さと大人っぽさがバランス良く同居している、と勇侍は思った。
勇侍は、ありったけの勇気を振り絞った。
「そっ、爽介は今どこにいるんですか?」
爽介は今、無事なのか。まずはそれを確かめたかった。目の前の元彼女は、平然と「どこにいるか分からないけど、生きている」と言って立ち去った。
本当は勇侍のことをもっと訊きたかったが、モゴモゴと口ごもっていたせいで元彼女は嫌気が差したのかもしれなかった。
配達の出発時間が近づいていたが、勇侍はどうしても店長に爽介のことを伝えたくなった。
「爽介、生きているって」
店内にいた全員の手が止まり、視線がこちらを向いた。全員が歓喜の声を上げて喜んだ。中には、涙を流している者もいた。スタッフ全員が接客そっちのけで、大きな輪になって勇侍を取り囲んだ。
勇侍は自らが憧れていた、今は居なき爽介になれたような気がした。
【了】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
