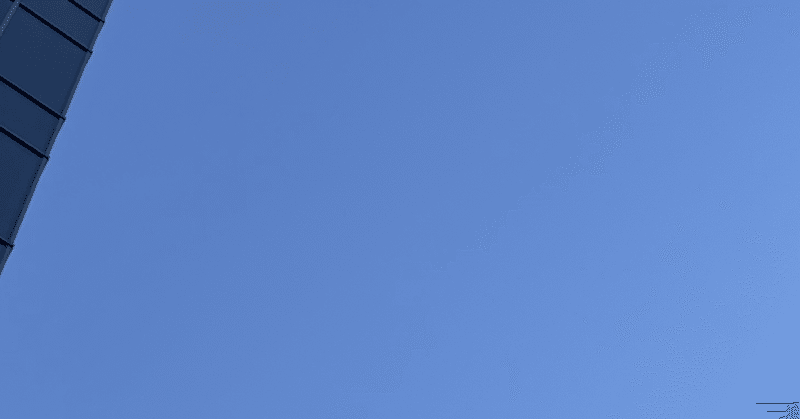
ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル5月号感想④変わる・変えていく介護の未来
nicoと申します。
よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。
日本FP協会より届くFPジャーナル5月号についての感想続きです。
今号の特集は「2025年問題を前に 変わる・変えていく介護の未来」です。
Part2の「FPができる分野別・介護のアドバイス」について感想を書いていきます。
「在宅介護」
親はできるだけ自宅で生活したいと希望しているが、金銭的に不安。今から将来の介護に備えておきたい
ここでのポイントは「できるだけ」という部分ではないかと考えます。
親と子で「できるだけ」の考え方が異なることがありそうです。
「何が何でも」と考えてしまい、介護離職をした先輩のケースを聞いたことがあります。
親は子に苦労をかけてまで自宅に固執している訳ではなかったと知って、誰も悪くないのにみんな苦しい結果になったことを切なく感じました。
なぜ自分で介護しようとするのか
私はひとり暮らしの母に「私は仕事を辞めて介護をすることはしない、介護が必要な状態になったら施設に入ってもらう」と伝えています。
私はガサツなので、私の介護で母が満足するとは思えないからです。
また母は賃貸住宅に住んでいるので、何かあったら施設へ、というのが単なる転居として検討できるのだと思っています。
逆に言えば、思い入れのあるマイホームに住んでいる人は施設入居のハードルが高くなるのではないでしょうか。
実際に同僚は単身で出身地のお母さまと暮らし、通院等のサポートをしています。
自宅は売ろうとしても買い手がない、と聞いたことがありますので、そういった点もネックになっているのかもしれません。
自宅で100歳まで独居は無理、何歳で施設に入居するか計画すべし
記事内では自宅で生涯生活するプランをケース1としてベースにしていますが、100歳まで自立生活を行うのはほとんど不可能です。
同居の娘さんの方が先に亡くなったり、要介護状態になるかもしれません。
私は健康寿命である男性81歳、女性87歳で、施設に入居することを前提に計画しておくのがよいと考えます。
そういう意味では記事内のケース2「81歳時で要介護認定を受けた後100歳まで在宅介護」も、ケース3「81歳時で要介護認定を受けた後在宅介護を経て88歳時に特別養護老人ホームに入居」のどちらも、サブフランとするべきものと感じました。
ケース3の在宅介護の期間を有料老人ホームに置き換えるべきだと思うのです。
もちろん介護費用として捻出できる金額が不足する場合は、サブプランを採用することになるかもしれません。
できるだけ自宅にいたいということであれば、健康に留意し、自立期間を少しでも長くしていただく。介護状態になったらプロの手を最大限活用する。
そうでないと、日本は介護にリソースが割かれすぎますます経済力が弱くなるように思われます。
お読みいただきありがとうございました。
ではでは。
よろしければサポートをお願いいたします!いただいたサポートは書籍の購入費として使わせていただきます。
