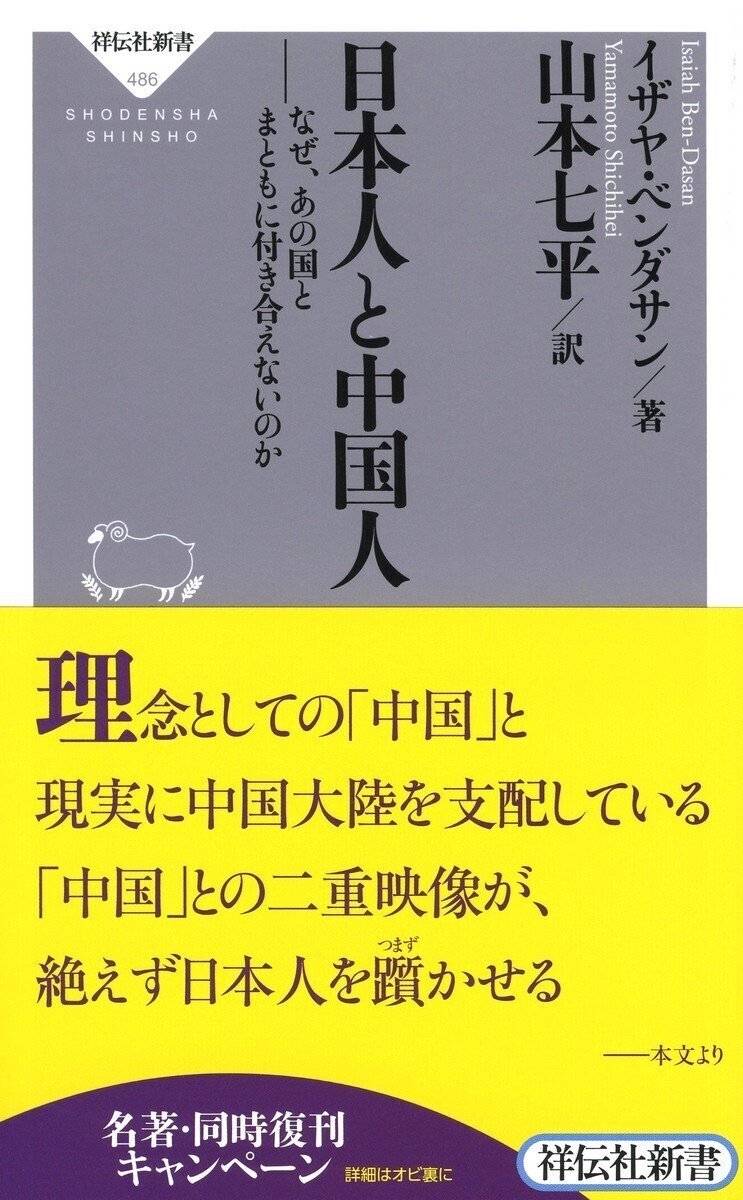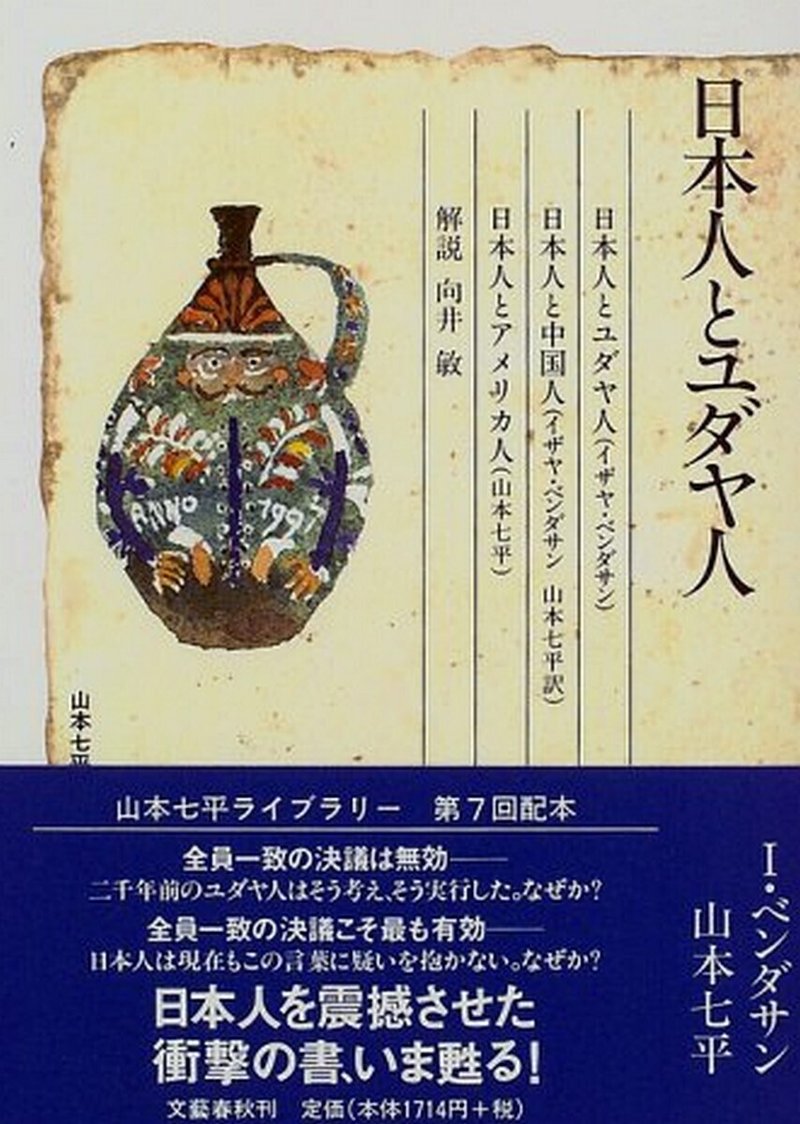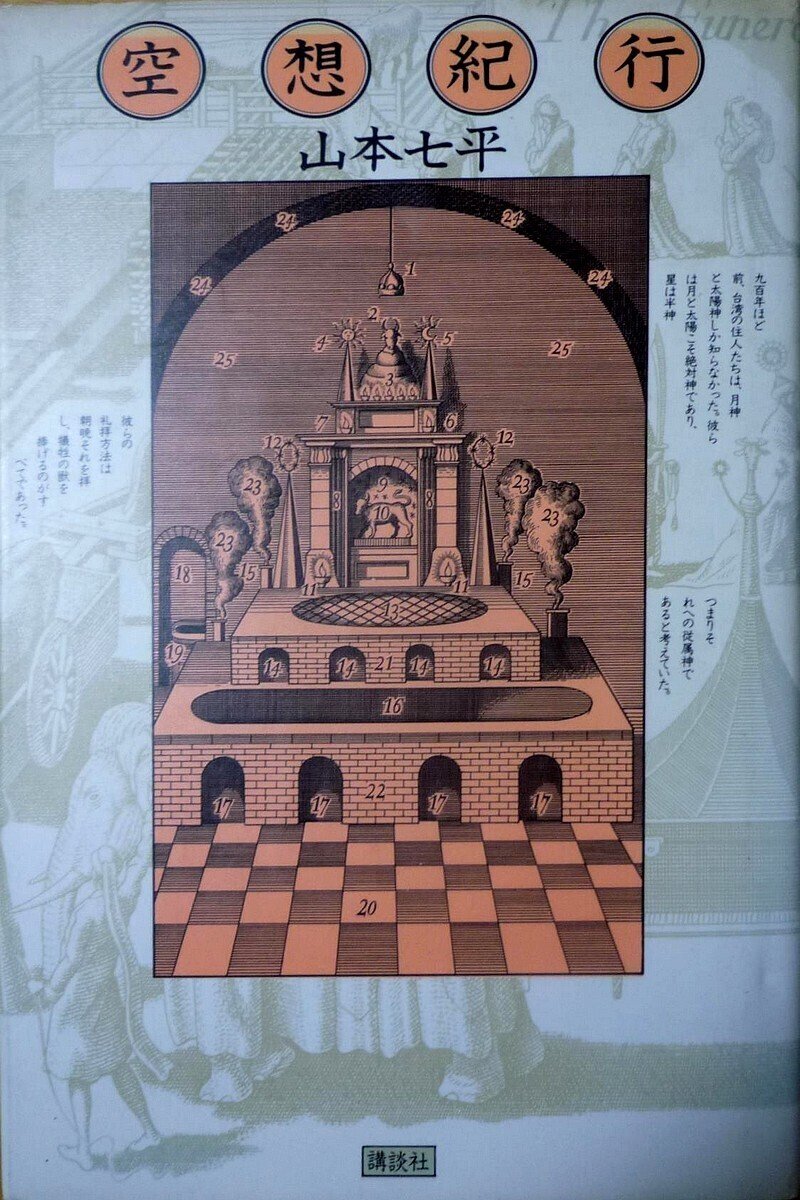「日本人とユダヤ人」講読
野阿梓
第二講 ベンダサン(2)
6
ベンダサンの著作権について。
「Voice」誌での山本氏の証言により、客観的に「イザヤ・ベンダサン=山本七平」であることを公的に立証しても、どうも、実社会においては、それが「事実」であるとは見なされない事がらも、残存しているようです。
私が言うのは、山本七平氏のペンネーム問題を批難して、偽名で書かれた偽書だから云々。と、そのベンダサン名義での著作物の価値まで貶めようとした一部のリベラル派のジャーナリズムやキリスト教左派のことではありません。
これは純粋に法律の問題です。細かくいうと、「著作権」の問題になります。
内田樹という人がいます。東京大学の仏文を出て、大学の先生などをしながら、厖大な数の本を出しています。たとえネット上の文章であっても、それなりの信用度はある、と思われます。氏が、「内田樹の研究室」(※1)なるブログに、以下のようなことを書いています。
※1)http://blog.tatsuru.com/2016/08/26_1843.html
「山本七平「日本人と中国人」の没解説
山本七平の『日本人と中国人』の文庫化に解説を書いてほしいと頼まれて書いたのだが、この本の著者はイザヤ・ベンダサンという架空の人物であることになっており、著作権継承者が「イザヤ・ベンダサンは山本七平の筆名」だということを認めていないので、誰が書いたのか曖昧にしたまま解説を書いてくれと原稿を送ったあとに言われたので、「そんな器用なことはできません」と言って没にしてもらった。
せっかく書いたので、ここに掲載して諸賢のご高評を請う」(同サイト一六年八月二六日)
――という、ちょっと穏やかならぬ背景を感じさせます。
内田氏の書いた文章の冒頭を引用すると、
「「日本人と中国人」はかつて洛陽の紙価を高めた山本七平の『日本人とユダヤ人』を踏まえたタイトルであり、その造りも似ている。いずれも「日本人論」であって、タイトルから想像されるような比較文化論ではない。中国人もユダヤ人も、日本人の特性を際立たせるために採り上げられているだけで、主題的には論じられているわけではない(『日本人とユダヤ人』では、著者イザヤ・ベンダサンが「米国籍のユダヤ人」であるという虚構の設定に説得力を持たせるために、ユダヤ・トリヴィアがところどころに書き込まれていた。だから、「日猶文化比較論」として読むこともまったく不可能ではなかったが、本書は「日中比較論」として読むことはできないし、著者にもその意図はなかったと思う)」
――とあり、没になった問題が奈辺にあったかを窺わせるに足るものがあります。
内田氏は、「文庫化の解説」と書いていますが、これは、祥伝社新書「日本人と中国人――なぜ、あの国とまともに付き合えないのか」(祥伝社、二〇一六年十一月二日刊)のことでしょう。この本は元版が祥伝社で、〇五年に単行本が刊行されており、この新書版は、それを底本としたものと思われます。
しかし、「日本人と中国人」は、さらに淵源すると、もともと、これはベンダサン名義で、「文藝春秋」誌に七二年から七四年にかけて十回にわたり連載されたもので、しかも、なぜか当時は書籍化されませんでした。理由は不明です。その間、同じ文藝春秋社から「日本教について」や「にっぽんの商人」などが刊行されているのですから、どうしてこの本だけ連載が完了しているのに、単行本として出されなかったのか。七二年に、日中の国交が正常化となり、台湾を斬り捨て、大陸との外交に方針が転換したので、それが関係しているのか、とも思われますが、不明です。
文藝春秋社が単行本化したのは、やっと九七年になって、それも「山本七平ライブラリー」十三巻に、「日本人とユダヤ人」「日本人と中国人」「日本人とアメリカ人」の三つを収録する形でした。しかも、この時の著者名は、「イザヤ・ベンダサン、山本七平」の両氏(つまり共著あつかい)でした。
祥伝社は、その内の「日本人と中国人」だけを書籍化し、さらにそれを新書化するに際して、解説内の文言をめぐって内田氏と揉めたようです。内田氏は、完全に「日本人とユダヤ人」の真の著者が山本七平氏である、と確信しており、それは「Voice」誌を読んでいれば、当然、そう思ったでしょうから、その他のベンダサン名義の文章も山本氏の書いたものだ、という認識だったと思われます。編集部からの「著作権」云々。という言い条で、すでに書いた解説の内容を枉げてくれ、という申し出には、物書きとして応えかねるのは当然でしょう。
しかしながら、担当編集者も、いわば著作権継承者と板挟みの恰好だったのは、容易に想像がつきます。依頼したくらいですから、いたずらに内田氏を困惑させよう、という意図ではなかったはずですし、純粋に著作権がからむ問題と、いわば論文内容の理路が交錯して阻害される状況があったもの、と想像されます。あらかじめ、そういうことを明示的に申し出て、解説を依頼すれば好かったのでしょうが、間に合わなかった、と思われます。
そこで問題は、九七年から〇五年、さらに直近の一六年にかけてまで、ずっとこの本の「著作権者」がベンダサンであった、という出版事情にあります。つまり、これは、半世紀前の出来事ではなく、ごくごく最近の話なのです。
単一の本としての祥伝社版「日本人と中国人」は、元版も新書版も、ともに「イザヤ・ベンダサン著, 山本七平訳」となっており、これを踏襲したがために、内田氏への編集部の依頼と、没騒動になったものと思われます。この点でも、山本七平ライブラリーとは異同があり、不可解です。
念のために言いそえておきますと、祥伝社は一ツ橋(小学館)グループに属する、きちんとした出版社であり、相手が誰であっても、いい加減な対応はしない版元です。一六年当時の内田樹氏は、それなりの地位を築いておられたので、祥伝社の編集者が横柄ないし横暴な態度をとるわけがない。従って、これは純粋な「著作権」の解釈をめぐるトラブルだ、と見て好いでしょう。内田氏は当然、ご不快に感じられたと思いますが、担当編集者としては、あまりに早く原稿を書き上げた内田氏と、その解説内容への対応に苦慮したものと思われます。
常識的に考えて、山本七平氏は九二年に逝去されており、当時の著作権継承者は、未亡人の山本れい子氏だったはずです。れい子夫人は七平氏と五四年に結婚しており、当時、七平氏が三二歳、夫人が二七歳とありますから、九二年時点で夫人は六五歳。現在、ご存命だとしたら九〇歳を越えます。山本七平氏が店主(社長)をしていた山本書店は、氏の没後も継続され、〇七年三月三一日に「閉店」しておりますので、もしかすると亡くなっておられるのかも知れません。ただ、その場合も、山本七平氏の著作権は長男の良樹氏に継承されます。
ですから、もし、ベンダサン名義の「日本人の中国人」の著作権が、山本七平氏であったならば、その著作権継承者はれい子夫人か良樹氏になっているはずです。
しかるに、こうしたトラブルが実際に発生している。奇妙なことです。
以前に、山本氏は、「日本人とユダヤ人」について「私は著作権を持っていないので、著作権法に基づく著者の概念においては著者ではない」と発言しており、これは氏一流の自己韜晦だ、という風に解釈されていたのですが、どうも、そうでもないらしい。「日本人とユダヤ人」の真の著者(執筆者)が山本七平氏だったとしても、その「著作権」は法的には異なっているのかも知れません。
7
著作権は、二つの側面を持ち、一つは「財産権」であり、もう一つは「人格権」であります。英米法と大陸法では微妙に異なるのですが、大まかに言うと、大陸法で保証されるこの二つです。
このうち、特に「共同著作物」に関しては、「共同著作権」が設定されています。簡単にいえば、単一の著作者の場合は、その著作権を他者に譲渡することが可能ですが、共同著作物の場合は、その共同著作権をもつ全員の同意がなければ、それが不可能になります。
なお、共同著作権が発生する要件としては、
1)著作権者が死亡し、相続人が複数いる場合
2)複数人による共同著作物の場合
3)契約や合意によって、複数の当事者間である著作物が共有とされた場合
――が有ります。
この際、1)は考えないでもいいでしょう。問題は、2)と3)です。
おそらく、これだけ、(当時から真の著作者だろうとされていたにも関わらず)当の山本氏が、自己韜晦と見なされるほど、周到緻密な発言をしていたこと、また実際に氏の没後二十四年も経っているのに、そうしたトラブルが発生していること、などを勘案すると、2)と3)が、ベンダサン名義の著作には関与しているのだ、と思われます。
要するに、上述したような経緯で、たとえ実際の執筆者が山本氏一人であっても、そのアイディアや助言を出していて、彼の友人であるローラー、ホーレンスキーの両氏、あるいは少なくとも、どちらか一人が「合作」として関わっていて、私欲のない山本氏が、(当初はまさか、そんなにベストセラーになる、とは思ってもいなかったせいもあるでしょうが)、律儀に「共同著作者」としての合意と契約をされていた。これはたとえ、口約束でも法的には有効です。
こういう風に考えると、この問題が、ここまでこじれる理由が、すんなり納得できます。
私が購読しているブロック紙「西日本新聞」の九一年の十二月二〇日付記事には、山本七平氏の逝去にからめて「家畜人ヤプー」の著者、沼正三氏も取り上げて、「覆面作家の正体 闇の中」という昭和を代表する異端の知性である両者を並べて論じていました。その中に、
「(ベンダサンと翻訳者の山本氏が同一人物ではないかという噂に対して)これについて、当時の山本さんは「ああ問題になると困るんだ」と笑い「外国に印税を送っているし、その相手が一人というのは間違い」と語り「イザヤ・ベンダサン」は複数の作家ながらも、山本さん以外の実在する人物であることをほのめかしていた。
出版界では「イザヤ・ベンダサン=山本七平」が定説になっているが、出版元の山本書店では「現在も印材は払い続けています。どなたにかは言えません」という」
――と記しています。
著作権法という法律がからむ話なので、これはさすがに本当なのではないか、とも思える証言です。
私たちは、今ではまた、似たようなケースを別なジャンルにおいて、すでに知っています。「羊たちの沈黙」で世界的な大ヒットとなったサスペンスミステリの巨匠トマス・ハリスは、七五年に「ブラック・サンデー」というモサドとパレスチナゲリラの諜報戦を描いたスリラーを書いていますが、最近、といっても一二年に、改訳版が出た「羊たちの沈黙」の解説では、
「『ニューヨーク・マガジン』の一九九一年四月十五日号に掲載された〝作家トマス・ハリスの沈黙〟という記事によれば、一九七三年、ハリスはサム・モール、ディック・ライリーという二人の親密な記者仲間(筆者注:当時ハリスはAP通信の社会部記者だった)と共に、当時の緊迫した世界情勢を背景にしたスリラーを書くことを思いいたった。その仲間の一人サム・モールは同記事でこう述懐している――〝ぼくたちはゆきつけの酒場で全体的な筋立てを話し合い、裏づけになる取材も共同で行って、三人で書きはじめたんだよ。クライマックス・シーンにグッドイヤーの飛行船を使おうというのは、最初からハリスのアイデアだったけどね〟。
その後、執筆者を一人に絞ったほうが得策ということになり、結局、言いだしっぺだったトマス・ハリスが全編をまとめて書き下ろした。そういう成り立ちであったため、完成後パトナム社から出版が決まった際、印税前払い金は三人で分配したのだという。この経緯については、『ブラック・サンデー』刊行直後の一九七五年二月に『ニューヨーク・タイムズ』に掲載されたインタヴュー記事で、ハリス自身もほぼ認めているから、大筋は事実なのだろう」
――とあります。
トマス・ハリスは寡作で有名な人ですが、処女作である「ブラック・サンデー」と「羊たちの沈黙」とでは、まるで作風が異なります。解説にもあるとおりで、こうした背景だったなら、それも肯けることです。
さらに、日本では三冊しか訳書がないにも関わらず、SF関係者の間で、かなり話題になったポーランド出身の亡命作家、イエールジ(ジャージー)・コジンスキーにも、同様の疑念が囁かれたことがあります。「異端の鳥」「異境」「予言者」、といった読む者に異様な感銘を与える著作、特に「予言者」は映画化され、主演のピーター・セラーズは、ほぼ遺作となったその映画「チャンス」で、これまでのコメディアンとしての演技を一切封印し、シリアスな役を演じてゴールデングローブ賞を獲っているのですが、原作は淡々と静かに描かれて「奇妙な味」小説を思わせるものがありました。
コジンスキーには、その著作が複数の人間のホームネームではないか、とか「異端の鳥」は彼自身の幼少期を描いた自伝的なものか、全くのフィクションか、さらには盗作の疑いまでかけられていました。CIAとの繋がりも噂される中、九一年に遺書を残して自殺し、一切は謎のままとなりました。「異端の鳥」を私が初めてその書評を読んだのは、「奇想天外」誌の星新一氏のコラムだったと憶えています。すぐに書店に注文して買い、読みました。
コジンスキーの件は詳細が不明ですが、こうした実例があるのですから、ベンダサンが複数の著作者の共同作業のホームネームだった可能性は、けして低くはないでしょう。そして、トマス・ハリスの場合も、コジンスキーの場合も、おそらく、執筆者が複数、ということは考えにくい。評論でも物語でも、そのナラティヴというものは、ソフトウェアの取り説とは違います。そこには統一した叙述というものが必要となり、それは決して複数の人間が章を担当を分担して出来るようなものではないのです。さらに言えば、トマス・ハリスやコジンスキーが他人のアイデアを取り入れたからといって、それでその作品の価値や、私たち読者の感動は、いささかも損なわれることはありません。誰がどんな筆名で実際に書こうが、結果、それが傑作であれば、その事実には何の関係もないのです。
ここで、付言しておくと、ベンダサン名義の著作物に関して、話をややこしくしているのが、必ずしも他の共同著作者であるローラー、ホーレンスキーの両氏ではない可能性です。すなわち共同著作者の一人であった山本七平氏の著作権継承者(一時は確実に山本れい子氏、今は、あるいは長男の良樹氏)が、当初の合意や契約どおり、それを履行しようとして、そうなっている。そういうことも考えられます。そうなると、一概に担当編集者を責められません。夫人やご長男としては、夫ないし父が成した合意や契約を、継承者の身で勝手に破棄するわけにはいかない。特に三代続いたクリスチャンの山本家としては、そういう没義道なことは断じて出来ない。しかも英米人において、その契約は絶対ですから、あくまでもそれを履行しようとしているのかも知れない。しかも、そうした内々の事情を、あまり外部に出したくはない出版社サイドとしては、気軽に依頼した内田氏から、案に相違した文章を解説として書かれて、困惑した。……といった図式がたやすく描けるでしょう。
8
ベンダサン名義の著作物は、さして多くはありません。単行本としては、
1)「日本人とユダヤ人」
2)「日本教について」
3)「にっぽんの商人」
4)「日本教徒」
5)「日本人と中国人」
6)「日本教は日本を救えるか」
以上だけです。山本氏存命時には、4)までの四冊のみでした。
このうち、2)については、元版だけに、雑誌掲載時に反論を寄せた本多勝一氏が共著者として名を連ねていますが、その後の文庫版では本田文献は収録されていません。
他方、山本七平氏の単独著作は、全部合わせると厖大なものになりますが、「Voice」誌の「人生論」に、その端緒が言及されています。
「もの書きとしてのスタート
私が初めて雑誌にものを書いたのは、横井庄一さんが出てきたときである。その前から『文藝春秋』に何か書かないかという話はあったが、断り続けていた。ところが横井さんが出てきたのが締切りの二日前で、当時の文春の編集長から何でもいいからジャングルのことを三十枚ほど書いてくれと強引に頼み込まれた。それで、横井さんはジャングルにいたはずはない、ジャングルにいたらすぐにマラリアにやられてしまう、恐らく私の考えでは竹林に近い所ではないか、そこならば確かに人間はある程度生きていける、というようなジャングルの体験を書いた。
それがきっかけで、ちょうど当時は中国懺悔時代だったこともあって、軍隊に関するものをかいてくれと『諸君!』に頼まれた。一回きりのつもりが連載になり、これが『私の中の日本軍』という本になった」
――というような経緯だったようです。
「文藝春秋」の記事は、NDL-OPACで見ると、「なぜ投降しなかったのか」(「文藝春秋」七二年四月号「横井庄一と日本人特集」所収)で、十頁ほどの文章です。横井庄一氏の「発見」は七二年一月でした。ただし、その後、同じ年のうちに、何度かベンダサン名義(山本訳)で文章を載せ、そして七二年十二月号から「日本人と中国人」の連載が始まります。翌る七三年に独著作の最初である同名の単行本となります(七四年五月)。
「私の中の日本軍」は、国会図書館も蔵書か書誌に遺漏があると見えて、NDL-OPACで検索しても「諸君!」誌の山本氏名義の掲載記事が全て漏れており、いつからいつまでの連載か不明ですが、上下二巻の大冊が刊行されたのは七五年十二月ですから、上記の経緯は少し氏に記憶ちがいがあるのかも知れません。
ついでに言うと、「諸君!」の方の記事も、やはり〆切り直前の依頼だったそうで、これは、七二年五月三〇年日に、テルアビブ空港で日本赤軍が無差別テロ銃撃事件を起こしたのが、〆切り前一日か二日前のことで、切羽つまった編集から頼まれて書いたものが、「岡本公三を生んだ日本軍内務班 私の中の日本軍隊」だったそうです(「人生について」(PHP研究所 一九七頁から一九九頁)。
ちなみに、やはりNDL-OPACでは漏れていますが、同年十月に、小野田少尉がフィリピンで発見された時に、地元民と銃撃戦となり小野田少尉の部下が死亡し、彼の生存が確認されました。家族や戦友が出向いて捜索したのですが、出てこない。七四年になって日本の冒険家が現地を訪れ接触に成功。その際、少尉は「直属の上官の命令解除があれば、任務を離れる事を了承」した、と言います。そこで山本氏は週刊誌に「実効性の高い」記事を寄稿しています。
「「未だに敗戦を信じないのはおかしい」という人がいれば、それはその人が国家間の戦闘状態の終結と、小部隊の戦闘状態の終結とを混同しているに過ぎない。小野田元少尉に関する限り、四七年十月一九日にジャパニーズヒルでフィリピン軍と銃撃戦?を行い、部下の小塚さんが戦死しているのだから、そのときもなお現実に戦闘状態であって、彼自身に関する限り、この状態に根本的な変化があったという確実な保証は、何一つ提示されていないのである。(中略)
日本軍では「上官の命令」が直ちに「天皇の命令」であるから、小野田少尉の言っている通り、直属上官の命令か指示があれば、必ず出てくる。従って、原則的にいえばそれだけ伝えれば十分なのである。
では、どのようにして「終戦」を伝達するか。これは「戦争法規」に基づいて行えばよい。日本軍は、戦後はまるで「ならず者集団」のように描かれているが、実際は一つの法規を持った組織すなわち正規軍であり、小野田少尉はその幹部だから、そのように対応すればよいのである。
彼は自分が戦闘状態にあると信じており、また彼自身にはそう信ずべき理由があるのだから、この戦闘状態を一時停止して「話合い」を行おうというのなら、こちらから出向いていくのは銃器をもった討伐軍ではなく「軍使」のはずである。従ってフィリピン軍の援助は鄭重に辞退すべきであろう。軍使は必ず、自国旗と白旗をもつ。白旗は、戦後、降伏のしるしと誤解されているが、それは使用法の一例にすぎない。
白旗については、特権だけでなく、「歩哨の一般守則」として、次の点は兵士まで徹底して教育されているはずである。すなわち「白旗ヲ掲ゲ遠方ヨリ軍使タルヲ表ワスモノト降参人トニ対シテハ敵トシテ取扱ワズ、歩哨線外ニ之ヲ止メ……」と。小野田少尉はこれを知らないはずはない。
従って、彼のいると思われる地点に、日章旗と白旗をもった人間が一人か二人で入って行き、「動かず」に、根気よく待てば、それで十分である(後略)」(「週刊文春」七四年三月一八日号)
実際に、この方法により、小野田少尉は即座に上官の下に出頭し、戦闘終結を受け容れ、彼の「戦争」は終わりを告げました。ただ、どのメディアも、そのアイディアを山本氏が週刊誌に出した、ということは報じられなかった由です。
ルソン島のジャングル戦で病熱に冒されながら敗走し、終戦を知ったのが四五年八月二七日だった、という山本氏が、自分とほぼ同年齢の、しかし、一般の徴兵ではない、職業軍人たる陸軍中野学校卒で、小野田少尉が、どういう思考回路を持っているか、熟知していたことが窺えます。
小野田少尉は、中野学校では、いわゆる「生きて虜囚の辱めを受けず」といった戦陣訓ではなく、あくまでも生きのびて遊撃(ゲリラ)戦を行い、最後の一人となっても戦い、玉砕はこれを許さず、捕虜となっても死んではならない、という特殊な教育を受けていました。さらに比島に到着した際、師団の参謀部付情報将校として師団長から直々に、「玉砕は絶対にまかりならん。何年かかっても必ず迎えに行く。それまで部下の兵士が一人でも残っていれば、その兵を使って頑張ってくれ」と言われたと言います。少尉はこれを忠実に守ったのです。
ルバング島は、地図を見れば一目で判るように、マニラ湾を一望できる要衝の地にあります。そこでただ一人の情報将校として残された意味は、小野田少尉にとって明白でした。彼は、本隊が去った(あるいは壊滅した後の)「残置諜者」として最前線でのゲリラ戦、後方撹乱、その他、中野学校で叩きこまれた教育を美事に成し遂げました。その間、奪ったトランジスタラジオを改造して、世界や日本での情勢は知っていた、というのも驚きですが、日本は米国の傀儡政権が支配している、と確信していたと言います。当時の上官が参謀部別班命令を口達で伝えると、翌日には比島軍基地に出頭し、軍刀を手渡し、毅然として投降の意思を告げます。軍司令官は、同じ軍人ですから、小野田少尉にその軍刀を返し、軍隊における忠誠の見本だ、と称賛したそうです。少尉の方は、その場で処刑されることを覚悟していたそうですが(その間、何人もの比島人を殺傷しているため)、ここにようやく、彼の、たった一人の軍隊の29年間におよぶ「戦争」は終わったのです。
山本氏が「私の中の日本軍」という大冊を書き上げたモチベーションの一つに、この「狂気」に満ちた「戦争」と「日本の軍隊」の加害者であり同時に犠牲者であった小野田少尉の面影が垣間見える気がいたします。
文庫版の第十四章「プールサイダー」の冒頭には、
「前章では、評論家に大分苦情をのべる結果になってしまったが、実をいうと、私が少々恋いこがれているものの一つが、日本における「評論家」といわれる人びとなのである」(二一七頁)
――と書いたベンダサンは、おそらくなるべくして文筆家になっていたでしょう。著作権上の名義がどうであれ、それはすなわち、山本七平氏にも同じことが言えると思われます。これだけ該博な知識を、しかもアカデミズムの体系的な教育ではなく独学で有し、さらにある時は軽妙洒脱、またある時は厳しい指摘をもって、古今東西の古典、哲学、思想、文芸の書籍を自在に引用し、読む人を飽きさせない平易な文章をもって、しかし深遠なテーマを書ける人ならば、放っておいても、いつか世に出たことは間違いない、と思われるからです。
9
ところで、「日本人とユダヤ人」ですが、国会図書館をNDL-OPACで検索すると、まだ文庫に落ちていない段階で、早くも週刊誌がこの本を取り上げています。一番古いものでは、「週刊現代」七〇年十一月の四七号で、「通産省でいま熟読されている一冊の本--日本人ビジネスの長所短所を鋭くえぐる隠れたベストセラー『日本人とユダヤ人』」という記事が見えます(通産省は今の経産省です)。
また、「日本人とユダヤ人」は「山本七平ライブラリー」一三巻(文藝春秋社、九七年刊)(※1)にも収録されていますが、その解説で、エッセイストの向井敏氏が次のように語っています。通産省より外務省の方が早かった、説でしょうか。
「はじめはひっそりと登場した『日本人とユダヤ人』だが、二か月とたたぬまにしきりに人の口の端にのぼりはじめ、たいして売れはしないだろうと出版部数を控えめに抑えた版元の思惑をくつがえして、つぎつぎと版を重ねだした。藤田昌司が『ロングセラー そのすべて』(初版昭和五十四年、図書新聞社)で調べたところによれば、その火付け役になったのは、外務省の地階の売店で、次いで通産省地階の売店に飛び火し、さらに丸の内界隈の書店へと広がっていったという。折から日米繊維交渉が難航し、日米互いにその言い分を譲らないという状況のなかで、日本人とユダヤ人、ひいては欧米人との思考方法の違いを説いたこの本が、まず外務通算両省の役人や貿易勝者のビジネスマンの興を誘ったということだったらしい。何だかできすぎた話だが、ありえないことではない」
※1 https://www.amazon.co.jp/dp/4163647309
山本書店は山本七平氏が個人でやっていて、しかも地味な聖書やユダヤ教に関する本を堅実に出していた小出版社でしたから、その版元が、このような文化論めいた本を出したのも、意外だったのだ、と思われます。地道に初版二五〇〇部から発売したところ、たちまち飛ぶように売れ出し、ついに山本書店版が七五万部に達した時点で、取次や書店とのやり取りに嫌気が差した山本氏は、本の版権を角川書店にゆだね、これでまた文庫版が累計二三〇万部売れた(だから、合計三〇〇万部のベストセラーと言われる)そうです。
角川文庫版が名実ともにベストセラーになっていくに伴い、同時に、それは先述したように、山本七平という隠れた知識人を表舞台に挙げる結果にもなりました。
七〇年当時の政治状況は、今の若い人には実感として、なかなか理解できないと思われますが、非常に政治的に熱い季節でした。なによりも六八年にパリから発した五月革命の余波が世界中に広がりをみせて、それは日本でも同じで、あちこちで学生のデモがくり広げられ、日米安保闘争が十年ぶりに再開しました。七〇年だけに絞ると、闘争とは直接関係なくとも、赤軍派が日航機よど号をハイジャックして北朝鮮に亡命したり、三島由紀夫が防衛庁(当時)にて白刃を抜いて自衛隊にクーデタを呼びかけ、自害するなど、穏やかならぬ事件が続きました。当時、高校生だった私には、左翼も右翼も、やたらと攻撃的だったことが記憶に残っています。
それより少し前ですが、六八年、当時の私はまだ中学生でした。その私が先年まで勤めていた九州大学に、ちょうど六八年六月に、近くの板付飛行場(現福岡空港)から飛び立った米軍のファントムF4機が墜落したことがあります。それも何の因縁か、その後、私が図書館員として一時的に籍を移したのが、「情報基盤センター」と呼ばれる昔の「大型電算機センター」だったのですが、よりによって、その電算機センターを建設中の工事現場に、ファントムは深夜、墜落・炎上したのです。もう数百メートル先に落ちていれば博多湾ですから、一体パイロットは何を考えていたのか、と皆、ため息をついたものです。
とにかく、ベトナム戦争の最中、米軍基地から飛び立った軍用機が墜落事故を起こしたわけですから、世論は沸騰しました。学生や職員は、ここを先途とデモを行います。それが当時の総長も加わって数千人のデモ隊に発展、一部学生はピケを張り、ファントムの機体引き下ろしを妨害しました。翌年一月には何者かがブルドーザーで引きずり下ろして、なんとか工事は再開され、七〇年三月には竣工しました。当時、中学生だった私は、まだ引っかかっていたファントムの機体を見た憶えがあります。七〇年四月からはミッション校に通うようになると、路面電車で通学する途中に見える建物を見るたびに、そのことを思い出していました。
九州大学電算センターに墜落したF4ファントム機結局、日米安保条約は七〇年六月に自動延長となるのですが、それまでに起きた様々な政治闘争は、いわゆる団塊の世代による全共闘の闘争として、既成の左翼政党(共産党や社会党)以外のラジカルノンセクトを自称する新左翼勢力によって担われ、同時期に隆盛をみたベトナム戦争反対運動や、成田空港(三里塚)闘争と連携して、日本全土をゆるがす政治闘争になりました。その中で、内ゲバと称される内部闘争などもあり、それが高じて、七二年の連合赤軍事件となって、学生運動は急速に衰退し、市民社会もまた冷静に返りました。
しかし、七〇年から七一年の時点では、まだまだ熱い季節として、政治は日常のタームだったのです。
文庫版には――、
「本書を校正している最中、沖縄返還のニュースをきいた。米中ソを巧みにあやつり、何とみごとな政治的勝利よ! 一滴の血も流さず失われた国土を取りかえすとは! と思っているのは私だけではない。西欧の新聞にもそういった論調がみえ、それを日本の新聞は「そねみ」に似た感情を抱いている、と評している」(九四頁)
――とあります。これも今となっては、注釈が必要でしょう。
安倍政権以前に最長を誇った佐藤栄作政権は、六九年のニクソンとの日米首脳会談で、迫りくるベトナム戦争終結にともない、その最前線基地だったオキナワの返還を確約したのです。実際に沖縄が返還されたのは七二年五月でしたが、六九年中に、返還は間違いなく約束されました。
沖縄は、もともとは琉球王国という独立国家でしたが、江戸時代に薩摩藩の征服により日本の領土となりました。太平洋戦争末期に、市民をまきこむ地上戦となった沖縄戦で、米英軍と日本軍との死闘の果てに四五年七月に入ってようやく戦闘は終結。軍部の思惑としては、ここで時間を稼いで、「本土」への連合軍の侵攻を少しでも遅らせようとの計算があったと言われていますが、それが本当だとしたら、とんだ貧乏くじを引いたことになります。残置諜者(ざんちちょうしゃ)と称する密命を帯びた中野学校出身の軍人が諸島のいくつかに潜伏していて、それまで学校の先生だったような人が急に自分は軍人だと名乗り、市民を戦争に巻きこんでのゲリラ戦に近い行動を取る。彼らによって強制的な疎開(緊急の移住)を余儀なくされた西表島ではマラリアが猖獗をきわめ、被害を拡大しました。若い女子も挺身隊と称して戦いに巻きこむ。学徒動員された「ひめゆり部隊」など、悲劇的な事件がいくつも起こりました。
日本の敗戦以後は、米軍を主とする連合軍の支配下におかれます。要するに、沖縄県だけが、日本の主権から外れて、米国の統治下におかれたのです。五二年(昭和二七年)にGHQから日本の国家主権が回復した後も、前線基地のある沖縄だけが、米国の統治は続きました。五〇年代には、朝鮮戦争やベトナム戦争があり、沖縄は米軍の最前線の補給基地となりました。通貨はドル、車道は右側通行と米国と同じになり、日本本土への渡航にはパスポートが要りました。それがベトナム戦争の終結を控えた米国の国策の転換により、返還されたのです。
それに先立ち、六八年六月、やはり米国の支配下にあった小笠原諸島も日本に返還され、主権が回復しました。これらは全て佐藤栄作政権での出来事であり、水面下では「非核三原則」を無視した米軍による核兵器持ち込みを黙認する。といった「密約」などもありましたが、いまだに返還されない北方領土と異なり、とにかく還ってきたのです。ふつう、戦争に負けたら領土は戦勝国に奪られるのが当たり前で、還ってくることは稀です。
今も沖縄は米軍基地の問題などを抱えており、私たち日本人としては、素直には喜べないのが当然の心理なのですが、世界史においては、敗戦で失われた国土が還ってくる、ということは滅多にないのだ、という常識を振り返る必要もあると思います。
ともあれ、七〇年とは、そういう時代だったのです。
その後、山本七平氏は、保守派の論客として頭角を現していき、当然のことながら、左派からは目の敵にされます。特に、左派の大新聞とは仲が悪かったように憶えています。そこの看板記者と誌上で論争をくり広げたりしていました。
そうなると、いかなもアヤシゲな、このイザヤ・ベンダサンという人物像がネックとなります。もし、本当に山本氏のペンネームだったら、すぐにそう公表しても良かったように思うのですが、山本氏は長いこと公表しませんでした。前述した「Voice」誌の記事が出たのは氏の死後の話ですから、生前は、まったくその間の事情が判らなかったわけです。
著作権の問題もあったのかも知れません。これは、財産権でもありますので、少しイヤらしい話をすると、お金の問題があります。山本書店版は一冊六四〇円でした。それが七一万部売れた。角川書店版は一冊三四〇円です。これは二三〇万部売れた。印税を単純に一〇%として合計すると一億二三六四万円になります。これ以外にも、角川書店が山本書店に払ったマージンも加算されるかも知れない。ともあれ、印税だけで一億を超えるお金です。七〇年当時の一億円は現在では、おそらく三倍以上の価値になります。これより少し前ですが、三億円事件が起きて、それに関連した記事では、現在の貨幣価値では二十億、いや五十億円の価値だ、といった諸説が飛び交いましたから、一億でも、ほとんど一人の人間の人生を狂わせかねない莫大な資産をもたらしたはずです。三人のホームネームとして三等分する、としても相当な額になります。むしろ口約束でもいいから、キチンとした決め事がなかったら、ホームネームで内一人だけが総取りというようなことになったら、友情にヒビが入りかねない。それほどの額のお金です。むろん、誰が支払われようと、源泉徴収で一〇%、さらに税金で相当な額を差し引かれますから、一億まるまる、というものではありませんが、著作権というのは、対価だけの問題ではなく、それに伴う名誉の問題でもあります。三〇〇万部のベストセラーを書いた人物、となると、それだけで世間の評価が変わってくるでしょう。
別の所で、山本七平氏は、「私は著作権を持っていないので、著作権法に基づく著者の概念においては著者ではない」とも述べており、以上を勘案して、シンプルに答えを出すとなると、三人のホームネームがベンダサンで、山本氏は実際の執筆担当だったが、その内容は三人の著作物だった。というのが一番、穏当な着地点でしょうが、その場合、誰がいくら貰うか、といった下世話な話にもなります。山本氏は、その後、三人の友情が壊れたとも言ってはいないので、平等に分けたのかも知れません。
が、しかし、私が問題とするのは、上述したように、明らさまに自分がアメリカのスパイだった、というベンダサンの告白です。それが巧みに文章内にまぎれこむ形で埋め込まれている。読み過ごす人も多いかと思いますが、これは奇妙な記述です。そんなことをわざわざ記す必要は全くないのですから。なんの変哲もない一ユダヤ人、としても良かったのに、なぜかスパイであること、それにともない、米軍機関で働いたことがあること、などなどを克明に記している。
おそらく、これは、上記のJ・J・ローラーという人物が、ベンダサンの直接的なモデルになっているからだと思われます。
この人は、米のメリーランド大学教授で、戦時中は、対日諜報関係の仕事をしていたらしい、とされています。しかし、私が米の議会図書館のOPACで「John Joseph Roller」ないし「J.J.Roller」で検索してもヒットしませんでしたので、何者かは判りません。メリーランド大学のサイトも検索しましたが、今では恐らく退官しているでしょうし、何も出てきません。アメリカ人は割りと大っぴらに諜報部員(CIAなど)のリクルートを大学でやったりしますから、あるいは本当にそうだったのかも知れませんが、半世紀前だったら何か資料もあったかも、とは思いますが、今となっては、ネットに上がっている情報以外、調べようがないため、不明です。元図書館員としてもお手上げです。
おそらくは、戦後、帝国ホテルで知り合った山本氏が、同じライトファン、ということで親しくなり、自分のことも詳しく語ってくれたローラー氏のプロファイルを借りて、本の中に散りばめたのではないか。そう思われます。いくらペンネームで書いた本だと言っても、ここまで作り込んだキャラクターは実在の人物をモデルにしているとしか思えないからです。また、全く架空の人物を捏造するにしても、それを七〇年の時点で、わざわざ米のスパイだった、というのは危険が大きすぎるでしょう。山本氏が、ローラー氏への親愛を込めて、いわばリスペクトして、このような真偽をとりまぜた人物造型をしたのではないか。だから、自分自身が(これは独力で)論壇にて著名になってからも、あえてそれを公開するのを控えた。というのが私の想像です。
本当のことは判りません。しかし、ここまで詳細に、しかもスパイだった、という事実を克明に記すのは、七〇年当時の日本の政治状況下では、かなりのリスクがともなうことでした。書いてある内容と合わせると、日本国内の左翼と右翼、双方を敵に回すようなものだからです。そのことを考えると、相当な覚悟をもって、異国の友人の横顔を本の中に誇張して素描していったのではないか、と思われます。実際に英国海軍情報部のスパイだったイアン・フレミングが書いた「ジェームズ・ボンド」シリーズは六〇年代から七〇年代にかけて、主に主役のショーン・コネリーによって映画化がヒットし、一般の記憶にも鮮やかでしたから、そういった波乱万丈なスパイの造形も取り入れた、としても不思議ではない。それが、ほとんど無名の山本氏が、三人の合同ペンネームのようにして書いた第一作において、一種のイタズラ行為として、親友に捧げる密かな尊敬の念だったのではないか。そう思うと、危険な記述内容にも、うなずけるのです。
現実的な立場から見れば、「イザヤ・ベンダサン」という人物は架空の人間だ、ということになります。今では、山本七平氏のペンネームであることが本人の証言からも明らかですし、当時から、外人が書いたにしては、あまりにも内容が日本に詳しすぎる、といった点から、その実在性を疑問視する声はありました。この翌年に刊行された遠藤周作「ぐうたら人間学」には「いざや、便出さん」の意味ではないか、との、いかにも狐狸庵先生らしい憶測も見えます。しかし、そういった興味本位の疑義ではなく、その後、保守派の論客となっていった山本氏を誹謗するための中傷めいた論考も多く見かけました。
彼らの論調は、一様に、「日本人とユダヤ人」は偽書だ。内容も学術的に間違っている。本当の著者は(現在、論壇で寵児となっている)山本七平だ。だが、こんな間違いだらけの偽書を書くような、いかがわしい人間の書く内容など一顧だにする必要もない。といったものです。本末転倒論とでも言いましょうか。実に無様な批判でした。
どだい、真っ当に論争して負けた結果が、そういう非難になったのですから、第一、見っともない。大ジャーナリズムの会社が、そんな論説を出したり、本を出して、よく恥ずかしくないものだ、と思って見ていました。
私は論争が好きですが、論争は、知的でないとつまらないのです。私に言わせれば、これらは、もの凄く頭の悪い。知性と教養と礼節に欠ける人たちによる、反論にもならぬ反論でした。しかも、会社という組織を挙げて、一個人をここまで攻撃したジャーナリズム、という事例も、おそらく初めてのことでしょう。イエローを通りこしてブラック・ジャーナリズムです。どこが社会の木鐸なんだか。
そして、個人対組織の戦いを、つねにどこでも余儀なくされてきた私にとっては、これらの組織的欺瞞に満ちた「反論」とやらに与した全員、法律がなかったらブチのめしてやりたかった。
ちなみに、私は、たとえ、この本が山本氏一個の創作であれ、三人の合作であれ、ベンダサンが架空の人物であれ、それを是として、まったく批判の対象には当たらない、という立場です。ある国の人間が、別な国の人間に扮して、その国の文明批評をするのは、「批評」という文芸における一手法であり、知的なゲームです。それは、なんら批難さるべきことではない、と信じるからです。そんなことを言い出したら、匿名批評を始め、私の尚愛する日夏耿之介の文芸批評だって、みんなダメということになってしまいます。
本当に教養がないということは恐ろしいことで、こうした地回りの言いがかりのような「批判」がまかり通るのが、七〇年代後半から今にいたる日本社会でした。しかも、自分では原典を当たらず、最近のバカなリツィートみたいに、当時は手書きでしたが、コピー&ペーストで悪口を拡散するのが、リベラル派や左派ジャーナリズムおよび、それに迎合し付和雷同する尻馬軍団のヤリ口だったのです。まったく嘆かわしい限りです。自分の頭で考えず、自分の言葉を持たない連中が、いかに多かったか。それは、今も大して変わらず、ネットを見れば、類似の引用によってのみ誹謗する言説がまだまだ消えていないことが判ります。目が汚れるので、私はできるだけ見ないようにしていますが、人は自分が信用したいことだけ信用するものだ、というのがよく判ります。そして、相手を誹謗するにも、自分の言葉を持たず、他人の言葉でしか喋れない知的文盲が腐るほどいる。
これらの中傷に対して、山本氏は、ほとんど何の言い訳もしなかったように見えました。ただ、後に「空想紀行」(講談社 八一年刊)(※2)という本を出しています。これは婉曲的ではありますが、痛烈な自分の批判者への再批判になっています。
※2 https://www.amazon.co.jp/dp/B000J7YNOI/
これが再批判だと判る程度の知恵と教養があれば、おそらく愚にもつかぬ批判もしなかったでしょうから、彼らが理解したとは到底思えませんが、大変、巧妙で洒脱な反駁でした。先に、私の母が奇しくも山本七平氏と同じ生年だと書きましたが、調べたら、山本氏が生まれたのも、母が戦時中に住んでいて、生命を拾った三軒茶屋でした。粋な人が住む街なんでしょうか。
なお、当講読では、後代の議論と、「日本人とユダヤ人」そのものを画然と分ける、というスタンスですから、これらの議論に与するつもりはありません。ただ、ベンダサンの実在性については、山本七平氏の証言の通り、それはゼロに近いでしょう。しかし、ここでは、本それ自体、その内容だけを問題にしているので、この件については捨象します。ベンダサンが誰であろうと構わない。それが今の私の立場です。
しかし、こういう、うがった読み込みが幾重にも可能なほど、この本が深く込み入った内容である、ということはお判り願えたかと思います。注意深く読んでいくと、思いもよらぬ「策み」が潜んでいることが判る。そういうミステリを読むようなスリリングな快感さえ、もたらしてくれる。だから、私は、この本を何度も何度も読み返してきたのだと思います。
みなさんも、どうか、そのように多角的な読み方が可能なこの本を愛読してくれたら。そうなったら、私も非常にうれしく思います。
PREV | NEXT
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?