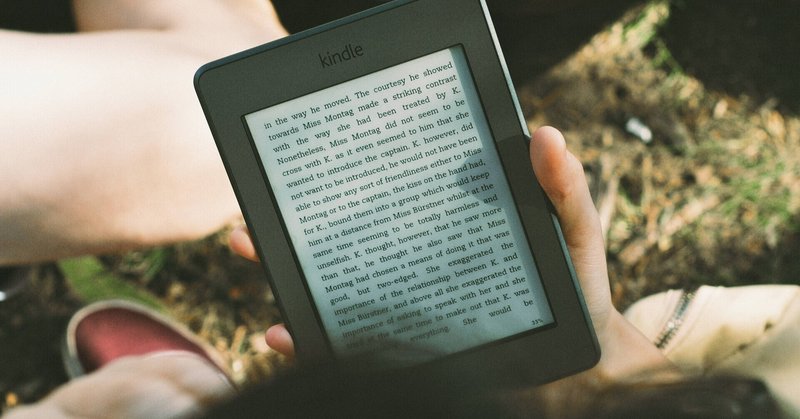
夏目漱石の「文学論」とDXの思考法
「日本経済復活への最強戦略」というサブタイトルがついた文藝春秋の本を読んでいたら、夏目漱石の「文学論」に関するきわめて興味深い話が出てきた。
世界最大級のオンラインマーケットを運営しているアリババのビジネスモデルを分析するところから始まる第4章に、「デジタル化したシステムに人間が望むことをどうやって指示するのか」という問題を解決するために、レイヤー構造が関係しているという話が出てくる。
そこに唐突に夏目漱石の『文学論』が登場するのだ。
アルファ碁がディープラーニングによって一流の棋士に勝ったのは、「囲碁というゲームを勝つという経験を成り立たせる質的な要素を因数分解し、学習」することができたからだという。
同じように、文学という営為を成り立たせる質的な要素を因数分解し、「デジタル化したシステム」に人間が「文学」だと感じる経験を成り立たせる質的な要素を因数分解し、学習させるために見出されたのが、(F+f)という定式だということになるわけである。
言いかえれば、「文学」なるものをAIに教える公式を、100年以上前の文豪が考案していたという話である。
私は、1980年代に大学院の内田道雄先生の授業で、うんうん唸りながら夏目漱石の「文学論」やドゥルーズ=ガタリの「アンチ・オイディプス」を読んでいたわけだが、それが今やDXやディープラーニングの話に接続してしまうのだからおもしろい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
