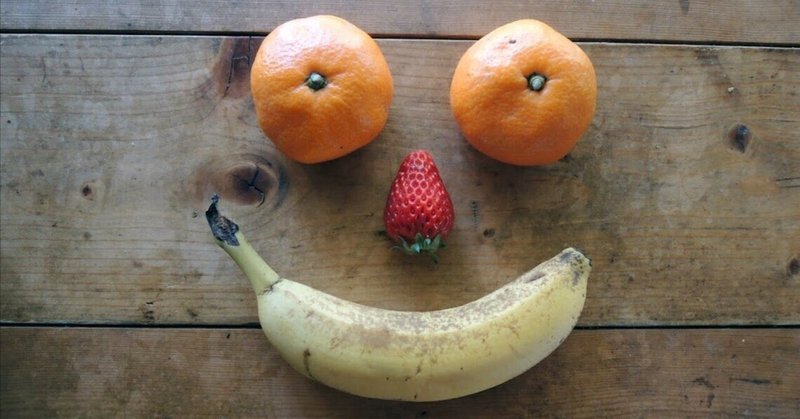
バナナはどこへ行ったかな ♪
田舎のスーパーには珍しく普通より小さいバナナを見つけたので買って来た。小さいといってもモンキーバナナほど小さくなくて1本が12~3センチ。でも味はどこかモンキーに似て濃密だった。こりゃうまいや。

タイのバンコクから夜行列車で一晩走ると、翌朝マレー半島のほぼ中央部にあるスーラターニという小さな町に着く。駅から港までソンテウ(乗り合いバス)で30分。そこからオンボロ船に揺られて小1時間。半島東側のシャム湾にはコ・サムイが浮かんでいて、僕は初めてタイへ行った34年前、その島で17日間ゴロゴロ過ごしたことがある。コはタイ語で島。だからコ・サムイの意味はサムイ島。
サムイは1980年代の後半までヒッピー崩れとパッカーの天国だったけれど、90年代のはじめに空港ができて急速に観光地化し、その後は第二のパタヤやプーケットになってしまったらしい。
パッカー達は一般観光客の来ない隣のコ・パンガンやコ・タオ、バンコック東のコ・サメットやカンボジア国境に近いコ・チャンへ流れたらしいが、今やそのどこもサムイと大して変わらないんだろうと思う。パッカーたちはどこへ行ったのか、どこへ消えたのか、おそらくパッカーたちは島から消えたのではなく、この世から消えてしまったんだろうな。
僕は本土からの船が着く港から一番遠い、島の反対側にあるビーチを選んだ。岬を一つか二つ挟んだ隣にはサムイで一番賑やかだったラマイ・ビーチがあったけれど、僕のいたコーラル・コーヴという小さなビーチはそれこそなんにもない、ただ珊瑚の砕けた白い砂と、海と森と、空と太陽しかない無音の天国だった。茅葺きのバンガローが8つだけあって、その他には経営者夫婦の自宅兼レストランがあるだけ。一泊120バーツだったバンガローを半月借りるからと80バーツに負けてもらった。
どこへ行くにしてもバスなんてないし、どうしても出かけたい時はバンガローのおっちゃんに頼んでトラックに乗せてもらうしかない。帰る日に港まで送ってもらうのはタダだけれど、それ以外は往復で100バーツかかる。
100バーツとて当時のレートで500円くらいなのだが、長い旅をしていると金を払う度に日本円で幾らという計算式が頭から薄れ、100バーツは100バーツの価値として定着してくる。あの頃は100バーツあれば朝昼晩3食のほかにタバコとコーラぐらいは十分買えた。そうすると、たいした用もないのにただ人恋しかったり、盛り場の喧騒を味わいたいがだけに100バーツ払うのがバカバカしくなる。
食い物だって飲み物だってタバコだって、僕は下戸だから関係ないけどビールも酒の類もバンガローのレストランで手に入るし、何か欲しいものがあるならオッチャンに頼めば買って来てくれる。だからよほどの用事か理由がない限りビーチを離れる必要なんて無いのである。
よく、「あーあ、南の島でのんびりしてみたいな」という溜息交じりの願い事を耳にするけれど、海と砂と空と森を眺めて昼寝をし、ゴロゴロと寝そべってノンビリする以外に何一つやることがない南の島の暮らしを、いったい彼らは何日耐えられるんだろうか? と思う。僕はそういう環境に対して相当な耐性を持っていると自負しているが、それでもさすが半月を過ぎた頃には文明生活への禁断症状が出始めた。
ごく一般的に友人知人と日頃会ってお喋りや食事をしたり、寝るまではテレビや映画を見たり、休みの日にはどこかへ出かけたりするのが普通の生活として骨身にしみ込んでいる人々にとって、何もない南の島でのノンビリな暮らしは2日か3日で音を上げるような気がする。
だからこそどんな南の島でも一般旅行者を呼び込んで観光収入を上げるためには便利な交通手段を整え、小奇麗なレストランではDVDを流し、レンタルのジェットボートやウインドサーフィンを並べて客を待つのだろう。そうやって都会生活の箱庭をそのままビーチへ置く事が即ち「南の島でノンビリする」ための舞台装置なのだと思う。
別にそんな事はどうでもいいんだがコーラル・コーヴ・リゾート、という名前だけはやけに立派なおんぼろバンガローに泊まっているのは僕のほかにフィンランド人のカップルだけ。レストランでメシを食っている僕に彼氏の方が尋ねる。
「お前、どっから来たの?」
「日本」
「日本って、どっちにあるんだ?」
「あっち」
僕は東の海を指差す。
彼女の方がクスクス笑う。
「あんたら、どっから来た?」
「フィンランド」
「フィンランドって、」
僕がそう聞き返す前に彼氏が西を指差して言う。
「あっちだ」
そうして陽が暮れて、夜になって、星が空いっぱいに瞬いて、耳障りな波の音を聴きながら暑さに寝返りを繰り返し、いつの間にか眠って一日が終わる。
バンガローの前には木で出来たオンボロの長椅子があって、僕は日がな一日そこで寝て過ごす。やらなければいけないことは何もなく、やりたいことも何もない。メシを食って、昼間は3冊しかない文庫本を繰り返し読み、またメシを食って、陽が傾いて涼しくなると入り江を端から端まで散歩する。なんだかそれは今の暮らしと似ていなくもない。
毎朝9時頃になると、小さな女の子が100円ショップで売っているような安物のカゴに果物を山積みにして売りに来る。一日に何人か天秤籠を担いだ物売りが通りがかりに声をかけていくけれど、彼女は一番最初にやって来る。初めの日、僕は彼女の置いたカゴを覗き込んでモンキーバナナを2房買った。カゴにはマンゴーやランブータンも入っていたけれど、僕は一番嵩のあるバナナの房を2つ買った。本当は1房あれば良かったけれど、2つ買えば小さな彼女の担ぐ荷物が少しは軽くなると思ってそうした。タイ語で幾らだい? と聞くと、彼女は真面目な顔で10バーツと答えた。10バーツ札を手渡すと小さな手を顔の前で合わせながら「ありがとう」と会釈をし、生涯忘れられないような笑顔を見せてくれた。
The land of smiles.
その後僕が20数年間タイへ足を運び続けるようになった理由は、あの子の美しい笑顔だったのかも知れない。翌朝もやって来た彼女に名前を聞いた。初めは黙って笑っているだけだったが、僕も両手を合わせてもう一度聞くと「トゥク」だと教えてくれた。トゥクは7歳。バナナを2房買って金を払うとまた恭しく頭を下げて手を合わせ、カゴを担ぎ上げてトコトコとビーチを歩いていく。小さな足跡が蛇行しながら砂の上に残った。
彼女がどこからやって来るのか僕は知らない。たぶんサムイに昔から住んでいる現地人なのだろうと思った。果物が山積みになったカゴを担ぎ炎天下を売り歩いて一体一日幾らになるのか。一瞬、いっそあのカゴの果物を毎日全部買ってやればと僕は思う。けれどそんな偽善は僕にとっても、もちろんトゥクにとっても良い結果を残しはしないものだ。僕はバナナを2房買って、朝メシ代わりに毎日それを食う。僕とトゥクの繋がりはそれ以上でもそれ以下でもない。そう自分に言い聞かせ、そう自分で納得しようと努力した。僕にとって何もかもが初めての経験だったあの旅は、そんな事にさえ心惑わされる新鮮さに満ち満ちていたように思う。
日本のスーパーや青果店でモンキーバナナを見かけることはあまりない。マレーシア原産のピサンマスバナナとかいうのがあって、それはモンキーよりもさらに小さいんだそうだ。毎朝トゥクから買っていたバナナは長さが7~8センチ。いちいち剥くのが面倒なくらいの一口サイズだったから、もしかするとそのピサンマスバナナだったのかも知れない。それともただ単に育ちの悪いモンキーバナナだったんだろうか。
30年前、バンコク中央駅から夜行列車と乗り合いバスで20時間近くかかったコ・サムイ。今なら飛行機の乗り継ぎで日本からその日のうちに辿り着けるらしい。日本語の観光ツアーサイトが無数に存在して、中には「サムイ移住情報」なんてサイトまであった。すげえなぁ、グアムかハワイみたいじゃん。
僕がウダウダと昼寝をし、何度も何度も同じ文庫本を読み、フィンランド人のネーチャンがトップレスで泳ぐのを眺めて過ごしたコーラル・コーヴも、YouTubeに動画が上がってた。当然のことだが、茅葺きのバンガローは見当たらなかった。あるわけないよな。多分、もう2度と行かないであろうコ・サムイ。
小さなバナナを食って思い出したこと。
タイ語でモンキーバナナは「クルアイ・カイ」
クルアイはバナナ、カイは卵。
曰く、卵のようなバナナ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
