
「わたし走り方少し変だったんだよね」と彼女がわらった。
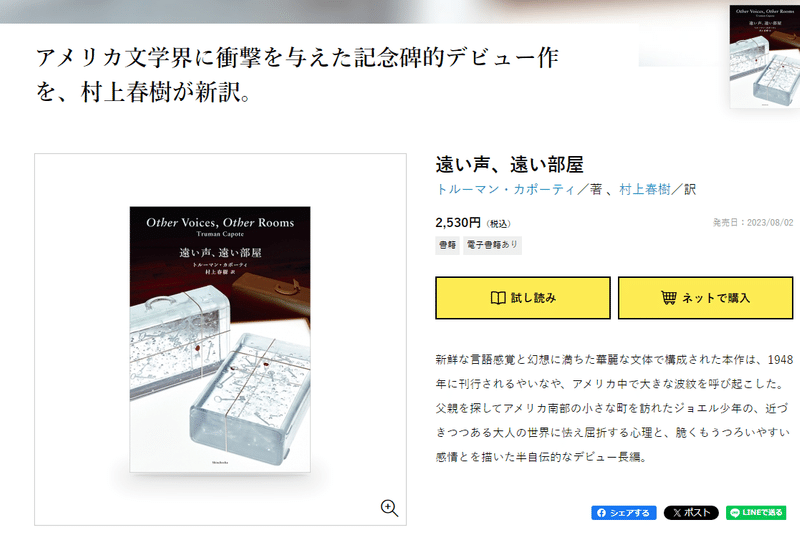
どんな言葉で謝ればいい?
隣りで眠るのは亜麻色の髪の女だった。
彼女はキャバクラで働いていた。
といっても、社交さんではなく今ではキャストの女の子たちにアドバイスをしたり、フォローをしたりする立場、いわゆる黒服の女性版だった。
もともとは本人も客につき、サーヴする側にいた。
その頃の彼女は、指名はいつもトップで(写真指も本指もずば抜けていた)、客にもスタッフにも評判のいい娘だった。
すすきのの目立つビルに、彼女がモデルになったお店の広告看板が掲げられていた。
お店のオーナーはそんな彼女を高く評価し、
君のそのスキルで今度はお店の女の子たちに教育してくれないか、とあるとき彼女に云った。
年齢も24になったし、という考えもあったかもしれない。
もちろんごく一般的に云って、24はまだ若い。
しかしそのお店のキャストはだいたい18~19歳がメインだった。
20歳を過ぎるとそろそろ引退…という空気が不文律のように漂っていたのは確かだ。
でも彼女の力量からいえば、まだまだ充分にやっていける。
だが店のこれからを考えると彼女のフォロワーを今のうちに作っておくのは得策である。
そんなわけで彼女は、軸足を店の女の子への指導に移し、自身はたまに気が向くと、あるいはお店がひどく混んだ時にだけ接客をするようになった。
客の中にはしばしば、そんな彼女を自分のとなりに座らせたがったが、今では立場が違うし、そのことを理解していただけるように彼女も酔客に説得をしていた。
意外なことに、男たちはおとなしくあきらめて他の子を、きちんとキャストの女の子をそばにおいてお酒を呑んでいた。苦笑いの表情を浮かべつつではあったが。
僕はひとり奥の厨房でそんな店内の風景をときどき垣間見ることが出来た。
厨房で働くのは僕ひとりだけだったので、とても忙しく、基本的にホールの中なんてのんびり落ち着いて眺めることはまず出来ない。たまに暇な時やオーダーに応えるとき、ホールに顔だけひょいっと出すことがあったのだ。
僕自身それで何も問題はなかった。
僕はキャバクラというものにはまったく興味がなかったからだ。
ときどき半裸の女の子がホールをうろちょろしているが、そんなものにかまけている暇なぞなかった。
ただ喰ってく為だけに、僕は夜の仕事をしていた。
僕はそのとき30歳で、若い彼女たちから見たら、いい歳こいた「おぢさん」である。
だから恋愛感情なんかハナっからない。
歳をくってるから、悩み事相談だとか、ちょっとした人生の知恵袋的な相手にはなっていたのかもしれない。
僕が過ごす厨房の中は時折、待機中の女の子たちのたまり場と化すことがあった。
僕はと云えば正直それどころではなかった。つまりゆっくり女の子たちの話を聞いてあげるという暇がなかったのだ。
そんな時、男のマネージャーが顔を覗かせて、こらこら、ちゃんと待機室で待機してなさい、と女の子たちを叱りにきた。蜘蛛の子を散らすように少女たちは退散していった。
彼女の源氏名は「ありさ」といった。
僕は彼女よりも遅れてその店で働き出したから、当然彼女は僕よりも先輩格である。
したがって僕は彼女のことを「ありささん」と敬称つきで呼んでいた。
ありささんも、僕の苗字を「さん」付けで呼ぶ。
誰に対しても分け隔てのない、感じのよい女性だった。
亜麻色の髪がいつも輝いていた。
ごはんでも食べてから帰ろうよ。
気まぐれにありささんが仕事終わりに僕に声をかけたことがあった。
僕は車で通勤していたから、ああ、いいよ。じゃあ車で一緒に帰ろう。
すすきのから出て、北へ向かって送った夜があった。
24時間営業の食堂に寄って彼女と定食を食べる。
ありささんはとめどなく仕事の話、客の話からスタッフのことなんかをほぼひとりで語り出す。
スタッフの黒服から交際を申し込まれたこと(お断りしたらしい)。
金持ちの常連客からアフターや同伴を強制されること(お断りしたらしい)。
彼女の処世術めいた、はたまた武勇伝らしきエピソードがジョークまじりに語られる。
僕はそれを興味深く聞いていた。
ただ黙って。ふむふむと。
時に笑ったり、時に感心したりして。
そんなこんなでだんだんと、彼女と僕は親しくなり、偶然にも住まいが同じ東区でとても近かったことも手伝い、公私共に一緒にご飯を食べたり居酒屋に行ったりし出した。
僕はそろそろ夜の仕事を辞めて、堅気になろうとしていた。
結局、堅気には成れなかったが、でもお店を辞めることは出来た。
そのお店で働きながら店の女の子(しかも黒服レベルの)と交際しているのが店のオーナーに知れたら半殺しの目に合ってしまうという事実もあった。
僕はまたブラブラと仕事を探しながら、いつの間にか彼女と交際をはじめることになった。
ありささんの仕事終わりめがけて僕は車で彼女を迎えに行き、どこか適当な場所でメシを喰ってから僕の部屋で一緒に寝た。
毎日毎晩ではなかったが、ほとんど一緒にいた。
彼女は実家暮らしで僕はひとり暮らしだった。
いつだったか彼女は自分のこども時代の頃のヴィデオテープを持ってきたことがある。
可愛らしい女の子である。
小学・中学・高校の頃の映像を見せられた。
陸上の選手だった彼女の、高校時代の走る姿も見た。
「わたし走り方少し変だったんだよね」と彼女がわらった。
見るとほんとうに、とても変な走り方だった。このままだと斜めに進んじゃわない?という走り方だった。
けれども良い選手であったようで、順位は常に上位である。
変な走り方だけれども、速かったのだ。
彼女が休みの日に、何をするでもなく、僕のリビングで一緒にTVドラマを観ていて、ふいに僕は彼女の身体に巻きついたことがある。
彼女の胸を揉みだし、服を脱がせていった。下着を一枚ずつ不器用に脱がして、ベッドではなく、居間でそのまま、行為をした。
そんなありささんも店の仕事を抑えるようになってきて、ますます僕と一緒にいる時間が増えてゆく。
時間が出来てくると今度は僕の部屋に来てよく料理を作るようになった。
カレーライスやオムライス、煮物など。
どれもたいへんおいしかった。
美味しすぎて食べ過ぎて、僕は夜中にこっそりトイレで嘔吐したことを覚えている。
隣りで眠っている彼女を起こさないようにして、静かにトイレに行って、カレーを吐いた。
オムライスをつくってくれた時に、彼女はケチャップで卵の上に字を書いた。それは彼女の源氏名である。
溶ろけそうな卵の上には、『あ・り・ご・ん』と書かれていた。
「ありさ」転じて「ありごん」である。
それ以来僕は彼女のことを時々「ありごん」と呼ぶようになる。
いつの頃からか、いっしょに眠る時、僕は彼女に本を読んで聞かせるようになった。
それはほんの気まぐれに始めたことだ。
いま自分が読んでいる本、かつて読んで印象に残った本など。
その頃ガツンと来た単行本で村上春樹の東京奇譚集、神の子たちはみな踊る、などがあった。神の子の中に、かえるくん、東京を救う、という一遍がある。
さりげなく何気なく、夜眠るときに彼女のとなりでその作品を読んでみた。
ひとりのサラリーマンが仕事から自分の部屋に帰ってくると、そこには大きなかえるがいて、彼の帰りを待っていたのだ。
そうしてかえるくんが不穏な話を語り出すという話。
いろいろな作品を彼女に聞かせたが、彼女はとりわけ「かえるくん」が気に入ったようだ。
「かえるくん読んで」と彼女は枕に頬をつけて云った。
ある時は半分眠ったまま。
またある時はしっかり目を開いたまま。
何度も何度も「かえるくん」をリクエストしてきたものだ。
「かえるくん読んで」「かえるくんが聞きたい」
僕も自分で朗読しながらだんだん「かえるくん」に感情移入してきた。
自分がかえるくんになったり、意味不明な世界に連れていかれて混乱しているサラリーマンの気持ちになったりした。
そんな夜が、彼女と過ごした夜の、印象的な映像として頭に残っている。
あるいは魂のどこか一部分に。
彼女はいつしかぱったり連絡をしてこなくなった。
僕が電話をしても、呼び出しは鳴るが出ることはなかった。
留守番電話に、棒読みで呼びかけてもみたが折り返し電話がかかってくることはなかった。
シンメトリックなフェイドアウトが現実味を帯びてくる。
原因は何かは判らない。
きっと何か彼女にとって不具合なことがあったのだろう。
あるいは何もなかったのかもしれない。
よくわからない。
貧乏で、将来が不透明で、フラフラしてる毎日だったけれど、笑い合えた日々があった。
それは確かなことだ。
1342407
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
