
【園館訪問ルポ】さいはての野生、すぐそこにある野生(後編)ーー釧路市動物園「コハク舎」(北海道釧路市)
「動物園が日本中、北から南に至るまでそれぞれの街で、『保全センター』ではなくあくまで『動物園』の看板を掲げ、人々に生きた動物たちの姿を公開し続けているのは何故だろう」という命題は、より一層強い実感を伴って私に問いかけてきました。
道東の希少鳥類保護の拠点施設として重要な役割を果たし、「動物園の新たな姿」を示すモデルケースとしても雑誌や書籍で紹介されていた釧路市動物園。
しかし、園内を実際に歩き地域の人から話を聞く中で、「この街の動物園」としてのアイデンティティが根強く支持されてきたことを目の当たりにしました。
園内の一角で、1枚のCDが紹介されているのが目に入りました。釧路市で活動するVtuber、鬼霧シアンさんの「コハクノウタ」です。

この楽曲は、釧路市動物園で2019年に生まれたアミメキリン「コハク」が生活する獣舎を整備する費用を集めるために作られたチャリティーソングであることが解説されています。
地域に強い愛着を持ち活動する人が「この街で飼育されている動物」のために始めたプロジェクトが展開されていたことを知り、先に見てまわった「北海道ゾーン」とは違った方向性での「動物園の未来」を考えずにはいられませんでした。

「コハク」は人工保育で育てられ、複数回の骨折など困難を抱えながらも成長してきました。
しかし、釧路市動物園には大人のキリンを3頭飼育するスペースがなかったため、クラウドファンディング等も活用しながら10年以上空舎になっていたゾウ舎をリニューアルすることになったのです。

かつてゾウ舎であったことが円形の構造や濠から読み取れる「コハク舎」。クラウドファンディングを経て2021年10月に完成したばかりです。

「コハク舎」の名のとおり、現在は単独で「コハク」が暮らしていますが、両親の姿も見ることができます。
釧路市動物園は、2009年からしばらくゾウだけではなくキリンも居ない時期が続いていました。コハクの父、「スカイ」が2013年に来園した時も、釧路市ゆかりの企業や個人の寄付による支援が大きな力となっています。
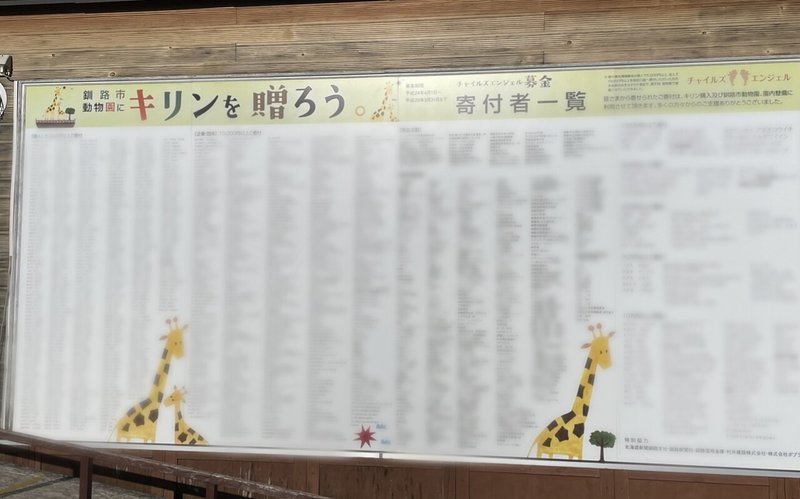
近年の日本の動物園において、昭和時代の動物園が挙ってシンボルとして飼育してきたゾウの存在は「当たり前の風景」ではなくなっています。「ゾウはいません」と入園口に掲げる動物園が話題になったこともありました。
ゾウの生態が広く知られていくにつれ、ゾウは群れで、かつ広い敷地面積で飼育するべきだという認識が広がっていき、また寿命が長いゾウを「幸せに」飼育し続けるコストも問われるようになりました。
かつての「ゾウ舎」は再整備されてある園では休憩場になり、またある園では他の動物の飼育舎になりました。

しかしその一方で、キリンは「ゾウの居ない動物園」でも幅広く飼育され、新たな子の誕生も各地で続いています。釧路市のように市民が声を上げて導入するケースもあります。
動物園がある街の人々がイメージする、「動物園で『こそ』会える動物」というシンボル性を近年の日本においてゾウに代わって担っているのがキリンという種なのかも知れません。

釧路市動物園では、「個」への着目も大きな特色として印象に残りました。「コハク」同様に個体名が付いた専用の獣舎で暮らすアムールトラの「ココア」は、先天的な障害を抱えながらも力強く育つ姿が全国の人々の支持を受け、長く園を代表する飼育動物として人気を集めています。

動物園で生活する動物を「個」としてまなざすのか、「種」としてまなざすのかについては、しばしば議論が巻き起こることがあります。
「ココア」と早世した双子の「タイガ」、そして「コハク」が支援を受けたように、具体的な固有名を与えられた動物はシンボルとして多くの人々から注目されるようになります。

(それが善いことか悪いことかという価値判断は一度置くとして、)野性動物の保全・調査活動の拠点としての動物園像には曖昧な感想しか持てなくても、自分が愛着を持てる動物になら喜んで支援をしたい、という人もいるでしょう。
人々の「愛着」は支援や寄付という形で園を動かし、園が在ることの意義を裏付けます。
現代の動物園が「個」と「種」の扱いについてある意味では矛盾した姿勢を取らざるをえない背景にある構造を垣間見た気がしました。

飼育動物を「種」としてではなく「個」として見据える強いまなざしは、旅行先としてこの園を選ぶ人だけではなく、地域の人々にも力強く訴えかけます。

友人のお母さんに空港まで送って貰いながら、友人と連れ立って親子で「ココア」と「タイガ」に会いに行ったことがあるというお話を聴きました。ここでも想い出の中心にいたのは、具体的な名前を持った動物でした。
動物園の姿は否応なしに変わっていくし、野生動物たちに対して果たすべき役割もかつての姿とは違うものになっている。それはやむのえないことでもあるし、そうあるべきだという想いを強固に持っていた私にとって、地域の中で自明なものとして受容されてきた動物園や飼育動物へのまなざしと、今目の前で立ち起こっている「動物園像の新たな姿」への変化はどのように整合性を持って受け止められているのだろうと再考させたことは、大きな発見でした。
「『動物園』って、こういうもの」という従来から続く像は変革を構想する文脈では否定的に捉えられることもありますが、地域の人々と動物園とを結びつける結節点としての役割は決して無視できません。

ゾウやホッキョクグマ、ゴリラなど、従来の動物園を象徴してきた種の全国各地での飼育展示が次第に困難になっていることは、「動物園は変わらなくてはならない」という議論を推し進める牽引車となっています。
しかし、飼育が継続されている海外産動物が地域の人々にとって「ここではない遠く」へ目を向けるうえでの水先案内役を務めている状況を目の当たりにしたいま、「動物園の新たな姿」もこれまでのあり方を全否定することは決してなく、ハイブリッドな形で進行していくのだろうと認識を新たにしています。
訪問のきっかけになるような「取っ掛かり」があること、そして「動物園って、こういうもの」という先入観を持っている人にも「変化への気付き」をもたらすことができるような仕掛けが「未来の動物園」にも満ち満ちているといいな、と考えながら、私は羽田へと向かう飛行機の中で目を閉じました。
