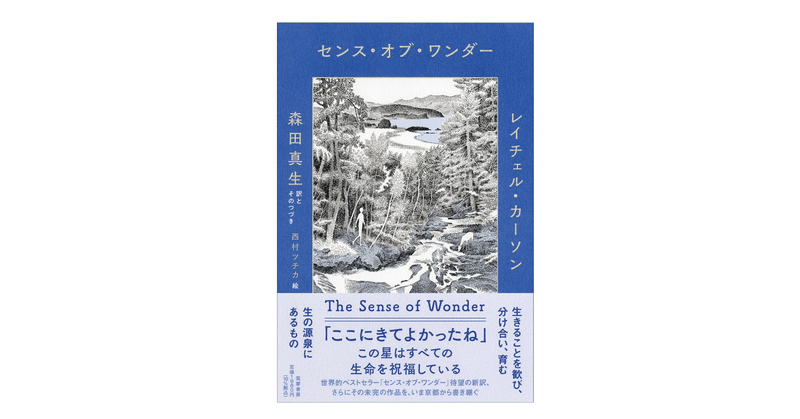
レイチェル・カーソン/森田真生『センス・オブ・ワンダー 訳とそのつづき』
☆mediopos3423 2024.4.1
数学の独立研究者・森田真生が
レイチェル・カーソンの遺著となった
未完の作品『センス・オブ・ワンダー』を訳し
さらにその物語に「参加」し
「センス・オブ・ワンダー」の続きを紡いでいる
「センス・オブ・ワンダー」とは
「自然がもたらしたワンダーに開かれた感受性」
森田真生は「都市に育ち、子どもが生まれるまで
ろくに虫をつかまえたこともなった」が
「子どもたちが生まれ、成長していくとともに、
庭で虫をつかまえ、カエルを追い、鳥の鳴く声を聞き、
大きな月を見上げてともに驚きの声をあげる日々が、
新たな日常になっていった」という
レイチェル・カーソンは
「この感受性を子どもが失わないためには、
「生きる喜びと興奮、不思議を一緒に再発見していってくれる、
少なくとも一人の大人の助けが必要」だと書いているが
森田真生は「この逆もまた真だ」という
「すでに大人になってしまった人間が、
忘れかけているセンス・オブ・ワンダーを
思い出すことができるとするなら、そのためには
「生きる喜びと興奮、不思議を一緒に再発見していってくれる、
少なくとも一人の子どもの助けが必要」になるというのだ
森田真生はそうしてじぶんの「子どもの助け」で
ともに「センス・オブ・ワンダー」を生きはじめている
幸いにしてぼくのばあいは
都市に生まれ育ってはいないこともあり
むしろ都会的な環境にはいられず
子どものころから今になるまで
なにがしか「センス・オブ・ワンダー」とともにあったようだ
いまも季節のめぐりとともに
「一緒に再発見していってくれる」ひととともに
虫や鳥や花やそれらを育んでいる環境のなかに
出かけていく機会をなによりも楽しんでいる
しかしそんななかにいるとむしろ
じぶんがいかに開かれていないか
そのことを実感させられることばかりだったりもする
レイチェル・カーソンは
「これまで見逃していた美に目を開く方法の一つ」は
「いま、これを見るのが、人生で初めてだとしたら?」
「もし、これを二度と見ることができないとしたら?」
と自分に問いかけてみることだという
この問いは自然に対してだけではなく
身近な日常のすべてにおいて必要なことだろう
生というかけがえのない
「センス・オブ・ワンダー」に目覚めていること
それはぼくがこのところ大切に感じている
「いつもはじめて」
ということばと通じているようだ
同じということは決してないのだから
(記憶力に乏しいということも多分には影響しているが)
「見慣れたものを見慣れたものとしてやり過ごすのではなく、
同じ虫を、同じ植物を、身近にある同じ土地の同じ場所も、
何度も自分の身体で感じ、経験し直してみる必要がある」
という森田真生のことばのように
何ごとに対しても「そういうものだ」ということで
常なる「一回性」をなくしてしまうと
「センス・オブ・ワンダー」を忘れてしまうことになる
森田真生は「根底から壊れていくこの世界で、
それでも生き延びていくためには、僕たちはなにを考え、
なにをなしていく必要があるだろうか」と問いかけ
こう答えている
「限りある生を生きる「歓び」を発見し、
分かち合い、育んでいくこと。
これから生まれてくるすべての子どもたちが、
「きてよかったね」と心から思える、
そういう世界を作り出していくこと」だと
まさに「根底から壊れていくこの世界」だからこそ
ひとりひとりがじぶんの
「センス・オブ・ワンダー」をいかに生きられるか
それがこれからの世界をつくっていく鍵となる
■レイチェル・カーソン・森田真生(イラスト:西村ツチカ)
『センス・オブ・ワンダー 訳とそのつづき』(筑摩書房 2024/3)
**(レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』より)
*「子どもの世界は瑞々しく、いつも新鮮で、美しく、驚きと興奮に満ちています。あのまっすぐな眼差しと、美しくて畏怖すべきものをとらえる真の直観が、大人になるまでにかすみ、ときに失われてしまうことさえあるのは、残念なことです。子どもたちの生を祝福する心優しい妖精に、なにか願いごとができるとするなら、私は世界中のすべての子どもたちに、一生消えないほどたしかな「センス・オブ・ワンダー(驚きと不思議に開かれた感受性)」を授けてほしいと思います。それは、やがて人生に退屈し、幻滅していくこと、人工物ばかりに不毛に執着していくこと、あるいは、自分の力が本当に湧き出してくる場所から、人を遠ざけてしまうすべての物事に対して、強力な解毒剤となるはずです。
妖精の力を借りずに、生まれ持ったセンス・オブ・ワンダーを保ち続けようとするなら、この感受性をともに分かち合い、生きる喜びと興奮、不思議を一緒に再発見していってくれる、少なくとも一人の大人の助けが必要です。」
*「子どもと一緒に自然を探索することは身の回りにあるすべてをもっと感じ始めることです。自分の目と耳、鼻と指先の使いかたを学び直しながら、使わなくなっていた感覚の経路を、ふたたび開いていくのです。
私たちはたいてい、この世界の知識の大部分を、視覚を通して得ています。とはいえ、いつもちゃんと目を見開いているわけではないので、実際には半ば盲目なのです。これまで見逃していた美に目を開く方法の一つは、自分にこう問いかけてみることです。
「いま、これを見るのが、人生で初めてだとしたら?」
「もし、これを二度と見ることができないとしたら?」」
*「自然を畏れ、不思議に思う感受性や、人間の存在を超えたものを認識する心を持ち、強くしていくことには、いったいどんな価値があるのでしょうか。自然界の探求は、黄金の子ども時代を、楽しく過ごすための方法にすぎないのでしょうか。それとも、そこにはもっと深いなにかがあるのでしょうか。
もっとずっと深いなにか、とても重要で、永続するなにかがあると、私は確信しています。科学者であろうがなかろうが、この地球の美と不思議のなかに住まう者は、決して一人きりになることはないし、人生にくたびれることもないのです。日々のなかにどんな悩みや心配があろうと、その思考は、内なる充足と、生きることの新鮮な感動に至る道を、やがて見つけることができるはずです。
地球の美しさをよく観察し、深く思いをめぐらせていくとき、いつまでも尽きることがない力が、湧き出してきます。鳥の渡りや潮の満ち引き、春を待つ蕾の姿には、それ自体の美しさだけでなく、象徴的な美しさがあります。夜はやがて開け、冬のあとにはまた春が来る————くり返す自然の反復には、人を果てしなく癒やす力があります。」
**(森田真生『僕たちの「センス・オブ・ワンダー」』より)
*「レイチェル・カーソンといえば僕にとってはなにより『沈黙の春』の著者であり、時代に先駆けて農薬などの化学物質が地球環境に及ぼす影響に警鐘を鳴らした科学者である。生物をそれぞれ単独で切り離して考えるのではなく、複雑に絡み合う生物同士の関係に着目する視点は、それまで見落とされていた化学物質の危険性を浮かび上がらせるとともに、地球規模で環境問題をとらえる見方を開いた。」
*「『The Sense of Wonder』は、カーソンが一九五六年に雑誌に寄稿したエッセイ「Help Your Child to Wonder」をもとに、カーソンの死後、友人たちの手によって出版された。カーソンは一九五六年のエッセイをさらにふくらませて、やがて一冊にまとめたいと願っていたが、生前にこれがかなうことはなかった。
雑誌に寄稿したエッセイと、その後に出版された本のタイトルに共通する「ワンダー(wonder)」という言葉に、カーソンの魂が込められている。」
「自力や自分の思考の枠を超えた自然の大きな働きを前にすると人の心は、おのずと「ワンダー」し始める。どこに向かうのでもなく感じ、なにを目指すのでもなく動く。合理的な選択や決定ばかりを迫られる社会の外で、山や川、虫や鳥とともにいるとき、人の心はその場に静かにとどまりながら、決められた目的も尺度もないまま、周りと響き合い、揺動している。
自然がもたらしたワンダーに開かれた感受性————これをカーソンは「センス・オブ・ワンダー」と呼んだ。そして、この感受性を子どもが失わないためには、「生きる喜びと興奮、不思議を一緒に再発見していってくれる、少なくとも一人の大人の助けが必要」だと綴った。この本のなかで最も印象的な言葉の一つだが、同時に僕は、この逆もまた真だと感じている。
つまり、すでに大人になってしまった人間が、忘れかけているセンス・オブ・ワンダーを思い出すことができるとするなら、そのためには「生きる喜びと興奮、不思議を一緒に再発見していってくれる、少なくとも一人の子どもの助けが必要」になる、
七年前に長男が生まれるまで、僕は庭の植物や虫の姿に、特別な関心を寄せてこなかった。だが子どもたちが生まれ、成長していくとともに、庭で虫をつかまえ、カエルを追い、鳥の鳴く声を聞き、大きな月を見上げてともに驚きの声をあげる日々が、新たな日常になっていった。」
*「この自然界においては「単独で存在しているものなどなにひとつない(nothing exists alone)」とカーソンは『沈黙の春』のなかで記している。カーソンとロジャーの「センス・オブ・ワンダー」もまた、時空を超えた無数の大人と子どもたちの物語に開かれている。カーソンのテキストをただ座して読むだけでなく、その続きをそれぞれに紡いでいくこと。これこそが、この物語を「読む」ことであり、この物語に「参加」することなのだと思う。」
**(森田真生『僕たちの「センス・オブ・ワンダー」』〜「1」より)
*「自然は単なる個物の集まりではなく、さまざまな関係の織りなす網だ。
複雑な土の表面を巧みに歩き、どんな茎や葉の上でも見事にバランスをとる虫の身体性は、虫かごrの単調な空間のなかでは十分に発揮されることがない。風の凪がれ、木の葉の揺らぎ、樹皮の起伏など、複雑で多様な環境との関係のなかにこそ、虫の知性は表現されていく。虫だけでなく、どんな生き物でもそうだ。個体としてそれだけ環境から切り離してしまえば、本来の個性を発揮することはできない。
子どもという自然もまた、この点においては同じだろう。虫や鳥、花や木々など、多くの他者とかかわり、感じあっていてこそ、子どもの心もまた、溌剌と、いきいきと動くことができる。
僕たちはだれもがみな、同じ自然の一部であるが、同時に、たがいに独立した個でもある。同じ海、同じ宇宙から生まれて、異なる個として出会い、個として生きていく。この繊細な矛盾が、生きることの難しさと面白さをつくりだしている。」
**(森田真生『僕たちの「センス・オブ・ワンダー」』〜「2」より)
*「環境の変化に抗うのではなく、変化に合わせて生まれ変わっていくこと。その喜びを、虫や、植物や、子どもたちが、いつも僕に教えてくれているのだ。」
**(森田真生『僕たちの「センス・オブ・ワンダー」』〜「4」より)
*「僕は子どもたちが眠る前に、必ずすることがある。彼らの目を見て、背中に手をあてながら、今日もありがとう」と、感謝の気持ちを伝えるのだ。それは植物に水をやり、庭の手入れをすることにも似ている。
そこにいてくれてありがとう。生まれ、育ち続けてくれてありがとう。これからも元気に、健やかに。育ちますように。
天地の恵みと、自然からの祝福に感謝しながら、庭に水をやり、落ち葉を拾い、まだ小さな子どもたちの背中に手をあて、「ありがとう」の気持ちを伝えるのだ。」
**(森田真生『僕たちの「センス・オブ・ワンダー」』〜「5」より)
*「どんなに美しい風景も、刻々と移り変わっていく。だから、同じ景色を、同じ人と分かち合える瞬間は二度とない。
そのことを思うと、僕は悲しくなる。
カナシ(悲し、哀し、愛し)とは、「・・・・・・することができない」という意味を添える接尾語「カヌ」と同根であるという。「愛着するものを、死や別れなどで喪失するときのなすすべのない気持ち。別れる相手に対して、何の有効な働きかけもしえないときの無力の自覚に発する感情。また、子どもや恋人を喪失するかもしれないという恐れを底流として、これ以上の愛情表現は不能だという自分の無力を感じて、いっそうその対象をせつなく。大切にいとおしむ気持ち」と『古典基礎語辞典』の「かなし」の項には書かれている。」
*「「化け物の進化」と題したエッセイのなかで寺田寅彦は、「全くこのごろは化け物どもがあまりにいなくなり過ぎた感がある」と嘆く。日常生活の彼方には、「常識では計り知り難い世界」が広がっている。人間の理解を超えた自然界の不可解な現象を、昔の人は「化け物の所業として説明した」のである。
だから、「化け物がないと思うのはかえってほんとうの迷信である。宇宙は永久に怪異に満ちている。(・・・・・・)その怪異に戦慄する心持ちがなくなれば、もう科学は死んでしまうのである」。
夢中になってドングリを拾い、化け物を恐れて泣きそうになる。生命の開かれた秘密に驚き、宇宙の怪異に戦慄しながら、子どもたちは、うつくしく、かなしく、おそろしい視線を、全身でいつも探索している。」
**(森田真生『僕たちの「センス・オブ・ワンダー」』〜「7」より)
*「花は、そこを訪問する者たちに呼びかけ、受け入れ、他者を映し出す鏡となっていく。そこには、鳥や虫だけでなく、美を求め、花の咲く姿を愛で、育ててきた人間の心もまた、映り込んでいる。
かつてチリの生物学者フランシスコ・ヴァレラは、ある屋外で開かれた座談会の場で、植物学者で人類学者のフランシス・ハクスリーの言葉を引きながら、花と虫の共生関係について、次のように印象的な発言をしている。
私にとって進化とは、動物の認識や適応力が向上していくこととは無関係です。進化とは、ハチが花を、そして花がハチを、たがいに創り合うことです。どちらか一方を取り去ってしまえば、他方も一緒に消えてしまう。ハチと花とは、そういう関係にあるのです。
ここで筆者が「創り合う」と訳した箇所でヴァレラは「dream up」という言葉を使っている。「dream up」とは、「思いつく」「ひねりだす」「想起する」といった意味を持つ言葉だが、ここでは、ハチと花が相互を思い、まるで夢見合うようにしながら、たがいの存在を生み出しあっていく関係が、「dream(夢)」という言葉とともに詩的に表現されている。」
**(森田真生『僕たちの「センス・オブ・ワンダー」』〜「11」より)
*「『虫は人の鏡』のなかで著者の養老孟司は、「擬態は一見よく似たものの実態がまったく異なる状況を指す」と書いている。「よく似る」ことが擬態だと僕は思っていたが、考えてみればむしろ「実態がまったく異なる」ことにこそ、擬態の不思議さや面白さがあるといえるのかもしれない。
(・・・)
人工知能はまさに知能の擬態である。近年話題の生成AIなどは、すでにある種の言語能力でも人間を凌駕しつつあるように見えるが、それが生み出す言葉がどれほど僕たちの知っている言葉と「よく似た」ものであったとしても、身体を持たない機械が膨大なデータを統計処理しながら吐き出す記号列は、人間が迷い、逡巡しながらつぶやく言葉と「実態」はまったく異なっている。
自分の経験で確かめたわけではない二次的な情報は、どれほど真実に似ていようとも、しばしば実態とかけ離れている。そのことに蓋をして、膨大な情報を摂取しているだけでは、擬態と実態の区別がつかなくなってしまう。
(・・・)
だからこそ、何度でもくり返し、自分の身体でたしかめる必要がある。見慣れたものを見慣れたものとしてやり過ごすのではなく、同じ虫を、同じ植物を、身近にある同じ土地の同じ場所も、何度も自分の身体で感じ、経験し直してみる必要がある。」
**(森田真生『結 僕たちの「センス・オブ・ワンダー」』より)
*「根底から壊れていくこの世界で、それでも生き延びていくためには、僕たちはなにを考え、なにをなしていく必要があるだろうか。「必要」はますます切迫している。しかしだからこそ、僕たちは必要の奥で、必要に意味を吹きこむ、歓びの源泉を見つけ出していかなければならない。
必要よりも、本原的なもの————限りある生を生きる「歓び」を発見し、分かち合い、育んでいくこと。これから生まれてくるすべての子どもたちが、「きてよかったね」と心から思える、そういう世界を作り出していくこと。僕たちが何度でも新たに、それぞれの「センス・オブ・ワンダー」を生き、書き継いでいこうとしているのもまた、このためなのである。」
○レイチェル・カーソン:
1907-64。アメリカの生物学者。研究の傍ら、大ベストセラー作家に。1962年公害問題を『沈黙の春』で厳しく告発、環境問題の嚆矢となる。『センス・オブ・ワンダー』は1956年に雑誌発表、未完のままに死後単行本化された。ほか著書に『潮風の下で』『われらをめぐる海』『海辺』などがある。
○森田 真生(もりた・まさお):
1985生。独立研究者。京都を拠点に研究・執筆の傍ら、ライブ活動を行っている。著書に『数学する身体』で小林秀雄賞受賞、『計算する生命』で第10回 河合隼雄学芸賞 受賞、ほかに『偶然の散歩』『僕たちはどう生きるのか』『数学の贈り物』『アリになった数学者』『数学する人生』などがある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
