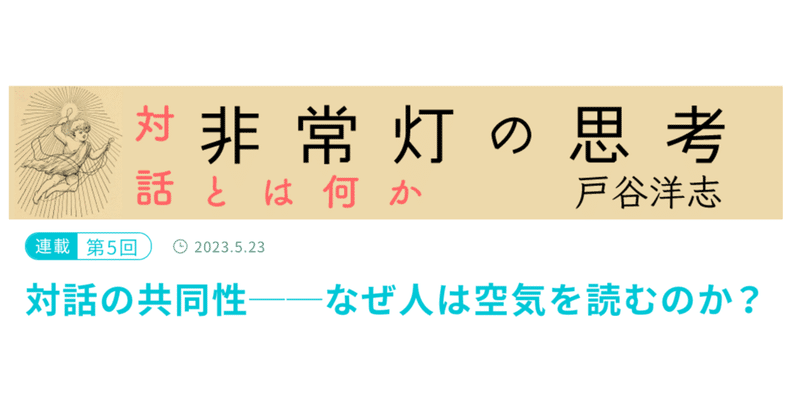
戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か」 連載第5回「対話の共同性──なぜ人は空気を読むのか?」
☆mediopos-3123 2023.6.6
他者と対話するときには
対話に先行した共同性が必要となる
その「共同性」とは
対話に必要なところでは
「みんな」の一員であることだ
その「みんな」は
わたしでなくてもいい誰かであり
「わたし」も「他者」も
特定のだれかである必要はない
ある意味「みんな」として
共有されている言葉と思考表現で
アルゴリズム化されているChatGPTどうしが
対話しているようなものともいえる
つまり「他者」は実質的にそこにはいない
けれども通常わたしたちが日常において
交わしているコミュニケーションを
言葉だけとりあげるとすればその多くは
そうした「対話」以外のものではないことが多いだろう
ハイデガーは「このように道具の使用において
「私」が関係する「みんな」を
「特定の誰かではなく、誰でもない誰か」という意味で
「世人 das Man」と呼んでいる
とはいえこうした「世人」こそが
日常的なコミュニケーションを可能にしている
それは「「みんな」が言うことを、
「みんな」と同じように言うこと」であり
それは「「空気を読む」という行為によく似ている」のである
私たちは「常に、この場において何が逸脱と見なされるのか、
どんな言動が空気を読まないと評価されるのかを
意識しながら、語り合」っている
けれどもそうした「逸脱」は
たとえば芸術的な表現の場において
もちろんそこにはそれぞれの条件があるだろうが
許容されたり積極的に評価されたりもする
しかしそうでない場合の「対話」は
まさにChatGPT化されてしまった「みんな」のそれであり
そこは人間不在のものになってしまいかねない
「誰かと対話するためには、
その誰かと共同性を交わさなければならない。
しかしその共同性は「私」を「みんな」の一員にし、
非本来的にする。
この矛盾を乗り越えるにはどうしたらよいのだろうか」
というのが今回の論考の最後の問いかけになっているのだが
おそらくその際には
「対話」に付随した「人間であること」
つまり声・仕草などの身体性や
感覚・感情といった側面における
過剰な「逸脱」を避けた範囲内での要素が鍵ともなるだろうし
対話そのものの内容・表現でいえば
ChatGPT化され得ない
これも「人間であること」ゆえの創造性
あるいはポエジーなども鍵となってくるのではないか
それらは単に「空気を読む」だけの「みんな」として
「共同」化され得ないものだろうから
しかしそれらがなんらかの形で発揮されないとき
人間はすでに人間であること
つまり「自由」を失いはじめるのだといえる
■戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か」
連載第5回「対話の共同性──なぜ人は空気を読むのか?」(2023.5.23)
「対話が始まるとき、そこには、対話に先行した共同性がある。他者と対話するとき、さしあたり──これが「さしあたり」であることは強調しておきたい──、「私」はその他者とバラバラの個人として関わるのではなく、「私たち」として関わっている。
では、その「私たち」はどのようにして成立するのだろうか。
たとえば、様々な社会的な属性は、そうした共同性の根拠として機能するだろう。国籍がその典型だ。しかし、日常的な対話の場面に焦点を定めるなら、それはあまりにも抽象的な共同性でもある。私たちは、同じ国籍を共有するからといって、いきなり街ですれ違った人と対話できるわけではない。そこには、もっとささやかで不確かな、その場限りの頼りない共同性が生じているはずだ。
では、その頼りない共同性とはいったい何なのか。今回も、ハイデガーとともに考えてみたい。
ハイデガーがこだわったのは、人間存在を日常的な生活のなかで捉えること、それによってそのありのままの姿を分析することだった。伝統的な哲学において自明とされてきた専門用語をすべて排除し、日々の何気ない姿から自ずと明らかになってくる人間のあり方を解明すること──それが、彼の考える現象学のアプローチだ。
その際にハイデガーは、「私」が「存在する bin」を意味するドイツ語が、語源的に、「~の傍らにいる bei」という言葉と通底することに注目する。つまり存在するということは、何かの傍らにいるということなのだ。では、私たちには日常において何の傍らにいるのだろうか。それは、道具・・に他ならない。」
「道具を考えるときに重要なのは、それを使うことができるのが、「私」だけではないということである。たとえば「私」はストローによってコーヒーを飲むことができるが、「私」以外の人も、同じようにストローを使うことができる。というよりも、むしろ、「みんな」がストローを使えるからこそ、「私」もまたストローを使えるのだ。
このようにして、ストローという道具は、「私」を「みんな」と関係させる。もっとも、ここでいう「みんな」は特定の誰かではない。それは誰でもない誰か、顔も名前もない誰かである。
(・・・)
この意味において、道具を介した「私」と他者の関係は、「私」が実際に他者と出会うことを必要としない。別の角度から言い換えるなら、実際に他者と会っていなくても、「私」は関わりを断っているということにはならない、ということになる。道具を使う限り、そこに他者が現前していようといまいと、「私」は不可避に他者と関わっているからである。
ハイデガーは、このように道具の使用において「私」が関係する「みんな」を、「世人 das Man」と呼んだ。世人には実体がない。なぜなら、特定の誰かではなく、誰でもない誰かだからである。「私」は世人と対面したり、コミュニケーションしたりすることはない。なぜなら世人は、「私」もまたその一員であるところのものとして、「私」が経験するものであるからである。
しかし、だからといって世人がコミュニケーションと関係がない、ということではない。むしろ世人こそが日常的なコミュニケーションを可能にしている。」
「こうした会話が成立するのは、その会話をしている当事者が、道具の使い方を互いに分かっているから、つまりその道具を使うことができる「みんな」の一員であるからだ。ともに「みんな」に属することが、「私」と他者の会話を可能にするのである。
こうしたハイデガーのコミュニケーションのモデルは、一般的に考えられているものとは異なっている。普通、私たちは、まず「私」と他者が別々に存在していて、その二人が出会い、自分の思っていることを話すことで、コミュニケーションが始まると考える。そして、そのように話がスタートすることによって、はじめて、それまで別の存在だった「私」と他者が、「私たち」になる。つまり、コミュニケーションが人間を「私たち」にし、そこに共同性が成立する、と考える。
ところが、ハイデガーの発想に従うなら、この構造は逆になる。「私」と他者がコミュニケーションできるのは、双方がすでに「みんな」の一員だから、つまりもう「私たち」になっているからだ。もし、双方の間にそうした共同性が存在しないなら、何を話そうとも意思疎通ができない。それはコミュニケーションと呼べるものではなくなってしまう。
ただし、こうしたコミュニケーションのモデルからは、豊かな対話の可能性を導き出すことができない。それはなぜだろうか。
それは、「みんな」が世人として道具に関わる、という点にコミュニケーションの基点が置かれている限り、そのコミュニケーションもやはり道具的なものとなり、「みんな」と同じようにコミュニケーションしなければならなくなるからだ。
(・・・)
道具との関係が希薄に思えるコミュニケーションも、同じ構造をしている。」
「「みんな」が言うことを、「みんな」と同じように言うこと──それは、「空気を読む」という行為によく似ている。」
「逸脱を犯す人は「空気が読めない人」と呼ばれる。そうである以上、世人として、「私たち」の一員としてコミュニケーションすることは、空気を読むことと同義なのである。空気とは、その場を支配する指示関係に他ならない。
ただし、注意するべきことがある。たとえ「私たち」の一員としてコミュニケーションすることが空気を読むことだとしても、具体的に何を語るかまで決まっているわけではない。これが、ハイデガーの哲学の面白いところである。
ハイデガーは、世人はある種の規範として機能すると考えたが、しかしその規範は、私たちが直接意識できるような対象として現れてくるわけではない。つまり、「みんな」が言うこと、「みんな」と同じように言うことが求められているにもかかわらず、何を言うべきかがあらかじめ決まっているわけではない。むしろ、その規範から逸脱する者、空気を読めない者が顕在化され、それが排除されることによって、逸脱ではない範囲が規範として緩やかに輪郭づけられるのである。つまり、どこからが逸脱で、どこからが逸脱ではないかは、あらかじめ規範によって画定されているのではなく、誰かが逸脱することで初めて意識されるのである。」
「ハイデガーは世人の規範性がもつこうした性質を、「懸隔性」と呼んだ。「みんな」の一員としてコミュニケーションすることは、こうした懸隔性に支配された会話を営むことである。常に、この場において何が逸脱と見なされるのか、どんな言動が空気を読まないと評価されるのかを意識しながら、語り合うことである。
懸隔性は、多くの場合、暴力的な排除として立ち現れる。たとえば教室におけるいじめがその典型だ。ある日、誰かが恣意的に、「空気を読めないやつ」というレッテルを貼られ、いじめが始まる。すると、いじめられている生徒はその教室の逸脱者となり、そこから反照されるようにして、教室のなかの規範的な振る舞いが画定される。いじめられている生徒と同じ振る舞いをしないことが、空気として醸成されていく。しかし、その空気に従って行動することは、いじめに加担し、そのいじめを強化し、再生産するように機能する。
とはいえ、懸隔性が常に暴力として作動するとは限らない。逸脱者は、必ずしも蔑まれ、馬鹿にされる対象とは限らないからだ。
たとえば、音楽アーティストがそうである(・・・)日常において、私たちが決して口にしないような言葉を、アーティストは平気で語る。その言葉が観客を一つにするのだ。
このとき、アーティストは明らかに逸脱者である。空気を読まず、私たちが日常において行うのとは異なる言動を、あえて行っている。しかし、だからこそ私たちは、その会場において一つの「私たち」という実感を得るのではないだろうか。アーティストが「私たち」を破る存在だからこそ、その言葉に接することで、観客は「私たち」になるのではないか。
ライブにおいて立ちあらわれる、観客同士の異様なまでの親密感は、明らかにアーティストのコミュニケーションによって作り出されるものである。しかし、アーティストは空気を読んではいない。むしろ空気を破っている。「みんな」としてではなく、一人の個人として、自分以外の誰でもない自分として、語る。その言葉が、そこにいる人々の間に共同性を創出するのだ。
もっとも、それを可能にするためには、アーティストは観客の心を深く理解していなければならない。つまり、観客に共感しながらも、観客がなしえないことをし、観客が従う規範を破らなければならないのだ。ここに、ただ空気を読めない人と、あえて空気を破るアーティストとの根本的な違いがある。つまりアーティストは、人々を「私たち」にするために、「私たち」を逸脱する言動をするが、それが可能なのは「私たち」を深く理解しているからなのだ。
このことは、「型破り」という概念を考えると分かりやすい。型を理解せずに行われる行為は、たとえ結果的に型から逸脱したものであったとしても、「型なし」と評価されるに留まる。それに対して、「型破り」という積極的な評価を得るためには、型を身に着けていなければならないのである。」
「いずれにせよ、対話に先行した共同性があるとしたら、それを形作っているのは、その共同性を破る存在、「私たち」ではない逸脱者である。たとえ、そこに目に見える形で逸脱者が存在しないとしても、「私たち」は常に、「私たちではないもの」に支えられている。もしもそうした逸脱者が存在しなければ、「私」と相手の間に共同性は成立しないし、そこで何を語るべきか、語るべきではないかを、了解することもできない──少なくとも、それがハイデガーの哲学から読み取れる、対話のあり方だ。
このような対話のモデルはどこか消極的に見えるかも知れない。実際ハイデガー自身も、世人に従ったコミュニケーションを「おしゃべり」と呼び、人間の頽落した姿の一側面として説明した。そのようにして形成される対話は、常に表面的なものに留まり、人間同士の本来的な関係性を構築することには資さない。なぜなら、対話する相手が誰であるか、自分が何者として語るのかは、本質的にどうでもよいからだ。「みんな」が言うことを、「みんな」と同じように語ることが要求されるとき、語る人間が誰であるかは問題ではなくなるのである。
だからこそ、ハイデガーは人間が本来性を回復するために、他者との関係から自らを切断することが必要だと考えた。すなわち彼は、人間が本来の自分であるために、他者とミュニケーションすることを止め、孤立することが必要だと考えたのだ。
彼の哲学の枠組みに従うなら、確かにそうなるだろう。しかし、それは結局のところ、対話そのものの否定なのではないか。
誰かと対話するためには、その誰かと共同性を交わさなければならない。しかしその共同性は「私」を「みんな」の一員にし、非本来的にする。この矛盾を乗り越えるにはどうしたらよいのだろうか。」
■戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か」
連載第5回「対話の共同性──なぜ人は空気を読むのか?」(2023.5.23)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
