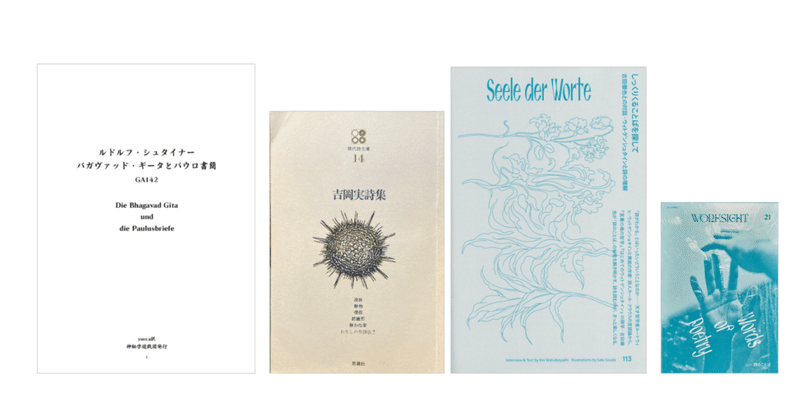
「しっくりくることばを探して 古田徹也との対話・ウィトゲンシュタインと詩の理解」 (『WORKSIGHT[ワークサイト]21号』)/『吉岡実詩集』/シュタイナー『バガヴァッド・ギータとパウロ書簡』
☆mediopos3268 2023.10.29
mediopos3266(2023.10.27)で
詩の言葉は「伝達」ではなく
「虹をさし示している指」に象徴されるような
読まれるたびごとに生成される
「形成」であることについてふれたところだが
今回は同じ『WORKSIGHT21号』から
古田徹也へのインタビュー
「ウィトゲンシュタインと詩の理解」をとりあげる
ウィトゲンシュタインもまた
「詩を理解する」ということに関して
論理学の言葉とは違い
「置き換えの出来ない言葉」として
理解されなければならないことを示唆している
つまりその言葉は
「それ自体がかたちを成す」
「形成」の働きである
そしてその働きは
言葉の背後にあるのではなく
言葉そのものにおいてとらえられなければならない
それはゲーテの形態学における
「現象の背後に何も探してはならない。
現象それ自体が学説なのだ」
というモットーと通底している
古田氏はそのゲーテのモットーが
ウィトゲンシュタインに影響を与えているといい
ただ違いはゲーテが
「植物の背後に何らかの「原型」を見ている、
そこに原初的な「本質」を見いだしたのに対して、
ウィトゲンシュタインは、目の前の現象の背後に
何らかの「本質」「謎」が隠されていると
考えてしまう欲求をキッパリと否定し」ているというが
ゲーテが「原型」を見るというとき
「背後」にそれを見ているというわけではなく
シラーとのあいだに交わされた議論にみられるように
見ているのは「理念」ではなく
「原型」としてあらわれているものそのもので
その意味ではウィトゲンシュタインが
言葉を「自然誌」と呼び
世界そのものの一部としてとらえていたことと
さほど違いはなさそうである
そうしたゲーテ/ウィトゲンシュタインの視点は
ルドルフ・シュタイナーが
『バガヴァッド・ギータとパウロ書簡』において
ゲーテの「感覚は欺かないが、判断は欺く」
という言葉をひいているように
世界がマーヤー(幻影、仮象)なのではなく
私たち自身のフィルターによって
世界はそうとらえられてしまっている
ということとも通底しているのではないだろうか
その意味においても詩の言葉は
その背後にあるメッセージを見ようとするのではなく
それそのものを「自然誌」のように
言葉そのものとしてとらえるときに
はじめて詩として立ち上がってくる
たとえば「詩はわからない」というとき
詩の背後にあるメッセージを探そうとするあまり
それそのものがマーヤーとなって
詩の言葉そのものが見えなくなっているのである
mediopos2883(2022.10.9)でも
古田氏が吉岡実の「静物」という詩によって
「作品には必ずメッセージがある。
それを見つけて書きなさい」
という小学校の先生からの「呪い」から
解放されたという話をとりあげたが
このインタビューでもまた
そのことを繰り返し次のように示唆している
「そこに隠されているものは何もない。
深遠なメッセージも、奇抜なイメージも、
巧妙な寓意も、そこにはない。
あるのはただ、言葉のかたちそのものだ」
詩の言葉に出会うことは
「置き換えの出来ない」ものとして
世界そのものに
出会うことでもあるだろう
■「しっくりくることばを探して
古田徹也との対話・ウィトゲンシュタインと詩の理解」
(『WORKSIGHT[ワークサイト]21号』コクヨ/学芸出版社 2023/10)
■『吉岡実詩集』(現代詩文庫14 思潮社 1968/9)
■ルドルフ・シュタイナー(yucca訳)
『バガヴァッド・ギータとパウロ書簡』(GA142)(神秘学遊戯団)
(「古田徹也との対話・ウィトゲンシュタインと詩の理解」〜「置き換えられない言葉」より)
「ウィトゲンシュタインの探求は、『論理哲学論考』に代表される「前期ウィトゲンシュタイン」と、『哲学探究』に代表される「後期ウィトゲンシュタイン」と、時期によって大まかに分けられます。「言葉の意味は使い方に宿る」という見方は前期にも後期にも共通していますが、「意味は使い方に宿る」という考えについて「本当にそれだけなのか」と疑い出したところかた、「後期」のウィトゲンシュタインの探求は始まっています。つまり、言葉をうまく使えていれば、それだけで「言葉を理解した」と言っていいのか、と考え出すわけです。そのことを考えていくにあたって、ウィトゲンシュタインは「詩を理解する」とはいったいどういうことかを論じています。彼はこう書いています。
「ある詩の言葉が、対応する決まりに従って別の言葉に置き換えられたとしても、その詩は本質的には変わらないなどとは誰も思わない」
「我々が文の理解について語るのは、それが、同じことを述べている別の文に置き換えられるという意味においてであるが、しかしまた、それがいかなる文にも置き換えられないという意味においてでもある。(ある音楽の主題を別の主題で置き換えることができないのと同様に。)
ある場合には。文の内容は異なる文に共通なものであるが、別の場合いんは。その言葉だけがこの配置のなかで表現している何かなのである。(詩の理解)。」
————どういうことでしょう。
ここでウィトゲンシュタインは「言葉を理解する」ということのなかに相反するふたつの側面があると語っています。ある言葉の「意味」を他の言葉によって置き換えることができるという側面と、言葉を置き換えた途端に「意味」が台無しになってしまうという側面があるということです。例えば、あるジョークを別の言葉で解説してしまうと、ジョークの面白みは死んでしまいますよね。同じように、詩をパラフレーズして置き換えたら、やはり詩は死んでしまいます。
(・・・)
ウィトゲンシュタインは「言葉を理解する」ということには、このようにふたつの背反する側面があって、彼はその両方を見渡した上で「言葉を理解する」ということを捉えなければならないと考えました。論理学の言葉とは違って、私たちが普段使用している「自然言語」には「固有の魂」があると彼が語るときに問題になっているのは、ふたつの側面のうちの後者の「置き換えの出来ない言葉を理解する」という「理解」のあり方が、論理学言語のみならず、わたしたちの日常においても十分に検討されてこなかったということです。」
「クラウスは、ウィトゲンシュタインと同様に、言葉にはふたつの側面があると語っています。それは思考内容などを伝える「伝達」の働きと「それ自体がかたちを成す」、つまり「形成」の働きです。クラウスによれば言語をめぐる探求は、前者の働きに価値を置こうとするものと、後者に重きを置こうとするもののふたつに大別されます。そして彼は、これまでの言葉の探求は前者の価値に重きを置きすぎていて、「それ自体がかたちを成すもの」としての言葉の価値が顧みられてこなかったと指摘します。これはウィトゲンシュタインが「言葉の理解」をめぐってふたつの側面があると指摘したことと重なり合う議論だと言えます。
(「古田徹也との対話・ウィトゲンシュタインと詩の理解」〜「生活と言語ゲーム」より)
「ウィトゲンシュタインはこんな言葉で「言語ゲーム」というものを説明しています。
「「言語ゲーム」という用語はここでは、言葉を話すということが活動の一部分、あるいは生活形式(Lebensform)の一部分であることを際立たせるべきものである」
「命令し、質問し、語り聞かせ、おしゃべりすることが、歩き、食べ、飲み、遊ぶことと同様に、我々の自然誌に属している」
————「自然誌」という言葉は面白いですね。つまり、言葉は、ある意味、私たちを取り巻く「自然」として観察されなくてはならない、ということでしょうか。
「言語ゲーム」という用語に込められたニュアンスは。それが日々生まれながら刻一刻と変化するもので、途方もない多様性をもち、生成変化するダイナミズムや可塑性を内包しているということです。こうした考えは、従来の哲学に対する批判としての側面が強くありました。それまでの哲学において重視されてきた「○○とは何か」という「普遍的」な「本質」を探り当てようとする問いの立て方に対する異議申し立てでもあります。彼は、こう書いています。
哲学者たちがある言葉を用いて————知識「知識」、「存在」、「対象」、「自我」、「命題」、「名」といった言葉を用いて————物事の本質を把握しようとしているとき、人は常に次のように問わなくてはならない。いったいこの言葉は、その故郷となる言語のなかで、実際にそのように使われているのか、と。————
我々はこれらの言葉を、形而上学的な使い方から日常的な使い方へと連れ戻す。
ここだけ読むと、哲学者の言葉使いを、ある意味超越的な位置から引きずり下ろして、民衆や大衆に返そうという保守主義的な物言いだと誤解されてしまいそうですが、彼の言語論にはそうした階級闘争的な視点はありませんし。人類学のように文化を相対的に捉えるという観点も強くはありません。実際、彼は「社会」や「文化」といった言葉を『哲学探究』のなかではほとんど使っていません。むしろ彼が疑うのは、物事の「本質」や「普遍的な規則」といったものを措定しようとする考え方そのものです。」
(「古田徹也との対話・ウィトゲンシュタインと詩の理解」〜「現象の背後に何も探してはならない」より)
「彼がここで「自然誌」という言葉を使っている背景には、詩人ゲーテが唱えた「形態学」という用語は大きく影響を与えています。ゲーテは植物を観察するなかで、有機体の個々の形態を「動的に関係し合う全体」において捉えることを提唱しています。彼はこう語っています。
「・・・・・・あらゆる形態、とりわけ有機体の形態を観察すると、変化しないもの、静止しているもの、他と関係していないものなど何ひとつ見出せず、むしろ、あらゆるものは絶えざる運動のなかで揺らいでいることに気づく」
簡単に言ってしまえば、ウィトゲンシュタインは植物画お互いに連関しながら変態=メタモルフォーゼを絶えず繰り返していくさまを。言語というものを考える上でのひとつのモチーフとしたわけです。ただ、ゲーテとウィトゲンシュタインとを決定的に分かつのは。ゲーテが、そうやってネットワーク化しながら変態を繰り返していく植物の背後に何らかの「原型」を見ている、そこに原初的な「本質」を見いだしたのに対して、ウィトゲンシュタインは、目の前の現象の背後に何らかの「本質」「謎」が隠されていると考えてしまう欲求をキッパリと否定した点です。ウィトゲンシュタインは、ゲーテの次のモットーを引用していますが、ウィトゲンシュタインは、ある意味ゲーテ本人よりもこのモットーに忠実でした。
「現象の背後に何も探してはならない。現象それ自体が学説なのだ」
(・・・)
ウィトゲンシュタインは、現象の背後に隠されている謎や秘密はないというわけです。そうだとすると、わたしたちの目の前で起きている現象は何かということになりますが、わたしたちは、目の前で起きていることを、ある固定された特定の「像」の下に見ているだけで、その異なる側面を見落としている、というのが、彼の考えになります。
(・・・)
ウィトゲンシュタインが言葉は生活そのものであると語り、それを観察することを「自然誌」と呼んだのは、言葉が世界そのものの一部であるという意味においてです。であればこそ彼は、言葉がわたしと世界を隔てているとは考えませんでした。ウィトゲンシュタインにとって言葉は世界の重要な一部なんです。それを取り払ってしまえば世界は大きな一部が失われてしまいます。」
(「古田徹也との対話・ウィトゲンシュタインと詩の理解」〜「ChatGPTと吉岡実」より)
「わたしたちは学校で言葉の扱いかたを学ぶとき、常にその背後に必ず「メッセージ」があるという前提で学びます。それがいかにつまらないことかと感じたのは、わたしの場合、吉岡実の詩に出会ったときでした。「この言葉でしかありえない」という感覚を、吉岡実の詩で初めて深く納得しました。それをそれとして味わう以外の読み方がないという感覚ですね。それによってひとつ呪縛が解けたと感じたことを覚えています。
————芭蕉の俳句に「メッセージ」を読み取るのはナンセンスですよね。詩という現象の背後に何も探してはいけない、ということですね。
詩をまるで自然の景色を眺めるように見る。そこに言葉が揺らぐのをただただ見る。そういうことかなと思います。『はじめてのウィトゲンシュタイン』を執筆した際にも、机の上に吉岡実の詩を置いていました。ウィトゲンシュタインについて執筆しながら、時折詩集を開くと、そこにウィトゲンシュタインの言語論が実践されているように感じていました。『絶版本』という書籍の企画で、吉岡実の詩について書かせていただいたことがあるのですが。そこでこんなことを書きました。
「そこに隠されているものは何もない。深遠なメッセージも、奇抜なイメージも、巧妙な寓意も、そこにはない。あるのはただ、言葉のかたちそのものだ」」
(シュタイナー『バガヴァッド・ギータとパウロ書簡』〜「第五講」より)
「東洋的な思考がまだ成し遂げることができたものと、パウロにおいてすぐさまかくもすばらしく明瞭に私たちに向かって現れてくるものとの間には、根本的な違いがあります。すでに昨日指摘されたことですが、クリシュナにおいてはすべてが、人間が形態変化から抜け出していく道を見出すということにかかっています。けれどもプラクリティは魂とは疎遠な何かのように外部にとどまっています。こういう東洋的な進化の内部では、東洋的な秘儀参入の内部においてすら、あらゆる努力は、物質的な存在[Dasein]から自由になること、自然として外部に拡がっているものから自由になることを目指すのです。と申しますのも、自然としてそこに拡がっているものは、ヴェーダ哲学の意味ではマーヤー(幻影、仮象)として現れるからです。外部にあるものすべてはマーヤーであり、ヨーガはマーヤーから自由になることです。私たちも示したことですが、人間は、為し、行い、欲し、考えるものすべて、欲求や思考の対象となるすべてから自由となり、外面性であるものすべてに魂として勝利することがまさにギーターにおいては求められているのですから。人間の行う営みをいわば人間自身から落とし、人間は自ら自身のうちに安らい、自身のうちで自足せよ、というわけです。このように、誰であれクリシュナの教えの意味で進化したいと願うひとの念頭にもあることは、根本的に言って、いつかパラマハムサ[Paramahamsa]、すなわちあらゆる物質的存在を離れ去り、彼自身がこの感覚世界の内部で行為として行ったすべてに打ち勝つ高次の秘儀参入者のような何かになることです、純粋に霊的な存在のなかに生き、感覚的なものを克服してもはや再受肉への渇望がなくなり、営みとしてこの感覚存在に習熟したものすべてにもはや関わりを持たないまでになった秘儀参入者のような何かに。つまりそれはこのマーヤーから抜け出すこと、いたるところで私たちに向かってくるこのマーヤーに勝利することなのです。
しかしパウロにおいてはそうではありません。パウロの場合はこうなのです、彼がこういう東洋的な教えに向き合ったとしたら、彼の魂の深い奥底において何かが次のような言葉を呼び起こすことでしょう、いかにも、お前は外でお前を取り巻いているすべて、お前がかつて外部で行ったすべてからも抜け出して進化したいと思っている。お前はすべてを置いていきたいのか?いったいすべては神のみわざ[Gotteswerk]ではないのか、お前が抜け出そうと欲するすべては神的に霊により創造されたものではないのか?お前がそれを軽蔑するなら、お前は神のみわざを軽蔑しているのではないか?いかなるところにも神の顕現が神の霊が生きているのではないか?まずお前自身の営みのなかに愛し信仰し帰依しつつ神を示そうとはしないのか、それでいて、神のみわざであるものに勝ち誇るつもりなのか?
パウロによって語られてはいませんが彼の魂の底で働いているこの言葉を私たち自身が魂の奥深くに書き記すのが良いでしょう、と申しますのも、そこには私たちがまさしく西洋的な啓示として知っているものの重要な神髄が表現されているからです。パウロ的な意味においても私たちは私たちを取り巻いているマーヤーについて語ります。なるほど私たちも、いたるところでマーヤーが私たちを取り巻いている!と言うでしょう。けれども私たちはこう言うのです、いったいこのマーヤーのなかには神の顕現がないのか、すべては神的ー霊的なみわざではないのか、いたるところに神的ー霊的なみわざがあるということを理解しないのは冒涜ではないのか?と。今や新たな問いが加わります、なぜこれがマーヤーなのか、なぜ私たちは私たちの周りにマーヤーを見るのか、という問いが。ーー西洋はすべてがマーヤーであるかどうか、という問いにとどまりません、なぜマーヤーなのか、が問われるのです。ここで、私たちの魂的なもの、プルシャの中心にまで入り込んでゆく答えが生じます、魂がかつてルツィファーの威力に屈したので、魂はすべてをマーヤーのヴェールを通して見るのだ、魂は魂としてあらゆるものの上にマーヤーのヴェールを拡げるのだ、という答えが。ーー私たちがマーヤーを見るということは、いったい対象の罪なのか?否。私たちがルツィファーの威力に屈しなかったら、魂として対象は私たちにその真実の姿を現すだろう。対象が単にマーヤーとしてしか私たちに現れないのは、私たちがそこに拡がっているものの根底を見ることができないからだ。これは、魂がルツィファーの威力に屈したことが原因である、これは神々の罪ではなく、自分の魂の罪なのだ。お前魂はお前にとって世界をマーヤーにしてしまった、お前がルツィファーに屈服したことによってだ。
このような定式化の最高の精神科学的理解から下降して「感覚は欺かないが、判断は欺く」というゲーテの言葉までは一直線です。俗物や狂信者たちはゲーテを、ゲーテのキリスト教を思うさま論難するがよろしい、それでも、やはりゲーテが、自分はきわめてキリスト教的な人間のひとりであると言うことは許されるでしょう、なぜなら、「感覚は欺かないが、判断は欺く」というこの定式に辿り着くほど、ゲーテはその本質の奥深くでキリスト教的に考えているからです。魂の見るものが真実でなく、マーヤーとして現れるのは、魂の罪です。ここでオリエンタリスム(東洋主義 Orientalismus)においては単純に神々自身の行為のようにそこにあるものが、ルツィファーとの大いなる闘いの起こる人間の魂の深みへと転じられます。
私たちがオリエンタリスムを正しく観察してみると、このようにオリエンタリスムは、まさにこのことによってある意味で唯物論なのです、マーヤーの霊性を認識せず、物質的なものから抜け出そうとするがゆえにです。パウロ書簡を貫いて脈打ち、未来において全地球上に目に見えて拡がってゆくであろうものは、魂的な教えなのです、たとえまだ萌芽のかたちでしかなく、そのため現在のようなタマス時代には見誤られることがあるとしてもです。マーヤーの特殊な性質についてこのことが理解されなければなりません、そうしてはじめて、人類進化の歩みのなかで肝心なことは何かを深いところで理解できます。そうしてはじめて、パウロが最初のアダムについて語るとき、パウロが何のことを言っているのか理解できるのです、魂においてルツィファーに屈服し、そのためにますますいっそう物質のなかに巻き込まれてしまった、すなわち誤った物質体験に巻き込まれてしまったということにほかならないのですが、そういう最初のアダムについてです。神の創造として外部にある物質は良いものです。そこで起こっていること、それは良いことなのです。人類進化の経過のなかで魂がそこで体験するもの、これはどんどん貧しいものになっていきました、なぜなら魂は最初にルツィファーの威力に屈したからです。ですからパウロはキリストを第二のアダムと呼ぶのです、なぜならキリストはルツィファーの誘惑を受けずに世界に登場し、人間の魂のあのような指導者にして友人であることができるからです、キリストは人間の魂を徐々にルツィファーから引き離し、つまりキリストとの正しい関係に導くということです。
パウロは、秘儀参入者として知っていたことすべてを、彼の生きていた時代には人類に伝えることはできませんでした。けれども彼の書簡を自らに作用させるひとは、これらの書簡が、外的に表明しているものよりも多くを深いところで語っていることを洞察することでしょう。つまり、パウロは教区に対して話さなければならず、その教区の知性を顧慮しなければならなかったということです。そのため、彼の書簡のなかには明かな矛盾のように見えるものもあります。けれども深部へ入り込んでいくことのできるひとは、実際パウロにおいていたるところでキリストの本質についての衝動を見出すのです。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
