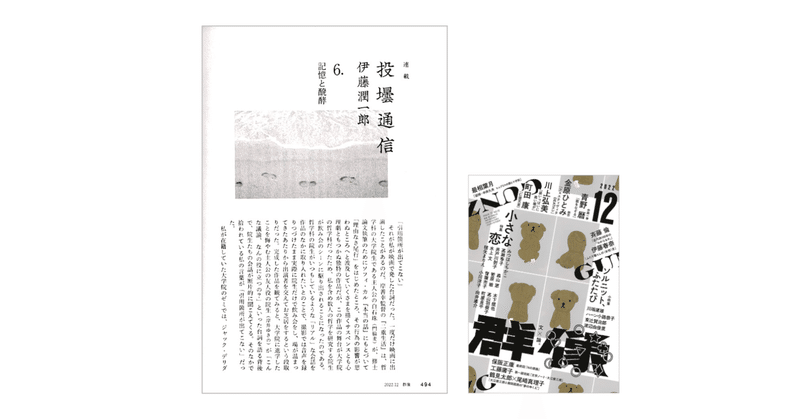
伊藤潤一郎「投壜通信 6.記憶と醗酵」」 (『群像 2022年 12 月号』 )
☆mediopos2914 2022.11.9
「発酵と腐敗は化学的には区別されない」
人間にとって有用な場合
それは「発酵」と呼ばれ
有用ではないものが生まれてくると
それは「腐敗」と呼ばれる
化学的には区別されないからといって
そして人間の有用性の如何によるだけだからといって
発酵と腐敗を分ける必要がないわけではない
それはパラケルススが
「すべてのものは毒であり、毒でないものなど存在しない。
その服用量こそが毒であるのか、そうでないかを決めるのだ」
といっているように
毒として働くか
薬として働くか
その違いは大きい
実際の有用性についてもそうだが
「人間中心の唯心論的概念」としてとらえるときも
「発酵」と「腐敗」の違いは
人間にとって重要な差異となる
そして発酵食品を生みだすような
「発酵」を可能にするためには
発酵させるために必要な複雑なプロセスが必要となる
そして多くの場合そのプロセスは「人間の予測を超えていく」
わたしたちひとりひとりのなかにも
さまざまなかたちで「発酵」と「腐敗」は
否応なく進行している
「発酵」できるように
「考え」「感じ」「言葉を使う」ためには
それに必要な経験と技術と
育てるためのプロセスが不可欠となる
もちろんそこには予測を超えた要因もまた働く
しかし必要なプロセスがそこに欠損してしまうとき
それらは「発酵」ではなく「腐敗」に向かってしまう
「発酵と腐敗は化学的には区別されない」ように
「腐敗」を「腐敗」と見なせないとき
それらが「腐敗」であることに気づけないまま
「考え」「感じ」「言葉を使う」ことになる
世に悪しき言葉が夥しく流されるのも
それが「腐敗」だと気づかないまま使われているからだ
「善魔」の言葉もまた
みずからの「腐敗」に気づけないときに発せられる
できうればみずからの発した
思考や感情や言葉が
長い時を経るなかで
「発酵」し得るものとなりますように
■伊藤潤一郎「投壜通信 6.記憶と醗酵」」
(『群像 2022年 12 月号』 講談社 2022/11 所収)
「ここ最近、醗酵に対する注目が高まっている。『メタファーとしての発酵』をはじめとするサンダー・エリックス・キャッツの一連の著作や小倉ヒラクの『醗酵文化人類学——微生物から見た社会のカタチ』、藤原辰史『分解の哲学——腐敗と発酵をめぐる思考』、松岡正剛とドミニク・チェンの共著『謎床——思考が発酵する編集術』など、広義の発酵をテーマにした書籍が次々と出版されている(もちろん、発酵に関する古典ともいうべき小泉武夫『発酵——ミクロの巨人達の神秘』も忘れてはいけない)。これらのほんのなかでほぼ必ず説明されるのが、発酵と腐敗は化学的には区別されないということだ。どちらも微生物が作用していることにかわりはなく、その結果として人間にとって有用なものが生まれてくれば発酵であり、有用ではない危険なものが生まれてくれば腐敗となる。小倉ヒラクの言葉を借りれば、「発酵というのは、普遍的かつ唯物論的な概念のようでいて、本質は「人間中心の唯心論的概念」である」。発酵と腐敗を分ける基準はどこまでも人間にとっての有用性にあるということだ。
微生物が働くという点ではシームレスな発酵と腐敗のこうした関係は、どこか薬と毒の関係に似ている。ギリシア語の「パルマコン」が薬であると同時に毒でもあるという決定不可能性を梃子に、プラトンのエクリチュール論を読みなおしたのはデリダだったが、ここではベンゾジアゼピン依存症について語る松本俊彦の実感のこもった言葉を引いておきたい。
薬学の歴史を紐解くと、改めて痛感することがある。それは、「薬と人間」の関係は同時に「毒と人間」の関係でもあるということだ。ルネサンスの医師にして錬金術師、パラケルススも同じことをいっている。「すべてのものは毒であり、毒でないものなど存在しない。その服用量こそが毒であるのか、そうでないかを決めるのだ」
(…)発酵と腐敗に関してもその境界線が見極められ、人間にとって有用な微生物の作用のみが発酵として選り分けられることで、味噌やヨーグルトやさまざまな酒などの発酵食品が生み出されてきた。しかし、発酵と腐敗を区別する知を手に入れたかたといって、人間が発酵のプロセスまでも完全にコントロールできるようになったわけではない。「ぬか床」をメタファーとして人間の認識やインターネットにおけるコミュニケーションのあり方などを捉えなおしているドミニク・チェンが、日々ぬか床を前にして抱いているという問いは、発酵のプロセスがどのようにしても人間の手をすり抜けていくさまを示している。
(・・・)
発酵が人間の予測を超えていくのは、そのプロセスにおいてあまりに多くの要素が相互に作用しあっているからである。たとえば、ある時期までの日本酒造りにおいては「火落ち菌」と呼ばれる雑菌の混入が脅威であったように、数多の微生物が気温や湿度などさまざまな要因のなかで織りなす関係性の網目は、その一部がほんの少し変化しただけで思わぬ結果を生み出してしまう。思えば現代哲学もまた、ネットワークの思考を発達させてきたのだった。ドゥルーズのリゾーム、デリダの差延、近ごろ話題になることの覆いアクターネットワーク理論や中動態などは、どれも独立した実体ではなく、関係性のなかに置かれた存在から思考をはじめるための理論装置だといえる。それは、ときには人間と人間の関係であり、ときには人間とモノの関係やモノとモノとの関係であるが、ヘーゲルが語る精神をひとりの人間の精神のあり方とみるならば(本来、ヘーゲル流の「精神」とは個人にのみ関わるものではないが)、精神が泡立つという事態が示しているのは、私たちひとりひとりの精神がすでにネットワークして存在しているということだろう。
言葉を記憶のなかに寝かせることは、心という酒樽のなかに言葉を置きいれ、心に住まう微生物たちの複雑なネットワークによって発酵が進むのを待つことなのである。そしてその結果、発酵した言葉が少しだけちがったかたちとなって現れるだろう。この変容のプロセスは、私というひとりの人間のなかで進むものでありながら、意識によるコントロールが及ばない領域へと言葉をゆだねることによって生じている。何か新たなものは、私の意識だけではなく、私の心に住む微生物たちとの協働によってはじめて生まれてくるのだ。記憶によって引用をおこなう哲学者たちは、意識しているかはともかく、どこかでこのことをわかっていたのではないだろうか。」
「最後にもうひとつだけ問うてみたい。それは、発酵というメタファーで語られる思考の対極にある知とはいかなるものかという問いだ。それは、正確な知なのだろうか。いま一度ドミニク・チェンの言葉を手がかりにしよう。
わたしたちは自己意識や組織管理といった「制御」型の認識論を大きく見直すことになるだろう。そこから、もっとゆるやかに、無意識や他者による作用に「発酵」を委ねるパラダイムが育っていくかもしれない。
発酵という思考のあり方のポイントは、やはり「ゆだねる」というところにある。意識による制御の外部へとゆだねることによって、はじめて言葉は発酵をはじめるが、このときの「ゆだねる」とは、時間にゆだねることであると同時に、関係性のなかにゆだねることででもある。ジル・クレマンの手がける庭が、人間の手を離れた時間のなかにゆだねられることによって、さまざまな生物や微生物との関係性のなかにゆだねられ、そのときにはじめて新たな風景が生まれてくるのと同じことだ。正確な知にもこうした側面はまちがいなくある。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
