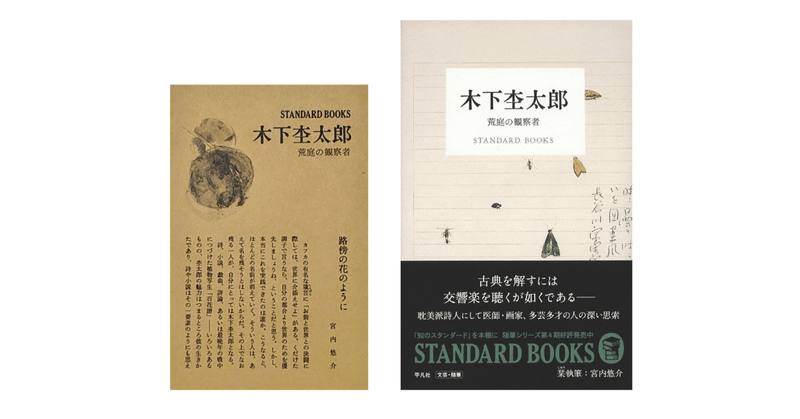
『木下杢太郎 荒庭の観察者』
☆mediopos2788 2022.7.6
平凡社の随筆シリーズ
STANDARD BOOKSの第4期の5巻目は
耽美派の詩人であり
医師でも画家でもあった
「木下杢太郎」(一八八五−一九四五)
耽美派の詩人というくらいしか
知らずにいたが
鴎外全集を編纂し
ハンセン病根絶に献身した
医師でもあったことを知る
解説にあたる「栞」は
作家の宮内悠介が担当しているが
それによれば
木下杢太郎は「ユマニテ(humanité)」の人
人類・人間性・古典学などを指す「ユマニテ」は
「杢太郎自身を象徴するもの」であり
木下杢太郎について語られた「ユマニテ」について
次のように語られてもきたという
「人間は古典を学ぶことによって、
人間として最も大切な『人間性』や
『慈悲の精神』を心に育てる」
「真の自由への人間解放を目指し、
古典研究によって教養を高め、
人間愛に基づく人間の尊厳の確立を目指す」
「ユマニテの人」としての杢太郎を
よくあらわしているのは
第二次世界大戦における空襲のなかで
学生に語ったというこんな言葉だ
「君たちは知識と知恵を区別しなくてはならない」
「いくら知識を積み重ねても、
それでは知識の化け物になるだけだ」
「人間のためになるようにするには、知恵が必要だ。
では知恵を学ぶにはどうすればよいか。
古典に親しむことだ。古典には人類の知恵が詰まっている」
そういえば
古典の知恵を実感できはじめたのは
比較的最近になってからだ
「古典」は必ずしも古い書物を意味しているわけではないが
「知識」ではなく「知恵」を得るためには
「古典」の言葉は助けになる
しかし皮肉なことに
若い頃はまだそうした「知恵」に応えられないことが多く
それらに盛られた「知恵」を少しなりとも理解できるのは
ずいぶんと歳を経てからのことになる
(個人的にいってもまさにそうだ)
「古典」を交響させ得る力こそが
未来へと向かう「知恵」を可能にする
いまさらのようだが
あらたなものを作り出すためには
過去をも再生させ得る力が必要だろう
「古典」は常にあらたに再生され得る力を持つ
それを引き出す知恵をこそ持ちたいものだ
■『木下杢太郎 荒庭の観察者』
(STANDARD BOOKS 平凡社 2022/4)
(木下杢太郎「古典に就いて」より)
「純粋の意味からいうと、古典とは優れた考察家、有徳の実践者、気力の熾(さかん)であった時代のたましいを多分に盛った本のことである。
古典に在っては文字を以て記された所はその用の全部ではない。その文字は大きな精神的潜勢力の象徴たるに過ぎぬ。ちょうど六角形を綴った有機化学の構造式が物質その者ではなく、それを表す符号であるようなものである。よしその表現に今の通念と合わぬ所が有ったとしても、その合わぬ所にその人、その時代を体験する管鍵を求めることが出来る。それを今見て合理的な表現を以て書き直したものに必ずしも古典としての価値が有るのではない。
(…)
それ故に本当に古典を体得するということは甚だ限られた範囲においてのみ行われるのである。好き古典を求め、そしてそれを原文の形において読む努力と能力とを先決の条件とする。
実際一般の人は古典に近づき難いのである。印刷の事が普及し、良本の復刻がたやすく手に入る現代でもなお然りである。一時代は古典を体読することの出来る哲人を必要とする。そしてその人の仲介によって古典を識るのである。そのために選ばれた人の責任は重大である。そういう人が凡庸である時代は、また時代の精神が凡庸である。
今のところ、我々の参通し得る古典は日本の古典と支那の古典とだけである。日本の聖典は古事記であり、支那の古典の最高峰は孔子である。現在の青年は孔子から甚だ遠く離れてしまった。
然しながら古典の研究の方法は孤立的、排外的であってはならぬ。史記や漢書のもにたよっていた昔の人よりも、ギリシャ、ロオマ、ペルシャ等の古文書と併せ読むことの出来る今の学者の方が古への支那、古えの中央亜細亜を一層好く理解することが出来る。
ギリシャ、ロオマの賢人、印度、ナザレの祖師、ルネサンスの学者を知らずして、周、程、張、朱のみを学んだ時代はやがて因循姑息に陥り、ついに明治の維新を招来するに至った。
支那は大国であったが、漢書より後はその文化が閉鎖的になった。宋、明に至って萎靡振るわず、清の康熙、乾隆の英邁を廻すことが出来なかった。
譬が不倫であるかも知れないが、古典を解すにはなお交響曲を聴くが如くである。伴奏の無い歌唱は鼓舞する所が狭い。日本の古典を歌唱に較べると、それは支那古典を伴奏せしめることによって更にその影響を大きくする。
然し今の時代はその伴奏のうちに泰西の古典、現代の思想、科学、技術等の器を吹弾する者をも容れることを要求する。
そして世人は、この大交響曲の大指揮者を翹望しているのである。
(一九四四年 五九歳)」
(木下杢太郎「科学と芸術」より)
「其の結果は違うが、其の生成に於いては科学研究と芸術的創作とかなり相似たものがある。孰れも第一に、まだ持っていないものを作り出そうと欲望する。そして強い空想力が手段と過程とを離れて、其の結果の幻影を形作る。レオナルド・ダ・ヴィンチが飛行機の設計図を作ったというが、それは科学的と判ずべきか、芸術的と判ずべきか、恐らく其の両者の混融したものであろう。空想力の弱い人は大きな芸術を創作することが出来ないように、科学の新境を開拓することも出来ない。空想力は長く持続しなけfればならない。人間は醒めている時だけ考えるのではない。日中其の考察に沢山の材料を与えて置くと、睡眠の間に、考察の生理化学が、意識の閾下で不可思議なる醗酵をして、頭脳を、物質の結晶する前の溶液のような状態に置く。其の尖の一角が意識閾の上に頭を出すと、それをきっかけにして、意識のうちににょきにょきと結晶が蜂起するのである。
かくの如き心理作用は科学的研究の過程に於いても、芸術的創作の過程に於いても共通である。唯、両者は其の手段と其の技術と、其の目的とを異にするばかりである。
科学も芸術も其の結果は、世界的のものであり、人道的のものである。然し、其の研究、其の創作は、研究者、創作者の精神の統覚に依従する。其の統覚は国土、時代、国民性から影響せられる。熱烈なる愛国者から生まれる科学、芸術の果実も、其の真正なるもの、其の佳良なるものは、やがて世界的であり、人道的であり、両者に何等の矛盾はない。それ等の結果を取って之を特殊の目的に利用するということは、これは別の事である。
(一九四一年 五六歳)
(栞〜宮内悠介「路傍の花のように」より)
「カフカの有名な箴言に「お前と世界との決闘に際しては、世界の介添えせよ」がある。くだけた調子で言うなら、自分の都合より世界のためを優先しましょうね、ということだと思う。しかし、本当にこれを実践できたのは誰か。こうなると、ほとんどの名前が消えていく。そういう人は、あえて名を残そうとはしないからだ。その上でなお残る一人が、自分にとっては木下杢太郎となる。
詩、小説、戯曲、評論、あるいは最晩年の戦中につづけた植物写生「百花譜」——いろいろあるものの、杢太郎の魅力はつまるところ彼の生き方であり、詩や小説はその一要素のようにも思える。キューバ滞在中に描かれた何気ない絵も、医学者としてハンセン病を研究し、国の隔離政策に反対したことも、空襲下で教鞭を執りつづけたことも。「百花譜」の路傍の花は、ある意味では自画像のようだ。つまり、自己主張のない、その意味では地味な、けれども背筋を伸ばした姿が。
杢太郎の生きかたを知ろうとしたとき、必ず行き当たる言葉に「ユマニテ」(humanité)がある。フランス語で人類、人間性、古典学などを指すものだ。これは杢太郎の鴎外論に出てきたのち、どちらかというと杢太郎自身を象徴するものとなっている。いくつか引用すると、「人間は古典を学ぶことによって、人間として最も大切な『人間性』や『慈悲の精神』を心に育てるのだ」(『杢太郎のユマニスム』新田義之)、「真の自由への人間解放を目指し、古典研究によって教養を高め、人間愛に基づく人間の尊厳の確立を目指す」(『ユマニテの人——木下杢太郎とハンセン病』成田稔)など。
もっとも、このあたりは多くの人が首をひねりそうなところだ。まず、どうして古典研究が人間性につながるのか。そこで、「羅甸語一つ知らないで、それで仏蘭西の文化が分かると思ったら、それこそ大それたことです」(「巴里通信)という杢太郎の言にしたがい、ラテン語にさかのぼってみる。ラテン語のhumanistasは、紀元前にキケロが好んで用い、その考えかたを練り上げたもの。すごく簡単に言うと、教養が人と獣をわかち、ひいては寛容やよりよい社会につながるということだ。転じて、こうしたキリスト教以前の古典に倫理の源を求める姿勢がユマニスム(humanisme)。空襲中、杢太郎はこんなことを学生に語ったと言われる。「君たちは知識と知恵を区別しなくてはならない」「いくら知識を積み重ねても、それでは知識の化け物になるだけだ」「人間のためになるようにするには、知恵が必要だ。では知恵を学ぶにはどうすればよいか。古典に親しむことだ。古典には人類の知恵が詰まっている」——。
幸い、いまここに木下杢太郎という古典がある。だから、まずはこれに目を向けてみよう。最小限のボリュームで音楽が鳴っているようなこの筆致に、派手に広まったりすることをみずから拒むようなありかたに、そして、そういうものにしか宿らない何物かに。私たちの人間性のために。
それにしても、いまあらためて文章に接してみても、杢太郎の自己への興味のなさのようなものには驚かされる。杢太郎の興味の向かう先は、ほとんど常に外部の世界にある。そして病を研究し、路傍の花を写生し、鴎外全集の出版のために動く。彼の姿勢も、ユマニテの概念も、実際のところ、近代自我といったものより先を行っていたように感じられる。でも、杢太郎は先駆者であろうとはしない。もしかすると、そういうことは意識すらない。このあたりは、早くから自分がどう見られるかを鋭敏に意識し、セルフプロデュースしたであろう旧友の北原白秋とは好対照で興味深い。
同じくして、杢太郎はハンセン病の治療法を模索したが、それを成し遂げる最初の一人であろうとはしなかった。「動物接種が確実になった以上正攻法として僕らは完全な治療法を見出さなければならない。人間は空を飛べないといわれたのに今日の飛行機の発達の素晴らしさはどうだ。療法はかならず成る日がある。」(日刊紙インタビュー)。杢太郎は病の根絶をこそ願う。それをやるのは「僕ら」であって「僕」ではない。治療法を確立するのは誰でもよくて、治療法の確立が第一に優先されるということだろう。
なるほど杢太郎は芸術より医学を選んだかもしれない。けれどそれ以上に、というかそうだからこそ。芸術より大事なものを識っている。ゆえに杢太郎は実社会をまっとうに生きようとする者にとって星となる。そしてまた、ここには芸術家が見落としがちな、芸術家こそ見習うべき何かがある。だから筆者も芸術の関わる者のはしくれとして杢太郎を愛し、かくありたいと願うのだ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
