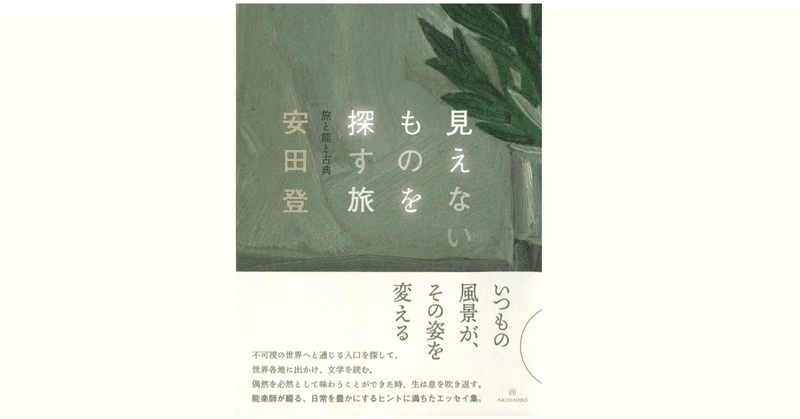
安田登『見えないものを探す旅』
☆mediopos-2399 2021.6.11
「みんな一緒」は「同」への信仰である
「信」は人と言から成る漢字であり
「言語」がそうであるように
「みんなの約束から生まれる」
「みんな」といっしょでないと
「みんな」に見てもらわないと不安だからと
「みんな」を拠り所にして不安を去ろうとするのは
じつのところ「孤独」から逃げようとしているだけだ
「みんな一緒」は
「世間」のなかのマスゲーム的な「散文的」世界だ
「みんな」の物語のなかで役割を演じ
「同」の一部となりその信仰とともに踊ることで
じぶんに目を向けないですむ
「みんな」との共感を求めるのも
過剰な被害者意識から外なるものを批判するのも
じぶんから目を逸らすための格好の手段になる
しかし魂にとって大切なものは
ひとりの「孤独」のなかで
みずからと向き合うことからしか生まれない
そこに「みんな」はいない
ひとり「孤独」に詠い舞うしかないのだ
「舞」という漢字が
もともと「無」であったように
「舞」は闇のなかで舞う
つまりは「見えない」孤独のなかでの捧げもの
現代人は「見えるもの」という
「みんな」に共有されるものを求めて生きている
その象徴が「科学(主義)」という信仰である
科学的に証明されている(とされる)ものを信じるように
その「信」もまた「みんなの約束から生まれ」ている
「みんな一緒」を去り
「見えないもの」を見るためには
「孤独であることの勇気」がいる
孤独のなかでひとり「詠う」とき
その深みのなかで非在の存在たちと出逢い
そこで自分のほんらいの霊である魂は蘇りを体験する
そうすることではじめて「他者」は現れ
「ともに」あることが可能となる
「みんな一緒」のなかに「他者」はいない
「他者」が存在してはじめて「愛」の可能性が生まれる
「ひとり」という個としての「孤独」がないとき
「他者」は決して存在できないのだ
■安田登『見えないものを探す旅/旅と能と古典』(亜紀書房 2021.6)
「「見えないものを探すとか、見えないものを見るなんてできるわけないじゃないか」と言う人がいます。むろん、その「なにか」は(正確にいえば)見えないわけじゃないし、ないわけでもありません。ただ、ふつうには見えない。見えることが共有されない「なにか」です。
私たちには、「見えないもの」を見る力が備わっています。「目」を使わないでものを見る力です。
そのひとつが「夢」です。夢を見るとき、人は器官としての目を使いません。夢を「見た」ということは他者に証明することはできませんし、見た夢を共有することもできません。それでもその人が「夢を見た」ということを疑う人はいません。夢は、「目には見えない」ものでも、確かに「見る」ことができるものがあるということを私たちに教えてくれます。
感覚器官を使わずにものを見るときには、肉体の器官という制限がない分、より自由に見ることができるし、ある意味、本質を見ることはできたりもします。だからこそ、古来、夢は重視されてきました。」
「今年(二〇〇〇年)の九月、喜多流の大島政允主催の台湾公演に参加した。私たち、日本の能楽師による演能だけでなく、大島師たちの指導のもとに能を学んだ台湾の芸術大学の学生たちによる演能もあった。」
「そのとき、一人の女学生から学生自身が演じた能についての話が出た。
学生たちは言葉に尽くせないほど感動している。そして、大島先生たちには本当に感謝している。中には人生を変えてしまうほどの体験だったと語る学生までいるという。しかし「感動と同時に能グループの帰国はとても大きな悲しみを残した」と真摯な表情で彼女は話す。(…)
世界中の人たちが台湾に来ると、「台湾人は明るくて、エネルギッシュで、ポジティブで、いつも幸せそうに見えるからうらやましい」と言います。しかし、私たちは本当はとても孤独なのです。孤独だからこそいつもエネルギーを外に出して、自分や他人を盛り上げていなければならないし、いつも誰かと一緒にいないと不安で仕方がない。人のことがすごく気になるのです。私たちが演じる現代演劇の舞台でも同じで、お客さんに受けているか、喜んでくれるか、。そればかりが気になります。お客さんに受けるように受けるようにと演技をする。それが私たちの演劇メソッドなのです。
しかし、能を学んで、自分の中に入っていくという演技方法があることを体験として知りました。演能を見てさらにそれを実感しました。舞台が進行すればするほど、演者は自分の中にどんどん深く入っていくように見えたのです。舞台全体としては一体化する方向に向かっていながら、個々人はさらに個人になっていき、どんどん孤独になっていく。(…)
私たち台湾人には、自分の中の孤独をあれほど深く見つめる機会も勇気もありません。だからこそ、自分の中の孤独と共に演技をしていく「能」に感動しました・でも、それを私たちができるかどうかを考えると悲しくなります。絶望感さえ感じます。自分の孤独を見つめるためには、何か「拠り所」が必要なのだと思います。」
「知人の精神科医が、今の日本人にとって重要なのは、「孤独であることの勇気」ではないかと言っていた。いじめ問題や少年犯罪、そして大人社会においてもこの力の欠如は様々な問題を引き起こしている。台湾の学生が学んだ、独りでいることの勇気を多くの日本人はすでに失いかけているだろう。
『姨捨(おばすて)』という能がある。そのシテは、姥捨山に捨てられた老女の霊だ。彼女は孤独を受容しながら、月の友びとを待ち続ける。旅の途中に姥捨山を訪れた月の友びとである旅人の前で、老女は胡蝶の舞を戯れ舞い、ついには月と一体化して山気の中に昇華する。
かつて日本人は、孤独の中で自然と一体化するすべを知っていた。それは、姥捨山に捨てられた老女という、絶対の孤独者であってすらだ。そして、それは芸能として長きに亘って人々に、老いとは何か、孤独とは何かという問いを投げかけていた。それは孤独の芸能、能だからこそできたことではなかっただろうか。
現代人である私たちは、そこから何を学び、未来に向けて何を提示することができるだろうか。」
「「舞」という漢字の甲骨文は(…)「無」という字と同じである。「舞」はもともと「無」だったのである。
その舞われていない「無」の舞(天宇受売命の、絶対の闇のなかでの舞)は、神々を咲わせる。そして、その咲いは天照大御神の心を動かし、彼女は岩戸を少し開ける。その瞬間、暗闇は裂け、光が戻る。暗闇が咲けて光が戻ったその瞬間を世阿弥は「花」という。「花」は草冠を取れば「化」となる。「化」、すなわち「花」とは「変化」であろう。
変化(花)は存在ではない。点は現象ではあるが、存在ではない。それは絶対の闇と同じく、時間も空間も所有しない。しかし花は絶対の闇とは違って、時間と空間を生み出す母胎たり得る現象だ。変化そのものがそこに立ち現れた瞬間に、時間と空間が誕生する。」
「平安末期の歌人、藤原定家は世阿弥にとっても特別な存在である。
「その定家の歌は」と尋ねると、多くの人は見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ」を挙げる。(…)
耳によって最初にこの歌を知った古人たちは、まず「見渡せば」と詠じられれば、実際に見渡さなくても、首を回る筋肉が反応したはずである。そして「花も」と詠われれば春空を埋め尽くす満開の桜を思い浮かべ、続いて「紅葉も」と詠われれば全山を紅や黄に染める紅葉を鮮明にイメージしたはずである。
が、それが「なかりけり」と否定される。否定されても一度しっかりとイメージされたものは、そう簡単になくなるものではない。縹渺とした霧の彼方に満開の桜や全山を紅黄に染める紅葉は、うっすらと、しかし厳然と残る。
霧の彼方の桜や紅葉を観るのは、私たちの普段使う目ではなく、もうひとつの次元(Altered State)の意識が有する目である。(…)
このように、<事実としての存在>はそこにはないが、しかし厳然とそこにある存在、それを「非在」と呼ぶことにしよう。「非」はただの否定ではない。(…)
定家の歌の企みは非在の桜、非在の紅葉そして非在の旅人を現前させるだけではない。非在を観じる意識、すなわち私たちが普段は自分ですら感じないようにしている、「もうひとつの次元」の意識状態を引きずり出してしまう。だから定家はちょっと怖い。
ところがもっと怖いのは能だ。能はこのような「非在」の手法を多く使う。
(…)
日本のすべての場所は物語を持っている。それはまだ全国に残る美しい地名が物語る通りである。そしてその物語の裡には非在の霊がいる。
漂白の旅人はそこで歌を謡う。
なぜ歌か。彼が今まで生きてきたのは現実的な叙事的世界だ。散文的な世界だ。しかし、組織から追い出され、物語を失ったとき、今まで確固たるものだと思っていた叙事的世界がカラカラと崩れ、極めて不安定なものだということを思い知る。だからこそ、歌を謡う。歌は叙情(抒情)的世界に属する。韻文的な世界だ。(…)
歌を通じて彼は土地の霊や物語と出会い、その出会いによって、喪失した自分の物語も再び紡がれ得る可能性を感じ、そして自分の霊である魂が蘇るのを体感する。」
「「信じる」という語の「信」が音(おん)であるように、かつての日本語には「信じる」という言葉がなかった。人々が神話の世界に住んでいたとき、そこには「信」というものは必要なかったのだ。「信」というのは漢字の右(旁)が示すように「言語」であり、抽象思考から生まれる。たとえばミサの中で「ここに神がいらっしゃいます。それを信じることができますか」というような文は成立するが、鉛筆を出して「ここに鉛筆があります。それを信じますか」という文は成立しない。「信」とは、いま目の前に見えないものを「ある」とする心的機能だ。そして、それはみんなの約束から生まれる。言語もそうだ。すなわち「同」でもある。
『古事記』上つ巻は、信仰も「同」もまだ無縁だったころの話である。
(…)
学習には運動性の学習と感覚性の学習があると脳科学者の茂木健一郎はいう。身体性が稀薄な現代の学習は後者に偏りがちだ。後者に偏ると、人は肚で感じることができなくなるし、そのものごっそりからだ全体で受け止めることができなくなる。素晴らしい芸術に出会っても圧倒もされず、芸術的感動も味わえずに、細かいことを云々するだけの口先の皮肉屋になってしまう。
かつて能を観る人々はそこに神々の姿を見ただろう。観能後に人生が変わったとい人もいたに違いない。からだまるごと能と向き合った。
(…)
が、感じることも、神を見ることもできなくなった現代人は「みんな一緒」という「同」信仰を生み出すマスゲームに踊らされるようになる。(…)
信仰と現実とは反比例することがある。信仰が強くなれば、どんなに現実がひどくても「これは神が与えた試練だ」と思うようになる。北京オリンピックの開会式は、「同」とヴァーチャルによる「信仰」の極限を見せてくれた。
北京オリンピックは、四川大地震やチベット暴動の後に開催された。神話的世界から追い出され、現実性、身体性を失った私たちにチャン・イーモウは開会式の場を借りて警告を与えたのだろうか。能を見るときも、私たちは自分の観能態度から自分自身を見つめなおすことができる。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
