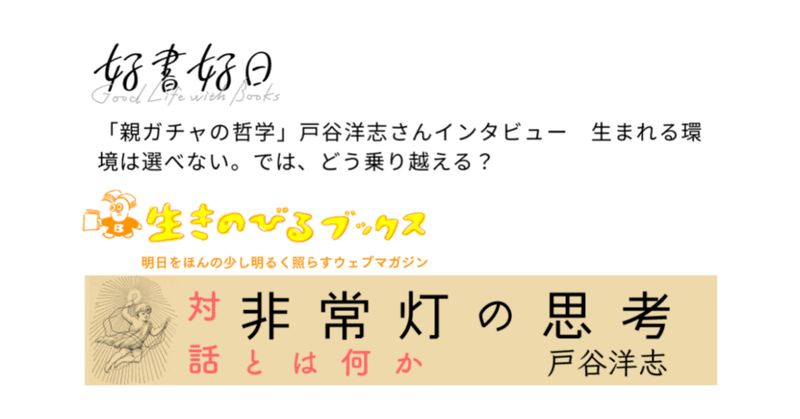
戸谷洋志さんインタビュー「親ガチャの哲学」(好書好日)/戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か 連載第10回 人間の社交性と非社交性」 (生きのびるブックス)
☆mediopos3431 2024.4.9
「親ガチャ」という言葉がある
生まれてきた家庭環境によって
人生の選択肢が大きく制約されてしまうため
自分の人生を変えることはできないと
最初から諦めてしまっている人生観を表している
生きづらいのは親の責任だと考えるのである
その考えに反発し批判する人もいるが
「「親ガチャ」という言葉を語らざるを得ない人々の
生きづらさは一体どこにあるのか」について考え
それを「どう乗り越える」かについて
戸谷洋志は近刊の『親ガチャの哲学』を著したといい
「好書好日」でインタビューが掲載されている
戸谷洋志はその生きづらさを
「親ガチャ的厭世観」と表現している
その厭世観では「自分が生まれてきた環境によって
人生が決まってしまう」ことが想定されていて
自分の人生は意志して選択できないことになっている
つまり「意志と選択の能力を否定する人間観」である
哲学的な議論では
それは「決定論」とされる考え方で
人間に自由意志はないことになる
しかしハイデガーの責任概念でいえば
「責任を行為ではなくて、その存在から説明している」ため
決定論の立場でも責任が生じる
つまり「私が責任を引き受けなければならないのは、
私が私であるから」「人生を引き受けないといけない」という
ごく常識的な考えに近くなるが
人は生まれ持った環境にある程度制約されるが
「人生を自分の人生として生きることはできる」
ということになる
しかしながらだからといって
それを「いわゆる自己責任論」だけでとらえることはできない
「自分の人生に責任を引き受け」ることのできる可能性について
考えていく必要がある
戸谷洋志は「親ガチャ的厭世観」で生きている人にとっては
傾聴や対話の場があることが重要になることを示唆している
ハイデガーは「自分の人生を引き受ける時、
人間関係を断って1人で孤独にならないといけない」
そう考えていたが
それに対して
「むしろ人間は孤独な状況において、
自分自身を引き受けられる余裕を持」てない
「自分自身と向き合うことすらできないほど
力を奪われているし、傷つけられている。
だから、自分自身を引き受けるためには、
むしろ他者とのかかわりが必要」であり
「他者との対話の中で、人間は自分の姿をあらわすと考え」
「自分の言葉を聞いてくれる他者が必要」だとしたのが
ハンナ・アーレントだった
戸谷洋志はその対話の可能性について
「生きのびるブックス」で連載されている記事で論じている
アーレントはハイデガーが賞揚する孤独が
ナチスドイツの全体主義を下支えしていたとし
「対話の機会が奪われれば、
人間の思考もまた停止する」と考えた
アーレントは「人間の存在にとっての対話の価値」を評価し
対話は「人間を周囲に同調させるものではなく、
むしろそうした同調に抗う複数性を持った思考を
可能にするもの」だとしたのだが
対話は同調圧力を生み出す傾向性と
同調圧力を克服する可能性をともにもっている
戸谷洋志はその問題を克服する視点として
カントの『判断力批判』において論じられた
思考の三つの段階をとりあげている
第一段階は「じぶんで考えること」
「偏見から自由な思考様式」である
第二段階は「他のあらゆるひとの立場で考えること」
「視野狭窄から自由な思考様式」である
そして第三段階は
「つねにじぶん自身と一致した考えであること」
第一・第二段階の「結合によって実現する思考」である
カントはこの第三の段階で
「様々な立場から物事を考えることができるのに、
そこに一つの首尾一貫性を与えることができる」
ような思考を求めたのだが
戸谷洋志は「現在、思考する力を発揮できていない人は、
どのようにすれば、思考できるようになるのか、
という問題」を示唆している
カントも楽観的には考えていない
「人間には、集まって社会を形成しようとする傾向」とともに
それに反する「一人になろうとする」「非社交的な傾向」があり
この相反する性質を「非社交的な社交性」と呼んでいるが
そうした「相反する性質の適正なバランス」が必要だというのだ
そこで戸谷洋志は「非社交性と両立するような形で、
対話の場を設計すること」が求められるという
最近よく話題ののぼることのある
「哲学対話」というのもそのひとつだろうが
適切な「対話の場」をどうつくるか
それがもっとも切実でおそらく困難な課題だといえそうだ
「親ガチャ的厭世観」から自由になることは
みずからの「責任」への「意志」が求められることでもあり
それは「思考」以前に「感覚」や「感情」から
変わっていく必要があるからである
それはニンジンがどうしても嫌いな人に
ニンジンを自分から食べるようにする働きかけにも似ている
ウマは自分からニンジンを追いかけるだろうが
ニンジン嫌いはなにがなんでもあらゆる理由をつけて
ニンジンを避けようとするからである
ニンジンを「責任」に置き換えればその困難さは明らかである
■戸谷洋志さんインタビュー「親ガチャの哲学」
「生まれる環境は選べない。では、どう乗り越える?」
(好書好日 2024.04.05)
■戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か
連載第10回 人間の社交性と非社交性」
(「生きのびるブックス」2024.3.27)
**(戸谷洋志さんインタビュー「親ガチャの哲学」より」
*「生まれてきた家庭環境によって人生が変わってしまうことをたとえた言葉「親ガチャ」。2021年には新語・流行語大賞のトップ10に入りました。今もSNSなどでよく使われますが、多くはその不公平を嘆き、時には他者に対して攻撃的な内容も含んでいます。この言葉の流行の背景に「生きづらさ」があると指摘する哲学研究者・戸谷洋志さんは、近著『親ガチャの哲学』(新潮新書)で、その生きづらさを乗り越える方法に哲学的な観点から迫りました。(文:篠原諄也)」
*「親ガチャ的厭世観」の正体は
「――「親ガチャ」に着目した経緯を教えてください。
「親ガチャ」は、2010年代から主にインターネット上で使われていた言葉でした。特にここ数年は非常に広く社会に浸透してきて、何か時代の空気を反映するキーワードになりつつあると思っていました。その一方で、テレビでは著名人が「親ガチャ」という言葉に強く反発を示していました。「親ガチャ」なんて馬鹿らしいとか、親に申し訳ないなどと頭から否定していました。
私はすごく違和感があったんです。人々の生きづらさを反映した「親ガチャ」という言葉が浸透してきている。同時に、それに対してものすごく反発する人も社会の中にいる。このいびつな関係の背後には、何があるのかと思いました。「親ガチャ」という言葉を語らざるを得ない人々の生きづらさは一体どこにあるのか。それを探求したいと思って、この本(『親ガチャの哲学』新潮新書)を書くことになりました。
――そうした生きづらさを本書では「親ガチャ的厭世観」と表現していますね。これはどういうものでしょうか。
生まれてきた家庭環境によって、人生の選択肢が大きく制約されてしまう。だから自分の人生を変えることはできないと最初から諦めてしまっている人生観のことです。自分の人生がすべて決まっているので、何かを成し遂げようとも思わない。成功している人を見たら「生まれた環境が良かったからだろう」と考えてしまう。つまり、親の功績になっている。そうすると、自分の人生を自分ごととして感じられなくなって、あたかも他人ごとのように眺めてしまう。そのように自分自身に対して冷めた眼差しを向けてしまう状態が、この厭世観の内実なのかなと思っています。
――自分の人生がうまくいかないのは、親の責任だと考えるのが「親ガチャ」です。改めて責任とはどのようなものでしょう。
責任は、意志の概念とセットで出てくる概念です。つまり、近代以降の人間観では、人間は自由意志を持っていて自分の行動を自分で選択することができる。その代わり、自分が選択したことに対しては責任を負わなければならないとされます。
例えば、私がペットボトルを手で持ち上げるとしましょう。これは「私がペットボトルを持ち上げるという意志を持って持ち上げた」と説明されます。逆に私はペットボトルを持ち上げないこともできる。その2つの選択肢がある中で、持ち上げるほうを選択しているわけですね。これが意志です。
ペットボトルが持ち上がった原因は、私が持ち上げることを選択したということにしかないわけです。したがって、自分で意志した行為の原因は自分自身にある。行為を起こした人間に責任があるというのが、伝統的な責任概念ですね。
――「親ガチャ」を考える上ではどういうポイントが重要でしょうか。
親ガチャ的厭世観で想定されているのは、自分が生まれてきた環境によって人生が決まってしまうということです。これは言い換えると、自分の人生では意志して選択することができないことになる。だから親ガチャ的厭世観というのは、意志と選択の能力を否定する人間観です。
これは哲学の議論では一般に決定論と呼ばれる考え方です。人間に自由意志などないのであって、すべてがある種の自然法則に従って決められていると考える。(・・・)
もしそのように考えるとしたら、自分では意志に基づいて行為していると思っていることであっても、実は自然法則にしたがって最初から決定されている行為となる。意志や選択という概念自体が、実は人間の幻想に過ぎないと考える。それが決定論の基本的な立場になります。そうすると、責任を否定しないといけなくなりますね。なぜかというと、私の行為に先行する原因がさらにあるからです。」
*「自暴自棄に陥るのは間違っている
――しかし、マルティン・ハイデガー(ドイツの哲学者)の責任概念を参考にすると、決定論の立場でも責任が生じるとのことですが。
ハイデガーは責任を行為ではなくて、その存在から説明しているんです。つまり私が責任を引き受けなければならないのは、私が私であるからだといいます。ハイデガーは決定論的な行為の連関、つまり自然現象の連鎖の一つとして私が何かをすることが仮に正しいのだとしても、それでも人間は責任の主体でありうる可能性があるんだというんです。
例えば今日(2024年2月27日)、私がペットボトルを持ち上げることは、決定論の立場で考えると、宇宙が始まった瞬間から決まっている。しかし、今日このペットボトルを持ち上げた人間が私であるということは、決して説明できないのだとハイデガーは考えます。つまり、私たちはある自然現象の連鎖の中で生まれてくるし、もしかすると決定論的に何もかも行為が決められている世界に生まれてくるかもしれない。しかし、その生まれてきた人物に私がなったということは、つまりその人物として私が生まれてきたということは、説明がつかないんだと。
そうだとすると、私の行為に対して私は何も意志していないかもしれない。しかし、その人間に私がなっていることには何の理由もなくて、それ以上遡れる原因がないんですよね。とにかく、なぜか私は私なんです。だから、私は人生を引き受けないといけないというんですね。
――「親ガチャ」を捉える上でどのような示唆があるでしょうか。
人は生まれてきた家庭環境によって、人生の選択肢がある程度制約されるのは否定できないことです。ただ、そこで自分の人生は何も変えられないんだ、自分の人生として引き受けることは無意味だと、自暴自棄に陥るのは間違っていると思っています。
たとえ生まれてきた環境によって制約があるのだとしても、その人生を自分の人生として生きることはできるはずです。その確信を持つことで、自分の人生を大切にできるようになる。何か暴力に誘惑されても、それに対抗できる自己配慮や自己肯定感を持つことができる。そのように自分を引き受けるためには、いわゆる自己責任論とは違う形で、自分の人生に責任を引き受けられないといけない。その可能性を、ハイデガーを手がかりに考えました。
*「他者と対話する機会を
――また、社会において「親ガチャ的厭世観」で苦しむ人が救われるためには、傾聴や対話の場があることが重要だと戸谷さんは指摘していました。
実はハイデガーの哲学には少し問題があるんです。自分の人生を引き受ける時、人間関係を断って1人で孤独にならないといけないと考えていました。しかし、私はその部分についてはハイデガーが間違ってると思っています。むしろ人間は孤独な状況において、自分自身を引き受けられる余裕を持てません。
とりわけ「親ガチャ的厭世観」を持って苦しんでいる人々は、自分自身と向き合うことすらできないほど力を奪われているし、傷つけられている。だから、自分自身を引き受けるためには、むしろ他者とのかかわりが必要なんです。自分の言葉を受け止めてくれる誰かがいるという信頼が必要だと思います。
そのようにハイデガーを批判した哲学者がハンナ・アーレントでした。ハイデガーは、孤独の中で人間の本来性を取り戻すと考えましたが、アーレントは他者との対話の中で、人間は自分の姿をあらわすと考えました。つまり私達は1人でいると、自分が何者であるかわからない。しかし、人前で何かを語る時に、初めてその人が誰であるかが明らかになってくるというんですね。自分の言葉を聞いてくれる他者が必要であると。
――どういう場所だと良いでしょうか?
アーレントの議論は政治的なディスカッションの場を想定していましたが、私は対話が行われるのはささやかでプライベートな場所でもいいと思います。現代社会では、地縁や血縁に根ざした伝統的でクローズドなコミュニティーはどんどんなくなっています。マンションで隣の部屋の人の顔を知らないことも当たり前ですよね。
(・・・)
もちろん哲学に限らず、趣味について語り合う場もいいですね。カフェで友達と対話するだけでも、自分自身を見つめ直すきっかけとなる。そのように人々が対話をする空間が、いろんなところに作られていくことが大事だと思っています。」
***********
**(戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か 連載第10回 人間の社交性と非社交性」より)
*「本連載はこれまで、対話に関するハイデガーとアーレントの思想を概観してきた。両者は、対話をまったく違ったものとして捉えていた。改めて、その違いを簡単に整理すれば、次のようになるだろう。
ハイデガーは対話をある種の雑談として捉えていた。それは、人間に対して空気を読むことを要求するものであり、いつの間にか人間を周囲に同調させるものである。彼の哲学の枠組みのなかで、それは自分の本来のあり方を忘れること、つまり非本来性に陥ることを意味する。それに対して、本来性の回復としての先駆的決意性は、他者との繋がりを絶った孤独のなかで発揮されなければならない。総じてハイデガーは対話について消極的な評価を下している。
一方、アーレントは、そうしたハイデガーの哲学における孤独の賞揚が、ナチスドイツの全体主義を下支えしていた、と指摘する。彼女にとって対話とは、決して人間を周囲に同調させるものではなく、むしろそうした同調に抗う複数性を持った思考を可能にするものである。思考は対話に基づいているのであり、もしも対話の機会が奪われれば、人間の思考もまた停止する。そして、彼女の考える対話とは、あくまでも友情に根差したものに他ならない。このことから、彼女は人間の存在にとっての対話の価値を、高く評価している、と言えるだろう。
ある種の対話は、同調圧力を生み出す。これは、一面において事実であると思える。しかし、また別の仕方で行われる対話は、そうした同調圧力を克服する可能性を、人間に開くものでもある。ではその違いはどこにあるのだろうか。私たちは、どんな風に他者と対話すると同調圧力を生じさせ、どんな風に対話するとそれを乗り越えられるのだろうか。
この問題を考えるために、今回から数回にわたって、近代ドイツの哲学者イマヌエル・カントの思想を検討しよう。」
*「カントは、人間が十分に思考できるようになるためには、他者との対話が必要である、と考える。この点においてカントの発想はアーレントに似ている。では、そもそも彼にとって、思考するということはどのような営みなのだろうか。
カントは『判断力批判』のなかで、思考を次のような三つの段階に区別して説明している。
1 じぶんで考えること
2 他のあらゆるひとの立場で考えること
3 つねにじぶん自身と一致した考えであること1
順に見ていこう。
*「第一の段階、「じぶんで考えること」は、「偏見から自由な思考様式」を指している。私たちは、世間で言われていること、親や教師など、権威を持つ者から教えられたことを、鵜呑みにしてしまう傾向がある。しかし、その内容が正しいかどうかを自分で検証していないなら、そうした知識はただの偏見である。そして、偏見に留まる限り、他者から与えられた知識に支配されるため、受動的な状態に置かれることになる。
しかし、権威を持つ者から教えられたことの正しさを、自分の力で検証するなら、そのようにして得られた知識は偏見ではない。また、そうやって知識に向かい合うとき、私たちは能動的な態度を取ることになる。これが、カントの考える「じぶんで考えること」である。」
*「これに対して第二の段階「他のあらゆるひとの立場で考えること」は、言うなれば視野狭窄から自由な思考様式である。たしかに、「私」は物事を自分で考えることができる。しかし、それが「私」一人の視野から生まれた思考であれば、その思考は依然として限定されている。もちろん、思考が制限されているということは、それが不合理であることを意味するわけではない。自分で思考できるなら、そこから合理的な答えを見つけ出すことはできるだろう。とはいえ、合理性が一つしかないわけではない。ある物事に対する合理的な考え方には、複数のパターンがありえるのだ。
自分の立場からしか思考しない人は、そのように複数ありえる合理的な答えのうち、一つしか知ることができない。それ以外の答えの可能性には、辿り着くことができない。しかし、そのように自分の立場から導き出された答えが、様々な答えの可能性のうち、もっとも適切なものであるという保証はない。それに対して、もっとも適切な答えに到達するためには、自分以外の立場からも物事を考えることができなければならないのだ。
カントは、このように、他者の立場を取り入れた思考の仕方を、「拡張された思考様式」と呼ぶ。それは、「判断の主観的な個人的条件を抜け出すことができ、普遍的立場(この立場を、その者がかろうじて定めることができるのは、他者たちの立場に身を置き入れることによってである)にもとづいて、じぶん自身の判断をめぐって反省する」ような、思考に他ならない。言い換えるなら、「他のあらゆるひとの立場で考えること」とは、自分が思考したことを、他者の立場から見つめて反省すること、再び思考し直すことである、と考えられる。
*「第三の段階、すなわち「つねにじぶん自身と一致した考えであること」は、「じぶんで考えること」と「他のあらゆるひとの立場で考えること」の結合によって実現する思考のあり方である。そのため、それは「達成するのにもっとも困難な準則」である。カントは、この第三の思考様式について、あまり多くを説明していないが、さしあたり、その内実は次のように解釈することができるだろう。
私たちは、自分自身と不一致の状態で物事を考えることがありえる。それは、前に言ったことと、後で言ったことが、違うということである。つまり、ある状況と、別の状況で、考え方が一貫していない、ということだ。しかし、私たちはどのような状況においても、ある一つの首尾一貫した思考に基づいて、物事を考えることができなければならない。この意味において、この第三の思考様式は、時間的な性格を帯びている。
カントによれば、この思考様式は、「前二者の思考様式を結合することによってのみ、またそのふたつの思考様式に熟達するまで繰り返し遵守したのちに、はじめて到達しうるもの」である。つまりそれは、様々な立場から自分自身で思考することによって獲得されるものなのだ。様々な立場から考えるということは、その度ごとに別の立場から考えることもできてしまう、ということである。それぞれの状況において最適な考え方を選択していけば、そのような状態に陥りうることは容易に想像できる。しかしそれは、時間的に俯瞰すれば、場当たり的で首尾一貫していない思考とも言える。
第三の思考様式は、このような事態に抵抗するものである。すなわち、様々な立場から物事を考えることができるのに、そこに一つの首尾一貫性を与えることができる、という思考の仕方なのだ。」
*「カントの思考概念の基礎は、思考を偏見からの自由として捉える、という点にあるだろう。偏見とは、与えられた知識への依存である。それを自らの力で吟味することを重視する彼は、思考の特徴をその能動性と自律性のうちに見ていた。こうした傾向は、カントの他の著作においても一貫している。
(・・・)
カントによれば、啓蒙とは「未成年の状態」を脱出することだ。未成年の状態とは、すなわち、自分で物事を考えることができず、思考を他者に委ねることである。自分の代わりに誰かに考えてもらう状態と言ってもいいだろう。なぜ、未成年状態の人は、思考を他者に委ねるのだろうか。思考する力をそもそも持たないからだろうか。カントによれば、そうではない。なぜなら人間は誰でも思考する力を、つまり「理性」を持っているからだ。むしろ、未成年状態の人は、自分で思考する「勇気」を持てないのである。したがって、未成年状態の人を啓蒙するということは、そうした人に思考する勇気を抱かせる、そしてその勇気を発揮させる、ということを意味するのである。
ここには、すべての人間には思考する力が備わっている、というカントの基本的な信念が示されている。しかし、ここで疑問がわきあがる。現在、思考する力を発揮できていない人は、どのようにすれば、思考できるようになるのか、という問題だ。
極めて素朴に考えれば、いま思考する力を発揮していない人は、そもそもその必要を感じていない。そうした人には、思考することの必要性を説いたり、あるいは思考することを強制したりすればよいのだろうか。しかし、強制されて思考することは、結局はそのように強制してくる他者がいなければ思考しない、ということであり、啓蒙の条件である自律的な思考とは呼び難い。思考を強制されることは、依然として、他者に依存した状態にあるのであり、厳密に言えばそれは思考していることにはならないのだ。
(・・・)
では、現在思考する力を発揮していない人は、その力をただ潜在的に有しているだけで、結局はずっと発揮できないのだろうか。もちろん、カントはそうではないと考える。ではいったいどのようにすれば、もともと思考する必要性を感じていない人が、自ら思考するようになるのだろうか。
カントが提案するのは、人間が自ら思考したいと思うような状況を、意図的に設計することである。彼は、『実践理性批判』のなかで、「人間の理性には、提示された実践的な問題に、きわめて微細な吟味を加えることを好む性向がある」と指摘し、それを未成年状態にある人の教育に活用するべきである、と主張する。人間は、ある種の状況に置かれれば、自ら「思考したい」という欲求を抱くようになる。この欲求に駆られて思考が始まるなら、それはあくまでも自律的な営みであり、真に思考と呼ぶに値するものだろう。」
*「私たちは、考えなければならないから、考えるのではない。考えたいから、考えるのだ。そして、「考えたい」という意志を触発するものこそ、他者との対話に他ならない。それが、思考と対話の関係をめぐる、カントの基本的な考え方である。
人間には、思考したいという欲求がある。そしてその欲求は議論の場において開花する。それなら、話は簡単だ。人々に無限に議論させればよい。気が済むまで対話させればよい。それで人間はどんどん思慮深くなり、どこまでも啓蒙されていく。ここまでの考察を総合すれば、そうした結論が見えてくる。
ところが、カントはそのように楽観的ではない。
カントによれば、「人間には、集まって社会を形成しようとする傾向が備わっている」。そうした傾向が、議論への参加を動機づけ、対話したいという気持ちを促すのだろう。そのように「社会を形成してこそ、自分が人間であることを、そして自分の自然な素質が発展していくことを感じる」ことができる。この意味において人間はその本質において社交的である、と言える。
しかし、人間にはこれと相反する性質もまた備わっている。すなわちそれは、「一人になろうとする傾向」であり、「孤立しようとする傾向」であって、「すべてを自分の意のままに処分しようとする非社交的な傾向」に他ならない。カントは、人間に備わるこの相反する性質を、「非社交的な社交性」と呼ぶ。」
*「非社交的社交性は、社交性と非社交性という、相反する性質の適正なバランスを要求する。どちらが欠けても、私たちは人間らしい生活を営むことができない。私たちは、仲間と協調しようとしながらも、同時にその仲間よりも優れた存在でありたいと思う。それは人間が、仲間との関係性のなかで自己実現しながら、同時に仲間と切磋琢磨することで自らを成長させるからだ。
対話に関するカントの思想は、こうした人間の相反する性質を前提として展開される。すなわち人間は、一方において、他者との対話を自ら求める。しかし、他方で、対話することを忌避しもする。彼にとって、対話は楽しいものであると同時に、苦痛でもあるのだ。」
*「カントは思考を、自分の立場を逃れ、他者の立場から物事を考えることと捉えていた。しかし、知識のひけらかしや自慢合戦に陥った対話は、思考を自分の立場へと固着させ、他者の立場への視野を閉ざすことになる。それはむしろ思考を妨げる。人間の非社交性は思考を閉塞させるのだ。
そうであるとしたら、私たちは、人間には思考することを望む意志が備わっている、などという楽観的な洞察に居座るべきではないだろう。たとえそれが真実だとしても、人間には思考することを拒否し、知識をひけらかしたり自慢したりすることで、対話を破壊しようとする傾向も備わっている、ということも言わなければならないだろう。人間にはその両面が存在するのだ。
カントは、人間の非社交的な社交性を肯定する。同時に、人間はあくまでも啓蒙されるべきであり、自律的に思考するべきである。そうである以上、たとえ人間の非社交性を認めざるをえないのであったとしても、知識のひけらかしや自慢によって対話を破壊することは、避けるべきなのだ。そしてその上、人間から非社交性が解消されることはないだろうし、それはむしろ人間にとって有害ですらある。
このように考えるとき、思考と対話の望ましい関係を作り上げるために、残されている可能性は一つである。それは、非社交性と両立するような形で、対話の場を設計することだ。人間が、他者と議論したり対話したりすることを面倒に感じ、隙あらば知識をひけらかしたり自慢したりする存在であることを前提にしながら、それでも健全に機能する対話のスタイルを、考案することだ。それが、人間を啓蒙し、自律的な思考を促進するためには求められるのである。」
□戸谷洋志(とや・ひろし)
1988年、東京都生まれ。立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授。専門は哲学・倫理学。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。『ハンス・ヨナス 未来への責任 やがて来たる子どもたちのための倫理学』『未来倫理』『友情を哲学する 七人の哲学者たちの友情観』など著書多数。
□篠原諄也(しのはらじゅんや)
ライター。本にまつわる記事(著者インタビュー、書評など)を執筆。1990年、長崎生まれ。
■戸谷洋志さんインタビュー「親ガチャの哲学」
「生まれる環境は選べない。では、どう乗り越える?」
(好書好日 2024.04.05)
■戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か
連載第10回 人間の社交性と非社交性」
(「生きのびるブックス」2024.3.27)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
