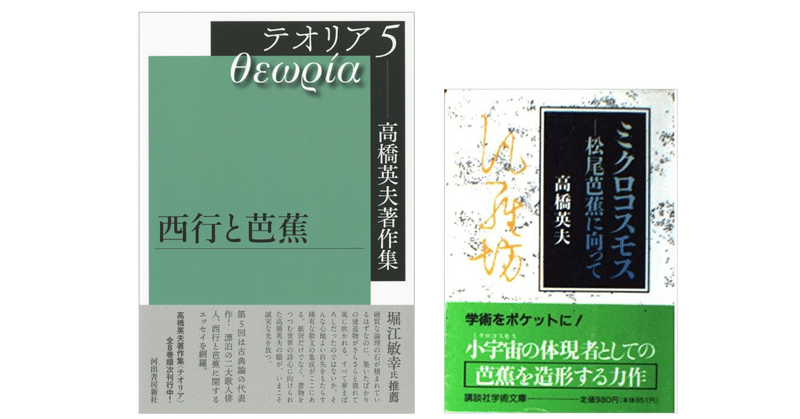
『高橋英夫著作集 テオリア5 西行と芭蕉』/高橋 英夫『ミクロコスモス・松尾芭蕉に向って』
☆mediopos2649 2022.2.16
高橋英夫著作集の第五巻目は
西行と芭蕉である
(2冊分が収められている)
芭蕉が1989年(文庫は1992年)
西行(岩波新書)が1993年なので
ほぼ30年ぶりの邂逅になる
今回はとくに印象に残っている
芭蕉をとりあげてみることにした
(全十二章からそれぞれ少しずつ引用している)
高橋英夫はほぼ芭蕉の亡くなった年齢になって
この芭蕉についての著作を刊行しているが
みずからを芭蕉に寄り添わせながら
書き進めていったのではないかと思われる
ぼく個人でいえばずっと若い頃最初に
そして今度は二人の年をこえて
こうして読む機会をもつことになったが
やはり「月日は百代の過客にして、
行かふ年も又旅人」である
じぶんの過去と今を往還しながら
本書での12の「変奏」を追ってみることにする
まず「ミクロコスモス」
ミクロコスモスは
「行く」が「帰る」に
風雅が俗に対応するように
マクロコスモスと照応する
そんな世界を芭蕉は俳句としてとらえている
つづいて「自己引用」
芭蕉はみずからの内部から
もうひとつの自己をとりだし
自己引用者というかたちで照応させる
また芭蕉は「風羅坊」という
「ほとんど剥き出しに近い小宇宙として」
みずからをとらえ
そこから世界をとらえている
芭蕉は俗を去り「隠」を求めもするが
連句を巻くために一つの場に立ち
またその場を後にするように
「隠」と「顕」とは
メビウスの輪のように連鎖している
それは「翁」の遊行でもあるように
「隠」に入りふたたび「隠」を出る
「隠者的往還の歩み」でもあり
「旅」することで
「死」と「再生」を繰り返すことでもあった
芭蕉は俳句を「流れゆく知」としてとらえる
俳句の作法はすみやかに成り
すみやかに変化するものなのだ
そんななかで芭蕉は晩年になって
「軽み」を唱える
それは「決して一つのところになずみ、滞らないという、
一期一会の知の中に遠い根をおろした」ものだ
その意味で俳諧全体は「非局所的」であり
「花の座、月の座、恋の座」といった局所のトポスを
自在につなぐ「風のトポス」を必要とする
芭蕉は神秘家のごとく
ミクロコスモスやマクロコスモスの極へと
みずからを収斂させようとはしない
あくまでも「俳諧という詩の永遠化」のために
「旅を空間化し、言語化」し
「物の見えたるひかり」を俳諧として表現する
以上が『ミクロコスモス―松尾芭蕉に向って』 を
かなり強引に辿ってみたところだが
芭蕉が死にあたって作られた
「旅に病で夢は枯野をかけ廻る」という句がある
おそらくこの句で芭蕉は
死へとみずからを向かわせているのではなさそうだ
そこでも「隠」と「顕」
そして生と死を往還しながら
俳句というミクロコスモスのなかに
「ひかり」を見ているのではないだろうか
■『高橋英夫著作集 テオリア5 西行と芭蕉』
(河出書房新社 2022/1)
■高橋 英夫『ミクロコスモス―松尾芭蕉に向って』
(講談社学術文庫 講談社 1992/5)
(「あとがき」より)
「「ミクロコスモス」 − 「隠」 − 「老い」 − 「知」 − 「風」 − 「光」 − 「ミクロコスモス」という具合にキー・ワードの設定、競合、連接、切断、旋回の試みを十二回変奏しつつ進行したこの仕事は、私の意図では芭蕉についての想像力批評の試みである。」
「時に言葉を断たれる苦しさを味わった芭蕉だが、その時でも胸の内に湧き立つ思いはあったに違いない。それを思考の経路に導いて再考すること、また連鎖的流動体・連句の形で示された芭蕉の様式的生命体にクリティカルにもレトリカルにも並行し伴走すること、私がやってのはそれだったと言える。」
(「第一章 ミクロコスモス」より)
「芭蕉が実現したのは小なるものの世界、ミクロコスモスである。しかしミクロコスモスは、それと対応している筈の大なるもの、マクロコスモスとの相関においてはじめて活きた存在となる。(・・・)「行く」が「帰る」に対応し、風雅が俗に対応するように、小なるものは大なるものと対応する。対応すべきである。小それ自体は何ものでもないのだ。ただしこの対応関係の奥深さを保証しうるためには、まず第一段階において、小なるものをどれほど明確に見出しうるか否かが問題である。芭蕉の世界の成立いんは、アイロニーの介在を否定することはできない。」
(「第二章 自己引用の振幅」より)
「ミクロコスモスという概念には種々の含みがある。この概念の外延を少しずつ押し拡げてゆけば、ミクロコスモスとしての芭蕉を確かめることができるが、そうして得られる視点は、隠者、旅人としての芭蕉の映像にも届くものである筈だ。大と小は一つの出発点にすぎず、俳諧師である隠者の外形をしたミクロコスモスが、世界というマクロコスモスにいかに向きあったのかこそが問われるべき深奥であるにちがいない。
最小の詩型としての俳句は、内容的に天地の大と対応しているだけでなく、形式的にはたとえば『おくの細道』のそれぞれの段落の集約的対応物として、大に対する小を形づくってもいた。この形式的・内容的対応関係を、文学史の中で先鋭化した頂点におそらく芭蕉は立っていた。しかしここで付け加えて附け加えて言いたいのは、芭蕉が頂点に達するについては自己引用が小さくはないはたらきをしたであろう、ということである。自らの内部から、もう一つの自己を取り出し、切り離すこと、この方法によって大世界と小世界の対応が形を帯びて見えてきたのである。自己の内部かた取り出されたものは、もとより自己とは同質であり、これがマクロコスモスとミクロコスモスを関連づける原理となった。そうした見地に立つなら、ミクロコスモスの人芭蕉を自己引用者という規定からさらに、自己発見者というふうに言い換えてゆくことができる。」
(「第三章 風羅坊の実存」より)
「郷里伊賀から近畿地方を経て須磨までの旅を書き記した紀行文『笈の小文』の冒頭に、興味深い表現とイメージがあらわれる。これは、ほとんど剥き出しに近い小宇宙としての芭蕉自身に他ならない。
百骸九竅の中に物有。かりに名付けて風羅坊といふ。誠にうすものゝかぜに破れやすからん事をいふにはあらむ。かれ狂句を好こと久し。終に生涯のはかりごとゝなす。
冒頭の「百骸九竅」とは百の(多数の)骨と九つの穴を意味し、人体を形づくる要素であるが、そこらからこの表現は人体そのものをさしている。」
「芭蕉の句には「風羅坊」にしてはじめて捉ええたみごとな対比があった。そこには小なるものの名人芭蕉が大世界に視線の届く人でありえた照応の秘儀もこめられていた。」
(「第四章 「隠」に入り、「隠」を出ず」より)
「『おくの細道』それ自体を、連鎖上をなした連句に見立てることが行われているが、私もそれに同感である。旅することと連句を巻くこととは、芭蕉にとって心理的にも生理的にも、同一の律動、波長に己れを預けることにほかならなかった。彼を旅路に誘ったものと連句興行に赴かせたものとは共通性を帯びていた。共通性とは、到着して一つの場に立ち、やがて立ってその場をあとに出発するという流れであり、そこに私は「隠」と「顕」のメビウスの輪の連鎖を重ねて見るのである。」
「「隠」は(・・・)人界に時として立ち寄ることも、再度世俗にまみれることをさえ恐れないし、厭わない。逆接として言えば、ふたたびこの世に、人の世に立ち還れないような「隠」は、真の「隠」ではないのである。」
(「第五章 翁の遊行」より)
「「翁」の沈黙は、老いの時間の中を、刻一刻と最終のとき「死」に向かって歩みつづける人間の暗さの結果でもありながら、多分「知」の探索行が人間に要請する不可避な沈黙の結果である。「翁」芭蕉を旅する隠者、遊行する隠者とした私の規定は、芭蕉の携ったのが俳諧という「知」であったことを機縁として、その見えては来ない裏面の沈黙まで及ぶべきである。『おくの細道』をはじめとする紀行文、あまたの俳文、主だった弟子たちの俳論から、ほとんど一頁ごとに浮かび出てくる「翁」の遊行は、「隠」に入り、ふたたび「隠」を出る隠者的往還の歩みに縒り合わされるべきである。」
(「第六章 死のくぐりぬけ」より)
「老隠者の旅は再生を夢み、追い求めるさすらいだった。だが再生といっても、不老不死が思いえがかれていたのではない。芭蕉の肉体が露出させた老人様式は、「死」を通じて再生にいたり、再生をくりかえして最後の場所に達しようとする敢行と連れ立っていた。現実のすがたとしては一人の弟子曽良と二人づれであった老隠者は、我が胸の底には老若の二様式を畳みこんでいた。」
(「第七章 「行きて帰る心」」より)
「 師のいはく、学ぶ事はつねに有。席の望て文台と我と間に髪をいれず。思ふ事速に云出て、爰に至て迷ふ念なし。文台引おろせば即反故也と、きびしく示さるゝ詞もあり。
『三冊子』(「赤さうし」)の余りにも有名なこの一節は俳諧の作法を語りながら、俳諧に託された芭蕉の知のきびしい成立条件を自ずと洩していると読んでゆきたい。知はすみやかに成り、すみやかに変化する。文台から引き下げられてしまえば、反故の中に知もまた埋もれてゆく。しかしいかなる原因からか、埋没を免れた知がある。この知は、すみやかに立ち去ってゆき、次なる形を、次なる場を求める。俳諧、それは開かれた知でも閉ざされた知でもなく、流れゆく知であった。「行きて帰る」形を螺旋状にくりのべながら、旅路をさすらいつづける知というものであった。」
(「第八章 一期一会の知者」より)
「最晩年に芭蕉は「軽み」を唱え、自らその試みに辛苦しただけでなく、弟子たちに送った書簡の中でも、何度も「軽み」を説いている。晩年にいたって生じた作風の変化としてそれは理解されている。武学的にはそういうふうに受けとらなければならないが、「軽み」はそれとともに、つねに出立を志し、決して一つのところになずみ、滞らないという、一期一会の知の中に遠い根をおろした、芭蕉の認識のあらわれでもあっただろう、と私は感ずる。停滞と拘泥は「知」ではないのである。死の年、元禄七年の書簡では、何かに憑かれたように「軽み」のすすめがくりかえされている。」
(「第九章 生命の「軽み」」より)
「芭蕉は『おくの細道』の旅の肉体的記憶にたゆたっているうちに、生命そのものとしてひたぶるに「軽み」である−−ひたぶるに問い、ひたぶるに応答する−−連鎖形体というものに気付いただろう、と想像する。それは変化に身をゆだねることだ。芭蕉がうつしみの長旅の重さ、深さを心になお重くもちこたえながら、重さと訣別した「軽み」それ自体に開悟してゆく経緯がその中にはふくまれていた。」
(「第十章 風のトポス」より)
「俳諧は花の座、月の座、恋の座と定型的なトポスをいくつも設置した連鎖体共同制作詩である。だが人が人と相接し、志を共にして事を行うとき、志の中に秘められた唯一性と人間同士の形づくる多元性をつなぐ装置が必要だった。それが伝統様式の発展の線に沿って花や月や恋のトポスという形をとる。とはいえ俳諧の全体は、非局所的に風のトポスとなっている、そうも見られるだろう。風の「座」などは存在しない。だからこそどこで、どの時刻に風が吹いてもよい、吹かずともよい、ともあれ風雅としての本性を手放しさえしなければよいのだ。この「非局所的」という特色が、「風」を一層自在たらしめている。片方の局に厳重な形式が集っているとき、対極に結集しうる自在さの質がいかなるものであるかによって事は決まる。「風」は人間とものと存在(総体)のあいだを吹いて、変幻を喚び出した。芭蕉という人間は、自らが風となって関所を超え、もう一つの世界に踏み込んでいった。ものたちは木の葉のように舞ったり、一カ所に寄り集まったりしながら、しだいにトポスを形成するさまに整序していった。そういう整序も結局は個別性であり、局所的であると見えてきたとき、個別を否定するのでなく個別に対応し、局所を解体するのでなく無限へ向かって穴をうがつというふうにして、総体的なものがあらわれる。」
(「第十一章 「物の見えたるひかり」より)
「『三冊子』では、物から光がさしたと思ったその瞬間に、いささかの遅延もなしに「いひとむ」、すなわちひたと俳諧の言葉に定着してしまうのでなければならぬ、と語られていた。そのものが顕れ出る最高の一瞬というものがある。それが光のさす一瞬であり、そのときをのがしたら光はただちに掻き消える。気比明神での「月清し遊行のもてる砂の上」の一句は、さながら、光のさした砂の色合いや明暗を定着したかの観がある。捧げもって神殿に供えられようとしている、月光をうけた砂は「物の見えたるひかり」をそのまま凍結したようでもある。というより、それはかりそめの凍結ではなくて、俳諧という詩の永遠化といってもいいのではないか。何にもせよ、この地で芭蕉はかくの如く「物の見えたるひかり」を捉えたのである。」
(「第十二章 言語空間の旅人」より)
「ミクロコスモスとはむしろ意識の一点、知覚の一点という感覚から発して求められた存在の自己確認である。いま自分は一点として在るに至ったのだという自覚を抜きにしては、ミクロコスモスはありえない。そう考えたとき、芭蕉にとって先人たちとの同行は、ミクロコスモスの自由と不自由の両側面が、抜きさしならず絡まった生の燃焼であったと見えてくる。」
「大宇宙であり大世界である天地の間という場において、一個のミクロコスモスとして在ろうと決意したとき、芭蕉は二つのものを拒んだ。少なくともその二者に、同化吸収されることからは離れていったといえる。巨大な無、本質的な無なるものに吸収され、その奥に封じ込められてしまうことは、ミクロコスモスとしての存在喪失にほかならなかった。無の至近距離までは赴いたとしても、過程の最終団塊は無からの反転、無からの回帰である以外はない旅路を、芭蕉は生の習いとして身につけてしまったのである。当然これは涯の涯という観念の虚是湯をも意味している。究極という観念は芭蕉のものではなかった。世の涯まで趣、人外境に足を踏み入れた雰囲気の欠如はそれに起因している。ただしこれは究極という観念の欠如という意味に限定される。芭蕉の実存に究極的様相が出現しなかったわけではない。隠に入っては出、旅路においては出立しては到達し、生と死を循環ならしめた芭蕉には、はてもなく歩むことが究極体であって、そこは至福の距離なのか至近の地なのかすでに判然とはしていないのである。
(・・・)
ミクロコスモスとしての存在を選ぶというのは、広漠とした拡がりの中に消滅してしまわないためであった、と見たほうが正しいかもしれないのだ。ミクロコスモス芭蕉の二律背反である。
「紀行『おくの細道』が劃定したのは空間である。言うまでもなくそれは言語空間である。ただちに分かるように、この空間は正確に分節されていた。一単位ごとに出立と到着が組み合わされているだけでなく、ほとんど一節ごとに旅路の辛苦や展開する風景の叙述と、それをしめくくり、収束する句とが組み合わされていた。」
「現実の旅はどうではなかったにちがいないとは誰にでも分かる。旅を空間化し、言語化し切ったとき、芭蕉は一単位ごとの記述と結びの句という対の様式を自ら獲得した。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
