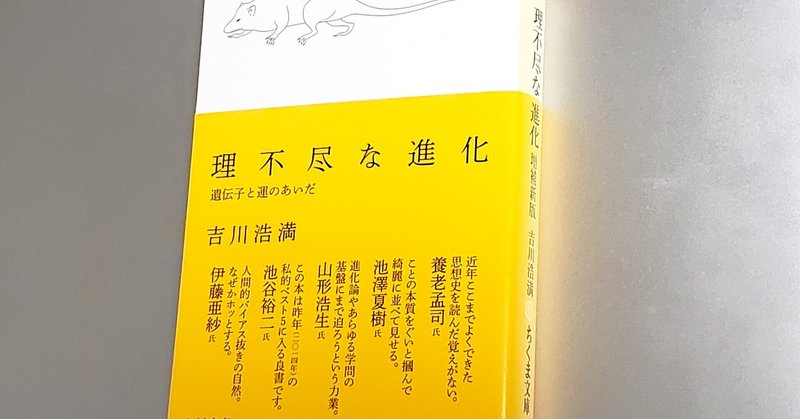
吉川浩満『理不尽な進化/遺伝子と運のあいだ』
☆mediopos-2381 2021.5.24
地球上にあらわれた生物種のうち
九九・九パーセントが絶滅してきたという事実から
本書は論じられはじめる
そして絶滅には
運が悪くて絶滅したもの
適応できずに絶滅したもの
適応するための状況が
運が悪くて激変したために絶滅したもの
という三つの絶滅のシナリオがあり
もっとも重要なのが
ひとつめとふたつめが複雑に組み合わさった
三つめのシナリオだという
小惑星が地球に落下したことで
恐竜たちが絶滅することになったシナリオは
その三つ目にあたる
かつて恐竜たちは適者生存して繁栄を謳歌していたが
その生存環境そのものが激変したために
不運にもそれまでの適者だった存在は
環境の変化が適応可能な範囲を超えてしまい
新たな環境では生存できなくなったしまったのだ
そして理由はさまざまにあるとしても
現在生き残っている生物種は〇・〇一パーセントでしかない
「いま私たちが目にすることができる生物の多様性も、
こうした理不尽な歴史の産物」であり
いま生き残っている生物のもまたやがてほとんどが絶滅してしまう
本書はその「絶滅」という観点から「進化論」を論じる
絶滅から説かれる進化論はとてもユニークで面白いのだが
おそらく本書を読み進めることで重要なのは
こうした視点から
「日常生活の重要問題、自分の生活や他人の生活や俗世間、
つまり私たちの世界と人生の問題」を
切り離さないことだと思われる
とはいえわたしたちは「進化」という言葉を
さまざまな科学的議論のなされている「進化生物学」とは
ずいぶん異なった状況でさまざまにそして便利に使い
ときにひどく政治的社会的な問題に
それをきわめて恣意的に用いたりもする
それらは学問的に議論されるような「進化」の問題ではない
けれども「なぜ絶滅したのか」という問いを
状況はさまざまに異なっているとはいえ
「適応できなかったからだ」で論じられることだけからでは
私たちの生きた生の問題にはつながらないし
学問領域でそれを扱うことはできない
いわゆる「科学では説明できない」領域だからだ
これはどこか心理療法的な問題ともつながるのだが
自然を科学的に記述する観点からは
自然のなかで起こったことは
そこに運不運という概念がでてくることはない
それはきわめて人間的な事情でもあるからである
しかし私たちはたとえば災害で亡くなってしまうことを
理不尽なことだとして受けとる
科学は「なぜ亡くなったか」の説明に
事象の説明の言葉しか持っていない
「なぜあの人は死んで私は生きているのか」に
科学はまったく関わることはないのだ
だからといって科学を「進化生物学」を学ぶことに
意味がないわけではないと著者は言う
説明可能なことは説明を尽くしながら
説明の難しさから逃避することない態度が
おそらくはもっとも重要なことなのだろう
昨今のコロナウイルスの問題にしても
コロナウイルスそのものの説明が足りない
それがいったいどういう存在なのか
いまだに議論が尽くされているとは到底いえない
そういう状態のまま執拗に検査がなされたり
副反応の危険性があいまいにされときに隠蔽されたり
他のさまざまなリスクとの比較検討も極めて少ない
そうした状況が続いている
そうした問題は
進化論が誤適用される問題と似ている
「事実の解明と説明の努力によって作り話を回避」し
「あらゆる可能な説明を尽くして、
これ以上によい説明は不可能だという地点まで進むこと」が
要らぬ不安や適正なリスクの回避に
つながっていくはずなのだが
現状はまるで見えないお化けと闘っている
ヴァーチャル・ゲームのようだ
■吉川浩満
『理不尽な進化/遺伝子と運のあいだ』
(ちくま文庫 2021.4)
「私たちはふつう、生物の進化を生き残りの観点から見ている。進化論は、競争を勝ち抜いて生存と繁殖に成功する者、すなわち適者の条件を問う。そうすることで、生き物たちがどのように姿形や行動を変化させてきたかを説明する。そこで描かれる生物の歴史は、紆余曲折はあれどサクセスストーリーの歴史だ。
しかし、本書は、それとは逆に、絶滅という観点から生物の歴史をとらえかえしてみようと提案する。敗者の側から見た失敗の歴史、日の当たらない裏街道の歴史を覗いてみるのである。
どうしてそんなことをするのか。生物の世界では、生き残りという表街道よりも、絶滅という裏街道のほうが、じつはずっと広いからだ。生物の歴史が教えるのは、これまで地球上に出現した生物種のうち、じつに九九・九パーセントが絶滅してきたという事実である。私たちを含む〇・一パーセントの生き残りでさえ、まだ絶滅していないというだけで、いずれは絶滅することになるだろう。」
「大いなる自然は、生き物たちに恵みをもたらすだけではない。それは生き物たちを特段の理由なく差別したり、えこひいきしたり、はたまたロシアンルーレットを強制したりと、気まぐれな専制君主のようにふるまう。いま私たちが目にすることができる生物の多様性も、こうした理不尽な歴史の産物なのである。」
「アメリカの代表的な古生物学者のひとりであったデイヴィッド・ラウブは、現在地球上に生息している生物種はおそらく四〇〇万種は下らないだろうと推定する。そしてこれまで地球上に出現した生物種の総数は、おそらく五〇億から五〇〇億ではないかと推定している。」
「ラウブは、絶滅のほうから生物の進化を考えるという、きわめてユニークな試みを行った。」
「「ラウブは、絶滅生物たちがどのようにして死に絶えるにいたったかを、古生物学上の化石記録や統計データを駆使して調べ上げた。(・・・)
そこで彼が注目したのは、絶滅する生物がたどる特有の筋道である。絶滅生物にはみなそれぞれに異なった事情があったにはちがいないが、それでも、絶滅へといたる筋道にはいくつかの特徴的なパターンが見出される。分析の結果、絶滅の筋道は煎じ詰めれば次の三つのシナリオに分類できると彼は考えた。いわば「絶滅の類型学」である。
それは次のようなものだ。
1 弾幕の戦場(field of bullets)
2 公正なゲーム(fair game)
3 理不尽な絶滅(wanton extinction)
生物の歴史において、どのシナリオによる絶滅も、ある時ある場所ある規模において起こったし、いまでも起こっていることはまちがいない。しかし、ラウブがとくに重視するのは第三のシナリオだ。それこそもっとも影響力のあるシナリオだと言う。」
「第一のシナリオは「弾幕の戦場」と呼ばれる。(・・・)これは、生物がどれだけ優れているかとか、どれだけ環境に適応しているかといったこととは関係のない絶滅を指す。人口密集地にたいして行われる無差別攻撃をイメージするとわかりやすいかもしれない。」
「第二のシナリオは「公正なゲーム」と呼ばれる。これは、同時に存在するほかの種や、新しく生じてきたほかの種との生存競争の結果として絶滅が起こるというシナリオだ。」
「第三のシナリオ(・・・)こそ、話をややこしくすると同時におもしろくもする張本人である。(・・・)第一のシナリオ(弾幕の戦場)と第二のシナリオ(公正なゲーム)の組み合わされた複雑なシナリオであるからだ。(・・・)
すなわち、「ある種の静物が生き残りやすいという意味ではランダムではなく選択的だが、通常の棲息環境によりよく適応しているから生き残りやすいというわけではないような絶滅」。あるいは、ある種の性質をもった生物だけが生き延びやすいという意味では選択性が働いている絶滅だが、普通の意味で「環境に適応したから生き延びられた」とか「適応できなかったから滅んでしまった」とはいえなような状況における絶滅ということもできる。」
「弾幕の戦場を支配するのは端的に運であり。存亡そのものが遺伝子(生物の特徴や能力)と関係なく非選択的に決まる。公正なゲームを支配するのは遺伝子であり、存亡はその生物の遺伝子が表現する特徴や能力に対して一定の生存ルールのもとで選択的に決まる。しかし理不尽な絶滅では、生存ルールは運次第で決まるにもかかわらず(天体衝突は生物にとっては運の問題以外の何物でもない)、そのように決まったルールは生物の特徴や能力つまり遺伝子におうじて選択的に犠牲者を決定するのである(衝突の冬を生き延びられたのは特定の生物だけだった)。いわば、万人に公平なはずの選択が不公平にもたらされるのであり、公正なはずのゲームが不公正にもたらされるのだ。」
私たちは昔の人文主義者とは異なり、近代の科学技術の世界に暮らしている。人文主義者にならって「それは人間であることとなんの関係があるのか」と問うことは有益ではあるが、しかし十分ではない。近代人である私たちには、もうひとつ逆向きの問いが必要である。すなわち、「それは人間であることとなんの関係があるのか」という問うだけでなく、返す刀でこんどは、「それは進化/進化論となんの関係があるのか」とも問わなければならない。」
「進化論を言葉のお守りとして用いる私たちは、どんな物事にも進化論を融通無碍に適用しているが、多くの場合、たいしょうぞ是認したり否認したりしたい自分自身の「生活感情の表現」に進化論の言葉をかぶせているだけであり、じつのろころその話は進化論や進化現象と関係ないどころか、学問=科学とも関係がない。」
「人間に対する遠心的/求心的な往復運動、あるいは人間からの離脱と帰還の往復運動が必要なのだが、こうした「人文的」な問題のやっかいなところは、誰もがそれをよくわかっていると思い込み、見くびっているところにある。これは「科学リテラシー」とか「科学コミュニケーション」と呼ばれるような、より広い文脈で考える必要があるのかもしれない。私たちの多くは、科学的知識を仕入れることそのものは比較的に得意としているが、それらと自分の足元の生活との関連を考えること、つまり日々の行動のために統計データを読み解いたりリスクを計算したりすることについては極端に不得手なようである(大震災と原子力発電所事故、そしてパンデミック以降、それはいっそう明らかになった)。
ここには、量子力学や相対性理論を理解するのとは別種のむずかしさがる。それは政治や社会問題と同じ種類のむずかしさであり、遠心化作用と求心作用のあいだの折衝のむずかしさである。」
「私にとって進化生物学は比類なく重要な学問である。それどころか誰にとっても重要なものであるに違いないと考えている。だが、もし人が進化生物学を学んだせいで、日常生活の重要問題、自分の生活や他人の生活や俗世間、つまり私たちの世界と人生の問題に対して恥知らずになるのだとしたら、それを勉強することに、どんな意味があるだろうか。
私の考えでは、進化生物学を学んだとしても、人は必ずしも恥知らずになる必要はない。というより、恥知らずな行いを避けるためにも進化生物学は必要である。
まずそれは、事実の解明と説明の努力によって作り話を回避する。犠牲者の死を美談にすることなく、父がタバコを買いに行ったまま帰ってこなかったこと。シュルツが配給のパンを受け取りに行って射殺されたことを正確に知るためには、歴史や生活史に関する調査と研究が必要である。『沈黙の艦隊』の痛快さを十分に味わうためにでさえ、伝説の特殊部隊指揮官であったライバック兵曹がどのような事情によりコックとして勤務することになったのかについて評価を知らなければならない。同じように、恐竜たちが小惑星落下後の「衝突の冬」に適応できず理不尽さな絶滅にいたったこと、珪藻類が季節的変化に対応するために身につけていた休眠機能によって、また哺乳類が恐竜絶滅後に空いた間隙によって理不尽な生存を遂げたことを知るためには、ぜひとも進化生物学の助けが必要である。
次なる局面は。ある意味ではさらに難しい。あらゆる可能な説明を尽くして、これ以上によい説明は不可能だという地点まで進むことが進化生物学の目標であるが、それはまたウィトゲンシュタインの壁が立ち上がる地点でもあるからだ。その意味でウィトゲンシュタインの壁は単なる障害物ではなく、私たちの目的地でもある。
壁の両側にはダークサイドが広がっている。終章で見た形而上学・神学的・宇宙論的暗愚学とスカイフックのダークサイド、つまり恥知らずと空想家のダークサイドである。私たちの世界と人生に現れる理不尽さ≒識別不能ゾーン≒ウィトゲンシュタインの壁をなかったことにしたいと感じたとき、私たちは簡単にダークサイドに墜ちてしまう。持ちこたえ続けるのは容易なことではないだろう。だが、そのための手立てを提供してくれるのもまた、進化生物学なのである。
知識を追求できるだけの賢さと、恥知らずな行いを控えられるだけの勇気と、その場に踏みとどまれるだけの力が、私たちとともにあらんことを。」
(養老孟司「解説」より)
「現代医学では患者は検査結果の集合として把握される。その検査結果を正常値に戻す。それがいまの医師の仕事である。患者としてのあなたは、それで満足するだろうか。病気を治してくれりゃいいんだよ。そういう患者がほとんどかもしれないが。
でもこういう例がある。ある患者が尿が出なくなって入院した。原因は頸椎にあり、それを矯正して排尿が可能になった。患者は現代医学の能力にいたく感銘を受けていた。しかし私とその話をしてからしばらく経って、あっ、あれだ、と叫んだ。本人はじつは特攻に出ることが決まっていたが、終戦となり機会を失した。それで戦後、二度首を吊って死のうとしたが失敗した。その古傷が原因だと気づいたのである。上山春平氏である。
進化論の面白さはどこにあるか。なぜそれが専門家の間でも極端な論争を呼ぶのか、本書はそこをみごとに説明する。近代の欧米思想史にもなっている。著者は自分の本の書き方は自分で掘った穴を自分でまた埋め戻しているようなものだと謙遜する。でも私は近年ここまでよくできた思想史を読んだ覚えがない。人文社会学の分野には近年良い著作が出る。個人的にそう感じる。経済だけではなく、日本社会は変わりつつあるのではないか。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
