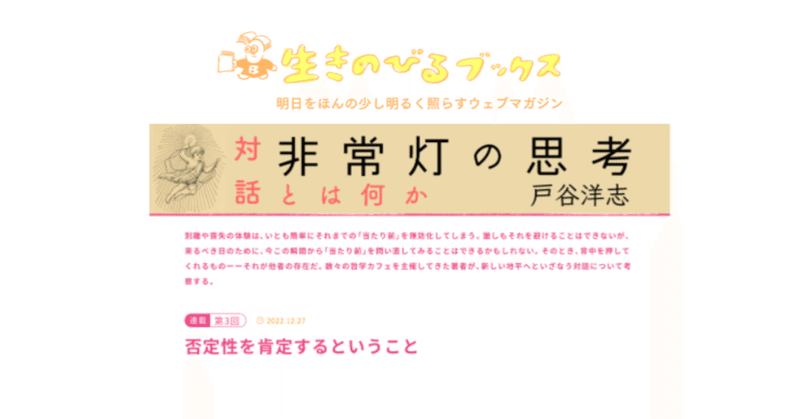
戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か」〜連載 第3回 否定性を肯定するということ(2022.12.27) (「生きのびるブックス」)
☆mediopos2971 2023.1.5.
自明のこと
当たり前だと思っていること
それは私たちの日常を支えるための
「常識」となっているのだが
それが「破局」に襲われ崩壊したとき
あらたな常識を再構築しなければならない
そのためにはまず
「「当たり前」を問い直すということ、
現在の常識を相対化し、
別の光のもとで物事を考える」ことが必要となる
しかしそれをひとりで行う困難さから「対話」
つまり「自分とは違った常識をもつ他者と対話する」ことが
その有効な方法となりえる
この「非常灯の思考 対話とは何か」の連載のなかで
著者は今後本格的にその「哲学対話」について論じる予定だったが
この連載3回目で軌道修正が必要だとしている
「哲学対話が人工的に形作られた対話であり、
そこには普通の対話に本来備わる性質のいくつかが、
欠落しているように思われてきたからである」
哲学対話は「保証された対話」であり
「勝手に終了しないことが約束され」
「終了時間がくれば必ず終わる」ものだからだ
逆にいえば現実の対話は
「対話しなくてもよいときにしか起きない」し
「常に終了の危機にさらされ」
「潜在的にはいつまでも終わらない」
現実の対話に対して哲学対話に欠けているのは
「対話がもつ否定性を肯定すること」であって
「その否定性こそが切り拓く可能性を見定めること」だ
というのが今回の記事の要点である
個人的な考えだが「哲学対話」なるものには
たとえその内容が深いものであったとしても
どこか胡散臭さというかわざとらしさを感じるほうだったので
今回興味深いこの記事をとりあげることにした次第
おそらくいわゆる「哲学対話」で
「「当たり前」を問い直す」ことはできない
まさにそこには必要に迫られるような「破局」がないからだ
結局のところ「ご専門」的な枠組みのなかでの
大団円のように収束してしまうところがある
著者はおそらく現実の対話の持つ働きを
「哲学対話」に持ち込むことを意図しているのだろうが
おそらくそれをアカデミックななかで
実現するのは極めて困難なことではないだろうか
アカデミックな「常識」から外れることができないからだ
まず前提となっている「常識」を相対化し
それを再構築するというとき
まず「常識」を「否定」するために必要なのは
「常識」の通用しない場に自らを投げ入れることである
それはある意味でグルジェフのワークのようなものだ
じぶんとはまったく異なった「常識」のなかでこそ
じぶんの「常識」を相対化することが可能となる
しかもそれを「再構築」するというとき
果たして「対話」が有効かどうかはわからない
とりあえず可能なのは「相対化」できているかを
確認することではないだろうか
「再構築」はどんなに小さなそれでも「創造」である
その「創造」のために使える「方法」はおそらく
道のない道をじっさいに
自分で歩いて見つけるしかないのではないか
■戸谷洋志「非常灯の思考 対話とは何か」
「連載 第3回 否定性を肯定するということ」(2022.12.27)
(「生きのびるブックス」連載)
「本連載の当初の構想は、およそ次のようなものだった。
私たちはさまざまな常識のなかで生きている。常識は、疑う余地のない「当たり前」として、日常を支えている。そうした常識を疑わないでいることができるからこそ、私たちの日常は確かなものとして、簡単には崩れないものとして信じられるようになる。そして多くの場合、日常を常識が支えているということ自体に、また常識に頼り切っているということに、私たちは気づかない。気づかないでいられるくらい、自明視しているのである。
しかし、そうした常識の自明性はしばしば崩れ去る。たとえばそれは、戦争、災害、事件、事故によって、あるいは結婚、出産、育児、出会い、死別によって、引き起こされる。「当たり前」の崩壊は、毎日のように起こるわけではないが、しかし、人生のなかではそう少なくない回数で、忘れたころにやってくる。地震のように、何の前触れもなく、私たちに容赦なく降りかかってくる。
常識の自明性が崩壊したとき──それを第一回では「破局」と呼んだ──、私たちの日常はもはや安心して信じられるものではなくなってしまう。そうした日常なしに生きていけるほど、人間は強くない。私たちは再び自分にとっての常識を再構築しなければならない。いままで「当たり前」だと思っていたことを捨て、別の「当たり前」を探さなければならない。
ただし、常識の再構築は簡単な仕事ではない。破局に襲われたとき、私たちがその困難な仕事へと飛び込んでいくことができるようになるためは、普段からある程度の練習をしておく必要がある。つまりそれは、「当たり前」を問い直すということ、現在の常識を相対化し、別の光のもとで物事を考えるということだ。
もっともそうした練習を一人で行うのは難しい。そもそも「当たり前」を相対化するためには、まず、その「当たり前」を意識することができなければならない。しかし、意識することができないということこそが、「当たり前」が機能している状態なのだ。そうでるとしたら、私たちは、普段は自分では意識していない「当たり前」を、つまり常識を意識化するような、何らかの特別な活動を自らに課すことが必要になる。
そのために有用なのが、対話である。「私」は、自分とは違った常識をもつ他者と対話することによって、翻って、「私」が身に付けている常識について、反省的に意志することが可能になる。そうした気づきは、「私」が「当たり前」だと思っていることが、決して唯一の考え方ではないこと、この世界には別の考え方も可能であるということを、「私」に教えてくれる。そこに、他者と対話することの価値がある。
こうした観点から考えるとき、「当たり前」を問い直すようにして他者と対話すること、言い換えるなら、哲学的に他者と対話することは、私たちの人生で大きな意味を持っているはずだ。そして、そうした対話の形式として、近年注目を集めているのが、哲学対話という活動である。そうであるとしたら、哲学対話について理解を深めていくことで、幾多の破局に襲われる人生を生き抜くための、生き生きとしたヒントが与えられるのではないだろうか。そして、そのような観点から眺めることこそが、哲学対話の真価をもっとも正当に評価することなのではないか。
このような想定にしたがって、筆者は本連載の内容を構想していた。そして前回の連載の末尾で述べた通り、今回から本格的に哲学対話の分析に入る予定だった。」
「しかしこのような考え方を大きく軌道修正することを余儀なくされた。幾度となく破局に見舞われる人生を私たちが生きるために、対話が必要である、という考え自体は変わっていない。しかし、哲学対話がそれに相応しいのか、という点に、筆者は疑問を抱くようになったのだ。それは、とりもなおさず、哲学対話が人工的に形作られた対話であり、そこには普通の対話に本来備わる性質のいくつかが、欠落しているように思われてきたからである。
哲学対話が普通の対話と異なる点はどこにあるのだろうか。筆者が考えるに、そこには大きく分けて、三つある。
第一に、哲学対話は、保証された対話である。言い換えるなら、対話してもよいということが確約された対話である、ということだ。たとえば哲学対話に来ているのに、進行役が一方的に自分の話をするだけで、参加者に何も喋らせなければ、参加者はその進行役を批判することができるだろう。哲学対話に来ているのだから、対話させるべきだ、と。すなわち、その場では対話することこそが「当たり前」であり、対話しないこと、させないことは、不自然なことなのである。
もちろん、それが哲学対話のよいところだ。しかし、現実の対話はそうではない。なぜなら現実の対話は、常に、対話しなくてもよいときにしか起きないからである。」
「第二に、哲学対話は、勝手に終了しないことが約束されている。つまり、一度哲学対話の開始が宣言されたら、終了時間を迎えるまで、対話が自動的に継続する。途中退席することはできる。しかし、席についてさえいれば、たとえ沈黙が支配したり、気まずい雰囲気が場を飲み込んだりしても、対話は終わらない。「なんだか変な感じなので今日の哲学対話はこれで終わりにしましょうか」といってお開きになることは、基本的には起こりえない。だからこそ参加者は、自分の発言や振る舞い一つによって対話が終わってしまうかも知れない可能性を無視して、話に集中することができる。
一方で、現実の対話は、常に終了の危機にさらされている。」
「第三に、哲学対話は、終了時間がくれば必ず終わる。どれだけ対話を継続し続けようと思っても、それは叶わない。言い換えるなら、参加者は対話をいつ終わらせるか、どのようにまとめるかを、考える必要がない。
それに対して、現実の対話では、対話を終わらせるためには、当事者が自らの意志で終了することを選択しなければならない。当事者たちが対話を終わらせようとしなければ、それは潜在的にはいつまでも終わらない。」
「以上の三つの点のように要約することができるかも知れない。すなわち哲学対話において、対話の参加者は、その成立条件に対して、まったく責任を負わないのである。対話は、参加者の意志や選択に影響されることなく、自動的に始まり、自動的に継続し、自動的に終わる。しかし、現実の対話はそうではない。参加者は、その対話を自らの意志で開始し、継続するための努力をし、そして終わらせることを選ばなければならない。その一つ一つに責任がのしかかるのだ。
こうした対話の成立条件への配慮は、対話の内容そのものに影響を与えもする。
たとえば「愛とは何か」という対話が行われているとしよう。そこでは「愛」が話題になる。対話の参加者は、それぞれの考えを語り合う。しかし、そうした語り合いは、それを可能にする空間、すなわち対話の場が必要である。対話の場が成立しているということは、愛について対話しようとするとき、その前提なのである。
哲学対話において人々は対話の場のことを配慮する必要がない。それは主催者によって、進行役によって、管理されているからだ。そのため、対話の成立条件への配慮は、対話そのものから超越している。参加者が何を語ろうとも、それは対話の成立条件に影響しない。哲学対話を擁護する立場から考えるなら、だからこそ、そこでは自由な議論が可能になる。
それに対して、現実の対話に、そのように対話の成立条件を配慮してくれる超越的な他者はいない。対話の成立条件は、対話に内在している。対話の参加者がどのように語るかによって、対話の場は継続したり、打ち切られたりする。だから愛について対話しているとき、相手に不快な思いをさせるようなことを言えば、対話は終了する。したがって、対話を続けようとするとき、そうした発言をすることはそもそもできないのである。
私たちはこのことをどう考えるべきなのだろうか。」
「筆者は、ある時期まで、対話の成立条件への配慮が免除されている哲学対話の形式は、対話をより深いものにすると信じていた。今でもそう思っている。だからこそ筆者は実践家として様々な場所で哲学対話を続けている。
しかし同時にそれは──ほとんど同語反復でしかないのだが──哲学対話の参加者から、対話の成立条件を配慮することへの責任を、奪うことでもある。参加者は、対話が成立するか否かということに縛られることなく、対話することができる。それは、一面では対話を一段自由にすることではあるだろう。しかし同時に、参加者が対話の成立条件に無関心であること、それどころかその条件を破壊するような言動をも許容することを意味する。」
「そうした行為を抑制するために、哲学対話には、一般的にルールが課せられる。代表的なものを挙げるなら、相手の話を最後まで聞かなければならない、相手を否定してはいけない、相手を不快にするようなことを言ってはいけない、といったものだ。そうしたルールは、対話を深化させていくファシリテーションの機能をも担っているが、それ以上に、対話の場を存続させるために設けられ、また進行役による介入の妥当性を担保するために定められる。しかしこのことは、裏を返せば、ルールがなければ対話の成立条件が破壊されてしまう、ということだ。
それに対して、当然のことながら、現実の対話にこのようなルールは存在しない。もちろんそれがよいことだと言いたいわけではない。ルールがないからこそ、対話が台無しになり、成り立たなくなることもあるだろう。しかし、当事者がその成立条件を配慮するなら、ルールがなくとも充実した対話が成立することはある。
おそらく、哲学対話と現実の対話の間にある大きな違いは、そこに「私たちが対話を作る」という心構えがあるか否か、ということであろう。「私たち」がポイントだ。本来、対話は一人では作れない。それには他者の協力が必要である。だからこそ、私たちは対話するとき、他者のことを配慮し、対話できなくなるような言動をしないようにする。それに対して哲学対話を作っているのは、原則的には主催者であり、進行役である。だから参加者は対話を破壊することができる。そして、参加者に対話を破壊する力があるからこそ、そこにはルールが必要になるのである。」
「哲学対話の特殊性を考えたとき、浮かび上がってきたのは、対話がもつ次のような一般的な傾向だろう。すなわち対話は、対話の成立条件への配慮を、そのうちに含むということである。そうした配慮は、対話のなかで語られることではなく、対話そのものへの反省に他ならない。そして筆者には、こうした反省性が、対話にとって重要な意味を持っているのではないか、と思えるのだ。
対話の当事者は、自分が話していることや、相手が話していることだけではなく、そうした語りがそのなかで行われているところの対話を意識する。たとえばバーで隣の人と対話を始めたとき、私たちは、対話そのものをどうやって進めていくかを思案しながら、何を語るかを考える。対話は選択の連続である。選択するということは、一方ではなく他方を選ぶこと、つまり何かを選び、何かを選ばないことだ。選択によって、対話の行く末は刻一刻と変化するのである。」
「対話がどこへ向かうかは、あらかじめ決まっていない。対話が始まるかどうかも、あらかじめ決まっていない。何が語られるのかも、決まっていない。だからこそ私たちは対話について反省しなければならないのだ。
それに対して、すでに語られることが決まっており、始まることが決まっており、終わり方まで決まっている意思疎通は、対話ではない。たとえば定例的な会議がそうした対話だろう。対話に先行してアジェンダが設定されており、すでに根回しされた事柄を確認するだけで、時間が浪費される。根回しは完了しているのだから、その議論の場で異議を唱えることはできない。そこにはいかなる否定性も存在しない。誰も「ない」と言うことができない。そして、そうである以上、そこには自由もまたないのだ。
しばしば哲学対話のルールでは否定が禁止される。そして、誰も否定されることがない、という安心のもとで対話が行われる環境は、「心理的安全性」とも呼ばれる。たしかにそうした安全性は重要だろう。しかし、私たちは同時に、それが犠牲にせざるをえないものにも目を向けるべきではないか。
否定性こそが、対話そのものが自由であるための条件である。そしてその自由が、対話の場を存続させるために他者を配慮することの、条件でもあるということだ。」
「否定性を無視することは、結局のところ、自己欺瞞ではないのか。それは対話を対話ならざるものにすることである。
あるいは反対に、実際には対話ならざるコミュニケーションが、自己欺瞞によって、あたかも対話であるかのように思い込まされることも、起こりうるかも知れない。そのとき、私たちは自由に対話しているように見えて、実はそうしたコミュニケーションを私たちに強制する何者かに、その権力に、服従していることになる。
そうした事態に抗うために必要なのは、対話がもつ否定性を肯定すること、その否定性こそが切り拓く可能性を見定めることではないか。
私たちはこの連載で、そうした道を探っていきたい。」
◎戸谷洋志(とや・ひろし)プロフィール
1988年東京生まれ。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科文化形態論専攻博士課程修了。現在、関西外国語大学英語国際学部准教授。博士(文学)。専攻は哲学。現代ドイツ思想を中心にしながら、テクノロジーと社会の関係を研究すると同時に「哲学カフェ」を始めとした哲学の社会的実践にも取り組んでいる。著書に『Jポップで考える哲学――自分を問い直すための15曲』(講談社文庫)、『原子力の哲学』(集英社新書)、『スマートな悪――技術と暴力について』(講談社)、『ハンス・ヨナス 未来への責任――やがて来たる子どもたちのための倫理学』(慶應義塾大学出版会)などがある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
