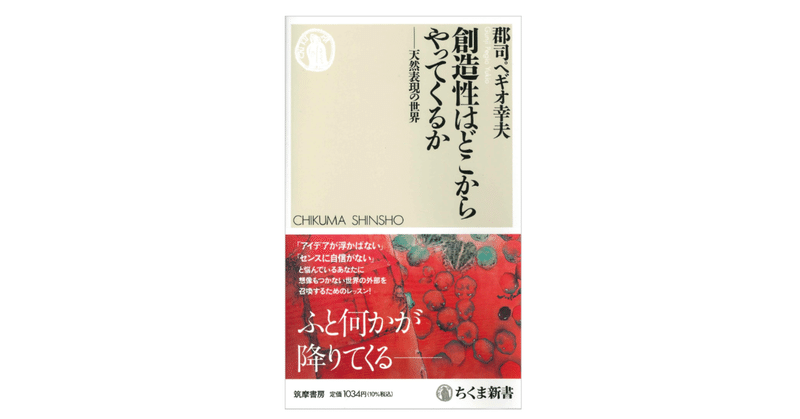
郡司ペギオ幸夫『創造性はどこからやってくるか――天然表現の世界』
☆mediopos3197 2023.8.19
創造とは
「外部」を召喚することである
「外部」を召喚するのは
「天然知能」である
「天然知能」による「表現」は
「自己表現」ではない
「わたし」は創造の当事者ではあるが
「外部」に「自己」はないからだ
「芸術にたずさわる多くのアーティスト」にとって
芸術は「自己表現」ではないように
「自己表現という意味での表現」は否定される
「「わたし」の中なんて空っぽで何もない。
わたしの中ではなく、むしろ外から来る何か、
インスピレーション(霊感)を受け取る」のだ
「天然知能」の「わたし」は
「外部」に接続する装置である
ちなみに「外部」は「外側」ではない
わたしの「内側」と「外側」が
「内部」という全体を成している
「外側」はわたしに想定可能だが
「外部」は知覚不可能で窺い知れない
「天然知能」による「創造」は
想定されるものを能動的に創るのではなく
未知のものを受動的に召還することである
能動的でなければならないのは
「外部」に接続するための当事者となることである
「人工知能」は当事者となることができない
「人工知能」には「わたし」がないからだ
さて「外部」を召還し創造する装置について
その「トラウマ構造」が示唆されている
トラウマ構造とは
二項対立的なものが「わたし」を支配しているとき
「対立する二項を共に成り立たせる肯定的矛盾と、
共に否定する否定的矛盾が共立」することである
ここで例として挙げられているのは
津波の被害者に見られる被害者意識と加害者意識
そして「お昼をラーメンにするか蕎麦にするか」と
決められないでいる状況だが
(二つの例が極端なのも天然なのかもしれない)
津波の被害者のトラウマにおいては
被害者意識と加害者意識という二者択一がもつれ
「被害者かつ加害者」をつくり出し
「その脱色の果てに「被害者も加害者もなくなり」、
そこへ「癒やし」が現れ」るように
二者択一でもつれた「閉域の外部を召喚」することで
「外部に触れることができ」
それが「創造であり、癒やし」となるのだという
ちなみに「ラーメンか蕎麦か」では
迷った挙げ句蕎麦とラーメンの意味が「脱色」され
著者は結局どちらかを選んだりせず
「帰って寝る」ということになる
「帰って寝る」のを「創造」と呼ぶかどうかは別として
「天然知能」によって「外部」が召還されるのは
「肯定的矛盾と否定的矛盾の共立」という
トラウマ構造のもとにみずからを置くときである
ある意味でこうした「トラウマ構造」は
禅問答のようなものでもあるかもしれない
その矛盾を生きるためには
「閉域の外部を召喚」しなければならない
■郡司ペギオ幸夫
『創造性はどこからやってくるか――天然表現の世界』
(ちくま新書 筑摩書房 2023/8)
(「はじめに」より)
「本書は、アートに基づく「創造入門」である。」
「アート作品を手がかりにしてはいるが、何の創造であるかは問わない。創造とは、「わたし」において、新しい何かを実現すること、「わたし」の外部との接触を感じることである。「やった」「できた」「わかった」という新たな扉を開くものだ。他の誰かがやっても意味がない。創造とは、自分でやるからこそ、意味がある。本書では、創造の当事者性という問題が明らかにされ、創造の当事者であることの意味と方法が論じられる。
人工知能が、あなたより評価される絵を描き、あなたより評価されるコンセプトやアイデアを打ち出し、あなたより評価される小説を書く。そういうことは、近い将来たやすく実現されるだろう。しかし当事者における創造の評価は、定量化したり、他と比較することができない。他人と比較しても意味がないように、むろん、人工知能と比較しても意味はない。人工知能が何をしようが、あなたはあなたなのである。
あなたは、「それは自己満足ではないか」と思うかもしれない。そうではない。自己満足は、「わたし」の中でも閉じた理解や納得を意味する。閉じているので創造体験の実感がない。しかし、自分を納得させるために自分を欺く理論武装だけはする。「自己満足ではないか」と言われることを恐れる状態が、自己満足である。「当事者として外部に接触する」体験は、そのような閉じたちっぽけなものではない。そんなものは吹き飛んでしまう。
それだけではない。本書での創造は、創ることが困難なものを創る実践的意味を持っている。」
(「第1章 「天然表現」から始める」より)
「近年、私は、いわゆる機械で実装された知能という意味での人工知能に留まらず、得られた経験やデータだけから推論し判断する知性のあり方全体を、広い意味で、「人工知性」と捉え、これに対して、想定もしなった自分にとっての外部を受け入れる、徹底して受動的な、しかし、それこそが創造的な「天然知能」という知性のあり方を提唱した。
「天然知能」は、知能というより創造的態度、創造の装置であり、だからそれは、制作それ事態とも言える。そして実は、制作された作品それ自体かもしれないのである。」
「本書は、「天然知能」に関する予備知識など、一切必要のないように書かれている。」
「「天然表現」は、創造し個物化する生成の現場として、制作過程を描いている。ただし、本書で制作はかなり広い意味で用いられる。作品の鑑賞もまた制作と考えられている。だからこそ、完成した「作品」もまた「天然表現」を実装している。」
(「第1章 「天然表現」から始める」〜「外側と外部」より)
「読者は。表現、表現活動というと、カタカナのアートの話であり、いわゆる美術(ファイン・アート)に限定しない、身体を含むさまざまな媒体を用いた「表現」をイメージするかもしれない。もちろんそれも含むのだが、アートや表現として多くの読者が想像する、自己表現であるとか、「わたし」の中にあるものの吐露であるとか、そういうことではない、むしろ芸術にたずさわる多くのアーティストは、自己表現という意味での表現を否定する。「わたし」の中なんて空っぽで何もない。わたしの中ではなく、むしろ外から来る何か、インスピレーション(霊感)を受け取るのだ。そういう言い方をする。ここでいう天然表現は、この感覚を拡張することで構想される。そして、自然現象や、人間の意識、心の形成まで、天然表現として展開していくものなのである。」
「天然表現は、表現の結果であったり、表現を説明したりするものではない。そのような終わったことを後付けることはしない。天然表現は表現に向かうための態度であり、完全な不完全体である。芸術家は、「外から来る何か、インスピレーション(霊感)を受け取るのだ」と言ったが、その受け取るための態度である装置は、形式化できる。それは、何がもたらされるかはやってみないとわからないものの、「やってみよう」という賭けに出るだけの仕掛けなのである。」
「天然表現とは、「外部」に接続する装置であり、外部に接続することが「作品化」される営みである。ここに二つ説明すべき言葉がある。第一に「外部」であり、第二に「作品化」である。外部とは、「わたし」が想定する世界、その外にある無限の宇宙とでもいうべきもので、認識不可能なものである。」
「私はしばしば、窺い知れない外部とか、知覚不可能だが存在する外部、という言い方をするが、そうすると、「そういう、解決不可能なものを特権化するのがダメで、内と外をつないだ世界観を構想することこそ大事なのだ」などとお叱りを受ける。しかし、わたしの知っている内(こちら側)とつなげられるように想定された外(向こう側)とは、内から勝手に規定された外に過ぎないだろう。むしろ、そのようにつなげられた内と外によって構成される全体こそ、「わたし」が想定する、閉塞的な世界なのである。私は常にそのように反論するのだが、わかってくれる人はそう多くない。
まだ行ったことはないが、存在するらしい向こう側とか、わたしはあなたではないが、同じ人間として理解可能な、あなたとか。このような向こう側やあなたは。こちら側にいるままにして、「可能なもの」と想定されている。現に知覚できたり現れていなかったりしても、知覚できるとしたらこのようなものであろうと、そのあり様を想定できる。このような、いまだ現れないが可能なもののいる場所を、本書では「外側」ということにする。すでに現れ、知覚しているもので満たされた場所が内側であるが、外側は、この内側と対を成すものと定義される。内側と外側から構成される全体は、しょせんわたしが想定する世界である。
これに対して、外部とは、この内側と外側の成す全体からは窺い知れない、その全体の外に位置づけられるものである。(・・・)「内と外をつなげることこそ重要な問題である」という場合の外は、外側のことであって、外部ではない。外部は可能なものとして想定できない。」
「外部に触れる体験とは、どのような体験だろうか。(・・・)とりあえず、以下の三つをあげ、次の節以降、なぜそれらが外部に触れる体験なのか述べることにする。創造という行為、とりわけ芸術家の営みは、これに当たると言っていいだろう。そして死を感じる体験である。他人の死を外から経験することはできても、わたしの死は生きている限り知覚しようがない。死はわたしの外部にある。しかし、不幸にも私は、それを直観してしまう。もう一つ、ここではトラウマにおける癒やしをあげておこう。本来、外部に触れる体験は日常的に起こっているのだが、なかなか気づくことがない。その日常的な外部に触れる体験に気づき、これを作品化していくことで、天然表現を起動する。」
「創造が外部に触れることであるなら、それは決して有限の形式で捉えられない無際限さを含むことになる。わたしが決定する価値は、無際限さに開かれ、自分でさえ確定的に記述できないものの、わたしにおいては自明である。かくして、わたしが感じる創造とは原理的にはわたしだけのもの、当事者のものとなる。創造とは何かという問いは、客観的に創造を定義しようという問いであったが、問い自体がむしろ解体され、当事者性という性質が現れたことになる。」
「外部に触れることの最も端的な例は、死を想うことだろう。」
「死を想うことで発生する議論、および私の死に対する直観さえ、このように、その全体が原理的にわからず、宙吊りのまま進行する。生から死を想いながら、同時に生と死の関係自体をも疑い、しかし、それを超越した絶対的な死を感じながら、仮のものである生と死自体が、曖昧模糊としたものになる頃、すべてが押し流されていく。生きようとして苦闘しているものを押し流すものこそ、死ではないか、というように。このどうしようもない本流の感覚こそ、私にとっての死を感じる感覚だ。そしてそれこそ、外部に触れる感覚なのである。」
「トラウマとは心的外傷、すなわち心の傷を意味し、それがもとで、その後の人生に大きな影響を与えるものだ。」
「津波の被害者に見られるトラウマ(・・・)。彼らは端的な被害者であるにもかかわらず、自分だけ生き残ってしまったことに罪悪感を覚える。それはおおよそ、被害者の一割程度との報告がある。それはサバイバーズ。ギルト(生存者の罪)と呼ばれている。つまり津波の被害者は、同時に加害者の感覚も持ち合わせている。」
「被害者意識と加害者意識は、明確に区別されながらも、糸が絡まってほどけなくなったように分離しがたいものとなる。」
「創造の本質は価値に依存する点にあり、価値は確定的に書き下ろそうにも、後かあ後から書き足りない部分に気づかされ、「これが価値だ」と決められるものではない。その無際限さが価値の肝なのであり、だからこそ、既存の価値からはみ出る創造は、あらかじめ規定できない外部との接触において起こるのである。この点は極めて重要な点だ。」
(「第2章 外部へ出るために」より)
「大学で、お昼をラーメンにするか蕎麦にするか、散々迷った挙句、帰って寝ることに決めた。自分には得てしてこういうことが、よく起こる。人によっては、そんな馬鹿な、と思うかもしれない。なにしろ、選択肢二つの中で選んでいたにもかかわらず、その土台を台無しにするというのでは、お話にならないからだ、しかし、この「帰って寝る」がいかにして現れるのか。これは考えるに足る問題だろう。それは素朴ながら。創造の種に関与しているからだ。」
「これは、何かに似ていないか。そう、トラウマと同じではないか。本来なら二者択一であるはずの被害者意識と加害者意識が、もつれにもつれ、両義的構造、つまり、「被害者かつ加害者」をつくり出してしまい、その脱色の果てに「被害者も加害者もなくなり」、そこへ「癒やし」が現れた、その津波の被害におけるトラウマ構造だ。」
「蕎麦かラーメンか悩んだ挙げ句、帰って寝るという選択に、トラウマ構造を見出し、むしろトラウマ構造を、創造の準備の構造として一般化する。これを考えていこう、両者に共通に認められた第一の構造、それは、二項対立的な二つの概念だった。二項対立とは、二つのものからどちらかを選ばなければならない。のっぴきならない状況であり、世界観である。
(・・・)
第二に、想定された二項対立の項目がもつれにもつれ、共に存在する状況が共通に認められた。それが「被害者かつ加害者」であり、「蕎麦かつラーメン」であった。二項対立である二つの概念が、もちろん同時に存在することはない。(・・・)相反するものが共に存在する矛盾を。肯定的矛盾(肯定的アンチノミー)と言うが、まさに、被害者意識と加害者意識が共に存在する状態、そして、蕎麦とラーメンが共に存在する意識状態は、肯定的矛盾を実現しているのである。これが、二つの事例に共通な「第二の構造」である。
しかし、そのもつれ状態は、解消するわけではなかった。
(・・・)
二項対立的状況があって、トラ今では、強度においてその各々が存在せず。蕎麦かラーメンかでは、意味を理解する点においてその各々が存在しない。そういう状況が、完全に脱色された状態である。とするなら、それは二項対立的二者のいずれもが存在しないことで生じる矛盾であり。それは一般的に否定的矛盾(否定的アンチノミー)と呼ばれるものである。
世界は二項対立的な二者によって構成され、そのいずれかを選択するしかない状況と仮定されている。だからこそ、その二者を共に成立させることも矛盾(肯定的矛盾)だが、そのいずれもが存在しないことも矛盾(否定的矛盾)なのである。これこそ、トラウマと蕎麦かラーメンかの事例に共通な「第三の構造」である。」
「こうして肯定的矛盾と否定的矛盾を各々定義しておくとき、トラウマとは、肯定的矛盾が作り出す二項対立的二者の「もつれ構造」を維持したまま、その二者の強度を限りなく弱めたものだった。つまり、ここrは、「もつれ」において肯定的矛盾が、強度を脱色する意味において否定的矛盾が、見出される。これは、両者が共に存在している状態、「肯定的矛盾と否定的矛盾の共立」という形式で規定できるものと考えられる。これを、「蕎麦かラーメンか」と「トラウマ」という、二つの事例に共通な、「第四の構造」とみなることができる。特にこの、第四の構造を「トラウマ構造」と呼ぶことにする。」
「二項対立的なものが、そこから抜け出せない閉域のように「わたし」を支配しているとき、対立する二項を共に成り立たせる肯定的矛盾と、共に否定する否定的矛盾が共立することを、トラウマ構造と呼ぶ。わたしがトラウマ構造にあるとき、わたしは、この閉域の外部を召喚し、外部に触れることができる。それが創造であり、癒やしである。トラウマ構造は、創造のための構えであり、装置ということができる。」
◎郡司ペギオ幸夫(ぐんじぺぎおゆきお):
1959年生まれ。東北大学理学部卒業。同大学大学院理学研究科博士後期課程修了。理学博士。神戸大学理学部地球惑星科学科教授を経て、現在、早稲田大学基幹理工学部・表現工学専攻教授。著書『生きていることの科学』(講談社現代新書)、『いきものとなまものの哲学』『生命壱号』『生命、微動だにせず』『かつてそのゲームの世界に住んでいたという記憶はどこから来るのか』(以上、青土社)、『群れは意識をもつ』(PHP サイエンス・ワールド新書)、『天然知能』(講談社選書メチエ)、『やってくる』(医学書院)、『TANKURI』(中村恭子との共著、水声社)など多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
