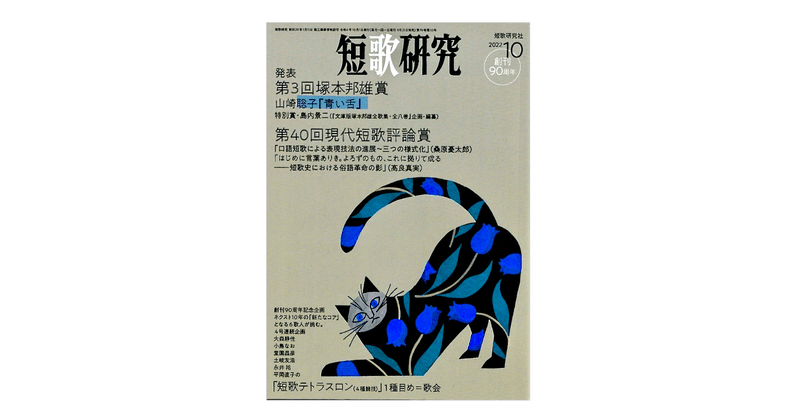
桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展」/高良真実「はじめに言葉ありき。よろずのもの、これに拠りて成る」(『短歌研究2022年10月号』)
☆mediopos2868 2022.9.24
『短歌研究』という雑誌をはじめて読む
創刊九〇周年を迎えているらしい
「塚本邦雄賞」の発表という文字が目に入り
(そんな「賞」があるのさえ知らずにいた)
その「特別賞」が
『文庫版 塚本邦雄全歌集・全八巻』の
企画・編纂を行った島内景二に贈られていたからだ
塚本邦雄について見ておこうと思えば
島内景二を外しては考えられない
しかし今回の収穫はそのことよりもそれと同時に
「第40回現代短歌評論賞」を授賞した二つの論文である
この賞の課題のひとつが
「口語短歌の歴史的考察」だが
二つともそのテーマに取り組んだものだ
短歌に興味をもちはじめたのは比較的最近のことだが
「口語短歌」の問題がずっと気になっていた
「口語短歌」はそれなりに面白いところもあるのだが
その作品を読むにつけ
「わざわざ口語の短歌定型にする意味があるのか」
「それははたして「短歌」といえるのだろうか」
と感じることが多いからだ
二つの論文はその疑問の一端に
糸口を与えてくれるものでもあった
桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展」では
口語表現ゆえにそれを「短歌定型」にする際に
解決する必要のある表現の問題がとりあげられている
「口語短詩特有の文末処理問題」である
過去完了の助動詞「た」の扱いのこと
文末を「た」の形で終わらすと散文的になりすぎて
韻詩作品として成立しにくいということである
文語であれば「き・けり・つ・ぬ・たり・り」といった
過去形や完了形の助動詞を使って文末の処理ができるが
口語にそんな多様な表現は存在しない
そのために口語短歌による表現技法として
現在様式化していると思われる
特徴的な三つの技法があるという
①動詞の終止形の活用
②終助詞の活用
(「ぜ」「ね」「さ」といった終助詞の活用)
③モダリティの活用
(「作品を、独り言や他者への発話といった
話し言葉で叙述する、という方策」)
である
たしかにこれらの技法は
短歌表現を口語で成立させるために欠かせない
しかしそれよりも重要なのは
高良真実「はじめに言葉ありき。
よろずのもの、これに拠りて成る」で論じられている
言文一致と普通文や俗語の問題である
「口語短歌は書かれた時点ですでに口語ではない」
「書かれたものは、口語かもしれないが、
口語(発話)そのものではない」
ということが問題になる
口語短歌によく違和感を感じてしまうのは
それが「短歌定型」になってはいるものの
「口語」との差異に無自覚であることである
口語短歌は現在進行形での試行の最中ではあるが
その表現の可能性を拓くためには
「短歌定型」ゆえのあらたな韻律が必要になる
そうでなければそれが短歌形式である必要はないからだ
塚本邦雄は文語や文語表記にあくまでも拘ったが
その稀有の営為ではなしえなかった表現領域を
口語短歌が垣間見せてくれますように
■桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展」
高良真実「はじめに言葉ありき。よろずのもの、これに拠りて成る」
島内景二『文庫版 塚本邦雄全歌集』の企画編纂の功績に対して
(『短歌研究2022年10月号』短歌研究社 2022/9 所収)
(桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展」より)
「現代の短歌状況を振り返ると、ここ数十年による口語短歌の進展は著しいものがあろう。その進展については多様な論点で議論できようが、短歌形式の表現技法に話題を絞るならば、口語短歌による口語ならではの技法が生まれている、ということはいえよう。それは、文語形式ではなし得なかった新しい技法であり、そして、そうした表現技法が様式化するにいたり、結果、短歌文芸の表現の幅を広げることになった、ということもいえるだろう。
一方、そうした口語短歌による表現技法に進展は、口語をいかにして短歌定型になじませるか、という試行の連続であったと指摘することもできる。そもそも、口語で発想された事柄を、そのまま口語で述べても短歌にはならない。定型意識を持ち、韻律や調べを整え修辞や統辞を施してはじめて韻律文芸としての短歌作品になる、ということがいえるからだ。それに、どうして口語で発想した事柄を、わざわざ韻詩である短歌形式に変換して叙述するのか、という根本的な疑問もある。すなわち、口語で発想した事柄を韻詩へといわば翻訳する意義は何なのか、という疑問だ。
本稿では、そんな定型になじませるための試行や、韻詩に変換することはの疑問を抱えながら進展してきた、口語短歌による表現技法について議論することを目的としている。なかでも、現在、様式化していると思われる特徴的な技法として、1動詞の終止形、2終助詞、3モダリティ、の三つの活用による技法について取り上げた。繰り返しになるが、この三つは、口語短歌による口語ならではの表現技法であり、現在、多くの歌人がごく普通に使用している技法である。そして、それは、口語を短歌定型になじませるためにあれこれ試行し、また、口語を韻詩へ変換することへの疑問を抱えながら進展した結果、広く短歌文芸全体の表現の幅を広げることにもなった技法といえるのである。」
「口語短詩特有の文末処理問題とは何か。というと、端的にいえば過去完了の助動詞「た」の扱いのことだ。
例えば文語であれば、いくつもの過去形や完了形の助動詞を使って文末の処理ができる。文語の過去と完了の助動詞といえば、「き・けり・つ・ぬ・たり・り」であり、これらを駆使して時間の経過を重層的に韻律にのせる技法が文語短歌には積み上がっている。しかし、口語はというと、過去や完了をあらわす助動詞は「た」しかない。そうすると、口語短歌で、文語がこれまで積み上げてきた多様な文末処理の真似事をしようにも、到底、文語短歌の豊かな表現を越える作品は提出できるわけがなかった。
それに、文末を「た」の形で終わらすと、どうにも散文叙述のようになり、韻詩作品としてうまくいかない、という事情もあった。」
「①動詞の終止形の活用
では、そうした「た」によらない文末処理としては、どのような処理の仕方があるか、というと、その一つとして、過去にしないで終わらせる、すなわち、動詞を「ル形」(終止形)でおさめるという技法を挙げることができる。
(・・・)
この「ル形」でおさめる技法は、現在ではすっかり様式化されていると思われ、(・・・)さほど違和感がないかもしれないが、日本語の用法としては誤用である。これらの動詞は、すべて動態動詞と呼ばれるもので、その動詞の「ル形」は未来を表す。(・・・)
では、なぜ、こうした誤用が、短歌文芸ではさほど違和感もなく作品として提出されているのか。といえば、これまで議論している助動詞「た」の使用を避けるためだった、ということが理由の一つとしてあげられよう。」
「②終助詞の活用
口語短歌の文末処理では、動詞を「ル形」で終わらせる用法の他に、次のような用法が試行された。
マガジンをまるまで歩くいい日だぜ ときおりぽんと股で鳴らして 加藤治郎『サニー・サイド・アップ』
たぶん口をとがらせてるね だまったきりひとさし指をまわしてる、ふん
バック・シートに眠ってていい 市街路を海賊船のように走るさ
加藤治郎の八〇年代に提出された作品から三首掲出したが、注目したいのは「いい日だぜ」の「ぜ」、「とがらせてるね」の「ね」、「海賊船のように走るさ」の「さ」だ。
こうした「ぜ」「ね」「さ」の助詞は終助詞とよばれるが、この終助詞の効果的な使用が。口語短歌ならではの文末処理を生み出したのだった。」
「③モダリティの活用
口語短歌の文末処理の解決策の三つ目として、作品を、独り言や他者への発話といった話し言葉で叙述する、という方策がある。話し言葉であれば、語尾に「た」をつけずとも自然な表現で文末処理ができる。
ところで、そんな独り言や他者への発話といった話し言葉の文末は、話し手の判断や態度の部分を表していることが多い。この話し手の判断や態度の部分を「モダリティ」という。例えば、「私はカレーが食べたい」という命題を独り言として叙述するなら、「カレーにするか」と「カレーでも食べるか」とかになる。この時の、「か」とか「でも」というのが「モダリティ」である。」
(高良真実「はじめに言葉ありき。よろずのもの、これに拠りて成る」より)
「(一)口語の不可能性
口語短歌は書かれた時点ですでに口語ではない。(・・・)書かれたものは、口語(話し言葉を元にしたいわゆる言文一致体)かもしれないが、口語(発話)そのものではない。」
「(二)言文一致と普通文
(・・・)
口語短歌は一般的に書き言葉である。しかし口語短歌は、しばしば発話に近いものとして位置づけられ、あるいは考えを表現するにあたって自然なものとして語られる。
文章と発話と思考は全て同一でなければならず、そのためには、言葉と文字が一体化された、思考を透明に表現できる記号が必要である。これは言文一致運動の基本的なテーゼであった。しかし一方で、言文一致とは、話すように書くことだけでなく、書くように話すことも要請していた。(・・・)
たしかに普通文は、口語に比べると古いものに見えるかもしれない。しかし、江戸時代の擬古文や、公文書などの文体である候文に比べれば、新しいものと言えよう。短歌は口語であっても文語であっても、日本人のこころに訴えるものとして語られる。短歌における俗語革命とは何か。口語短歌の考察にあたって、普通文の性質まで考察することは回り道に見えるかもしれない。しかしこれは、例えば斎藤茂吉は文語にこだわり続けた理由を考えるために、ひいては二〇二二年現在の短歌において文語が継続的に用いられている理由を考えるために、必要な回り道である。」
「(三)俗語革命の影
(・・・)
俗語革命における俗語=「ナショナルランゲージ」としては、言文一致だけでなく、普通文もそこに組み込まれる資格を有している。しかし、「音声中心主義的」に語られる傾向の強い言文一致体は、普通文に古い言葉としての印象を与え、俗語としての役割を見えにくくしてしまう。そして、俗語革命の進展を言文一致の過程と同一視してしまうことも、普通文・言文一致体の対立軸を際立たせ、普通文の持つ俗語としての役割を見えにくくしてしまう。このように、俗語としての普通文は二重に覆い隠されている。だからこそ、短歌における口語は、「定型との調和の問題」として片づけられてしまうのである。」
「(四)書き言葉の身体/声
(・・・)
短歌という装置は、想像の共同体における話し手としての身体を立ち上げることができる。想像された領域の身体を以て、歌人は国家に仕えることができる。とはいえ、近代のはじめから短歌はナショナリズムの臣であったと絶望するのとは違う。」
「言文一致の眩惑の中で、はたして口語短歌は、公共の言葉の合間を縫って、きわめて私的なものを描き出すことができるのか。
(・・・)
私は口語短歌の可能性を信じている。口語短歌の試みが、言葉の所与の網の目をすり抜け、自由な言葉の身体を得る砦となることを、私は願っている。」



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
